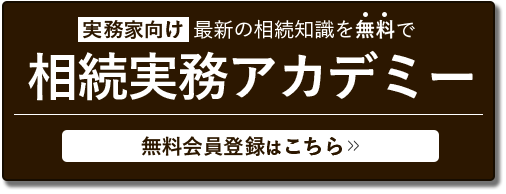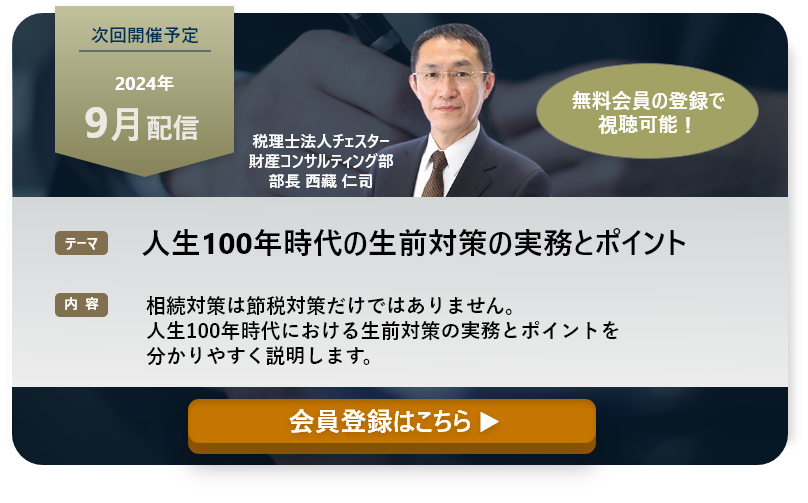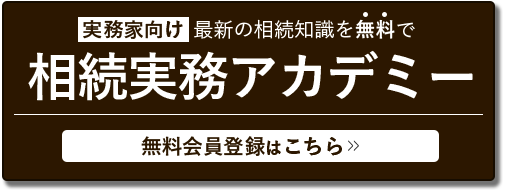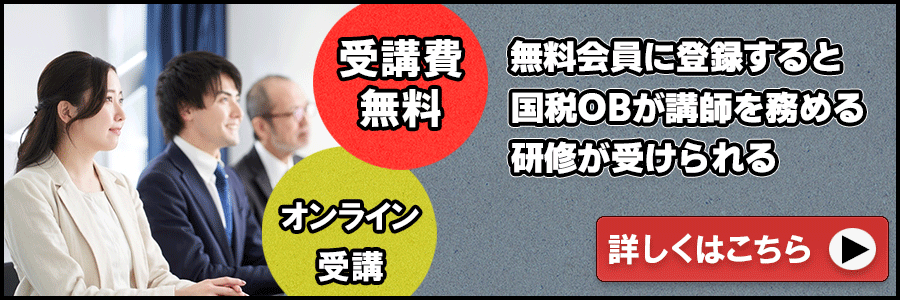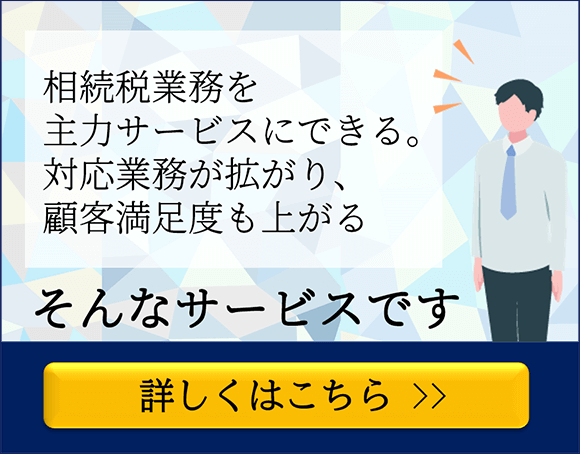土地の有効活用の方法のひとつに建設協力金方式があります。建設協力金方式は、土地を所有したまま、少ない資金でその土地から収益を得られる優れた方法ですが、建築協力金方式で契約を結んだ後、相続が発生した場合、相続税の計算において建設協力金の残債の扱いはどのようにすればよいのでしょうか。
~目次~
1.建設協力金とは?
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!土地保有者が自ら保有している土地に建物を建築して有効活用しようとする場合、土地所有者が少ない資本で土地の有効活用を図れるのが建設協力金方式です。土地の有効活用の方法には、信託銀行に依頼する土地信託方式、デベロッパー(土地開発会社)に依頼する等価交換方式などありますが、建設協力金方式は土地保有者が自分の土地を保有したまま有効活用することができる方法です。
1-1.建設協力金方式の具体的な流れは?
建設協力金方式では、その土地に出店を希望するテナントが「建設協力金」という名目で貸主(地主)に資金を預託します。貸主(地主)はその資金を建物の建築費用に充当します。建物が完成すると建設協力金は保証金に名目を変え、月々の賃料と相殺する形で借主(テナント)に返済する形となります。建設協力金方式の具体的な流れは以下のようになります。
1. 土地保有者が出店希望者(テナント)を募り、建設協力金という名目で無利息の資金を借り建設資金に充当する。貸店舗を建築しその店舗のオーナーとなる。
2. その貸店舗をテナントに賃貸する。建設協力金は保証金と名目を変え、賃貸期間中に全額返済できるように均等返済する。
3.オーナーは賃借人から月々の家賃を受け取るが、保証金の返済分は家賃と相殺するため、オーナーが受け取る家賃は相場よりも少ない額となる。
1-2.建設協力金方式の土地所有者のメリットとデメリットは?
自分の土地が更地のままでは収益を生み出さないばかりでなく固定資産税の支払いなどコストが掛かってしまいます。自己建設方式や事業受託方式で建物を建築するとなると、莫大な資金が掛かってしまいます。その点、建設協力金方式ならテナントが資金を拠出するため、自己資金が不足している場合でも土地を有効活用することができます。
建設協力金は建物の建築資金の全額が供託される場合もありますし、一部のみの場合もあります。全額供託する場合は、その分、月々の賃料と相殺され、受け取る賃料が少なくなります。
あらかじめテナントと契約し、建物が完成後、テナントが一括して借り上げるのが一般的で、完成後にテナントを募集する手間もなく、空室のリスクもありません。
土地所有者は土地を手放す必要がなく、建物も自分で所有することができます。賃料収入で固定資産税などを支払うことができ、建物の減価償却費は経費にすることができます。
一方デメリットとしては、建物をテナント仕様で建築するので、退去後の使途に困る、テナントが倒産してしまうなどのリスクがあるなどが挙げられます。
1-3.建設協力金方式のテナントのメリットとデメリットは?
建設協力金方式では、総合リース建築会社などの仲介で土地所有者と協力して建物を建築します。テナントの意向に沿った建物が建築できるのは、テナントにとって大きなメリットでしょう。通常10年以上の定期賃貸借契約となるため、安定して事業を営むことができます。
あらかじめ多額の建設協力金を預託する必要があるのはデメリットとも言えますが、テナントが自分で建築することを考えれば、建設協力金方式の方がコストを抑えることができます。
2.建設協力金の残債の債務控除については割引計算が不要
建設協力金方式で建物を建てた後に相続が発生した場合の相続税評価については、土地は貸家建付地、建物は貸家の評価になります。
建設協力金として預託された資金は、建物の賃貸借契約を結ぶ際に保証金の名目となります。相続税の計算にあたって、この保証金の扱いはどのようにすればいいのでしょうか。
無利息の保証金(建設協力金)は、賃貸契約の終了までに家賃と相殺する形でテナントに返済していきます。その際に、建設協力金を差し入れたことによって土地所有者が受ける経済的利益を考慮して家賃が設定されます。
相続税の課税遺産総額を計算する際、無利息の長期借入金等の債務は、経済的利益を考慮して現在価値に割り引いて債務控除するのが一般的ですが、建設協力金の利息については、家賃と相殺する形で賃貸人が実質的に負担していることになります。
そのため、建設協力金は割引計算は不要で、その残額のすべてを相続財産から債務控除することができます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。