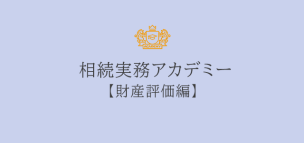
後継者不足による廃業や重い税負担による事業の縮小・廃業など、中小企業の事業承継にはさまざまな問題があります。これらの問題に対応して事業の円滑な継続を図るために、中小企業経営承継円滑化法が施行されました。あわせて定められた事業承継税制の一つに、非上場株式についての贈与税の納税猶予の特例があります。 1.自社株に係る贈与税の納税猶予 後継者が先代経営者から自社株の贈与を受けて会社を経営する場合には……
記事を見る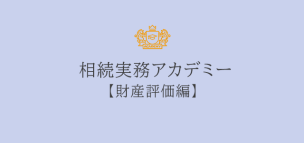
後継者不足による廃業や重い税負担による事業の縮小・廃業など、中小企業の事業承継にはさまざまな問題があります。これらの問題に対応して事業の円滑な継続を図るために、中小企業経営承継円滑化法が施行されました。あわせて定められた事業承継税制の一つに、非上場株式についての贈与税の納税猶予の特例があります。 1.自社株に係る贈与税の納税猶予 後継者が先代経営者から自社株の贈与を受けて会社を経営する場合には……
記事を見る
「車は相続税がかかる?かからない?」 「自動車の相続税はいくら?」 この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。 結論から言うと、相続で取得した被相続人の車(自動車)は、相続税の課税対象になります。 車は一般動産として評価するため、原則として、相続開始時点で売却したと仮定した場合の、「中古車販売業者の買取価格(時価)」が評価額となります。 なお、相続し……
記事を見る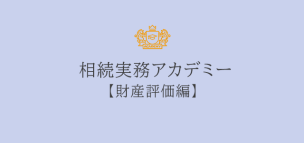
近年は証券会社のサービスが充実していて、個人でも手軽に外国の市場で株式取引ができるようになっています。そのため、外国の株式が相続財産に含まれることも珍しくなくなりました。 ここでは、外国の証券取引所に上場されている株式の相続税法上の評価方法について説明します。 1.外国の証券取引所に上場されている株式の評価 外国の上場株式は、日本国内の上場株式と同じように評価します。これは、外国の上場株……
記事を見る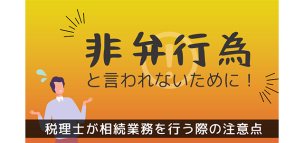
弁護士法には、弁護士でないものが行ってはいけない業務が定められており、その業務を弁護士以外の者が行うことを「非弁行為」と呼びます。 相続税申告業務においてどのような業務が非弁行為に当たるのかを解説します。 1.「非弁行為」とは? 1-1.要件 弁護士法72条では、弁護士でないものが報酬を得るという目的で、法律事件に対して業として除外事由なく鑑定、代理、仲介、和解、斡旋をする事ができない事が……
記事を見る
故人が遺言をしていた場合には、遺言通りに遺産分割を行うのが一般的です。しかし、相続人の望む分割方法と異なっているケースや、相続税の税務上不利になる分け方になっているケースなどでは、遺言と異なる遺産分割は可能なのでしょうか。 1.相続人全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割協議は可能 1-1.遺言と異なる遺産分割もできる 遺産相続では遺言があれば、遺言に従って遺産分割を行い、遺言がなければ相続……
記事を見る
太陽光発電設備(太陽光パネル)の相続税評価については、財産評価基本通達129に基づき「一般動産」として評価を行います。そのため、建物付属設備や構築物のように0.7を乗ずることはできませんので注意が必要です。 一般動産は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとなっていますが、太陽光発電設備自体には市場はなく売買実例価額や精通者意見価格は存在しないと考えられます。 ……
記事を見る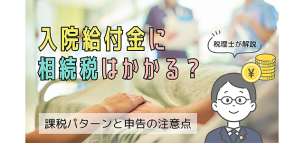
亡くなった人(被相続人)が民間保険会社の医療保険に加入していた場合、入院給付金を請求できることがあります。 受け取った入院給付金は、相続税の課税対象になるケースとならないケースがあります。また、みなし相続財産となる生命保険金とは異なり、相続税の計算時に「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠は適用されません。 この記事では、被相続人が加入していた医療保険の入院給付金が相続税の……
記事を見る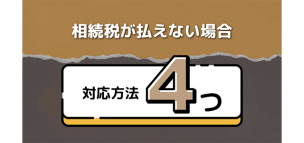
「父が急に亡くなって相続税が必要になったが、現金がなくて払えない…」 そんなとき、あなたはどう対処しますか? そんな状況を切り抜けるために、4つの対応方法を、相続税専門の税理士が解説します。 相続財産を換金・売却して納付する方法 「延納制度」を利用する方法 「物納制度」を利用する方法 銀行等から借り入れをする方法 納税義務があるにも関わらず払わない……
記事を見る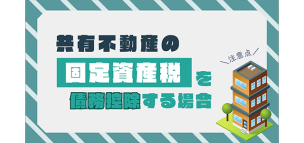
相続税は、少しでも減らしたいものです。相続税を減らすためには、相続税の対象額から控除される項目を把握しておきましょう。 不動産を相続する際に納める義務が生じる被相続人の未払いの固定資産税は、相続税の対象額から債務控除されます。 その際の注意点や、共有不動産の場合について解説します。 1.未払いの固定資産税は相続税の債務控除の対象 1-1.不動産を相続したら固定資産税の未払い分も納め……
記事を見る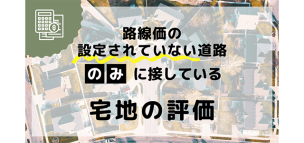
相続税の評価において、路線価がない道路のみに接する宅地の評価は特殊な対応が必要です。 具体的には、「特定路線価」の設定を税務署に申請する方法などがあります。 本記事では、「特定路線価」の設定の手続き・留意点や、路線価なしの地域の相続税評価方法などについて解説します。 1.路線価がない道路のみに接している宅地の評価方法の概要 路線価地域内において、相続税、贈与税の課税上、路線価の設定……
記事を見る