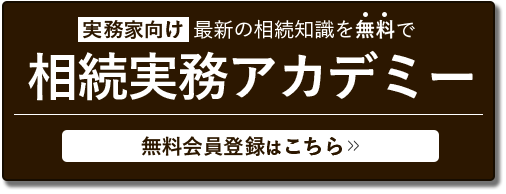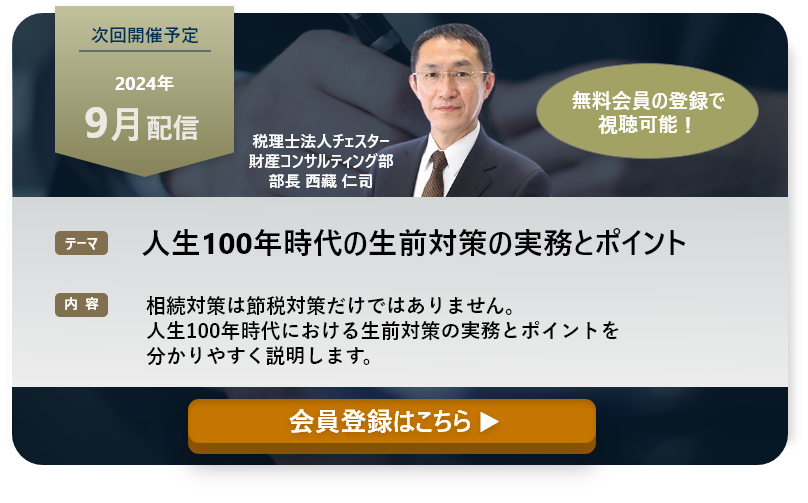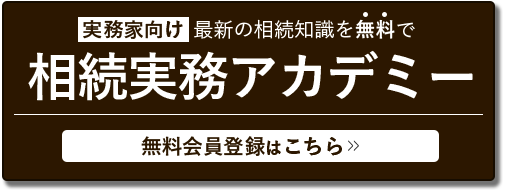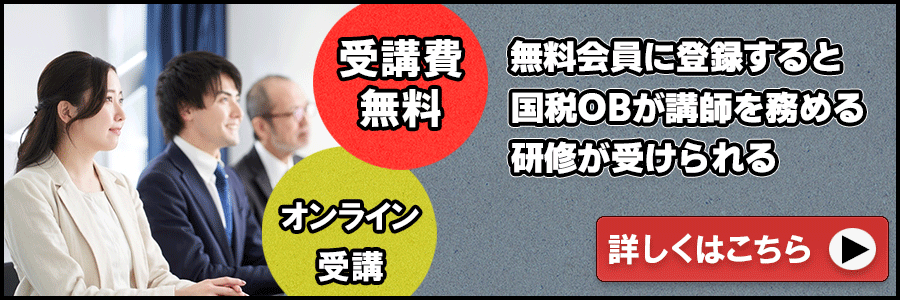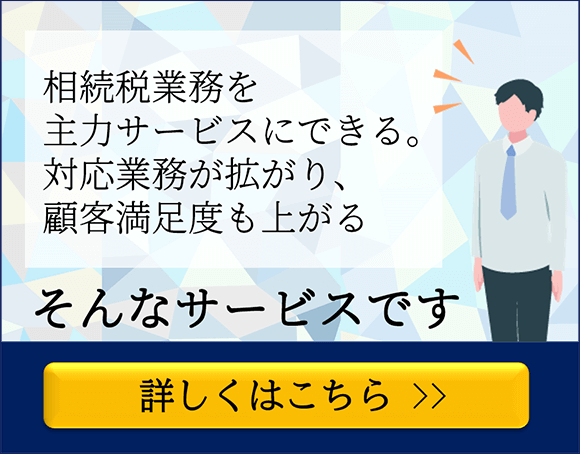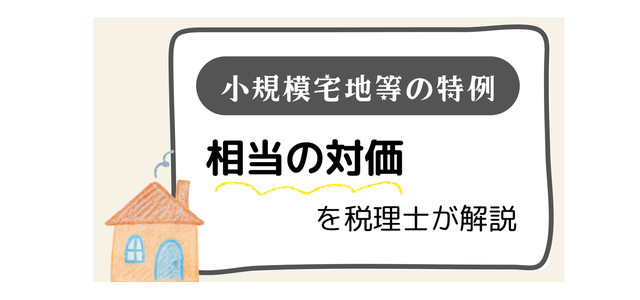
相続税の評価において小規模宅地等の特例が適用されるかどうかは、課税額に大きく影響します。「相当の対価」は、小規模宅地等の特例の一つである貸付事業用宅地の重要な成立要件です。けれども、実は「相当の対価」の定義は法令や通達に規定が無く、過去の裁判の判例が判断材料となります。「相当の対価」について解説していきましょう。
1.「相当の対価」は貸付事業用宅地の特例の重要な成立要件
>>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!!「相当の対価」とは、主に親族同士で貸借している事業用宅地で問題になる要件です。親族同士の貸借の場合、市場の相場よりも安い賃貸料で貸借契約を結ぶこともできてしまいます。そこで、貸付事業用宅地であると判定される相当の賃貸料(=相当の対価)が支払われていたかどうかが焦点になるのです。貸付事業用宅地として認められると、200㎡までなら50%もの評価減になりますので、裁判で争われるのも合点がいきます。
なお、「相当の対価」が支払われていたとしても、貸付事業用宅地と認められないケースもあるので注意が必要です。それは、該当物件が被相続人から相続人に貸付されていたケースです。貸付事業用宅地であると判定されるためには、相続税の申告期限まで貸付事業が継続されている必要があります。けれども、このケースでは被相続人が亡くなると同時に、物件が貸付されていた本人の資産になりますので、貸付事業が継続されていないということになるのです。
2.「相当の対価」についての判例紹介
「相当の対価」についての2つの判例の、判決主旨をご紹介しましょう。
①平成10年4月の東京地裁の判決主旨
貸付された宅地等の固定資産税や減価償却費、またその他の必要経費の合計額よりも高い金額であり、貸付した側に利益が出る場合に、相当の対価と判定される。
②平成7年1月の国税不服審判所の判決主旨
該当物件の賃貸料は1㎡につき4,825円。物件の周辺地域が1㎡につき13,447円や18,181円という賃貸料であること、および該当物件の第三者への賃貸料と比べても著しく低廉であることから、相当の対価で賃貸されたとは言えない。
すなわち、賃貸料から諸経費を差し引いてもなお、貸付した側に利益が出る金額であること。また、近隣相場や、同物件の第三者への賃貸料と同等の金額であることで、「相当の対価」と判定されるという判例です。
3.「相当の対価」であると認められるために重要な「近隣相場」と「事業性(利益)」
判例とも重なりますが、「相当の対価」であると認められるためには、近隣相場と同等の金額であることや、該当の賃貸契約に事業性(利益)があるかどうかが重要です。とはいえ、これらの条件が2つ共に満たされないと「相当の対価」と認められないわけではありません。
例えば、賃貸事業として利益が出ていなくても、近隣相場と同等の金額であれば、「相当の対価」と認められます。反対に、賃貸事業として利益が出ていても、近隣相場より金額が低いという場合も、「相当の対価」と認められるのです。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問い合わせ→記事内容に関するお問い合わせ」よりお問合せ下さい。
但し、記事内容に関するご質問や問い合わせにはお答えできませんので予めご了承下さい。