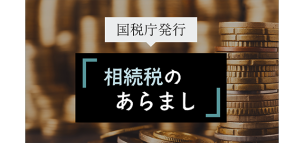
国税庁発行の“相続税のあらまし”には、相続税についての基本的な考え方や計算方法の具体例などが簡単に記されています。この“相続税のあらまし”を読むことで、どのような場合に相続税を支払う必要があるのか、相続財産には何が含まれるのかなど基本的なことがわかります。 1.国税庁発行の“相続税のあらまし”とは? 国税庁発行の“相続税のあらまし”とは、相続税の仕組みについて、わかりやすく簡単に説明してあるも……
記事を見る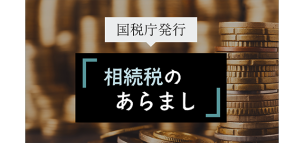
国税庁発行の“相続税のあらまし”には、相続税についての基本的な考え方や計算方法の具体例などが簡単に記されています。この“相続税のあらまし”を読むことで、どのような場合に相続税を支払う必要があるのか、相続財産には何が含まれるのかなど基本的なことがわかります。 1.国税庁発行の“相続税のあらまし”とは? 国税庁発行の“相続税のあらまし”とは、相続税の仕組みについて、わかりやすく簡単に説明してあるも……
記事を見る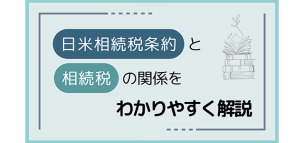
日本国籍を持つ人がアメリカで財産を築いて亡くなった場合、相続税はどうなるのでしょうか。遺産に関わる税金の仕組みは国によって異なり、税制の違いなどから、二重課税が生じるケースもあります。日本とアメリカは日米租税条約を締結することで、二重課税の問題に対処しています。 1.日米相続税条約と日本の相続税の関係 日本の法律では、被相続人や相続人の居住地に関わらず、被相続人が日本国籍である場合は、民法に従……
記事を見る
相続税は、相続財産から債務を控除した金額に対して計算されますが、債務以外にも葬式費用を控除することができます。葬式費用にはさまざまな費用がかかりますが、どの費用について葬式費用として控除対象とすることができるかを解説します。 1.相続税の葬式費用の範囲 相続税を計算する場合、遺産から債務を差し引いた金額となりますが、債務だけでなく葬式費用についても控除することができます。亡くなった方に関する支……
記事を見る
一次相続で未分割財産があるまま、二次相続が発生してしまった場合、相続税の扱いはどうなるのでしょうか。父親と母親が相次いで亡くなったケースでは、配偶者の税額控除の特例が問題になるケースもあります。そこで、一次申告で未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告についてまとめました。 1.一次相続の未分割財産がある場合の二次相続の相続税申告 遺産が相続税の課税対象にならない場合など、一次相続で未分割財……
記事を見る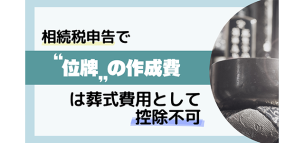
相続税を計算するときは、遺産総額から葬式費用を控除できます。しかし、葬式費用としてかかった全ての費用が控除の対象となるわけではありません。葬式費用として控除できるものとできないものの違いや位牌の概要についてご紹介します。 1.葬式費用として相続財産から控除できるもの・できないもの 1-1.葬式費用として控除できるもの 葬式やその前後で必要となった以下の費用は、葬式費用として遺産総額から控除で……
記事を見る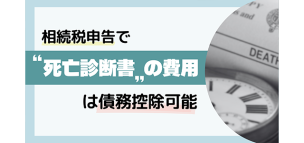
相続税を計算するときは、遺産総額から借入金などの債務や葬式費用を控除できます。葬式費用には、医師に交付してもらう死亡診断書も含まれます。死亡診断書の概要や相続税債務控除との関係、医療費控除上の取り扱いについてご紹介します。 1.死亡診断書とは 1-1.死亡診断書に記載される内容 死亡診断書は、人が死亡したことを医学的、法律的に証明する意義を持つ書類です。生から死への変化の事実が医学的、客観的……
記事を見る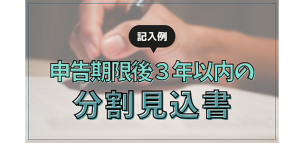
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ですが、なかには期限までに相続人間で相続財産をどのように分割するか話し合いがつかないということがあります。そのような場合に相続税の申告と同時に提出する「申告期限後3年以内の分割見込書」について解説します。 1.「申告期限後3年以内の分割見込書」とは? どういった場合に提出? 1-1.相続税の申告と遺産の分割 相続税は、被……
記事を見る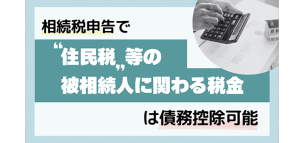
『相続税法』により、相続税を計算する際、亡くなった人が残した債務は、相続財産から差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。債務控除の対象になる債務には住民税や所得税などの税金も含まれます。ここでは、亡くなった人の税金と債務控除についてご説明します。 1.亡くなった方(被相続人)にかかる住民税について 1-1.住民税の仕組み 住民税は、1月1日時点で住民登録のある人が、その年の6月……
記事を見る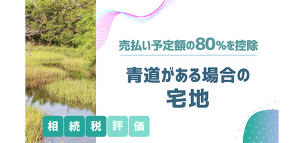
土地の評価減要因のひとつに、かつて水路などであった土地「青道」があります。青道は、現在は元の用途は廃止され宅地などの一部として利用されていることもありますが、その場合でも本来は国有地です。機能廃止された青道に該当する部分は、国からの売払い予定額の80%を控除して評価しなければなりません。 1.青道の定義 青道とは、以前川や水路として利用されていた土地で、現在は河川法などの法規が適用されていない……
記事を見る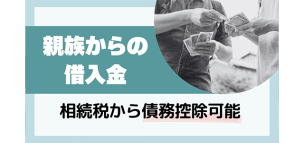
相続税の申告をする際、亡くなった人の債務は相続財産から差し引くことができます。しかし、親族からの借入金の場合は、税務署から「贈与では?」「相続税対策?」と疑われやすいのが実情です。ここでは、親族からの借入金を債務控除するための注意点についてご説明します。 1.親族からの借入金でも相続財産から債務控除が可能 1-1.借入金は相続財産から差し引くことができる 相続財産と被相続人の債務については、……
記事を見る