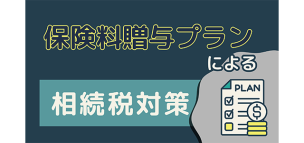
生命保険契約をする際に、生前贈与を上手に利用することで、子や孫に多額の現金を遺すことができます。いわゆる「保険料贈与プラン」と呼ばれる方法ですが、この「保険料贈与プラン」とはどのようなものか、さらに実施する際の注意点についてご説明します。 1.「保険料贈与プラン」の概要 1-1.「保険料贈与プラン」とは? 生命保険契約の際に、契約者を子供、被保険者を親、死亡保険金受取人を子供にすることで、親……
記事を見る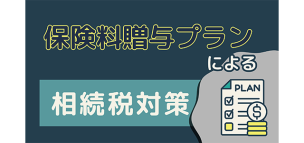
生命保険契約をする際に、生前贈与を上手に利用することで、子や孫に多額の現金を遺すことができます。いわゆる「保険料贈与プラン」と呼ばれる方法ですが、この「保険料贈与プラン」とはどのようなものか、さらに実施する際の注意点についてご説明します。 1.「保険料贈与プラン」の概要 1-1.「保険料贈与プラン」とは? 生命保険契約の際に、契約者を子供、被保険者を親、死亡保険金受取人を子供にすることで、親……
記事を見る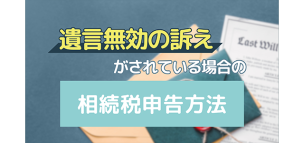
遺産相続で遺言がある場合には、本来は遺言書に沿って、相続や相続税の申告を行いますが、遺言書の有効性を巡って、遺言無効の訴えが起こされるケースがあります。遺言無効として係争中の場合には、どういった形で相続税の申告を行うべきか、また、懸念される点などについて解説していきます。 1.遺言無効の訴えがされている場合の相続税申告方法 遺言無効の訴えがされている場合の相続税の申告方法は2通りあります。遺言……
記事を見る
家庭菜園は、はたして農地に入るのでしょうか、宅地に入るのでしょうか?実は家庭菜園は宅地の一部とみなされて相続税評価されるのです。では、具体的にどのように評価されるのか、ということについてご説明します。 1.家庭菜園は宅地の一部として一体評価 1-1.家庭菜園の定義は? 土地は基本的に、宅地や田・畑・山林など、登記されている地目ではなく、相続税の場合であれば、被相続人が亡くなった日の現況によっ……
記事を見る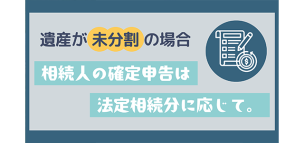
遺言がなく、相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わなかったとき、相続税の申告はどのような扱いになるのでしょうか。相続人によって対象か対象外か異なる特例は、誰が相続するのか決まっていない状態では、適用できないという問題が生じます。そこで、未分割の相続税の確定申告の扱いについてまとめました。 1.未分割状態の遺産から生じる不動産所得は法定相続分に応じて申告 相続税の確定申告の申告期限は、相続の開……
記事を見る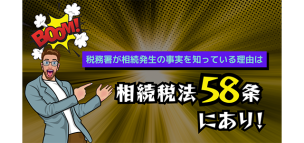
所轄税務署が、特定の人が亡くなったことにより、遺産相続が発生する事実を速やかに知りえている背景には、明確な法的根拠があります。具体的に相続税法における該当条文の内容を確認しながら、関連する注意事項についても併せて紹介していきましょう。 1.税務署に相続の情報を知らせる義務を定める相続税法58条 相続税法の第七章「雑則」において、第58条「法務大臣等の通知」という項目があります。その第1項では、……
記事を見る
相続対象となった土地が土壌汚染地の場合、相続税評価を減額することが可能です。土壌汚染地の相続税評価は、汚染がなかった場合の評価額から、浄化費用や使用収益制限による減価相当額、および心理的要因による減価相当額を差し引く減価方式によって計算します。 1.土壌汚染地とは? 土壌汚染地とは、直接もしくは地下水などを通して間接的に摂取した場合に人に健康被害をおよぼす有害物質に汚染された土地のことをいいま……
記事を見る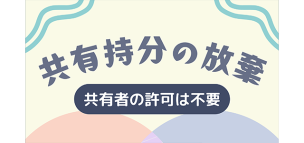
不動産には共有という所有形態がありますが、共有持分は放棄することが可能です。共有を解消するための手段として共有持分の放棄が行われることもありますが、他の共有者の許可は必要なのでしょうか。放棄された共有持分の扱いについて、税務上の問題も含めて解説していきます。 1.不動産の共有持分の放棄とは? 共有とは、不動産など一つのものを複数人が共同で所有している形態を言い、持分割合に従って権利を保有してい……
記事を見る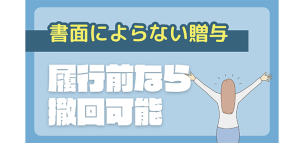
贈与とは、ある人が別の人に無償で自分の財産をあげる行為であり、民法第549条では「贈与契約」として定められています。 贈与契約なので書面で行う必要があると思われるかもしれませんが、口頭であっても「あげる」、「もらう」の意思が成立すれば贈与契約が結ばれたことになります。 書面によらない贈与とは何か、また、履行が撤回できるケースとはどういったものか解説していきます。 1.「書面によらない……
記事を見る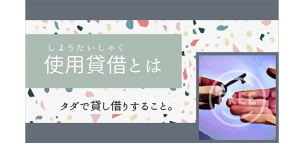
使用貸借とは、無償でモノを借りる契約のことです。「友人から傘を借りた」「自宅を建てるために親からタダで土地を借りている」といった貸し借りで賃料を支払っていない場合、使用貸借となります。 対して、賃料などの対価を支払ってモノの貸し借りをすることを「賃貸借」といいます。よく検討せずに使用貸借で不動産を家族に貸してしまうと、あとになってトラブルになるかもしれません。 また、相続が発生したとき……
記事を見る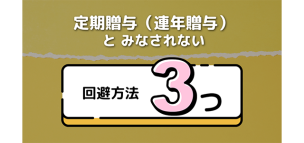
平成27年以降の相続から、遺産にかかる基礎控除の額が大幅に引き下げられたこともあり、相続税対策として生前贈与が注目されています。贈与税には基礎控除があるため、年間110万円までであれば無税で贈与できます。しかし、定期贈与とみなされてしまうと贈与税の対象になるため注意が必要です。 1.定期贈与(連年贈与)とは? 定期贈与とは、一定期間において一定額の給付を目的とする贈与です。例えば、「毎年4月1……
記事を見る