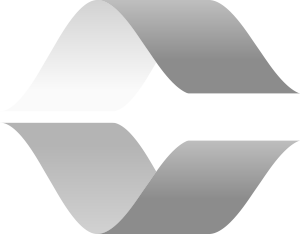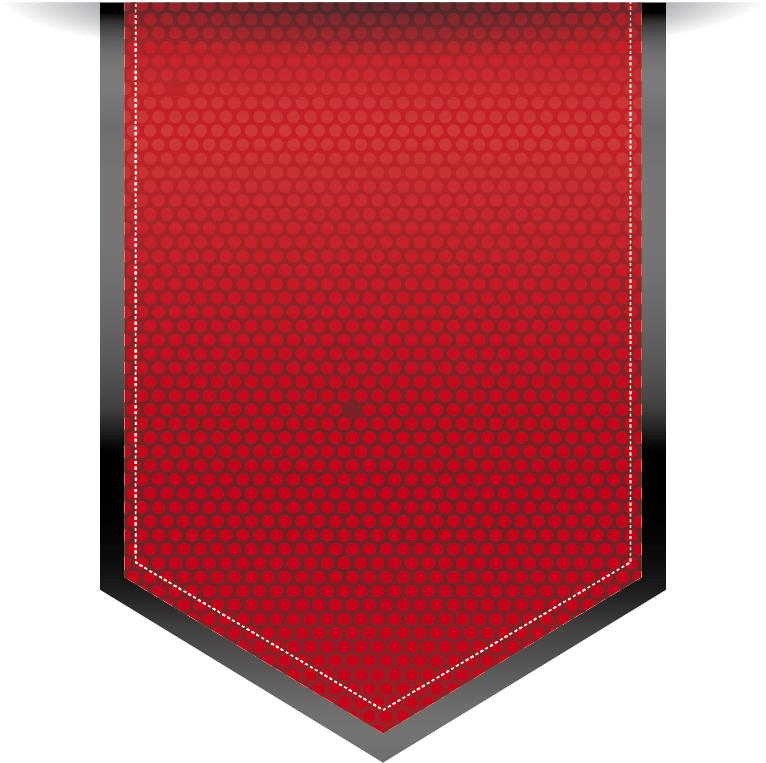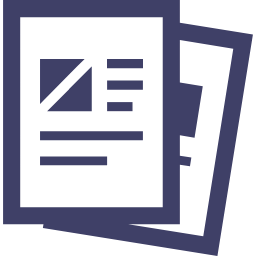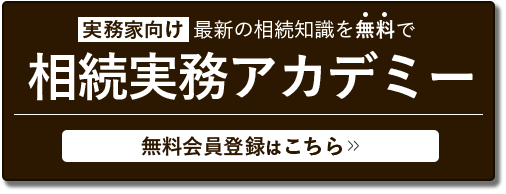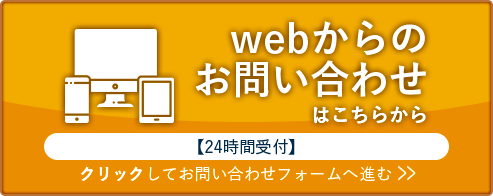チェスター相続税実務研究所
貸家建付地と貸付事業用宅地等の一時的空室の評価減は同一の基準で良いか
2018/10/22
平成13年税制改正において、貸家建付地(評価通達26)・貸家(同93)の評価において「賃貸割合」の概念が登場し、課税時期において賃貸していない場合には、評価減ができなくなりました。
その一方、評価通達26(2)(注)2において、以下の定めが加えられました。
上記算式の「賃貸されている各独立部分」には、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において、一時的に賃貸されていなかったと認められるものを含むこととして差し支えない。
その「一時的に賃貸されていなかったと認められるもの」の要件としては、国税庁タックスアンサーNo.4614において、「例えば」としながらも、以下の事実関係を掲記しています。
❶各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
❷賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
❸空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
❹課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。
その一方、貸家建付地が小規模宅地等の特例の適用対象宅地等の1つである「貸付事業用宅地等」に該当することもあり得ますが、両者の評価減の基準は同一と考えて良いのでしょうか。
国税庁ホームページには、小規模宅地等の特例についての個別通達があり、その「6 共同住宅の一部が空室となっていた場合」の(参考)に、以下の記述があります。
例えば、相続開始の直前に空室となったアパートの1室については、相続開始時において継続的に貸付事業の用に供していたものと取り扱うことができるか疑義が生ずるところであるが、空室となった直後から不動産業者を通じて新規の入居者を募集しているなど、いつでも入居可能な状態に空室を管理している場合は相続開始時においても被相続人の貸付事業の用に供されているものと認められ、また、申告期限においても相続開始時と同様の状況にあれば被相続人の貸付事業は継続されているものと認められる。
「新規の募集」といった共通の要件もありますが、両者の決定的な相違点は、「空室期間についての具体的な定めの有無」にあります。
貸家建付地については、❸において「課税時期の前後の例えば1か月程度」とありますが、貸家建付地の評価減に該当するか否かは、終局的にいえば「課税時期の時点で借家権による処分の制約があるか否か」の1点に尽きます。
そうすると、たとえ空室期間が生じたとしてもそれが「たまたま」生じたものであり、現実的な空室期間についても、退去・原状回復・入居といった一連の入退去に要する期間程度のものしか許容されないと考えるべきでしょう(過去の裁決事例において長期の空室期間であっても認容したものがありますが、将来にわたってもそうであるとは限りません)。
その一方、貸付事業用宅地等については事業の継続性、すなわち、空室期間に拘らず「賃貸できる状態であること」を重視していると考えられます。
また、上記個別通達が(平成13年よりも後の)平成22年に発出されたものであることからも、上記タックスアンサーの❶~❹の要件とは異なるものであり、かつ、緩和したものであると考えられます。
そうすると、貸家建付地の評価減をしていることが必ずしも貸付事業用宅地等の要件(前提)ではなく、貸家建付地の評価減をしていなくても50%の減額がなされる事例があり得ることになります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。