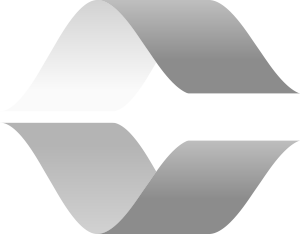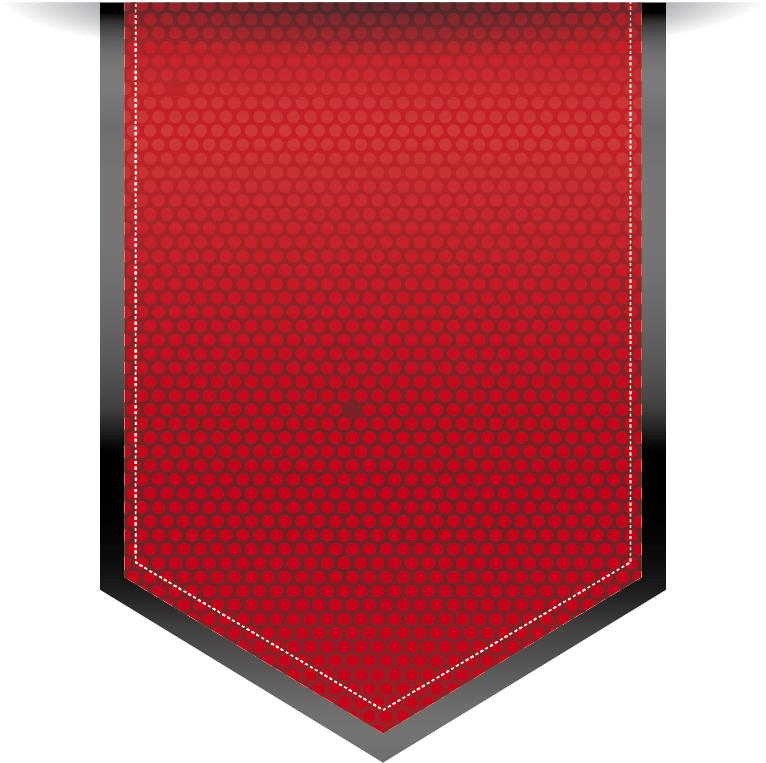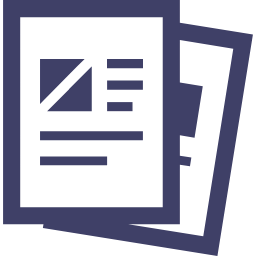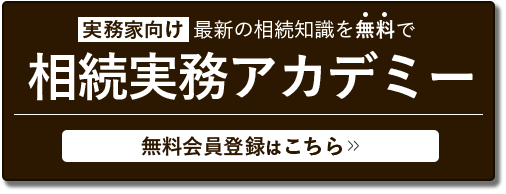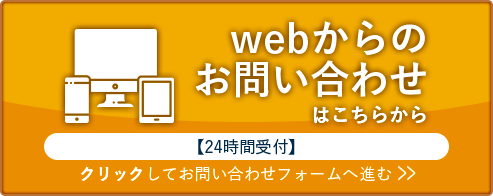チェスター相続税実務研究所
事業承継税制にありがちな誤解
2019/01/09
平成30年度税制改正における資産課税の目玉といって差し支えない、いわゆる「事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予とその免除)」ですが、その適用に当たって盲点になりかねない項目をいくつか含んでいます。
❶納税猶予対象税額は案外少ない
平成30年度税制改正に拠るものではありませんが、納税猶予税額は、「財産が対象株式のみと仮定した場合の税額」です。
相続税(贈与税)は超過累進税率を採用しており、課税価格が減少すると、その納税者に適用されているもっとも高い税率(限界税率)部分から削減されるのが通常ですが、事業承継税制は上記の仮定計算を行いますので、特例を実際に適用しようとするときに、自社株の評価額のボリュームの割には納税猶予税額が少ない(当てが外れた)といったクレームを受ける可能性があります。
❷常時使用従業員は厚生年金保険の被保険者である
後述の資産管理会社に該当しなければ、常時使用従業員数は1名以上(生計一親族可)でも対象になりますが、その者は「厚生年金保険の被保険者」又は「所定の75歳以上の者」でなければなりません。
厚生年金保険の被保険者となると、ある程度本格的に雇用することになりますし、「生計一親族をパート扱いで手伝わせる」といった関与では該当しないことになります。
❸資産管理会社の例外要件は一日たりとも欠くことはできない【平成31年度改正によって緩和の可能性あり】
資産管理会社に該当すれば、常時雇用従業員を対象期間の全てにわたって5名以上(生計一親族不可)継続して確保しなければなりません。
資産管理会社ではない(通常の)会社であれば、5年間平均で80%以上雇用を維持していれば(80%を下回っても所定の手続を経ていれば)適用を継続できますが、資産管理会社にはそういったバッファーがありません。
❹資産管理会社の判定における特定資産には現金預金が含まれる
総資産に占める「特定資産」の割合が70%以上(又は、売上に占める特定資産運用収入の割合が75%以上)であれば資産管理会社に該当しますが、その特定資産には、現金預金や同族関係者に対する貸付金が含まれます。
そうすると、投資用不動産を保有する会社のみならず、いわゆる「キャッシュリッチ」な会社であっても資産管理会社に該当することがあります。
❺事業承継税制上の「適格」は、組織再編税制のそれと異なる
合併により消滅した場合や株式交換により完全子会社に該当した場合には、事業承継税制の打切り事由に該当します(申告期限から5年経過後には所定の救済措置があります)が、「適格」要件に該当すれば打切りにはなりません。
しかし、ここでいう「適格」とは、後継者が複数の会社について事業承継税制を適用し、その会社間で合併するといった特殊なケースを指すものであり、少なくとも組織再編税制における「適格」要件とは別の概念です。
❻低額譲渡は事業承継税制の対象外
平成30年度税制改正によって、先代経営者からの贈与以後であれば、親族外の株主から贈与を受ける場合にも事業承継税制の対象にすることができます。
しかし、親族外の株主から株式を回収するに当たり、「無償では申し訳ないから額面価格(当初の出資価格)又は少し色を付けた価格水準で購入したい」と申し出て取得した場合には低額譲渡に該当してしまい、事業承継税制の対象ではなくなってしまいます。
これは、中小企業承継円滑化法上の「贈与」は民法上の「贈与」をいい、税法上のみなし贈与に該当するか否かは関係がないからです。
❼親族外の株主からの贈与についても相続時精算課税制度が適用できる
制度上は許容されていますが、贈与者の将来の相続税申告書に、親族関係ではない第三者の受贈者が関係してしまうことになります。
たとえ、相続時精算課税制度の控除枠である2,500万円相当額の自社株の贈与であっても、贈与者の相続財産の多寡によって、全く相続税が課税されないケースから、最高税率が適用されるケースまで想定されますので、相続開始に思わぬ相続税を負担する可能性があります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。