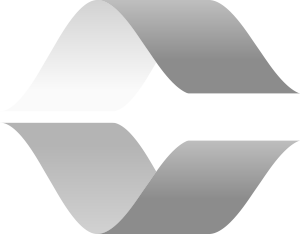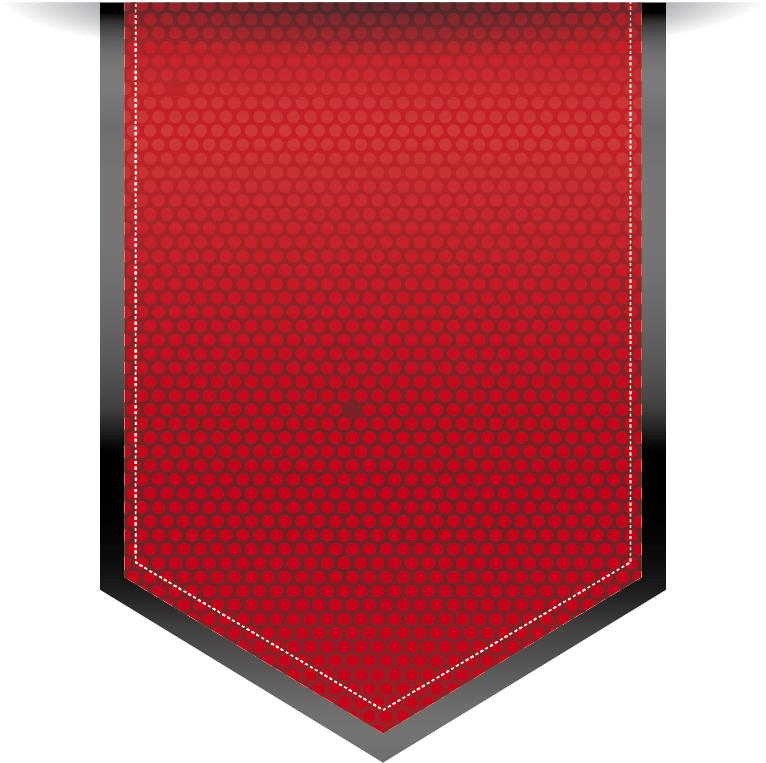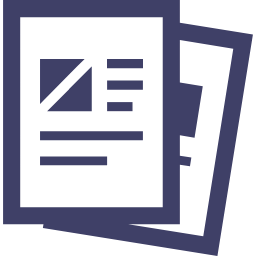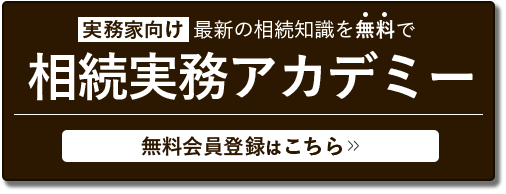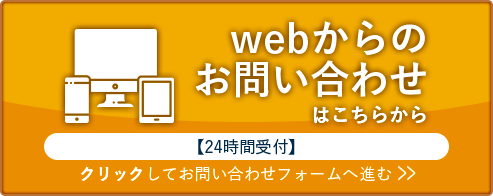チェスター相続税実務研究所
評価通達からの離脱がどの程度許容されるのか
2019/03/25
評価通達もあくまで通達であり、通達は「行政の上位機関が下位機関に対して、行政上の処理の統一を期するために発する指示文書」でしかありません。
そうすると、納税者が税務職員による業務執行によって間接的に通達の拘束を受けることはあっても、納税者が通達そのものに雁字搦め(がんじがらめ)の拘束を受けるものではなく、趣旨解釈することによって柔軟に判断すれば良いのではないかというご意見があっても然るべきでしょう。
ただし、評価通達に限っては、通常の通達の域を越えて、規範としての役割を事実上負っているという考え方があります。
東京地裁平成26年10月15日民事3部判決(平成24年(行ウ)第382号)に、評価通達の位置付けについて以下の法令解釈があります。
「同通達の定める評価方式が形式的に全ての納税者に係る財産の価額の評価において用いられることによって,基本的には租税負担の実質的な公平を実現することができるものと解されるのであって,同法22条の規定もいわゆる租税法の基本原則の1つである租税平等主義を当然の前提としているものと考えられることに照らせば,特段の事情があるとき(同通達6参照)を除き,特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ同通達の定める評価方式以外の評価方式によってその価額を評価することは,たとえその評価方式によって算定された金額がそれ自体では同法22条の定める時価として許容範囲内にあるといい得るものであったとしても,租税平等主義に反するものとして許されないものというべきである。」
(註)引用部の下線は執筆者による
評価通達の基礎となる法令が相続税法22条以下数条しかなく、その数条によって財産評価全般を賄うことはとても困難であることからすると、評価通達の規範性が自ずと浮上しても不思議ではありませんが、租税公平主義の観点から同一の物差しによって評価することの重要性を強調しているように考えられます。
もちろん例外はあり、上記判決でも「特段の事情があるとき(同通達6参照)を除き」との言及があるものの、換言すれば、「(6項以外の)評価通達を離脱できるのは『特段の事情がある』場合のみ」ということになり、「特段の事情」とは、評価通達を画一的に適用することがかえって租税公平主義の要請にそぐわなくなるケースに限定されるものと考えられます。
そうすると、「相続税の課税対象である財産は多種多様であり、評価通達は典型的な相続財産の評価例を示したものに過ぎない。そもそも通達の範疇であるのだから、より相応しい評価方法があるならば評価通達を離脱しても許容される」との考えは、課税庁のスタンス(少なくとも、現実に税務訴訟に至った場合のスタンス)とはかなり異なるものと言わざるを得ません。
実のところ、現在の多種多様な相続財産(特に金融商品)に対する手当てが評価通達によって十分にできていないのですが、少なくとも、現在の評価通達の定めによって評価しようと思えばできる財産についてまで任意に離脱できるほどには、評価通達の規範性は低くはありません。
納税者にとっては、租税公平主義を殊更に意識することはない(他の納税者がその財産をどのように評価しようが関係がない)のですが、税務行政の執行側からすると租税公平主義を意識せざるを得ないからです。
そうすると、納税者の相続税申告を受任する税理士としては、個々の財産評価について評価通達という同一の物差しを当てることに多少の違和感があったとしても、ある程度は受忍しなければならないと心得ておいた方が、税務調査における摩擦が少なくなると考えられます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。