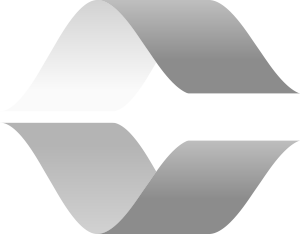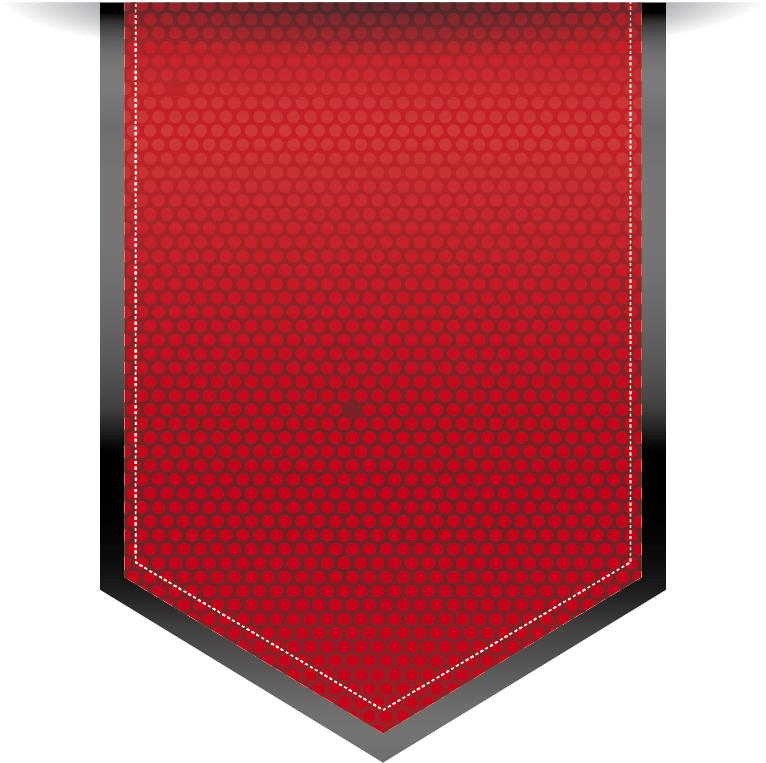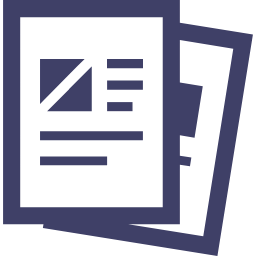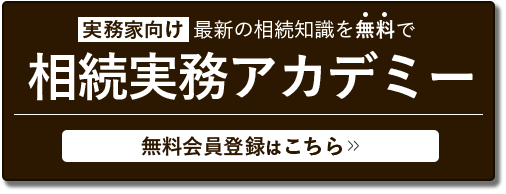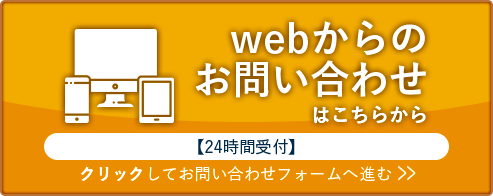チェスター相続税実務研究所
【先代名義の不動産にも「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は適用可能か】
2023/11/01
(1)「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の概要
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」とは、 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(※)まで控除することができるものです(租特法第35条③、以下「本特例」という。)。
なお、本特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
② 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
また、「被相続人居住用家屋の敷地等」とは、相続の開始の直前において、上述の要件を充たす被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます(同条④)。
(注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を相続又は遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
(2) 特例を受けるための添付書類の一例
本特例を適用するには、次の3つの事項を明らかにした売った資産の登記事項証明書等を確定申告書に添付することが必要要件の一つとされています(同条⑪、同法施行規則第18条の2②)。
① 売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと。
② 被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
③ 被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。
※上記書類以外にも、売った資産の所在地を管轄する市町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」等の一定の書類を、確定申告書に添付する必要があります。
(3)事例検討
(2)①の通り、本特例を適用するには、「売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したことを証明する」書類を添付する必要があります。では、被相続人居住用財産について登記事項証明書に記載されている所有者が先代名義のままである場合、本特例は適用できないのでしょうか。
【前提】
・被相続人:母
・相続人:長男、二男(父は以前死亡、子はいずれも同居親族でない)
【被相続人の居住用財産について】
・家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものである。
・区分所有建物登記がされている建物でない。
・被相続人は、死亡の時まで、この居住用財産に居住していた。
・登記事項証明書に記載されている土地及び家屋の所有者は、父のままである。
(被相続人が父から相続したものであるが、当時の遺産分割協議書等の客観的な書類が存在しない。)
・長男が当該財産を相続により取得し、数年後に土地も建物も売却予定である。
上記事例の場合は、相続時点での登記事項証明書では、その所有者及び共有か否かが不明です。このことから、上記(2)①の「売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと」について、登記事項証明書だけでは明らかになりません。
ただし、父及び母の遺産分割協議書を作成し、「平成○○年○○月○○日母相続、令和△△年△△月△△日相続」を登記原因とする所有権移転の登記を申請すれば、相続人である長男が被相続人である母から被相続人居住用財産を相続した旨の証明となり、本特例の適用が可能であると考えられます。
よって、被相続人居住用財産が、相続開始時点において被相続人名義(本ケースでは母)に変更登記していなかった場合でも、本特例を適用できる場合があるため、特例適用の可能性を見逃さないように注意が必要です。
※参考:国税庁タックスアンサー№3306
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。