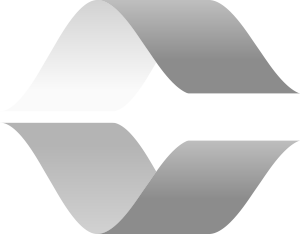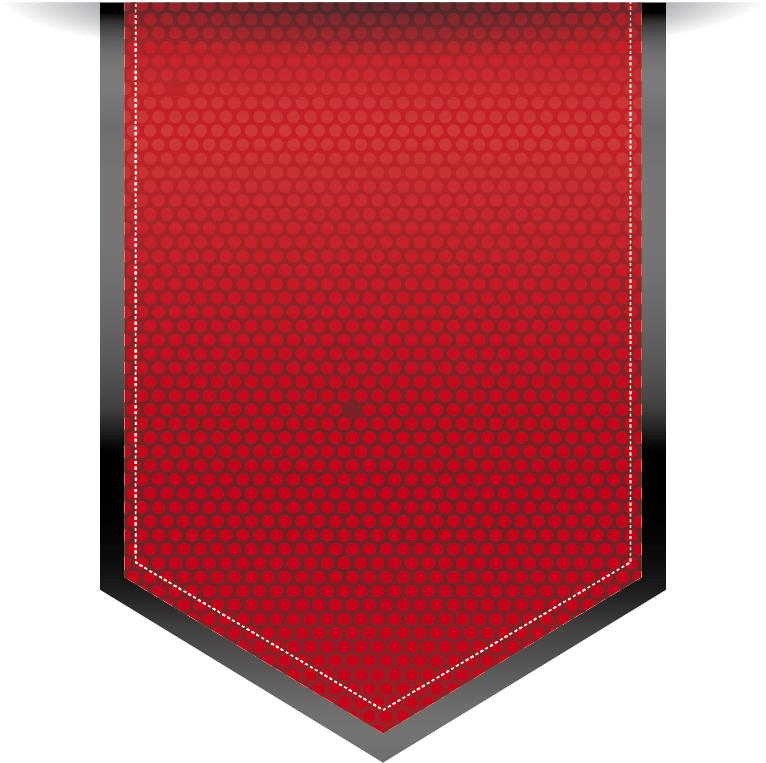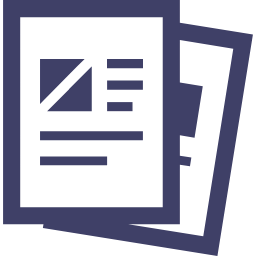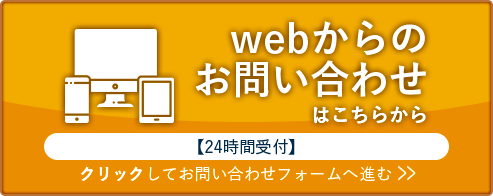チェスターNEWS
非上場株式の純資産価額算定は「直前期末」と「直後期末」のどちらかが争われた事例

1.はじめに
親族間における非上場株式の売買において、売買に係る課税時期における各株式の1株あたりの純資産価額がいくらか争われた事例をご紹介します(令和5年7月24日大裁(諸)令5第2号/未公表裁決)。
本事例では、同族会社の株式の1株あたりの純資産価額を算定するにあたり、「直前期末法」と「直後期末法」のどちらの資産及び負債の金額を基に計算するべきかが争点になりました。
本稿では、事実関係を元に本事例の概要をご案内します。
2.非上場株式の1株あたりの評価方法
非上場株式の評価方式は会社の規模によって異なり、業種・総資産価額・従業員数・直前期末以前1年間における取引金額によって規模区分が決定され、評価方法も異なります(財産評価基本通達178 )。
会社の規模が「小会社」に該当する場合は、納税義務者の選択により、【類似業種比準価額×0.5+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-0.5)】により評価額を計算することができます(財産評価基本通達179 、185 )。

純資産価額方式における評価時点は、「課税時期(贈与であれば贈与が成立した日)」で、原則として「仮決算法(課税時期に仮決算を行い確定した資産・負債の価額に基づいて計算)」が採用されます。
ただし、課税時期に仮決算をするのは実務上手間がかかるため、要件を満たしている場合は、例外的に「直前期末法」や「直後期末法」に基づいて評価することが認められています。
3-1.直前期末法とは
直前期末法とは、直前期末の総資産及び負債の金額を、課税時期における資産及び負債の金額として、1株あたりの純資産価額を算定する方法のことです。
直前期末法を用いることができるのは、直前期末から課税時期までの間に、資産及び負債に著しい増減がない場合とされています。
3-2.直後期末法とは
直後期末法とは、直後期末の資産及び負債の金額を、課税時期における資産及び負債の金額として、1株あたりの純資産価額を算定する方法のことです。
直後期末法を用いることができるのは、課税時期が直後期末に非常に近く、課税時期から直後期末までの間に資産負債の著しい増減がない場合とされています。
3.「直前期末法」か「直後期末法」かが争点となった事例
祖父が全株式(500株)を保有する同族会社X(事業年度:4月~3月)の非上場株式を、孫である請求人A・B(以下、請求人ら)が売買により250株ずつ取得しました。
しかし相続税法第7条 「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合(低額譲受)」、いわゆる「みなし贈与」に該当するとして、贈与税の更正処分及び過少申告加算税の割賦決定処分(以下、更正処分等)を行われました。
3-1.本事例の前提的な事実関係
平成29年10月17日以降、同族会社Xにおいて法人税等の税務調査が行われ、前代表者が売り上げを不当に減算していたことが発覚しました。
元代表者はその事実を認め、同年11月17日に同族会社Xに対して、損害賠償金の支払いを申し出ました(同年12月15日に損害賠償金の一部を支払い)。
同年12月11日、同族会社Xは法人税等の修正申告を行いました。
そして同年12月から翌年の1月にかけて、元代表者を債務者として、損害賠償請求権の一部を被保全債権とする、不動産仮差押命令及び債権仮差押命令の申立てを行い、裁判所は各仮差押を決定しました。
3-2.同族会社Xの株式売買契約に係る事実関係
平成31年1月21日、請求人らは祖父から同族会社Xの株式250株ずつを譲り受ける内容の、売買契約を締結しました。
請求人らは、財産評価基本通達185 に基づき「直前期末法(平成30年3月31日)」の資産及び負債の金額をもって、株式の時価を1株あたり64,528円(各1,613万2,000円ずつ)と算出しました。
なお、株式の売買契約書には「売買日は平成31年3月4日」とした上で、売買代金の振込を行っています。
同族会社Xの取締役会においても「譲渡日は平成31年3月4日」として株式の売買を承認し、株式名簿に記載された請求人らの株式の取得日も平成31年3月4日とされています。
3-3.不動産や現金の贈与に係る事実関係
令和元年9月20日に、請求人らは祖父からそれぞれ不動産等の贈与を受けました(贈与①)。同年12月23日にも、請求人らは祖父からそれぞれ現金の贈与を受けました(贈与②)。
令和2年4月30日、請求人らは贈与①と贈与②についての贈与税の申告書を提出しました。
3-4.原処分庁が贈与税の更正処分等を決定
令和4年5月20日、原処分庁は、同族会社Xの株式売買に係る課税時期を平成31年3月4日とした上で、課税時期に近接する本件同族会社Xの「直後期末法(平成31年3月31日)」の資産及び負債の金額に基づき、株式の時価は1株あたり27万8,200円(各6,955万円ずつ)であると指摘しました。
その結果、同族会社Xの株式売買価額の差額に相当する5,341万8,000円が、相続税法第7条 に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合(低額譲受)」、いわゆる「みなし贈与」に該当するとして、請求人らに対し令和元年分の贈与税について更正処分等を行いました。

3-5.請求人らと原処分庁の主張
請求人らは、直前期末の純資産価額は1億4,226万4,000円(配当込み)で、直後期末の純資産価額は1億3,910万円(配当込み)であるため、純資産価額に著しい増減はないとして「直前期末法」を主張しました。
しかし原処分庁は、直前期末の翌日から株式売買に係る課税時期までに資産等の著しい増減があり、直前期末の純資産価額3,259万9,380円と、課税時期における純資産額1億4,140万2,232円には著しい差額が生じていることから、直前期末と課税時期までの間の資産及び負債に著しい増減がないと認められないとし、「直後期末法」の採用を主張しました。
4.国税不服審判所の審判
国税不服審判所は、直前期末から売買に係る課税時期までの間に、適正に処理が行われた会社の資産及び負債に著しい増減がないため、評価明細書通達で定められた「直前期末法」によることができると判断を示し、原処分の一部取消しを行いました。
このような裁決となった根拠について、確認していきましょう。
4-1.各株式売買に係る課税時期は「平成31年3月4日」である
国税不服審判所は、同族会社Xの株式の各売買に係る課税時期は、各株式に係る権利が請求人らに移転した「平成31年3月4日」であるとしました。
同族会社Xは株券発行会社であるものの、請求人らに対して各株式に係る株券は交付されておらず、株券を引き渡した日を課税時期とすることができません。
そこで、本件各売買に係る課税時期について、以下のような事実関係を元に検討しました。

売買においては民法第555条 の規定により、特段の合意がなければ、原則として契約の成立により権利が移転するとされています。
そのため、本件各売買に係る各事情を総合考慮すれば、請求人らへの本件各株式に係る権利の移転時期を「平成31年3月4日」とする旨の合意をしたと認められ、同日に本件各株式に係る権利が譲渡人から請求人らに移転したと解されるとしました。
4-2.各株式の1株あたりの純資産価額の算定方法は「直前期末法」である
国税不服審判所は、本件各株式の評価においては、評価明細書通達に定める「直前期末法」により計算することができるか否かを判断する必要があるとしました。
そして賃借対照表に計上されていないものの、直前期末の資産及び負債とすべきものについての検討がなされました。
本事例においては、会社の既存の賃借対照表に計上された資産及び負債に、直前期末である平成30年3月31日において、以下の存在が認められるとしました。

その上で、直前期末(平成30年3月31日)から、各売買に係る課税時期(平成31年3月4日)までの間には、株式の価額の計算に影響を及ぼすような著しい資産及び負債の増減は認められないため、本件各株式の1株あたりの純資産価額の計算は、評価明細書通達に定める「直前期末法」によることができるとしました。
4-3.株式の1株あたりの純資産価は「24万1,762円」である
国税不服審判所は、同族会社Xの株式売買に係る課税時期において、株式の1株あたりの純資産価額は「直前期末法」による24万1,762円(総額6,044万500円)としました。
結果として、請求人らの各売買価額である1,613万2,000円を大きく上回るため、社会通念に照らし、請求人らの株式の取得は相続税法第7条 の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合(低額譲渡)」に該当すると認められるのが相当としました。

よって差額に相当する4,430万8,500円は、みなし贈与として、贈与税の課税対象となるとの裁決をしました。
5.まとめ
本事例は、贈与税の課税時期が直後期末に近いものの、直前期末と直後期末の資産等に著しい増減がないため、請求人らが主張する「直前期末法」が採用されました。
しかし、請求人らが前代表者の不祥事に係る損害賠償権・薄外資産等・未払い法人税等を、同族会社Xの株価に反映させることなく売買を行ったことが敗着となり、社会通念に照らし「みなし贈与」に該当するとして、贈与税が課税されました。
実務においては、贈与税の課税シミュレーションのみならず、課税時期に反映すべき資産や負債の有無を確認することが、非常に重要と言えるでしょう。
※本記事は記事投稿時点(2024年6月3日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:小規模宅地等の特例の適用宅地を事実誤認した事例~東京地裁は更正の請求を認めず~