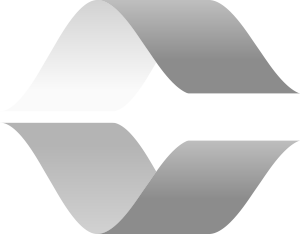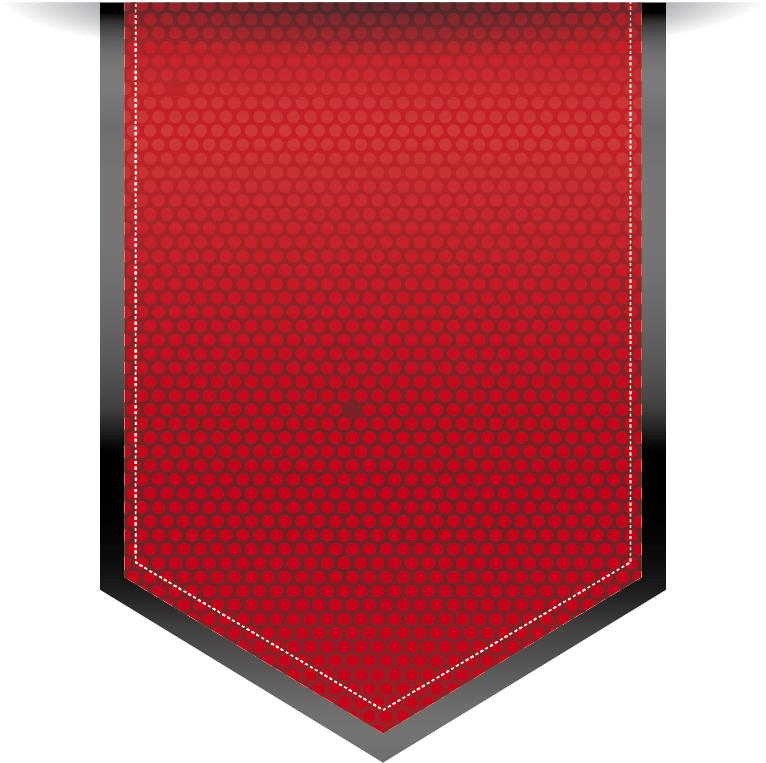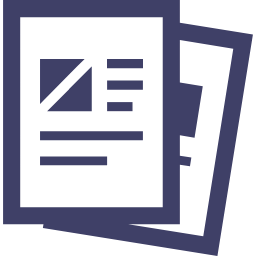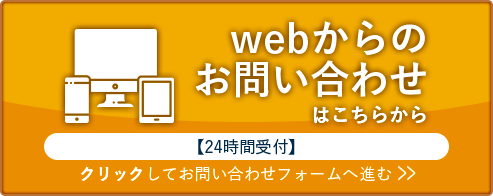チェスターNEWS
配偶者名義有価証券等を相続財産と判断

1.はじめに
相続税の対象となるのは、基本的に被相続人名義の財産です。しかし、配偶者や子供・孫などの名義の預貯金や有価証券、保険商品であっても、その名義が形式的なものにすぎず、実質的には被相続人の財産であると判断されるものについては、相続財産として申告する必要があります。
このような財産のことを名義財産といい、申告漏れしやすい財産の一つです。
仮に、税務調査によって申告漏れが指摘されると加算税や延滞税の追徴課税が行われることになります。
では、どのような場合に、名義財産と判断されるのか、その判断方法について、以下で説明いたします。
2.名義財産の評価方法
いわゆる名義財産(預貯金、有価証券、生命保険契約など)の評価方法や判断方法については、財産評価基本通達において特に定められていません。
実務上の判断は、過去の判決や裁決で採用された方法を参考に判断し、財産計上するか検討していきます。具体的には、次のようないくつかの点を考慮して総合的に判断していきます。
① 原資(誰の出捐か=実際にお金を出したのは誰か)
誰の口座から資金が移動しているのか。また、名義人の収入に見合わない預金残高や有価証券等の所有であれば、その資金の源泉がどこにあるのか。そして、その資金の源泉が誰の収入なのか、などを考慮します。
② 管理
預金通帳、証書、印鑑、キャッシュカードなどは誰が管理していたのか。預貯金や有価証券を運用するにあたって、最終的に意思決定していたのは誰なのか。この財産に関する郵送物が誰に届いていたのか、などを考慮します。
③ 利益
定期預金証書で利息が生じている場合はその利息が誰に帰属しているのか。有価証券の場合にはその配当や運用益は誰が受け取っているのか。誰が申告しているか、などを考慮します。
④ 経緯
預貯金や有価証券を、被相続人以外の名義とすることとなった経緯はどのようなものか。
仮に、預貯金の額や有価証券残高が名義人の収入に見合わなかったとしても、被相続人から名義人に対して贈与により財産を移転していたのであれば、その預貯金や有価証券などは名義人に帰属する財産となります。
⑤ 関係
被相続人と、預貯金や有価証券の口座名義人は、どのような関係なのか。
主に、以上のような要素を考慮して、 名義財産に該当するかどうかを総合的に判断します。
3.名義財産と判断されないための対策
それでは、このような名義財産と判断されないようにするためには、どのような対策をとっておけばよいのでしょうか。
ⅰ)贈与契約書を作成しておくこと
被相続人から名義人に対して贈与契約があったことを示す証拠として重要なものの1つに、贈与契約書があります。これを作成し、しっかりと管理しておきましょう。
贈与契約書の中には、「いつ」「誰から」「誰に対して」「何を」贈与するのか明記しましょう。その場合に、何か条件があれば(例えば、被相続人の介護をした場合には贈与するなど)、その条件も契約書の中に明記しておきましょう。
ⅱ)金銭の授受は口座振込で行うこと
被相続人から名義人に財産を譲り渡すときには、口座に振り込みをするのが良いでしょう。口座に振り込みをすることで通帳に記録が残り、実際に贈与されたことの証拠の1つとなります。
ⅲ)贈与が行われた後の預金や印鑑の管理
被相続人から名義人に対して財産を贈与した後も、被相続人が預金通帳、証書、印鑑、キャッシュカードなどを管理したままでいると、名義財産であると疑われる可能性がありますので、預金通帳、証書、印鑑、キャッシュカードなどは贈与を受けた人が管理をするようにしましょう。
ⅳ)贈与税の申告をしておくこと
受贈者一人当たり年間110万円以下の贈与金額であれば贈与税の申告をする必要はありません。原則的に暦年課税制度(※)によって贈与税の計算を行います。一般的に、自身の財産総額に対応する相続税の限界税率よりも低い贈与税の実効税率におさまるように、贈与金額を設定するのがポイントです。
(※暦年課税制度:贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。ここで、下記の国税庁HPに掲載された速算表を利用します。速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算します。それにより贈与税額が分かります。
(国税庁HP「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
では、配偶者名義の有価証券が被相続人の相続財産に含まれると判断された実際の事例について、以下で説明いたします。
4.具体例(東京地裁平成30年4月24日判決)
本件では、被相続人の配偶者名義の口座で管理されていた有価証券等(総額:約1億5千万円)が被相続人の相続財産に含まれるのか否かが問題となりました。
【事実関係】
被相続人は、生前、税理士事務所を経営しており、その事務所で被相続人の長女(=原告)も税理士として勤務していました。原告である被相続人の長女は、被相続人の配偶者名義有価証券等のうち、その45%相当額についてのみ相続財産として申告していました。これに対して、税務当局は、配偶者名義有価証券等の全部が被相続人の資産を原資として形成されたものと考え、配偶者名義有価証券等の全額について相続財産とする課税処分を行いました。
この課税処分を不服として、原告は課税処分の取り消しを求める訴えを提起しました。
【原告(納税者側)の主張】
本件配偶者名義有価証券等は、被相続人から原告に支払われた給与を原資として形成されたものであることなどから、配偶者名義有価証券等のうち、少なくともその2分の1に相当する部分については原告に帰属し、相続財産には含まれないと考える。
【被告(税務当局側)の主張】
本件配偶者名義有価証券等は、その全部が被相続人の資産を原資として形成されたものと考えられるため、配偶者名義有価証券等の全額について相続財産と考える。
【裁判所の判断(東京地裁平成30年4月24日判決)】
相続税を計算する上で、相続財産の帰属はその財産の名義のみではなく、その財産の取得が誰の出捐によるものか、被相続人とその財産の名義人及び管理・運用者との関係、名義人がその名義を有することになった経緯などの各事情を総合考慮して認定判断することが相当であるとし、本件について、裁判所は次のように認定しました。
〇被相続人は、自ら事務所で営んでいた税理士業の収入を家族4名分の名義を利用して資産の管理運用を行ってきたものであり、配偶者名義有価証券口座もそのなかで開設されたものであると認定した。
〇配偶者名義有価証券等の購入原資として、配偶者名義の預金口座又は証券口座に対して被相続人名義財産口座からその大半を占める資金が流入していることなどから、その購入原資は全額が被相続人に帰属するものであったと推認できるとした。
〇原告名義財産口座からは配偶者名義有価証券等の購入原資となるような資金流入は認められず、原告が被相続人から受けた給与及びその運用利益は既に原告名義の資産として形成されているものと認められるとした。
〇以上から、配偶者名義有価証券等は、その全部が被相続人に帰属する(相続財産に含まれる)と判断したうえで、課税処分は適法であるとした。
4.終わりに
以上のように、名義財産は明確な検討方法が決まっていて機械的にあてはめて判断できるものではありません。実務上は、これまでに集積した判決や裁決を基に、いくつもの要素を勘案しながら総合的に判断していきます。
それゆえに、名義財産と疑われるような財産を所有している被相続人の相続税の申告に関しては、判例や裁決を熟知し、その上で、課税庁を納得させるだけの論理の組み立てができる税理士に依頼することが大切になります。
※本記事は記事投稿時点(2018年10月30日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:小規模宅地特例の「特定貸付事業」の判定基準
【前の記事】:平成30年度税制改正・複数後継者への贈与