相続時精算課税制度を分かりやすく解説。どんな場合に有効な方法か
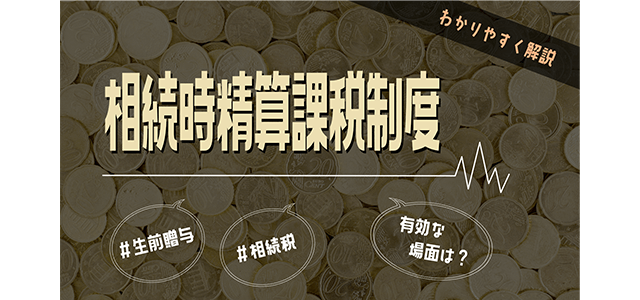
相続時精算課税制度は、複数年にわたる贈与に対し、贈与時に、累計2500万円まで贈与税が課税されない仕組みです。有効活用できるケースを知ることで、相続対策にも活かせます。対象となる贈与が決まっているため、適用される要件を確認した上で利用しましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続時精算課税制度とは?

贈与税の課税制度には『暦年課税』と、『相続時精算課税制度』があります。全ての贈与に対して毎年110万円の控除が適用される暦年課税制度に対して、相続時精算課税制度は適用される贈与が決まっており、また、複数年の贈与に対し合計2,500万円までを贈与時に贈与税の負担が無く、贈与することができ、相続時に精算する点が特徴です。
相続時精算課税制度についてくわしく知るために、まずは制度の概要を解説します。
1-1.両親から子、祖父母から孫への贈与が対象
誰からの贈与であっても適用される暦年課税に対し、相続時精算課税制度は適用される贈与が決まっています。対象となるのは『60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与』です。
年齢は贈与を受ける年の1月1日の満年齢で判断されます。相続時精算課税制度の適用は贈与者ごとに決定可能です。例えば父からの贈与に適用し、母からの贈与は暦年課税を用いるといった使い分けもできます。
1-1-1.住宅取得等資金の贈与の場合は贈与者の年齢の条件はない
住宅の購入等に使う資金の贈与を受けて一定の要件を満たす場合は、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税制度を適用することができます。これは、2026年12月31日までの特例です。
1-2.【2024年施行】110万円の基礎控除がある
令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
改正前は、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税の年間110万円の基礎控除を適用することはできず、少額の贈与であっても申告が必要でした。改正により、相続税精算課税制度を選択した場合であっても年間110万円までの贈与であれば、申告は不要になります。
相続時精算課税制度の基礎控除は、2024年1月1日以降に贈与された財産について適用されます。
1-3.2,500万円の特別控除がある
『2,500万円』までの特別控除を受けられるのも、相続時精算課税制度の特長です。父母や祖父母から子や孫への複数年の贈与に対し、2,500万円までは税金がかかりません。
2024年1月1日以降に贈与された財産については、110万円の基礎控除額を引いた残額が特別控除の対象になります。
2,500万円を超えて贈与を受けた分には、一律20%の税率で課税されます。毎年の基礎控除額が110万円の暦年課税制度と比較すると、一度に多額の贈与を受けても支払う贈与税の金額が少なくて済みます。
1-3-1.住宅取得資金の贈与には別の特例制度がある
住宅の購入に使う資金の贈与を受けるなら『住宅取得等資金贈与の非課税の特例』を利用するのもよいでしょう。父母や祖父母から住宅取得資金として贈与される資金は、一定額が非課税になります。
期間は2026年12月31日までです。取得した住宅の種別によって非課税になる限度額は異なります。最大で1,000万円まで非課税になります。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
この『住宅取得等資金贈与の非課税の特例』は、相続時精算課税制度と併用することもできます。
1-4.相続税が発生する場合、贈与税の精算が必要
相続時精算課税制度は、相続税が発生するタイミングで贈与税を『精算』する仕組みです。相続が発生すると、相続時精算課税制度の対象となっている財産(基礎控除分は除く)と相続財産の価額を合計します。
この金額をもとに相続税を求めるルールです。ただしこの相続税額を全て支払うわけではありません。基礎控除額・特別控除額を超える部分に対して既に納めた20%の贈与税額を控除した金額を納税します。
既に支払っている贈与税額のほうが相続税額より多いなら、その差額分は還付されます。
2.相続時精算課税制度活用のメリット
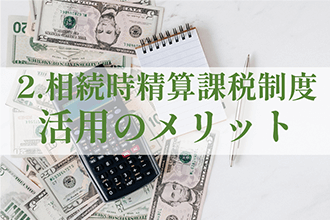
相続争いの回避や節税対策につなげるなら、相続時精算課税制度が役立ちます。計画的な贈与の実施で、相続人の将来の負担の軽減につながります。しかし扱い方を誤ると、負担が増す可能性があるため注意しましょう。
2-1.計画的な贈与で相続争いを防げる
例えば、事業の跡継ぎや同居の子どもに財産を多めに引き継がせる必要がある場合、相続時精算課税制度が役立ちます。贈与には相続時の遺留分のように、最低限受け取れる割合がありません。
親の生前に『財産をあげる』『受け取る』という双方の合意があって成り立つため、贈与者・受贈者間で円満に財産の引き継ぎが完了するはずです。
ただし、贈与された財産が『特別受益』とみなされた場合には注意しましょう。相続人への過去10年以内の特別受益は相続財産に加えられるため、遺留分を請求される可能性があります。遺留分を巡る相続争いも起こり得る事態です。
単に贈与をすれば安心というわけではありません。贈与の配分といった考慮も必要です。
2-2.精算は贈与したときの価額で評価される
相続時精算課税制度を用いると、相続が発生したときに相続税から既に納税した贈与税を差し引き精算されます。このとき『贈与時の価額』で計算するのも特長です。
不動産や株式のように、贈与時より相続時の価額が上がる可能性のある財産ならば、生前の贈与によって節税につなげられるかもしれません。
アパートやマンションなど、収益物件に対し、相続時精算課税による贈与を行うと、相続時精算課税を選択した以降は、その物件からの収益は受贈者が受け取ることになり、所得の分散にもつながります。
なお、令和5年度税制改正では、相続時精算課税制度を適用して贈与された土地・建物が災害にあった場合の特例が設けられました。2024年1月1日以降に生じた災害によって被害を受けた場合は、贈与時の価額から被害を受けた部分の金額を差し引いた残額で相続税を計算することができます。
3.相続時精算課税制度の主なデメリット
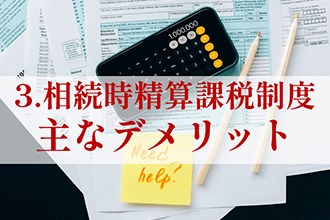
生前にまとまった金額を贈与できる相続時精算課税制度を活用すると、トラブル回避や節税につなげられる可能性があると分かりました。一方で、暦年課税や小規模宅地等の特例を使えないデメリットもあります。
3-1.一度適用すると暦年課税に戻せない
暦年課税は1月1日~12月31日の1年間に受け取った贈与額から、基礎控除110万円を差し引ける制度です。特に手続きをしなければ、基本的にはこの制度が適用されます。
ただし相続時精算課税制度を利用するための選択届出書を税務署へ提出すると、それ以降はその選択に係る贈与者からの贈与は、暦年課税制度を使えません。その選択に係る贈与者からの贈与は、すべて相続時精算課税制度の対象となります。
参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
3-2.小規模宅地等の特例も使えない
『小規模宅地等の特例』を使えないのもデメリットです。亡くなった方の居宅に係る土地などを相続した場合、定められた要件を満たすと相続税評価額が最大80%減額できます。大きく節税に役立つ制度です。
対象となるのは相続や遺贈により受け取った土地のみで、贈与によって受け取った土地には適用されません。引き継ぐ土地の種類によっては、相続時精算課税制度を用いた贈与より相続のほうが節税につながります。
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
4.相続時精算課税制度を利用するには
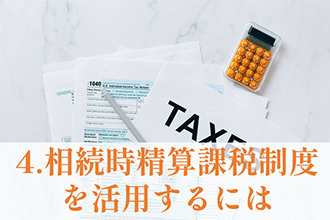
贈与税は手続きをしなければ暦年課税で計算する決まりです。相続時精算課税制度を適用するには、税務署へ届出書を提出します。また、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
4-1.必要書類を揃えて期限までに税務署に提出
相続時精算課税制度を利用するには、適用したい贈与を受けた翌年の『2月1日~3月15日』に、納税地の税務署で手続きします。『贈与税の申告書』に『相続時精算課税制度選択届出書』を添付して提出すれば完了です。
万が一期限内に届出書の提出を忘れると、贈与税の計算には暦年課税が適用されます。贈与額によっては、贈与税に数百万円の差が出る事態です。
忘れていたからといって後から適用できませんので、必ず期限内に手続きしましょう。
参考:No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類|国税庁
国税庁の動画では「パソコン申告 相続時精算課税を適用した贈与税の申告書作成手順」を公開しています。
4-2.110万円を超える贈与があったら申告を
これまで、相続時精算課税制度は、贈与を受けたら年間110万円以下であっても申告が必要でした。
しかし、2024年1月1日からは、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたため、贈与額が110万円以下であれば申告不要となりました。
年間で110万円を超える贈与があった場合は、特別控除で贈与税がかからない場合であっても申告が必要です。また相続時にも精算のために手続きが必要です。
5.株などの贈与、相続税が0円の場合に活用
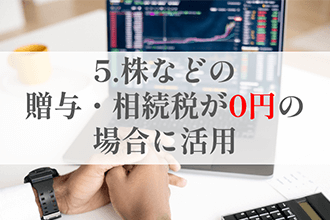
相続時精算課税制度は、年間110万円の基礎控除に加えて、2,500万円までの贈与が控除されるため、一度に大きな金額の贈与を受けられます。
計画的に贈与できれば、相続争いの回避や節税対策にもつながるでしょう。
将来的に価額が高まりそうな財産、収益物件からの収入の移転も考えている財産や、相続税が0円と考えられるケースでの利用が向いているでしょう。相続時精算課税制度の利用を検討するには『税理士法人チェスター』へお問い合わせください。
『相続時精算課税制度』についての詳細は、下記もご覧ください。
(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































