【相続財産の調査費用】専門家別の相場やかかる時間も徹底解説!
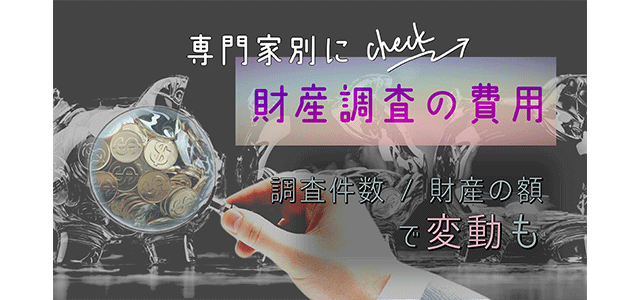
専門家に依頼したときにかかる故人の財産調査費用は、約数万円から100万円以上と状況によって大きく異なります。
確実に相続手続を進めたいなら、財産調査は相続に特化した専門家への依頼をおすすめします。どの専門家に頼むべきか、思っていた以上に費用がかかることがないか、事前にチェックしておきましょう。自身の相続状況にあわせた費用感で財産調査を頼めるはずです。
この記事の目次 [表示]
1.相続財産調査を依頼できる専門家ごとの費用相場
相続財産調査をする必要があるが、何から始めればよいのかわからない、調査のための手間も時間もかけることができない、といった相続人も多いでしょう。下にあげた専門家は、そのような相続人に代わって、相続財産調査をしてくれます。ただし、一口に相続財産調査といっても、各専門家によって対応できる領域、特徴が異なるため、相続人の事情に応じて依頼先を選ぶ必要があります。
| 専門家 | 費用 | 対応範囲 | 調査期間 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 10万円〜30万円程度 | 相続手続のほぼすべてを代行可能 | 1~2ヵ月程度 |
| 司法書士 | 10万円〜30万円程度 | 各種調査も可能 | 1ヵ月程度 |
| 税理士 | 財産額のおよそ0.5%〜1.0% | 相続税の申告業務 | 2ヵ月程度 |
| 行政書士 | およそ数万円~ | 不動産登記を含まない代行業務 | 1ヵ月程度 |
| 信託銀行 | およそ100万円~ | 必要に応じてそれぞれの専門家への橋渡し的存在 | 遺産整理全体として10ヵ月 |
1-1.弁護士に調査依頼すると10万円〜30万円程度
弁護士へ依頼する相続財産調査の費用は、弁護士費用と調査に必要な実費を合わせて10万円~30万円程度です。相続財産調査のために必要な資料は膨大であるため、実費等だけで数万円程度になる場合もあります。
弁護士は、相続手続のほとんどすべてを代行できる専門家なので、のちに説明する司法書士、税理士、行政書士の専門業務はすべて弁護士にもできます。
なかでも、訴訟手続の専門家として、相続代理人となって相手と交渉できる権限は、弁護士以外には与えられていません。
したがって、特に相続人同士で遺産をめぐって争いになることが予想される場合には、代理人として相手方と交渉したり、遺産分割調停や裁判で代理人になれます。
弁護士へ依頼する際には、遺産相続に力を入れている事務所が知識も豊富で安心できるでしょう。
1-2.司法書士に調査依頼すると10万円〜30万円程度
司法書士へ依頼する相続財産調査の費用は、弁護士への調査依頼費用と同様、司法書士費用と調査に必要な実費を合わせて10万円〜30万円程度です。
司法書士は、登記手続業務の専門家のため、相続人間で争いのない相続不動産の登記を中心とした、財産権利関係の移転業務を依頼できます。
なお、相続登記手続の一連の流れで、相続人の対象範囲を調べる戸籍調査、相続財産の調査、そして遺産分割協議書の作成などを依頼することも可能です。さらに、相続放棄を検討している場合の、必要な手続も依頼できます。
したがって、司法書士は、弁護士を除いて最も広く相続手続の代行が可能な専門家といえます。
遺産相続に力を入れている司法書士は、相続に関する知識も豊富で慣れているため安心できるでしょう。
1-3.税理士に調査依頼すると財産額のおよそ0.5%〜1.0%
税理士へ依頼する相続財産調査の費用は財産額のおよそ0.5%〜1.0%です。
税理士は、税務業務の専門家です。相続税の申告を依頼する場合、税理士だけが代行して相続税を申告できます。
一方、税理士は、法律業務のみを対象とした代行業務はできません。税理士は法律の専門家ではないからです。たとえば、誰がどの遺産を相続したかを記す文書(遺産分割協議書)を作成する場合を考えてみましょう。そもそも相続税の申告が必要のない場合、税理士は作成手続を代行することができないのです。そのような場合は、税理士に依頼を断られるか、税理士が提携している法律の専門家を紹介してもらうことになるでしょう。
したがって、税理士へ調査を依頼する場合とは、ある程度の資産があり、相続税の申告が確実だと考えられる場合です。
特に相続税を得意としている専門家であれば、相続税の削減につながるアドバイスを受けることもできるでしょう。
1-4.行政書士に調査依頼するとおよそ数万円から
行政書士へ相続財産調査を依頼する場合の費用は、およそ数万円から可能です。一般的に、他の専門家に比べると費用は安めに提示されることが多いようです。
行政書士は、相続人の財産調査や遺産分割協議書の作成、自動車や株式といった不動産以外の名義変更などができます。
費用の安さから、誰に相談すればよいのか、どこから手を付けていいのかまったくわからない場合に、最初の相談先として選ぶことが多いでしょう。相談を受けた行政書士は、相続手続をどのように進めていくのかを説明し、必要なサービスを提供します。
ただし、行政書士の代行業務として認められていない業務に関しては、別途費用がかかります。たとえば、不動産の名義変更をともなう場合、不動産登記の専門家である司法書士に依頼する必要があるため、別途司法書士費用を請求されることになります。
したがって、入口としての費用は安めですが、依頼内容によっては他の専門家の費用もかかるので、最初から他の専門家へ依頼したほうが、結果的に費用が安くなる場合もあります。
1-5.信託銀行に調査依頼するとおよそ100万円から
信託銀行に調査依頼をする場合、通常およそ100万円からとなっています。
信託銀行は、被相続人財産調査の窓口として、他の金融機関や信頼できる他の専門家と連携を取りながら必要な手続を代行してくれます。そして、相続にともなう金融機関での換金手続を依頼できます。ただし、これまで見てきた他の専門家へ依頼する場合の費用に比べると、大企業としての知名度もあり割高な印象があるかもしれません。一方、相続発生以前から被相続人と取引のあった信託銀行であれば、安心感があり、窓口を銀行に一本化できて財産関係の把握がしやすくなる可能性もあります。ただし、あくまでも窓口としての役割を担い、やはり割高ではあるので、相続額があまり多くない一般の人やこれまで信託銀行と取引をしたことのない人であれば、あまりメリットはないかもしれません。
2.財産調査にかかる費用の仕組み3タイプ
財産調査にかかる費用は大きく分類して下の3パターンに分けられます。
財産調査にかかる費用の仕組み
- 調査件数に応じて請求
- 定額で請求
- 相続財産の額に応じた費用を請求
相続人が相続する財産の金額や内容によって、おすすめのパターンはそれぞれ異なります。
たとえば、被相続人の財産をほとんど確認できているが、念のために調査をしたい場合と、被相続人の財産をまったく確認できていない場合では、その財産調査の仕方も大きく異なるでしょう。
相続内容別にどのような費用パターンが合っているのか順に見ていきましょう。
2-1.調査件数に応じて可算|依頼したいものが決まっている人におすすめ
調査件数に応じて請求されるパターンでは、依頼する財産1件につき料金が決められており、依頼件数に応じて費用が決まります。
したがって、依頼する財産調査が1件から数件であるような場合、調査件数に応じて費用を請求される専門家を選べば費用を抑えることができるでしょう。
ただし、専門家と相続人の間で、1件とはどの範囲までを指すのかについての考え方が食い違ってしまうと予想外の費用を請求されることも。そのため、具体的にどのような調査をお願いしたいのか、相続人がお願いしたい調査は専門家にとって何件にあたるのか等、事前に相談、見積もりをお願いすることをおすすめします。
2-2.調査件数に関わらず定額で請求|どれだけ依頼するか不明な人におすすめ
調査件数に関わらず定額で請求されるパターンの場合、調査を依頼する際に提示された定額で費用が請求されます。調査件数や相続額の多少に関係なくすでに請求額が確定しています。そのため、どれだけ依頼することになるのかわからない人にとっては、どんどん費用が加算され、最終的に思いがけない費用が請求されることがないのでおすすめです。
ただし、相続人と専門家双方の意見の食い違いを防ぐためにも、具体的にどのような調査をお願いしたいのか、事前に相談、見積もりをお願いすることをおすすめします。
2-3.相続財産の額に応じて費用を請求|最低報酬額に注意
相続財産の額に応じて費用が請求されるパターンでは、最低報酬額に注意が必要です。相続財産が少ない場合、最低報酬額を支払うことによって、かえって相続額がマイナスになってしまう可能性もあるからです。さらに予想外の財産が見つかった場合には、結果的に高額費用を請求されることも考えられます。
したがって、相続財産自体の金額はそれほど多くはないが、調査件数が多くなると予想されるような場合には、選択肢の一つとして考えてもよいでしょう。逆に、調査自体はそれほど複雑ではないが高額不動産を一件相続する予定といったような場合、相続額に応じた費用を請求されることになると、高額な費用の請求を受けることも考えられます。
3.財産調査の費用について確認したい3つのポイント
財産調査といってもその範囲は多岐にわたります。安く済ませるつもりで、調査件数に応じて加算される費用パターンを選んだのに、実際には次々と必要な調査数が増え、結局は定額費用のほうが安くなってしまうこともあります。まずは、どのような調査をお願いしたいのかをなるべく具体的にイメージしましょう。実際にどのような依頼をすればよいのか、どのような費用パターンを選べばよいのかを理解するために、以下の3つのポイントを確認します。
財産調査の費用パターンを選ぶ3つのポイント
- 実費はどれくらいかかるか
- 財産調査をどこまで依頼できるか
- 財産調査のみにかかる費用かどうか
3-1.実費がどれくらいかかるか
どの専門家に依頼しても、基本報酬の他に実費がかかります。
実費とは、専門家に依頼することで発生する、報酬以外に必要な費用のことです。例としては、財産状況に関する書類を取り寄せるために必要な通信費や不動産登記に必要な手数料、現地へ出向く必要がある場合にかかった交通費といったものが考えられます。
したがって、自分でできる簡単な資料の取り寄せすべてを専門家に依頼することにより、思った以上に交通費が発生してしまうことも考えられます。
このような予想外の出費を避けるためにも、専門家に依頼する前に、あらかじめ実費の見積もりを出してもらいましょう。見積もりに納得がいかない場合には、他の専門家へも見積もりを依頼することで、提示された見積額の相場がわかるでしょう。
3-2.財産調査をどこまで依頼できるか
財産調査を依頼しても、内容によっては依頼した相続人本人が実際に対応しなければならない場合も考えられます。たとえば、専門家が銀行で手続をするのではなく、専門家の指示を受けて依頼主である相続人が銀行で手続をする必要がある場合などです。遠方に住んでいる場合や、平日は仕事が忙しくて時間がとれない場合は特に、相続人本人が対応しなければならない手続はできるだけ減らしたいものです。相続人本人が対応せずにすべて任せることができる方法はあるのかも含め、依頼を検討している専門家に、任せられる範囲を確認しておきましょう。一方、費用を抑えてできるだけ自分で対応することで手数料を減らしたいといった場合には、それに応じた費用請求をお願いできる専門家なのかを確認しておきましょう。
3-3.財産調査のみにかかる費用かどうか
提示された費用が、財産調査のみにかかる費用なのかも確認しておきましょう。
専門家によっては、名義変更もセットで行うところもあるからです。
各専門家のウェブサイトでは、あくまでも自社が考える調査範囲についての費用が掲載されています。同じ財産調査という言葉を使っていても、すべての専門家に共通した調査範囲とはかぎりません。同様に、実際に依頼人が考えている財産調査も、専門家が調査範囲とする財産調査とは異なる可能性もあります。このような誤解を避けるためにも、専門家へはなるべく具体的な状況を説明して、事前にできるだけ細かい見積もりを出してもらうようにしましょう。
4.故人の財産調査が必要な3つの理由
相続が発生した場合に、故人の財産調査が必要になる理由は、次の3つです。
故人の財産調査が必要な理由
- 遺産分割協議をスムーズに進めるため
- マイナスの財産を把握し相続放棄の判断をするため
- 正しい相続税額を申告するため
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。すべてを合わせた被相続人の財産について相続が発生するため、個人の財産調査が必要になります。そして、財産調査の結果をもとに、どのように相続財産を分割し相続するのか、いくら相続税を収める必要があるのか、マイナスの相続財産しか残らないといった状況の場合に相続放棄するのかしないのか、といった判断をするのです。
4-1.遺産分割協議をスムーズに進めるため
相続が発生し、相続人が相続財産をどのように引き継ぐかといった話し合いを行うためには、財産目録が必要です。財産目録とは、被相続人の財産の内容すべてが一覧で記載されているものです。
相続人全員が、被相続人にどのような財産があるかについての内容を知らなければ、不公平な分割をされてしまうかもしれません。財産目録がないことで、他の相続人から、ひょっとしたら他にも相続財産があるのではないか、と思われてしまう可能性もあります。財産調査によって財産目録が作られれば、調査でわかった内容はすべて記載されるので安心です。たとえば、財産調査の過程で、相続発生直前に遺贈が行われていた事実がわかったとします。このような遺贈についても、遺産分割協議の対象として財産目録へ表示されるので、相続人全員に周知されることになります。
4-2.マイナスの財産を把握し相続放棄の判断をするため
相続にはプラスの相続財産もあればマイナスの相続財産もあります。
被相続人の財産を総合し、相続するかどうかを判断するために、プラスの財産とマイナスの財産を正しく把握しておく必要があります。たとえば、預貯金や証券などはプラスの財産で、クレジットカードでの使用金額といった借入金はマイナスの財産であることは、わかりやすいでしょう。
しかし、ローン残高額が不動産の価値を上回っているような場合は注意が必要です。他の財産も合わせるとプラスになったとしても、手間暇を考えて相続放棄をする決断にいたるかもしれません。逆に、他の財産も合わせてマイナスであったとしても、相続人それぞれの考えから相続する決断をする場合もあるでしょう。
4-3.正しい相続税額を申告するため
相続人は、相続財産の内容によっては最終的に相続税の支払いが必要になる場合があります。相続税の額は、相続人の非課税枠や相続財産の価値などに応じて決められています。特に、相続財産の価値を算出する際には注意が必要です。相続人の財産のなかには、何十年も前に取得して現在では非常に値上がりしている不動産など、購入時点の価値に比べて現在の価値が大きいものもあります。逆に、昔は価値の高かったものでも現在は価値がほとんどなく、財産評価の低いものもあります。たとえば、すでに市場価値のまったくない昔の高級車といったものがこれに当たるでしょう。
このような被相続人の財産に関して、それぞれの実態に合わせた現在の価値を出すために、財産調査によって財産を把握しておく必要があります。
5.各相続財産の調べ方|自分で調査する場合は要チェック
相続財産がそれほど多くない、相続財産はシンプルで専門家に依頼するまでもない、相続人自身で調べたい、といった場合には自分で調査することになります。この場合、調査もれによって修正申告や延滞税の発生といった事態を避けるためにも下の5つのポイントに注意しましょう。
| 財産の種類 | 調査方法 |
|---|---|
| 預貯金 | 銀行で残高証明書を取得する |
| 不動産 | 登記簿謄本と評価証明書を取得する |
| 有価証券 | 証券会社で残高証明書を取得する |
| 借金 | 債権者に対してローンの残高証明書を取得する |
| その他の財産 | 問い合わせ先に残高の有無を確認する |
5-1.預貯金|銀行で残高証明書を取得する
| 調査方法 | 通帳、郵送物を確認 |
|---|---|
| 取得すべきもの | 残高証明書 |
預貯金確認の基本は、被相続人の取引銀行で残高証明書を取得することです。書類の取得にあたっては、通常残高証明手数料がかかると考えましょう。取引銀行がはっきりとはわからない場合には、自宅や貸金庫に保管されている通帳や郵便物から特定します。最近は、ネット銀行での取引も増えているため、被相続人の取引銀行がわかりにくく、すべてを特定することは難しいかもしれません。ただし、他行との送金記録といった取引内容から、他銀行との取引も確認できることもあります。また、被相続人の手帳やメモからパスワードのようなものが見つけられれば、これを手掛かりに見つけることができるかもしれません。しかし、すべての取引銀行を把握することが難しいのであれば、専門家に任せたほうが安心でしょう。
5-2.不動産|登記簿謄本と評価証明書を取得する
| 調査方法 | 郵送される固定資産税の明細 |
|---|---|
| 取得すべきもの | 登記簿謄本、評価証明書 |
不動産に関する財産確認は、登記簿謄本と評価証明書を取得することで行います。
登記簿謄本は誰でも取得できますが、評価証明書は、不動産の所有者または所有者と同居している親族のみが取得可能です。それ以外は、所有者の委任状が必要になります。相続開始後に相続人が取得するためには、被相続人との関係がわかる戸籍謄本や相続人本人の身分証明書等も必要です。
不動産が相続人以外の第三者との共有である場合や、賃借権の設定がされている場合など、権利関係が複雑な場合もあるので、不安であれば専門家に任せたほうが安心でしょう。
5-3.有価証券|証券会社で残高証明書を取得する
| 調査方法 | 通帳、郵送物を確認 |
|---|---|
| 取得すべきもの | 評価証明書 |
有価証券に関する財産確認は、証券口座への入金出金といった振り込みに使用される通帳、証券会社や投資会社からの郵送物で確認します。そして、各社から残高証明書を発行してもらいましょう。
預貯金と同様、最近はインターネット証券会社での取引も多くなっています。もしネット銀行とネット証券間でのみ取引が行われている場合には、取引の存在を見つけにくいかもしれません。被相続人がインターネット環境をよく利用していたような場合には、ネット系金融機関を利用していた可能性も大きいので、パスワードと思われるメモがないか、口座開設の際に送られてきたと思われる口座説明の郵送物などがないかどうかを注意して探しましょう。
5-4.借金|債権者に対してローンの残高証明書を取得する
| 調査方法 | 通帳の取引明細、郵送物を確認 |
|---|---|
| 取得すべきもの | 残高証明書 |
金融機関からの借り入れに関しては、全国銀行協会や日本信用情報機構といった信用情報機関に問い合わせることで、正確な情報を得られるでしょう。たとえば、自宅のローンがまだ残っているような場合には、貸手金融機関に、ローンの残高証明書を発行してもらいましょう。
一方、未納している税金や個人にお金を借りているといった、金融機関以外で発生している債務については、信用情報機関ではわかりません。しかし、このような借金や負債についても、個人名による多額の入金がないかを通帳の取引明細で確認することは可能です。他にも、郵便物や個人間の借用書といった書類からも確認できるでしょう。
5-5.その他の財産|問い合わせ先に残高の有無を確認する
その他の財産がある場合には、それぞれの財産について、各問い合わせ先に残高の有無を確認しましょう。
上記1~4にあげた財産以外にも、最近では、たとえば暗号通貨といった新たに財産的価値を持つものが出てきています。その他にも、一般的ではないかもしれませんが、特許のような法的に権利を認められている、金額に換算できる財産もあります。
このように、それぞれの相続ごとに対象財産も多岐にわたり、一見すると財産に見えないものもあるかもしれません。被相続人宛ての郵送物や保管書類等を注意深くチェックして、相続財産の範囲を確認しましょう。そして、それぞれの財産について、具体的にどのような財産的価値で評価されるのかを問い合わせ先に確認しましょう。
6.確実な財産調査をするなら相続に特化した専門家に依頼するのがおすすめ
相続は、どれ一つとってもまったく同じケースはありません。それぞれの状況に応じた対応が個別に必要です。また、相続に必要な財産調査は、予想外に複雑で手間や時間がかかることも考えられますし、間違った申告をすれば本来は不要な費用が新たに発生することもあります。このような不都合を避けて確実な財産調査をするために、相続に特化した経験豊かな専門家へ依頼するのもおすすめです。相続人が十分納得して満足のできる相続をするための一つの選択肢として考えてもよいでしょう。
チェスターグループなら、相続専門の弁護士、税理士、司法書士が在籍しているため、ワンストップで相続人の状況に合わせた解決策を提供します。
不安や疑問があっても親身に寄り添ってサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続対策編






































