【生前贈与のやり方】税務調査で否認されない方法・手続きの流れや必要書類を解説

生前贈与を行うにはどのような手続きが必要なのでしょうか?実施の流れや必要書類をあらかじめ知っておくことで、スムーズに進められます。生前贈与は、税務調査で申告漏れが指摘されることもあります。税務調査の対策として、注意しておかなければいけないポイントもチェックしましょう。
この記事の目次 [表示]
1.生前贈与の計画を立てよう
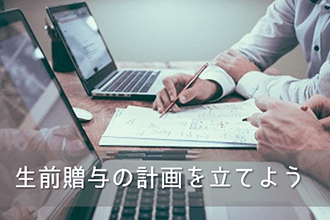
さまざまな決まりが設定されている生前贈与は、計画を立ててから行うのが大切です。制度を理解し計画的に実施することで、後悔のない贈与ができるでしょう。
1-1.二つの制度の選択
生前贈与を行った場合は、一定額を超える部分に贈与税が課税されます。
まずは、贈与税の課税について『暦年課税』と『相続時精算課税』のどちらを選ぶかを決めます。何も手続きをしなければ暦年課税が適用されます。1月1日~12月31日までの贈与に対し課税される制度です。
財産を受け取る受贈者は、1年に110万円の基礎控除が受けられます。そのため110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
相続時精算課税を利用するには届出書を提出します。すると特定の贈与者との間では、2,500万円まで贈与税がかかりません。暦年課税の基礎控除は適用されないため、贈与の金額にかかわらず毎年申告が必要です。ただし令和6年以降は、暦年課税の基礎控除とは別に相続時精算課税にも110万円の基礎控除が適用されるため、110万円以下の贈与であれば申告は不要になります。
1-2.計画的な贈与が必要な理由
生前贈与にはさまざまな制度があります。『生前贈与加算』というルールでは、生前贈与をしたつもりが相続税の課税対象になることがあります。
贈与者が死亡して相続が開始するまでの3年以内に贈与された財産は、基礎控除額以下の部分も含めて相続税の課税対象に加算されます。暦年贈与で贈与税が課税されなかったからといって、受け取った財産を使ってしまうと、生前贈与加算により相続税が課された場合に資金が不足しかねません。
生前贈与加算は、遺産を相続する人への贈与についてのみ適用されます。生前贈与加算による課税を回避するなら、法定相続人とならない孫や子の配偶者へ贈与することも一つの方法です。
事前に制度や特例を理解して計画的に贈与すれば、贈与税や相続税の負担を最小限に抑えられるでしょう。
なお、令和9年以降の相続では、生前贈与加算の対象になる期間が段階的に延長されます。最終的には、相続が開始するまでの7年以内に贈与された財産が相続財産に加算されます。一方、令和6年以降の相続時精算課税における基礎控除額以下の部分は、相続財産に加算する必要はありません。
1-3.住宅取得等資金や教育資金の非課税制度
計画的な生前贈与を実施する際に、さまざまな非課税制度を利用すると節税につながります。
夫婦間であれば居住用不動産やその購入資金の贈与について、配偶者控除により2,000万円まで贈与税がかかりません。
父母や祖父母など直系尊属からの贈与は、目的に応じて異なる非課税制度があります。
『教育資金』であれば、1,500万円を上限に贈与税がかかりません。『結婚・子育て資金』の一括贈与では、1,000万円までが非課税です。ただしどちらの制度を利用するのにも、金融機関と資金管理契約を結ぶ必要があります。
また『住宅取得等資金』も住宅の種類に応じて、最大1,000万円まで贈与税が非課税です。
なお、これらの控除や非課税制度を適用する財産については、生前贈与加算の対象になりません。
2.トラブルの予防や税務調査対策を行う
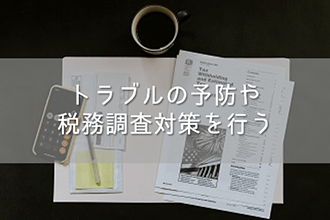
円満に財産を分ける目的や節税のために実施する生前贈与は、十分に対策してから実施しなければいけません。対策が不十分だとトラブルに発展する可能性や、税務調査で納税を求められることもあるため注意が必要です。
2-1.贈与契約書を用意する
贈与をしたときには必ず『贈与契約書』を作成しましょう。契約書があれば贈与の事実を客観的に証明できます。税務調査が入ったとしても、確かに贈与が成立していると分かれば、不当な課税を避けられるはずです。
契約書を作る際には、必ず2通作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ保管します。形式は決まっていませんが、最低限下記の内容を記載しましょう。
- 贈与する財産
- 贈与する財産の引き渡し方法
- 受贈者が贈与を受諾したこと
- 贈与の日付
- 贈与者の氏名・住所
- 受贈者の氏名・住所
慣れない契約書の作成に迷った場合には、実績のある弁護士や司法書士に依頼してもよいでしょう。
贈与契約書の作成に加えて、受贈者が税務署へ贈与税を申告すると、贈与の証拠として役立つかもしれません。たとえば、基礎控除額をわずかに超える金額を贈与して、少額の贈与税を申告するといった方法があります。
2-2.確定日付をもらう
契約書を作成するだけでも贈与の証拠になりますが、より客観性を高めるには『確定日付』をもらいましょう。公証役場で押してもらえる確定日付が入った契約書であれば、「後から作成したのでは?」と疑われません。
確定日付をもらうには、まず公証役場に電話し公証人がいるか確認します。予約をしておくとスムーズです。あとは指定の日時に公証役場へ行き、契約書へ確定日付をもらいます。
実際にもらいに行くのは契約を交わした本人でなくても構いません。委任状や印鑑証明なども不要のため、忙しいなら代理人に任せましょう。700円で契約書の客観性を高められます。
3.お金を贈与するときは銀行振込で
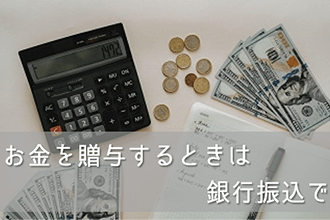
現金の贈与を行う場合には、必ず振込で実施しましょう。現金による手渡しでの贈与もできますが、後からトラブルに発展する可能性があります。
3-1.現金の手渡しを避けたい理由
贈与を行うとき、現金で手渡しをすると渡した記録が残りません。しかし税務署の調査を受けると、贈与のために預金を引き出した記録は確認されます。その結果、贈与を隠していたのではないかと疑われ、課税されるかもしれません。
また贈与者が贈与のつもりでも、受贈者は単に生活費を受け取っただけと考えているケースもあるでしょう。場合によってはトラブルへの発展も考えられます。そのため現金による贈与は実施しないのが賢明です。
3-2.本人が管理する口座に振り込みをする
贈与するお金は、受贈者本人が管理する本人名義の口座へ振り込むこともポイントです。口座の名義が受贈者のものでも、作ったのも管理しているのも贈与者だと、『名義預金』と解釈される可能性があります。
名義預金とされた場合、名義は受贈者のものであっても実質的な所有者は贈与者のままで、贈与は行われていないと判断されます。その結果、贈与者が亡くなったときに相続財産の対象となるのです。
このような状態を避けるには、受贈者が作成し自分で管理している受贈者名義の口座へ、贈与するお金を振り込みます。手付かずのままでも名義預金と疑われやすいため、少し使っておくのもよいでしょう。
4.土地や家の贈与は登記と税金の納付が必要

土地や家など不動産を贈与することもあるでしょう。不動産の贈与では現金と異なる手続きが必要です。具体的に実施しなければいけない登記と納税についてチェックしましょう。
4-1.必要書類を集めて法務局で手続きする
登記は法務局で行います。期限はありませんし、法律で義務付けられているわけでもありません。ただし贈与されたにもかかわらず登記をしていなければ、公的には不動産の所有者は贈与者のままです。
仮に贈与者が第三者へ売却し、その買主が所有権移転登記をしてしまえば、正式に買主の不動産になってしまいます。そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、登記は必ず実施しましょう。手続きには下記のものをそろえます。
- 贈与契約書
- 贈与者が持っている登記済証
- 贈与者の印鑑証明書
- 受贈者の住民票の写し
- 不動産の固定資産評価証明書
代理人に手続きを依頼する場合には、委任状も用意しましょう。
4-2.自分で申請もしくは専門家に依頼
登記の手続きは自分でできます。書類をそろえ法務局へ提出すればよいため、何が必要か分かっていれば、それほど難しい作業ではないでしょう。
ただし複雑なケースでは必要な書類が多く、慣れていないと1日で終わらないこともあります。書類取得の窓口はもちろん、法務局も手続きできるのは基本的に平日です。勤務形態によっては、仕事を休んで対応する必要があります。
慣れない手続きに手間取るなら、専門家に依頼するのもおすすめです。司法書士へ委任すれば、安心して手続きを任せられます。
4-3.不動産取得税を支払う
贈与により不動産を取得したら、都道府県に対して『不動産取得税』の納税が必要です。
登記を実施していれば、不動産取得後6カ月~1年くらいで納税通知書が送られてくるため申請は不要です。送付された通知書に従い、記載されている期限までに納税します。
税額は土地なら固定資産税評価額の1/2に税率をかけて、建物なら評価額に税率をかけて求められるものです。どちらも要件を満たすと軽減措置を受けられます。
不動産取得税は、土地や建物を取得すると納税義務が生じる税金です。ただし相続による不動産の取得は本人の意思と関係なく起こるため、課税されません。
5.贈与税の申告が必要なケース
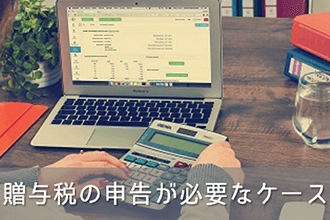
最後に、贈与を受けたときにどのようなケースで贈与税の申告が必要になるかをご紹介します。申告が必要なケースを把握して、適切に手続きしましょう。
5-1.暦年贈与の基礎控除額を超えた場合
暦年課税制度により贈与を受けた場合、1年間に110万円の基礎控除額を超えた贈与には申告が必要です。父母や祖父母など直系尊属から成年者への贈与であれば特例税率を、それ以外の人からの贈与なら一般税率を適用します。
申告書の『特例贈与財産分』『一般贈与財産分』とある欄に、それぞれの金額を書き入れましょう。贈与された財産の種類に応じて『種類』『細目』『利用区分・銘柄等』『所在場所等』『数量』なども記載します。
合計欄に贈与財産の合計額を記入し、基礎控除110万円を差し引いた金額に税率をかけて控除額を引けば贈与税額が求められます。慣れておらず正確に作成できているか不安なら、税理士への相談がおすすめです。
5-2.各種非課税制度などを活用する場合
各種非課税制度や控除を利用するときにも、贈与税の申告をしなければいけません。
贈与税の配偶者控除は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に税務署で手続きをします。手続きには『贈与税の申告書』『戸籍謄本』『戸籍の附票の写し』『登記事項証明書』などが必要です。
住宅取得等資金の非課税制度も同様に手続きをします。『贈与税の申告書』『戸籍謄本』『登記事項証明書』『契約書の写し』などが必要です。
教育資金と結婚・子育て資金の非課税制度については手続きが異なり、資金管理契約を結ぶ金融機関を通して税務署へ書類を提出します。
5-3.相続時精算課税を選択する場合
相続時精算課税制度を選ぶ場合には、適用する贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日に『相続時精算課税選択届出書』を税務署へ提出しましょう。その際、届出書には下記の事項を記載します。
- 受贈者欄:贈与税を申告する人の住所、電話番号、氏名、生年月日を記載
- 特定贈与者との続柄:贈与者との続柄を長男・孫などと記載
- 特定贈与者に関する事項:贈与者の住所、氏名、生年月日を記載
- 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合:養子縁組などで1年の途中に子どもや孫になった場合に記入
6.流れを知って正しい生前贈与を円滑に進めよう
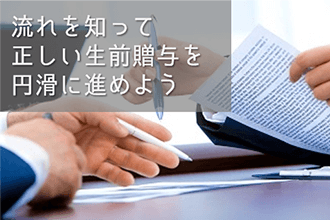
贈与者の意思を尊重した財産の移動や、節税を意識した生前贈与は、あらかじめ手続きの流れや制度の詳細を知った上で進めましょう。知らずに始めると後悔につながるケースもあります。
税務調査で不当な課税をされないためにも、契約書の作成や受贈者の口座への振込など対策を実施しましょう。加えて生前贈与なら、特定の目的に使う資金を非課税で贈与できる制度もあります。
さまざまな制度があるため、内容が難しく正しく申告できているか不安に感じる人もいるかもしれません。慣れない手続きに手間取ってしまうときには『税理士法人チェスター』へご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続対策編






































