【名寄帳とは】取得できる人・取得方法・必要書類・見方について解説
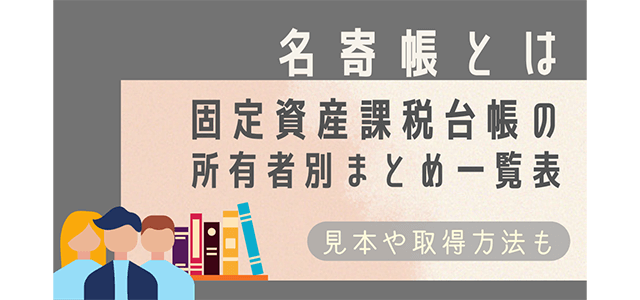
「相続財産に不動産が含まれるはずだけど詳細が分からない」
「被相続人が生前に多数の不動産を所有していたはず」
相続開始後にこのようにお悩みの相続人の方は、市役所で名寄帳を取得されることをおすすめします。
名寄帳とは、土地や家屋などの不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類のことです。
名寄帳は相続財産の調査・確定をする際に活用されますが、相続税申告や相続登記において、固定資産税評価額の証明としては利用できませんのでご注意ください。
本稿では、相続発生後に名寄帳を取得すべき4つのケースはもちろん、取得できる人・申請先・取得方法・必要書類・見方について解説します。
この記事の目次 [表示]
1.名寄帳とは不動産を所有者別に一覧表でまとめたもの
名寄帳(読み方:なよせちょう)とは、個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類のことです。
固定資産税が課税される土地や家屋などの不動産は、市区町村ごとに固定資産課税台帳で管理されています。
この固定資産課税台帳には、所有者・所在地・面積・固定資産税評価額などが登録されており、これを所有者ごとに“名寄せ”したのが名寄帳です。
なお、市区町村によって「土地・家屋名寄帳」「土地・家屋課税台帳」「名寄帳兼課税台帳」「固定資産物件一覧」などと表記されることもありますが、基本的に名寄帳と同じものと考えてください。
引用:久留米市公式ホームページ「名寄帳兼課税簿の見方」
相続が発生した場合、相続人は相続財産の調査をし、どのような財産が・どこに・いくらあるのかを把握しなくてはなりません。
しかし、被相続人が不動産を所有していた事実やその詳細を、相続人が把握していないこともあります。
このような場合に名寄帳を取得すれば、被相続人が所有していた不動産の詳細を一覧表で確認できるため、相続財産の調査に活用できます。
相続財産の調査について、詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」をご覧ください。
1-1.名寄帳を活用した相続財産の調査は専門家に依頼を
相続発生後には、速やかに相続財産の調査を行って、財産内容を確定しなくてはなりません。
この理由は、相続財産の調査・確定が終わらないと、以下のような相続手続きができないためです。
- 相続放棄の申述
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
- 相続登記の申請
相続財産の調査はご自身でもしていただけますが、財産の計上漏れがあると、遺産分割協議をやり直す必要があります。
仮に新たな財産が見つかったのが相続税の申告後であれば、修正申告をしなくてはならず、二度手間になってしまいます。
スピーディーかつ正確に相続手続きを終わらせるためにも、相続財産の調査は専門家に依頼をされることをおすすめします。
詳しくは「【相続財産の調査費用】専門家別の相場やかかる時間も徹底解説!」をご覧ください。
\\CHECK//
名寄帳以外にも、権利証・公図・被相続人が遺した書類などを利用して、相続財産の調査・確定を行います。
すでに相続が発生されたお客様でしたら、初回面談が無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。
2.相続発生後に名寄帳を取得すべき4つのケース
相続発生後に名寄帳を取得すべきなのは、以下のようなケースに該当する場合です。
被相続人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、名寄帳を取得する必要はありません。
ただし、思いもよらない不動産が見つかることもありますので、上記に該当するか否かに関わらず、名寄帳を取得されることをおすすめします。
2-1.固定資産税の課税明細書を紛失した場合
名寄帳を取得すべき1つ目のケースは、固定資産税の課税明細書を紛失した場合です。
固定資産税の課税明細書は、毎年4月から6月頃に不動産の所有者へ発送される、固定資産税納税通知書と納付書に同封されています。
引用:東京都主税局「課税明細書 見本」
課税明細書があれば、被相続人が所有していた不動産の詳細を確認できます。紛失してしまった場合は、再発行を依頼することも可能ですが、固定資産税が課税される不動産のみ記載されているため、非課税とされた不動産は記載されません。
名寄帳を取得すれば被相続人が所有していた不動産を、すべて把握することができます。
2-2.被相続人が複数の不動産を所有していた場合
名寄帳を取得すべき3つ目のケースは、被相続人が複数の不動産を所有していた(もしくはその可能性がある)場合です。
被相続人が不動産投資をしていたり、不動産賃貸業を営んでいたりした場合は、相続人が把握していない不動産を所有している可能性があります。
名寄帳を取得すれば一覧表で確認できるため、把握できていなかった不動産の存在に気付くこともあります。
2-3.被相続人が固定資産税を課税されない不動産を所有していた場合
名寄帳を取得すべき2つ目のケースは、被相続人が固定資産税を課税されない不動産を所有していた(もしくはその可能性がある)場合です。
固定資産税が課税されない不動産とは、公共用道路・私道・農地・山林などです。
これらの固定資産税が課税されない不動産は、固定資産税の課税明細書に記載されていない可能性があります。
しかし、相続税の課税対象にはなりますし、相続等で取得した人は相続登記をする義務もあります。
被相続人がこれらの固定資産税が非課税となる不動産を所有していた場合は、名寄帳を取得して詳細を確認しましょう。
2-4.被相続人が誰かと不動産を共有していた場合
名寄帳を取得すべき4つ目のケースは、被相続人が誰かと不動産を共有していた(もしくはその可能性がある)場合です。
固定資産税課税明細書が送付されるのは、共有者の代表者のみです。
仮に被相続人が誰かと不動産を共有していたものの、その代表者でなかった場合、手元に固定資産課税明細書が手元にないことも考えられます。
しかし、名寄帳には共有不動産の情報も記載されますので、詳細を確認することが可能です。
3.名寄帳を取得できる人は誰?どこで申請するの?
名寄帳の取得方法を知る前に、まずは誰が・どこで取得申請できるのかを知りましょう。
3-1.名寄帳を請求できる人は法定相続人など
名寄帳を請求できる人は、原則として固定資産税の納税義務者である不動産の所有者本人とされています。
しかし、不動産の所有者の相続が発生した場合は、本人以外の人も名寄帳を請求できるとされています。
- 亡くなった所有者の法定相続人
- 亡くなった所有者から遺贈を受けた受遺者
- 遺言執行者
- 法定相続人等の代理人
法定相続人等の代理人とは、各証明・閲覧の申請権限を有する人から委任を受けた人のことです。
代表的なのは、法定相続人等が相続に係る手続きの代行を依頼している、弁護士・司法書士・税理士などの専門家です。代理人が名寄帳を請求する場合は、委任状の提出を求められます。
3-2.名寄帳の申請先は法務局ではなく市役所
名寄帳の請求先は、不動産の所在地を管轄する、市区町村役場の資産税課です(東京23区の場合は都税事務所)。
法務局や税務署ではありませんので、間違えないようご注意ください。
なお、一部の政令指定都市では市税事務所で申請する場合もあるため、請求先は事前にホームページ等で確認しましょう。
3-3.名寄帳の取得手数料は自治体によって異なる
名寄帳の取得にかかる手数料は、自治体によって異なります。
手数料が無料の場合もありますが、ほとんどの場合でおおよそ150円~300円程度の手数料(区ごと・所有者ごとに)がかかります。
事前に市区町村のホームページなどで確認しましょう。
4.名寄帳の取得方法
名寄帳の取得方法は、市区町村役場や都税事務所の窓口に、申請書や必要書類を提出するだけです。
郵送による申請も可能ですが、発送までに1週間~10日程度の日数がかかりますのでご注意ください。
4-1.名寄帳を取得申請する際の必要書類
名寄帳を取得するのが法定相続人である場合、所有者が死亡していることや、申請人が法定相続人であることを証明しなくてはなりません。
具体的には、以下の必要書類の提出を求められます。
- 名寄帳の交付申請書
- 申請者の本人確認書類
- 申請者が相続人であることが分かる書類(※)
- 被相続人の死亡の事実を確認できる書類(住民票の除票や除籍謄本)
- 法定相続人の現在の戸籍謄本や抄本
- 遺言書(受遺者が申請する場合のみ)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
※法定相続情報一覧図や被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等でも可能
なお、名寄帳を郵送で申請する場合は、申請書と委任状は原本を、その他の必要書類は原本の写し(コピー)を送付します。
郵送の場合は、郵便局で購入した無記名の定額小為替で手数料を支払います。手数料分の定額小為替の同封を忘れずに申請しましょう。
法定相続情報一覧図について、詳しくは「法定相続情報証明制度とは?利用するメリットや申請時の必要書類、費用などを解説」をご覧ください。
4-2.名寄帳の交付申請書の書き方
名寄帳の申請書の様式は、申請先の市区町村役場によって異なります。
以下は東京都主税局が公開している、固定資産(証明・閲覧)申請書の書き方ですので参考にしてください。
引用:東京都主税局「固定資産(証明・閲覧)申請書」
名寄帳の申請書の書き方が分からない場合は、市区町村役場の窓口で相談しながら記入すると良いでしょう。
4-3.代理人が名寄帳を申請する場合の委任状の書き方
名寄帳の申請を代理人が行う場合は、必要書類に委任状が追加されます。
申請先の市区町村役場によって、委任状の様式などが異なりますが、代理人の住所や氏名、委任事項、物件の所在地、委任者(所有者または所有者の相続人)の住所や氏名などを記載し、委任者の印鑑を押印するのが一般的です。
以下は東京都主税局が公開している、固定資産(証明・閲覧)申請書の書き方ですので参考にしてください。
引用:東京都主税局「委任状等の記載要領・記載例」
5.名寄帳の見方をチェック【見本付き】
名寄帳の記載方法は市区町村によって異なりますが、以下のような形式で表示されます。

この章では、名寄帳に記載される代表的な記載事項についてご紹介します。
5-1.所有形態(単独・共有・区分)
名寄帳には、土地をどのように所有しているかを示す、所有形態が記載されます。
- 単有(1人で所有)
- 共有(複数人共同で所有)
- 区分(区分建物や敷地を所有)
例えば、土地を単独で所有している場合は「単有」と記載され、マンションなどの敷地であれば「区分」と記載されます。
5-2.所在地
名寄帳には、法務局の登記事項証明書や、市区町村が管理する固定資産課税台帳に登録されている、所在地が記載されます。
記載される所在地は、一般に使用されている「住所(住居表示)」ではなく「地番」です。
地番とは、土地の単位ごとに振られた登記のための番号で、位置を示す住所とは異なります。
市区町村で住居表示が実施されている場合、住所と地番が異なる可能性があるため、地番がわからない場合は市区町村に確認しましょう。
住所から地番を調べる方法について、詳しくは「住所から地番を調べるために知っておきたい3つの方法」をご覧ください。
5-3.地積と床面積
名寄帳には、地積と床面積が記載されます。
地積とは所有している土地の面積のことで、法務局の登記事項証明書や市区町村が管理する固定資産課税台帳をもとに記載されます。
床面積とは所有している建物の面積のことで、建物が一戸建てかマンションかによって計測方法が異なります。
なお、相続する不動産が代々引き継がれてきたものの場合、正しい面積が記載されているかの確認をおすすめします。
測量方法が現在と異なり、登記事項証明書上の地積と測量した地積が異なる可能性があるためです。
詳しくは、「登記簿地積と実測値が異なる場合の土地の相続税評価」をご覧ください。
5-4.固定資産税評価額
名寄帳には、固定資産税の基準となる、固定資産税評価額が記載されています。
固定資産税評価額の算出方法は各自治体によって異なりますが、国土交通省が発表する土地公示価格の70%程度が水準とされており、評価額は3年に1度見直されます。
不動産の相続登記や相続税申告の算定に使用されるのは、固定資産税評価額です。
固定資産課税標準額と間違えないようにしましょう。
詳しくは、「【税理士監修】固定資産税評価額と路線価の違いは?価格の決定方法を解説」をご覧ください。
5-5.固定資産税(都市計画税)課税標準額
名寄帳には、固定資産税額を算出する際の基準となる、固定資産課税標準額が記載されています。
通常、固定資産税「評価額」と固定資産税「課税標準額」は同一の金額となります。
しかし、特例措置などによって税負担が調整されている場合は、課税標準額は評価額よりも低く記載されています。
なお、固定資産課税標準額は相続登記や相続税申告の算出には使用しないため、算出の際には固定資産税評価額を確認しましょう。
6.相続発生後に名寄帳を取得する際の4つの注意点
相続発生後に名寄帳を取得する際には、いくつか注意点があるので知っておきましょう。
6-1.名寄帳は1月1日時点の固定資産所有状況のみ確認できる
被相続人が1月2日から相続開始日までに不動産の売却や購入していても、名寄帳にはその詳細が記載されません。
この理由は、名寄帳は毎年1月1日時点で、不動産の登記事項証明書に記載されている所有者を基準に作成されるためです。
名寄帳の取得の時期に注意して、漏れがないか確認しましょう。
不動産を売却・購入した事実を確認するためにも、登記簿謄本や売買契約書などを確認することをおすすめします。
6-2.名寄帳は不動産が所在する市区町村ごとに取得する
所在地が異なる市区町村で所有している不動産の情報は、名寄帳に記載されません。
この理由は、名寄帳の発行は、不動産の所在地である市区町村単位であるためです。
被相続人の所有不動産が不明な場合は、所有していた可能性のある所在地の市区町村すべての名寄帳を請求する必要があります。
被相続人が不動産投資をしていた場合や、県の境目にある山林を所有していた場合は、念のため不動産が所在している可能性のあるすべての市区町村に名寄帳を請求しましょう。
6-3.個人の名寄帳に法人名義の不動産は記載されない
個人名義の名寄帳に、法人名義で所有している不動産の情報は記載されません。
例えば、被相続人が会社を経営し、会社名義で不動産を所有していた場合は、個人名義の名寄帳には記載されないことになります。
仮に被相続人が法人名義で不動産を所有していた場合は、法人名義の名寄帳を取得申請する必要があります。
6-4.固定資産課税台帳や土地家屋名寄帳との違いはない
名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはありません。自治体によっては、名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。
しかし、固定資産税が課税されない不動産は、名寄帳には記載されても固定資産課税台帳には記載されない場合があります。
被相続人が所有するすべての不動産を把握するためには、名寄帳を取得しましょう。
7.名寄帳は固定資産税評価額の証明はできない!評価証明書の取得を
名寄帳は被相続人が所有していた不動産の情報を一覧にしたもので、固定資産税評価額を証明しているものではありません。
そのため、不動産の評価額を証明したい場合は、固定資産税評価証明書や公課証明書を取得しなくてはなりません。
なお、固定資産税評価証明書は、相続税申告や相続登記の際に添付を求められる書類です。名寄帳と共に取得しておくことをおすすめします。
7-1.相続税申告では固定資産税評価証明書の添付が必要
相続税申告では、固定資産税評価証明書の添付が必要です。
この理由は、土地や建物の相続税評価額を計算する際に、固定資産税評価額を用いるためです。

土地の相続税評価額は、国税庁が年に一度定める路線価の指標を用いる、「路線価方式」で計算します。
しかし、路線価が設定されていない「倍率地域」の場合は、固定資産税評価証明書に記載されている固定資産評価額に、評価倍率表で定められた倍率をかけた金額が評価額になるため、固定資産税評価証明書が必要となります。
不動産の相続税評価額の計算方法について、詳しくは「不動産(土地家屋)の相続税はいくら?│計算方法・手続き・相続税対策」をご覧ください。
7-2.相続登記でも固定資産税評価証明書の添付を求められる
相続登記の申請時にも、固定資産税評価証明書の添付を求められます。
この理由は、相続登記の際に納付する、登録免許税の税額が正しいことを証明するためです。

登録免許税の計算の基準となるのは、「固定資産評価証明書」の「価格」または「評価額」の欄に記載されている金額です。
登録免許税について、詳しくは「【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説」をご覧ください。
8.名寄帳を活用した相続財産の調査は専門家に依頼を
名寄帳は相続財産の調査をする際に役立ちますが、相続財産の調査はなるべく専門家に依頼をしましょう。
被相続人が所有していた財産があとから発覚した場合は、再度の遺産分割協議が必要となったり、相続税の修正申告が必要となったりする可能性があります。
相続手続きには期限が定められているものも多いため、相続財産の調査漏れを防ぐためにも専門家への依頼を検討しましょう。
相続財産の調査を依頼できる専門家は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの士業です。必要な相続手続きに合った専門家を選びましょう。

8-1.相続業務に特化したチェスターグループにご相談を
名寄帳を活用した相続財産の調査が必要な方は、チェスターグループまでご相談ください。
チェスターグループとは、相続税を専門とする税理士法人チェスターをはじめ、司法書士法人チェスター・行政書士法人チェスターなど、相続業務に特化した専門家集団です。
相続財産の調査のみならず、相続税申告や相続登記など、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
その他










































