葬儀の祭壇には種類がある?!飾り方や費用・選び方・宗教ごとの違いも解説
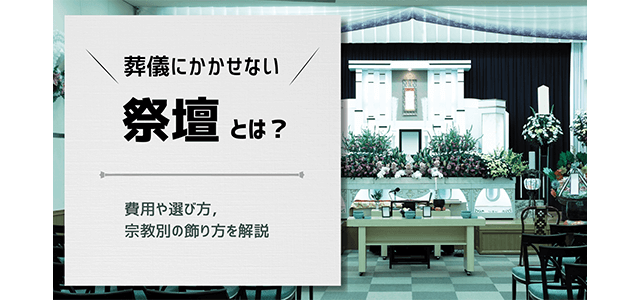
葬儀に参列したときに、最も目立つ位置に設置されているのが祭壇です。遺影が飾られていて、参列者が故人を偲ぶ場所でもあります。葬儀にかかせない祭壇ですが、実はさまざまな種類があり、費用も異なります。そこで、葬儀の祭壇の種類や費用、宗教別の祭壇の飾り方について解説します。
1.そもそも祭壇とは?
祭壇というと、葬儀会場の正面奥に飾られた壇のことを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
祭壇の意味を調べると、広辞苑には「祭祀を行う壇。供物をささげるために他から区別され、聖化された場所。普通には高い所に設けられ、諸宗教の儀礼の中心」と書かれています。つまり、葬儀の際に飾られるものだけでなく、寺院にあるご本尊を安置する壇や家庭に置かれた仏壇も祭壇の一種といえます。
葬儀にかかせない祭壇は、故人を偲ぶために設けられた壇です。中央に遺影を飾り、供花や供物で飾り付けられます。祭壇の手前には棺が置かれることが多く、焼香や献花の際には参列者が祭壇の前に立ち、故人にお別れをします。仏教式の葬儀では僧侶が祭壇に向かって座り、読経をするのが一般的です。
2.祭壇の種類
葬儀で使う祭壇は、主に白木祭壇・花祭壇の2種類があります。また、最近では故人の趣味や好みに合わせた、さまざまなタイプの祭壇を目にすることも増えました。それぞれの祭壇をご紹介します。
2-1.白木祭壇
白木祭壇とは、名前の通り、白木で作られた祭壇です。日本の葬儀でよく用いられる祭壇なので、葬儀に参列したことのある方は目にしているかもしれません。
形状は寺院の本堂に似ていて、荘厳な趣があります。屋根のように見える箇所は、棺を納める輿(こし)を表しています。これはかつて、日本で一般的だった野辺送りの習慣の名残です。野辺送りとは、親族や近所の方が葬列を組んで、亡くなった方の棺を納めた輿を火葬場まで運ぶ儀式のこと。野辺送りで故人を運んだ輿が、白木祭壇のデザインに残っているというわけです。
白木祭壇は主に仏教式の葬儀で使われます。また、葬儀会場の規模に合うものを選んで、葬儀社からレンタルするのが一般的です。
2-2.花祭壇
花祭壇は、祭壇全体を覆うように花を飾ったものです。花祭壇は白木祭壇よりも宗教色の薄い祭壇で、無宗教の葬儀・告別式でも用いられます。飾る花の種類によって、造花祭壇と生花祭壇の2種類があります。
2-2-1.造花祭壇
造花祭壇では、祭壇に飾る花がすべて造花になっています。枯れたり傷んだりしないので、扱いやすいのが特長です。造花といっても、最近では技術が進んでおり、ほとんど生花を使っているように見える祭壇ができあがります。
葬儀社によってはほとんどデザインが決まっている場合もありますが、故人が好きな花を入れたり色合いをアレンジしたりできることもあります。
2-2-2.生花祭壇
生花祭壇では、祭壇に飾る花がすべて生花になっています。生花を使うことで、葬儀会場は花の自然な香りで満たされるでしょう。
葬儀社ではおおまかな祭壇のデザインを準備していますが、故人の好きな花や色合い、モチーフなどの希望に沿って祭壇を作ることもできます。ただし、生花は季節によって手に入りやすさや価格が異なるため、場合によっては入手できなかったり高額になったりする可能性があります。花の種類や色を指定する場合には、注意しましょう。
2-3.オリジナル祭壇
オリジナル祭壇とは、多くの方がイメージするような、従来の祭壇とは異なる祭壇です。たとえば、祭壇に故人の作品や趣味のものを多く並べたり、スクリーンを設置して故人や家族の在りし日の姿を映し出したりと、アイデア次第で個性的な祭壇になります。
葬儀を行う場所によって使える設備や機材などは異なるので、オリジナル祭壇を希望している場合には、事前に確認しましょう。
3.祭壇にかかる費用の相場
祭壇にかかる費用は、祭壇の種類や規模、豪華さによって異なります。シンプルな祭壇は約10万円で準備できますが、大きくて豪華なものだと100万円以上する場合もあります。それを踏まえてではありますが、祭壇の費用相場は次の通りです。
- 白木祭壇:約10万円~
- 造花祭壇:約20万円~
- 生花祭壇:約30万円~
- オリジナル祭壇:約30万円~
また、多くの葬儀社では葬儀に関するプランを作っており、祭壇も基本的にプランに含まれます。しかし、プラン内の祭壇では若干質素になる可能性があるので、葬儀社の担当者に確認しましょう。
参考:葬儀費用控除してはいけないもの、控除できるもの|税理士法人チェスター
4.【宗教別】葬儀の祭壇の飾り方とお供え物
葬儀の祭壇は、宗教によって飾り方やお供え物が決まっていることがあります。一般的な例をご紹介します。
4-1.仏教式葬儀の祭壇
日本の葬儀として最も一般的なのは、仏教式の葬儀です。仏教の葬儀で用いられる祭壇の種類と飾り方、お供え物について解説します。
4-1-1.仏教式祭壇の飾り方
仏教式の葬儀では、白木祭壇を使うのが一般的です。祭壇の中心に遺影を置き、その周りにキクやユリなどの白い生花を飾ります。そして、祭壇の手前に棺を置きます。
4-1-2.仏教式祭壇へのお供え
仏教におけるお供え物は、「五供(ごくう)」と呼ばれるものが基本です。五供とは、「香・花・灯明・水・飲食」という5つのお供え物を表します。祭壇へのお供えも、五供に沿ったものを選びます。
「香・花・灯明・水・飲食」に対応するのは、それぞれ「線香・生花・ロウソク・水・果物や干菓子など」です。
飲食といっても生ものは避け、常温のままでも日持ちするものを選びます。肉や魚といった、殺生を連想するものも避けましょう。また、祭壇にお供えする花は、派手ではないものが適しています。バラやアザミなど棘のある花は、お供えには不向きです。
4-2.キリスト教式葬儀の祭壇
キリスト教式の葬儀は、教会によってルールが異なります。カトリック教会なら神父様に、プロテスタント教会なら牧師様に、事前に確認しておきましょう。
4-2-1.キリスト教式祭壇の飾り方
キリスト教式の葬儀の場合、教会で執り行われるのが一般的です。教会にはすでに常設の祭壇があるので、そこに飾り付けをします。
祭壇の両脇にある燭台にロウソクを灯し、手前に棺を置きます。祭壇の中央には遺影を置き、周囲を生花で飾ります。ほかの宗教に比べると、祭壇の飾り付けはシンプルです。
教会の祭壇にはあらかじめ十字架が掲げられていますが、葬儀会場でキリスト教式の葬儀を行う際も十字架は必須です。必ず準備します。
4-2-2.キリスト教式祭壇へのお供え
キリスト教では、とくにお供え物をするという考え方がほとんどありません。最近では、白い花の花束や花籠をお供えすることもあります。
4-3.神式葬儀の祭壇
神式葬儀では、仏教と同じく、白木の祭壇を使います。しかし、祭壇の飾り方やお供え物は仏教とは異なるので、しっかり確認しておきましょう。
4-3-1.神式祭壇の飾り方
神式祭壇は、白木で作られていて、神社の神殿を模した形をしています。神式の祭壇では、三種の神器のレプリカを飾ります。三種の神器とは、「八咫鏡(やたのかがみ)」「天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)」「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」です。
三種の神器は飾る場所が決まっています。鏡は祭壇上段の中央、剣と勾玉は祭壇の両脇の五色旗に吊るしましょう。遺影は鏡の1つ下の段の右側に置きます。
4-3-2.神式祭壇へのお供え
神道の祭壇へのお供えは、「神饌(しんせん)」や「幣帛(へいはく)」と呼ばれるものです。お供え物はすべて、白木で作られた台の上に三方を置き、その上に並べます。
神饌とは、神様に捧げる飲食物のこと。洗ったお米・御神酒・餅・魚介・海藻・菓子・果物・塩・水などを、神様に近い祭壇中央から順番にお供えします。
幣帛とは、神饌以外の神様へのお供え物のことを指します。かつては衣類や農耕具をお供えしていましたが、現在は絹や木綿、麻製の赤い織物をお供えするのが一般的です。
神道のお供え物には、ほかの宗教と異なる点があります。生花は仏教でもキリスト教でもお供え物として一般的ですが、神道ではお供えする習慣がありません。また、神式の祭壇には線香も使いません。
4-4.無宗教の告別式では祭壇はどうする?
無宗教の告別式の場合には、宗教色の薄い花祭壇を用いるのが一般的です。白色だけでなく、故人の好きだった花やデザインなどを取り入れて花祭壇を作る方もいます。葬儀社によっては、海や山、ハートなど希望の形を取り入れた祭壇を作れる可能性もあるので、打ち合わせの際に確認してみましょう。
最近では、無宗教の告別式を葬儀会場以外の場所で営むケースも増えています。たとえば、故人を偲ぶ会をホテルやレストランのパーティルームで行う場合には、祭壇自体を設置しないという選択も可能です。
5.祭壇の選び方
祭壇の種類によって費用が大きく異なるため、どのように祭壇を選んだらよいのかわからないという方も多いでしょう。祭壇の選び方は、主に次の3つを基準にするのがおすすめです。
5-1.宗旨宗派によって決める
葬儀社は宗旨宗派ごとの祭壇を準備しています。菩提寺がある場合には、その宗派にあった祭壇を選ぶのがおすすめです。葬儀社の担当者は、打ち合わせの際に写真やカタログなどを見ながら説明してくれるので、アドバイスを受けるとよいでしょう。
5-2.葬儀会場の規模に合わせて決める
祭壇のサイズは、葬儀会場の大きさに合わせて決めることをおすすめします。会場が大きいのに祭壇が小さいと、見栄えが悪くなる可能性があるからです。反対に、小規模な会場にも関わらず祭壇が大きいと、会場の大部分が祭壇で埋まってしまうこともあります。
祭壇はサイズが大きくなればなるほど、高価になる傾向にあります。このため、大きな会場で葬儀を執り行う場合には、祭壇の費用が高くなると考えておきましょう。
5-3.予算に合わせて決める
予算を先に決めて、それに合わせて祭壇を決めるのもよいでしょう。たとえば、花祭壇は使用する花の種類や量によって金額が変わってきます。故人の最期をしっかり見送りたいと思うあまり、希少な花やたくさんの花を使う祭壇にすると費用はぐっと高くなります。
予算を決めておけば、際限なく祭壇にお金を使うことを避けられるでしょう。
6.まとめ
葬儀における祭壇の種類や費用、宗教別の飾り方について解説しました。
祭壇は葬儀会場の最も目立つ場所に設置されるため、参列者の印象に残りやすいものです。このため、恥ずかしくない祭壇を選んで、故人をしっかり見送りたいというご家族は多いでしょう。しかし、祭壇は葬儀にかかる費用のなかでも高価です。予算と見栄えとのバランスを取って、しっかりと選ぶことが大切といえます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
その他






































