葬儀費用がないときの対処法とは?誰が払う?そもそも相場はいくら?
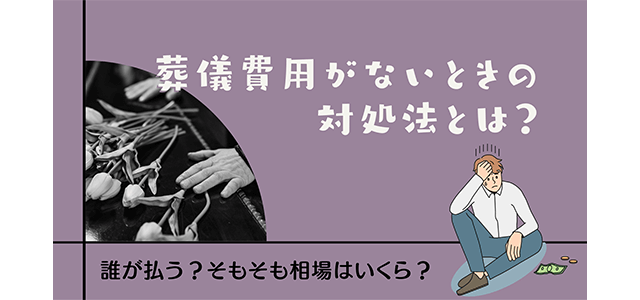
家族が亡くなった喪失感のなかで、葬儀の準備はバタバタと行われます。しっかりと最期の見送りをしたいと思うものの、打ち合わせを進めていくと、葬儀費用がかなり高額になってしまい、支払いができるかどうかが不安になったという話をよく聞きます。しかも、葬儀費用は急に必要になるものです。まとまったお金を急に準備するのは大変でしょう。また、そもそも葬儀費用は誰が支払うべきなのか、改めて聞かれると答えられない方が多いのではないでしょうか?そこで、葬儀費用の相場やすぐに出せるお金がないときの対処法、葬儀代を誰が負担すべきなのかについて解説します。
この記事の目次 [表示]
1.そもそも葬儀費用の平均はどのくらい?
経済産業省が発表している「特定サービス産業動態統計調査」によると、2021年に執り行われた葬儀の平均費用は約113万円でした。2019年は約134万円なので、コロナ禍になって葬儀が小規模に行われるようになった影響があるのかもしれません。
参照:経済産業省「特定サービス産業動態統計調査(15.葬儀業)」
多少縮小傾向になったとはいえ、葬儀費用の平均は100万円以上になっています。葬儀の規模や形式によって金額は変わってきますが、ある程度まとまった金額が必要になることは間違いありません。しかも、葬儀は故人が亡くなってから数日以内に行われます。このため、短期間に高額な支払いをする必要があるのです。
2.葬儀費用は誰が支払うもの?
そもそも、葬儀費用は誰が支払うべきものなのでしょうか?法律上、誰が葬儀費用を負担するかということは決まっていないため、家庭や親族の考え方によって答えは異なるでしょう。
一般的には、葬儀費用を負担するのは、次の3つのうちのいずれかになることが多い傾向にあります。
- 喪主が支払う
- 相続人になる人たちで出し合う
- 故人の財産のなかから出す
「喪主になったが、持ち合わせがないから葬儀費用を支払えない」と、不安に思っている方がいるかもしれませんが、もしかすると一人で負担する必要がない可能性もあります。悩んでいる場合は、葬儀費用は誰が出すのかについて、ほかの家族や親族と話し合うようにしましょう。
3.葬儀代を支払えない場合はどうする?
葬儀代が高額で払えなさそうだという場合には、葬儀自体の規模や形式を検討し直したり、支払いの方法を変更したりするのがおすすめです。具体的な例を4つご紹介します。
3―1.簡略化した葬儀を執り行う
参列者が多かったり、豪華な葬儀だったりすると、その分葬儀費用は高くなります。費用を抑えたいなら、葬儀を簡略化するとよいでしょう。故人の供養に必要なものと不要なものをしっかりと見極め、不要なサービスを省くと、費用を抑えることができるはずです。
また、最近では、従来よりも小規模な葬儀にして、アットホームな形式で見送る方も増えています。次の3つは、選択される方の多い小規模な葬儀です。
3―1―1.家族葬
家族葬とは、家族や親しい友人など少人数で執り行われる葬儀のことです。故人に特別な縁がある方たちのみで見送るため、従来の葬儀よりもゆっくりと故人を偲べる式になります。会場の規模が小さく、準備する料理も少なくなるため、葬儀費用は安くなることが多いでしょう。
3―1―2.一日葬
一日葬とは、お通夜をせずに葬儀・告別式だけを執り行う葬儀の形です。従来の葬儀では、故人が亡くなった当日、もしくは翌日の夜にお通夜を営みます。そして、お通夜の翌日に葬儀・告別式を終えたあと、そのまま火葬を執り行います。
一日葬ではお通夜を執り行わないため、斎場の使用料や通夜振る舞いの費用などが必要ありません。お通夜を営まないことで、金銭的にも肉体的にも負担が軽減されます。
3―1―3.直葬(火葬のみの葬儀)
直葬とは、火葬のみを執り行う葬儀のことです。お通夜や葬儀・告別式を執り行わず、家族や親しい友人など少人数で火葬場に集まって、故人とお別れをします。
直葬では、祭壇に飾る供花や参列者向けの料理などが必要ないため、一般的な葬儀よりも費用を抑えられます。
3―2.市民葬や区民葬を利用する
市民葬や区民葬とは、自治体が住民サービスの一環で行っている葬儀の形です。自治体は葬儀社と協定を結び、一般的な葬儀よりも費用を抑えたプランを提供しています。
市民葬・区民葬は、葬儀社に直接申し込みをするよりも費用が抑えられる分、プランに含まれるサービスは質素になる傾向があります。サービスを追加していくとそれなりの金額になることもあるため、しっかり比較検討して選ぶことが大切です。
申し込み方法は自治体によって異なり、自治体から申し込みをするか、直接提携している葬儀社に申し込みをするケースがあります。市民葬・区民葬を検討する場合には、故人の住所地の役所に問い合わせをしてみましょう。
3―3.クレジットカードで葬儀費用を支払う
家族が急逝した場合など、葬儀費用を支払うタイミングで手元に現金がないこともあるはずです。葬儀社によってはクレジットカードで支払えることもあるので、確認してみるとよいでしょう。
ただし、僧侶へのお布施や車代は、現金での手渡しが一般的です。お布施などの費用は、現金で準備しましょう。
3―4.葬儀費用は分割払いできる場合も
葬儀社によっては、葬儀費用を分割払いできる場合もあります。葬儀費用の分割払いのことを「葬儀ローン」とも呼びます。もし一括で支払う現金を持っていない場合には、分割払いを検討してみるのもよいでしょう。
ただし、葬儀ローンには利息がかかります。このため、分割払いにすると、総額では葬儀費用が高くなるので注意が必要です。
4.支給されるお金を葬儀費用に充てる
人が亡くなったときに、給付されるお金があります。支給されるお金には、亡くなったあとすぐに支払われるものと、葬儀のあとに支払われるものがあるので注意が必要です。
どの給付金も、勝手に給付されるのではなく、申請しなければもらえません。支給されるお金をしっかり受け取って、葬儀費用に充てることも検討しましょう。
4―1.健康保険の給付金
健康保険に加入している場合、被保険者や被扶養者が亡くなったときに、埋葬料として5万円の支給を受けることができます。加入していた健康保険組合に、問い合わせて申請しましょう。亡くなった方が会社員だった場合は、会社の人事に相談すると代わりに手続きをしてくれることもあります。
参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
国民健康保険でも、加入者が亡くなったあと葬祭費として数万円の支給を受けられます。故人の国民健康保険証と葬儀の会葬礼状や葬儀費用がわかる領収書などを持参して、所在地の役所で手続きをしましょう。
自治体によって金額は異なりますが、5~7万円程度が一般的です。たとえば、東京都練馬区では、7万円が支給されます。葬儀が終了してから2年以内に申請しなければもらえないお金なので、忘れないようにしましょう。
参照:練馬区「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」
4―2.国民年金の死亡一時金
死亡一時金とは、亡くなった日の前日までに第一号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めた方のなかで、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらっていない方を対象に支給されるものです。保険料を納めた月数に応じて、12~32万円受け取ることができます。
受け取れるのは、亡くなった方と生計をともにしていた遺族です。年金を受け取る年齢よりも若いうちに亡くなってしまった場合には、死亡一時金を受け取れる可能性が高いので、確認しておくことをおすすめします。
申請は、亡くなった日の翌日から2年以内に行う必要があります。
参照:日本年金機構「死亡一時金」
参考:死亡後の年金のほか遺族がもらえるお金と必要な手続き-司法書士が回答
4―3.葬祭扶助制度
故人や遺族が生活保護を受けていて、葬儀費用を負担できない場合には、葬祭扶助制度を利用できます。葬祭扶助制度は、最低限の葬儀ができるように自治体が費用を負担してくれる制度です。利用する場合には、申請者の住民票がある自治体の役所で手続きをしましょう。
葬祭扶助制度で執り行える葬儀は原則的に直葬で、遺体搬送・安置・火葬を行えるだけの費用が支給されます。
5.残された家族が葬儀費用で困らないようにやっておきたいこと
ご自分に万が一のことがあったとき、残された家族が葬儀費用に困らないように、生前のうちにやっておきたい対策があります。ご自身の葬儀代が心配な方は、次の2つを検討してみてはいかがでしょうか?
5―1.生命保険に入る
亡くなったときに遺族が受け取れる生命保険に入っておくと、保険金を葬儀費用に充てられます。生命保険の保険金は、健康保険や国民年金の給付金よりも比較的早く受け取ることが可能です。また、相続財産にはならないため、葬儀費用として使えます。
5―2.冠婚葬祭互助会を利用する
冠婚葬祭互助会とは、葬儀に備えて生前のうちから毎月一定の金額を積み立てるシステムです。冠婚葬祭互助会は、もともとまとまった金額が必要になる結婚式や葬儀に備えるものでした。しかし、最近では、結婚式よりも葬儀のための積み立てシステムとして一般的です。
互助会では、生前のうちに葬儀社を選び、毎月お金を積み立てていきます。そして、万が一のことがあったときに、葬儀費用から積み立てた金額を差し引いて支払いをするというものです。積み立てた金額の分、支払う金額が少なくて済むだけでなく、会員向けの特典や割引を受けられる場合もあります。
冠婚葬祭互助会に入っていることを家族が知らないと、万が一の際に別の葬儀社を利用してしまう可能性もあります。提携している葬儀社でしかサービスは受けられないので、必ず家族に伝えておきましょう。
6.まとめ
葬儀費用がない場合に検討すべきことをご紹介しました。親や家族が亡くなったとき、葬儀費用を誰がどのように負担するのか、心配になる方は多いでしょう。法律上葬儀費用を負担すべき人は決まっていないため、家族や親族の考え方によって、「①故人の財産から出す②喪主が全額負担する③子どもなど相続人全員で負担する」という3つのいずれかを選択することが多いようです。
葬儀費用が足りない場合には、葬儀を簡略化したりカードやローンでの支払いをしたりすることを検討しましょう。カードやローンを使っても、葬儀費用の総額が安くなるわけではありません。葬儀費用を抑えられるように考えたうえで、もらえる給付金の手続きは忘れずに行うようにしましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
その他






































