子供名義の口座に贈与税がかかるケース|節税対策も解説
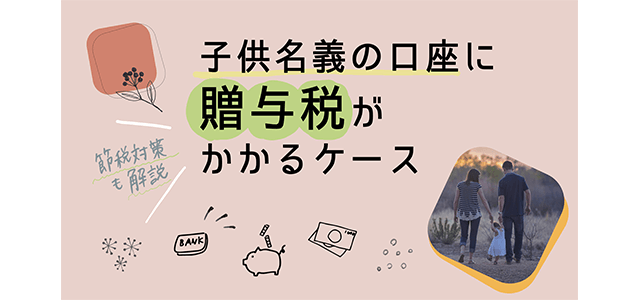
子ども名義の口座にお金を振り込んだときや、口座を子ども本人に渡すときには贈与税が発生するケースがあります。税務調査で課税されないよう対策をおこなうことで、子どもへより多くの財産を残しやすくなります。
子ども名義の口座に入っている預金に贈与税が課される具体的なケースから、それぞれの対策を見ていきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.子ども名義の預金口座に贈与税がかかる5つの具体例と対策
子ども名義の預金口座に贈与税がかかるケースは、以下の5つが考えられます。
【子供名義の口座に贈与税がかかる具体例】
- 年間110万円超の入金
- 教育資金として1500万円超の入金
- 生活費以外の仕送りとして入金
- 住宅購入資金のために500万円(一定の場合は1,000万円)超の入金
- 子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金
上記5つのケースそれぞれに対策を立てることにより、贈与税を抑えられます。なお贈与税が発生した際の、税率と控除額は以下のとおりです。誰から誰への贈与かで、税率が異なります。
【特例贈与に当てはまる場合(特例税率)】※
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
※直系尊属からの贈与で、受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えている場合に限ります
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
【特例贈与に当てはまらない場合(一般税率)】※
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
※直系尊属からの贈与で受贈者が贈与のあった年の1月1日時点で成人を迎えていない場合のほか、夫婦間、兄弟間の贈与など
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
1-1.年間110万円超の入金|贈与の証明を残す
年間110万円を超える贈与をした場合には、贈与税が発生します。
例えば、未成年の子ども名義の口座に500万円を入金して贈与したとしましょう。この場合の税率は、一般税率が適用されるため贈与税の金額は以下のとおりです。
なお、基礎控除額である年間110万円以下の贈与をおこなっている場合は、こうした贈与税はかかりません。
| 贈与税の基礎控除 | 年間110万円 |
|---|
参考:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」
例えば子どものお小遣いを親が預かり複数年分をまとめて渡すと、年間110万円を超過していた、あるいは預かっている額がわからなくなったといったリスクがあります。子どものお小遣いを保管しておく場合、小分けにして年間110万円を超えない範囲で子ども名義の口座へ入金しましょう。
ただし、相続税の税務調査において、贈与契約に双方の合意が確認できない場合など、贈与が成立していないと判断されるケースがあります。その場合、今まで貯めた額を贈与者受贈者の相続財産と判断され課税されてしまうため、税務署に対する証明が必要です。
税務署から説明を求められた際にきちんと証明できるよう、契約書や口座の入金記録を残しておきましょう。贈与契約は口頭でも成立しますが、毎年贈与契約書を作成しておくことにより、暦年贈与について双方の合意があったことの証明になります。
また、実際に贈与が履行されたことを証明するために、手渡しではなく口座への振込を選択し、入金記録を残しておきましょう。
1-1-1.お年玉や児童手当の入金も110万円を超えると贈与税が発生するケースも
子ども名義の口座に一度に高額のお年玉を入金した場合や、何年かにわたって貯めていた児童手当をまとめて入金した場合も、贈与税が発生することがあります。例えばお年玉を複数人から受け取り、合計額が基礎控除額の110万円を超える場合は、贈与税が発生します。
また、児童手当は児童を養育している者に支給されるため、本来は親の資産です。そのため、児童手当として親名義の口座に入金した分は親の資産ですが、子どもに渡す目的で入金しているのであれば贈与とみなされます。
お年玉や児童手当を子ども名義の口座に預け入れる場合にも、年間110万円以下となるように意識することが大切です。
| 名目 | 概要 | 留意点 |
|---|---|---|
| お年玉 | 原則、非課税 | 合計額が基礎控除額の年間110万円を超える場合は課税対象 |
| 児童手当 | 原則、親の資産 | 子どもに渡す目的の場合は課税対象 |
1-2.教育資金として1500万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける
教育資金の贈与について、教育資金の一括贈与の非課税の適用を受ける場合は、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に提出するなど所要の手続が必要で、単に子や孫の預貯金口座に入金しただけでは非課税の適用を受けることはできず、暦年課税贈与の対象となります。
教育資金の非課税措置は、30歳未満の子どもに適用されるため、原則として受贈者である子どもが30歳を迎えるまでに教育資金を使い切らないと、残額に贈与税がかかるため注意しましょう。
また、教育資金の非課税措置を利用する場合は、その金銭が教育目的で使われたと証明できる領収証が必要です。
参考:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
教育資金には次のようなものが含まれます。
【教育資金に含まれるもの】
- 入学費・授業料
- 教材代・文具費用
- 通学の交通費
- 修学旅行費
- 塾・各種教室などの月謝
ただし、学校以外に支払った教育資金の非課税限度額は500万円です。
教育資金にかかる贈与税の非課税措置を受けるためには、口座開設から入金までの間に、金融機関を経由して『教育資金非課税申告書』を税務署に提出しなくてはなりません。
また、口座から教育資金を支払った場合、支払いの事実を証明した明細や領収証を金融機関へ提出しましょう。
1-3.生活費以外の仕送りとして入金|生活費の援助であることを明確にする
親から子どもへ生活費として仕送りをする場合には、年間で110万円を超えたとしても生活費として費消していれば贈与税はかかりません。しかし、生活費以外の目的で子ども名義の口座にお金を入れると、仕送りとみなされず贈与税が発生することがあります。なお親が生活費として仕送りした現金を、子どもが貯金や投資に充てていた場合も同様です。
参考:e-Gov法令検索「相続税法第21条の3」
例えば、親が子どもに一度に150万円の仕送りをしたとします。親が生活費に充ててほしいと思っていても、子どもが仕送りをすべて投資に回した場合、贈与と判断される可能性があります。
この場合仕送り額は150万円のため、基礎控除額の110万円を超える40万円に贈与税がかかる可能性があります。
1-4.住宅購入資金のために500万円超の入金|住宅取得資金として特例を受ける
『住宅取得等資金の非課税の特例』では、2026年12月31日までに直系尊属から住宅取得資金の贈与があった場合に、一定限度額まで贈与税が非課税になります。ただし、以下の非課税枠を上回る入金があった場合は、贈与税がかかります。
| 住宅の区分 | 非課税枠 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
例えば成人した子どもが省エネ基準を満たさない家を購入する場合、非課税枠は500万円です。これに対し1000万円を贈与した場合、贈与税は以下のとおりとなります。
※住宅取得等資金の非課税の特例は、暦年贈与との併用が可能です。
住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告の際に決められた書類の用意が必要です。
- 登記事項証明書
- 売買契約書
- 贈与税申告書
- 受贈者の戸籍謄本、または贈与者との関係が証明できる書類
- 源泉徴収票、または前年分の所得金額が証明できる書類
なお申告時に必要となる書類はケースによって異なるため、注意しましょう。
参考:国税庁「住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分」
非課税措置適用後の贈与税額が0円であっても、贈与税の申告手続が必要です。特例を適用するためには税務署に申告書の提出を行わなければなりません。申告しないと、基礎控除額を超える全額に贈与税がかかることもありうるため、注意が必要です。
住宅資金における贈与税の特例を詳しく知りたい人は、ぜひ以下の記事もご覧ください。
参考:【親の支援で住宅購入】1,000万円まで非課税になる特例とは?
1-5.子どもの結婚・子育て資金として1000万円超の入金|非課税枠内に抑えて特例措置を受ける
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の適用を受ける場合は、結婚・子育て資金口座の開設等を行った上で、結婚・子育て資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に提出するなど所要の手続が必要で、単に子や孫の預貯金口座に入金しただけでは非課税の適用を受けることはできず、暦年課税贈与の対象となります。
『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』は、18歳以上50歳未満の子ども(または孫など)に対し2027年3月31日まで適用される制度です。
贈与した金銭が、結婚や子育て資金として使われたことが証明可能な記録も必要です。口座から支払った場合は、支払いの事実を証明した領収証を金融機関に提出する必要があります。
このように正しい手続で制度を利用しないと、1000万円の非課税枠を適用できません。
2.子ども名義の口座で贈与する際のポイント3つ
子ども名義の口座へコツコツと貯めたお金は、少しでも多く残せるのが理想です。そのためにも、贈与税を発生させないための対策が必要になります。
子ども名義の口座に贈与する際のポイント3つ
- 贈与であることを子どもに認識させる
- 贈与契約書を作成する
- 子ども本人に口座管理をさせる
2-1.贈与であることを子どもに認識させる|贈与として成立するように
子ども名義の口座に贈与をする場合は、贈与について子どもに認識してもらいましょう。民法上、贈与が成立するためには、贈与を受ける人が贈与について認識し承諾する必要があります。贈与として成立していなければ、子ども名義の口座は親が亡くなった場合に親の遺産(名義預金)と判断され、相続税の対象になってしまいます。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
引用:e-Gov法令検索「民法第549条」
未成年者の場合は親権者の同意のみで問題ありません。ただし子どもが成人している場合は、親子間で贈与契約をしているという共通認識が必要です。親が一方的に子ども名義の口座を作り、子どもに内緒でお金を入金している場合は贈与として成立しません。
子どもが成人するまでは問題ありませんが、成人した子どもにはきちんと贈与の存在を伝えておきましょう。一人暮らしするまでや結婚するまでの間、本人に内緒で口座へ入金し続けている場合は要注意です。
2-2.贈与契約書を作成する|贈与の証明と入金の把握
親子間であっても、贈与契約書を作成しておきましょう。贈与契約書は親子が双方贈与に同意した証拠となるだけでなく、実際にお金がどのように移動したかを把握する書類にもなります。
贈与契約書があれば、万が一税務調査が入ったときにも贈与の事実を証明できます。こうした物的な証拠がないと、正しく基礎控除額内で贈与していても贈与とみなされないリスクがあります。
贈与契約書は、税務調査に備えるための大切な書類であるため、必ず作成して大切に保管しておきましょう。贈与契約書の書き方は、以下の記事をご覧ください。
参考:【雛形つき】贈与契約書とは?書き方・生前贈与の注意点を解説!
2-3.子ども本人に口座管理をさせる|名義預金ではないことの証明
子どもの将来のために積み立てをおこなう場合、口座管理を本人に任せましょう。なぜなら、預金通帳やカードを親が管理していると、いわゆる名義預金とみなされてしまうからです。名義預金とは、口座名義人と実際に財産の所有者が異なる預金のことをいいます。
名義預金とみなされた場合、その口座は子どものものとして扱われません。通帳やカードを子どもに渡した時点で贈与が成立し、贈与税が課せられます。名義預金とみなされないために、口座の管理は子どもに移しておくことが必要です。住所変更の必要があれば行い印鑑やカード、通帳などもすべて子どもに渡し、管理を任せましょう。
3.子ども名義の口座に関する3つの注意点
子ども名義の口座を管理するときには、以下3つの点に注意しましょう。
子ども名義の口座を管理する際の注意点
- 成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要
- 10年以上の利用がないと休眠口座になる
- 口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意
「子どものための預金管理のためにとりあえず口座を作った」だけでは、想定外のトラブルが起こりかねません。場合によっては預金の引き出しに手間取ったり、予想外の贈与税が発生したりする可能性があります。混乱を避けるためにも、対応策を確認しておきましょう。
3-1.成人した子どもの口座を操作する場合は委任状が必要
成人後の子どもの口座から、親が引き出しや振込をおこなう場合には委任状が必要です。
子どもが未成年のうちは、親が法定代理人の立場で口座の管理ができますが、成人後に口座の管理を許されるのは原則として本人のみであるためです。
3-2.10年以上の利用がないと休眠口座になる
子ども名義の口座を作っても、10年以上取引実績がないと休眠口座となってしまいます。休眠口座になってしまうと、払い戻しは可能であるものの窓口での手続が必要となったり金融機関側の手続に時間がかかったりします。そのため入金する予定がなくても、定期的に預金を出し入れして取引実績を作っておくなどの対応が必要です。
定期的に積み立てていれば心配ありませんが、子どもの幼少期にのみ利用し、その後は放置している場合は休眠口座となるため注意しましょう。
3-3.口座を介さない贈与は申告・納税漏れに注意
口座を介さず手渡しで贈与した場合、贈与税の申告や納税漏れに注意しましょう。基礎控除額や一定の非課税限度額を超える場合は、たとえ少額であっても、贈与税の申告納税が必要です。手渡しで贈与する場合、受贈者の口座に多額の現金が入金されたときや、贈与者が亡くなったときに税務署に指摘される可能性があります。
贈与者の相続が開始し相続税の調査において、相続開始前の財産から行き先のわからない出金がある場合、税務署はさまざまな方法でお金の行き先を突き止めます。贈与の成立を証明するものがなにもなければ、贈与者の相続財産と認定され相続財産に加算される可能性があります。
4.子ども名義の口座開設に必要なもの
子ども名義の口座を開設する際には、以下のものが必要です。
子ども名義の口座開設に必要なもの
- 親子それぞれの本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証など)
- 子どもの印鑑
- 金融機関ごとの追加の書類
本人確認書類は、親であればマイナンバーカードや運転免許証、子どもであればマイナンバーカードや健康保険証、住民票の写しなどが基本です。
子どもの印鑑は、下の名前が印字されたものを届けておくことにより、親の届出印との混同を防げます。追加の書類は銀行ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
5.贈与税の節税は子どもの将来にゆとりをもたせる
子ども名義の口座に入金する場合、基礎控除額や特例措置を確認しておきましょう。適切に対応すれば、子どもの将来にゆとりをもたせるために入金した預金口座にかかる贈与税を、うまく抑えられるはずです。
ただし、贈与税がかかるケースをすべて想定し、非課税制度のような対応策を正しく理解するには多大な労力を要する可能性があります。
税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。子ども名義の預金口座に贈与税をかけないためのサポートを受けたい人は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































