自己信託のメリットや注意点を解説。公正証書で信託内容を明らかに

自己信託は、利益を受ける人のために、自分で自分に財産の管理や運用を任せることです。活用範囲は幅広く、生前贈与の名義預金対策や、企業の事業承継などに用いられます。2007年より認められるようになった自己信託の活用法を見ていきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.自己信託とは
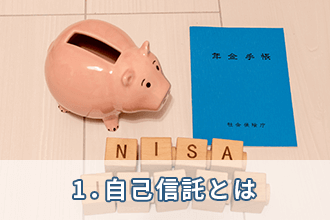
自己信託は個人も法人もさまざまなシーンで活用できる仕組みです。具体的な事例をより深く理解するために、まずは自己信託について確認します。
1-1.信託は財産の管理などを受託者に任せること
『委託者』がある財産を他の財産と切り離し、『受益者』のためになる管理や運用を、『受託者』へ任せることを『信託』と言います。
- 委託者:信託を依頼する人で、財産を誰のためにどのように使うかを決定する
- 受託者:受益者のために財産を管理・運用し、利益を渡す人
- 受益者:委託者が決定した信託財産による利益を受け取る人
信託は『商事信託』『民事信託』の2種類に分類可能です。商事信託は信託会社や信託銀行を受益者とします。信託会社や信託銀行は営利目的で財産の管理・運用を行っているため『信託報酬』が必要です。
民事信託では、家族や親族をはじめとする信頼できる人に財産を任せ、受託者として管理・運用してもらいます。
1-2.自己信託の場合は委託者=受託者=自分
信託の中でも、委託者と受託者がどちらも『自分』なのが自己信託です。通常の信託であれば、委託者と受託者の間で信託契約を結びます。しかし委託者も受託者も自分のため、単独の『意思表示』のみで成立するのが特徴です。
どの財産を信託財産として切り離し、誰のためにどのように管理・運用するのかを、第三者にも分かりやすく明らかにすればよいため『信託宣言』とも呼ばれます。
参考:自己信託|金融庁
1-2-1.受益者の設定が必須
特定の目的を達成するための、『目的信託』という方法もあります。ただし自己信託において目的信託は認められていません。自己信託では必ず受益者を設定します。
ただし受益者の設定だけして、利益を渡さないケースが発生するかもしれません。実質的な目的信託になるのを避けるため、受益者へ1年以内に利益を受け取る権利『受益権』が渡されないときは、信託が終了する決まりです。
2.自己信託の倒産隔離機能の注意点
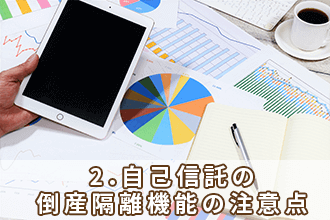
中には『倒産隔離機能』を目的に自己信託を使いたいと考える人もいるかもしれません。ただし意思表示のみで成り立つ自己信託では、受託者にほかの誰かを定める場合と比較して、簡単に強制執行できる仕組みになっている点に要注意です。
2-1.倒産隔離機能とは
信託財産は受託者の名義となります。そのため信託が成立すると、委託者が破産や倒産などで債務を返済できなくなったとしても、信託財産には影響が及びません。
委託者の本人名義で所有しているその他の財産が差し押さえられても、信託財産は守られます。強制執行・仮差し押さえ・仮処分・担保権の実行や競売・国税滞納処分のどれもできません。
このように債権者と関係のない信託が守られる働きを『倒産隔離機能』と呼びます。
2-2.債権者を害する目的の信託は取り消し対象
倒産隔離機能は自己信託にもあります。そのため自己信託で財産の一部を信託財産として扱えば、信託財産の範囲は債権者に強制執行や仮処分などで財産を回収されるのを避けられそうです。
借入金を返済できない事態に陥る前に、その債務と関わりのない自己信託をしている場合には、該当する信託財産は守られます。しかし自己信託によって債権者が債務を回収できなくなると分かって実施する自己信託は別です。
自己信託は自分1人で宣言できるため、返済が難しくなった段階で財産保護のために自己信託を選択するケースが想定されます。それでは債権者の利益が守られません。
債権者の強制執行を避けるために自己信託を悪用していると認められる場合には、信託財産も強制執行の対象となります。
3.家族のための活用方法

自己信託の仕組みは家族のためにも活用できる方法です。特に生前贈与をするときの名義預金対策や、障害者や高齢者のための信託に役立てられます。
3-1.名義預金の対策
生前贈与をするときに問題になりがちなのが『名義預金』です。相続税対策も兼ねて子どもや孫へ財産を少しずつ贈与したいけれど、まだ幼く、お金の管理能力が不十分なケースもあります。
そのような場合、財産の贈与者である父母や祖父母が、子どもや孫名義の口座を作り財産を管理するケースがあります。贈与は『する人』と『される人』の間に同意があって成立するため、同意がない状態では名義預金になってしまいます。
名義預金は贈与が成立していないとみなされ、父母や祖父母の死後には相続税の対象となります。
自己信託で生前贈与する分の財産を切り離し、受益者を子どもや孫に設定すると『みなし贈与』とされます。財産の管理や運用は自分で続けつつ、名義預金とは扱われずに贈与できる方法です。
3-2.福祉型の自己信託
自己信託によるみなし贈与は、障害者や高齢者のための『福祉型信託』としても役立てられます。決まった信託の形式はなく、個々の事情に合わせて内容を決定します。
例えば障害のある子どものために自己信託すれば、親が生きている間は引き続き財産を管理可能です。親の死後は信頼できる人や法人へ、管理を引き継いでもらうこともできます。
子どもへ財産を残すためにと贈与し名義変更すると、成年後見人が管理するようになるでしょう。信託銀行へ預けられた財産は、本人に特別な事情がなければ使えません。
その結果ほとんどが残り、障害者の子どもに兄弟姉妹がいなければ、最終的には国庫に帰属してしまいます。自己信託であれば、このような事態も避けやすいはずです。
4.事業承継での活用方法
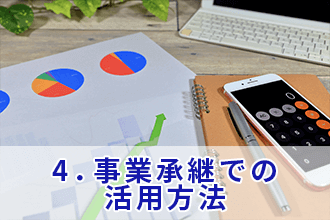
事業承継は会社の株式を経営者から後継者へ譲ることで成立します。この株式譲渡に自己信託を活用すると、確実かつスムーズな事業承継が可能です。加えて節税や、後継者の自覚を促すことにも使えます。
4-1.自社株=信託財産、受益者=後継者とする
自己信託を事業承継に用いる際には、自社株を信託財産に、受益者を後継者に設定しましょう。株式を一定数以上保有していると、会社の経営権があるとみなされます。
そのため自社株を信託財産に設定し、経営者の死亡とともに信託が終わるようにすれば、将来は確実に経営権が後継者のものとなる仕組みです。このとき委託者と受託者はともに経営者が担います。
すると経営者は会社の経営権を保持したまま、事業承継を見据えた対策が可能です。生涯現役で仕事に取り組んだ場合でも、相続の影響を事業運営に及ぼさずに済みます。
なお、中小企業経営者の事業承継に対しては、別途、事業承継税制による相続税・贈与税の猶予・免除の特例制度があるので、注意が必要です。
4-2.相続税軽減の可能性などメリットあり
株式を贈与すれば贈与税がかかります。自己信託によるみなし贈与も同様です。ただし株価が低いタイミングで譲渡できれば、将来相続する時点での相続税より税額を抑えられるかもしれません。
今後株価が上がると予想される場合には、税負担の軽減のために有効な方法です。また後継者の自覚を促すのにも役立ちます。自己信託は後継者の指名と同じ働きです。
早いタイミングで自覚や責任感を持ち始められるでしょう。名義預金同様、経営者が基礎控除110万円の範囲内で株式の贈与を繰り返していると、子どもは知らない間に株主になっている状態かもしれません。
これでは実質的な贈与が発生していないと考えられ、相続の段階で問題になる可能性があります。名義株を避けるためにも役立てられる仕組みです。
『信託』を活用した事業承継の手法はほかにもあります。詳しい解説は下記をご覧ください。
5.その他の商業的な活用方法
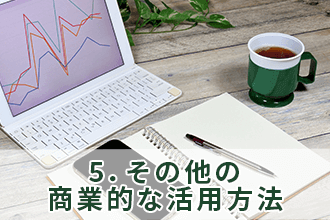
法人が委託者兼受託者になり、自己信託を商業上で活用するケースもあります。事業を分社化しなくても独立させられるため、リスクを抑えつつ新規事業に挑戦しやすい方法です。
5-1.スピーディーな事業展開の実現
新規事業を展開するときには、子会社を設立したり分社化したりする方法がよく取られています。加えて事業部門を自己信託する方法でも、資金調達が可能です。
信託財産にしている事業の収益や資産の受益権を、投資家に購入してもらい資金調達します。自己信託により事業を会社から独立させているからこそできる方法です。
新規事業を既存事業と切り離すことで、万が一新規事業が立ち行かなくなったときには、リスクを最小限に抑えられます。
6.自己信託はどのように成立させるのか

委託者と受託者が同一人物の自己信託は、信託銀行を活用しなくとも1人で成立させられます。ただし勝手に宣言するだけで自己信託できるわけではありません。公正証書の作成により、信託内容の効果が及び始めます。
6-1.自己信託公正証書を作成する
自己信託の成立には『自己信託公正証書』の作成が必要です。公正証書は公証人法に基づいて、公証人が作成する公文書であり、証明力や執行力があります。
公正証書を作り自己信託するには、公証役場へ行き作成しなければいけません。1人で成立させられる信託だからこそ、成立のための要件として公正証書が必須です。
6-1-1.自己信託公正証書の内容
自己信託公正証書には、必ず盛り込まなければいけない内容が下記の通り決まっています。どのような内容の信託なのか、誰が誰のために行う信託なのかが明確に分かる内容になっていなければいけません。
- 信託の目的
- 信託する財産とその管理方法
- 自己信託する人の情報
- 受益者の情報
このほかに必要に応じて入れられる内容もあります。例えば『条件』や『期限』に関する決まり、信託の『終了事由』、信託の『条項』などです。
6-2.信託財産となったことを登記する
信託財産の中には、登記が必要なものもあります。例えば不動産や債権など登記によって第三者へ対抗できる財産です。このとき必要な登記は『信託登記』のみです。
自己信託では委託者と受託者が同一人物のため、信託財産の移転が行われているわけではありません。委託者兼受託者のもとで、信託財産として区別されるだけです。そのため所有権移転登記はしません。
また登録によって第三者への対抗要件を満たす財産は、自己信託の登録が必要です。例えば特許権・意匠権・商標権の通常実施権・通常使用権は、特許庁の登録原簿へ登録しなければいけません。
6-3.信託業法の自己信託登録が必要なケース
自己信託では『自己信託登録』が必要な場合もあります。例えば下記に該当するケースです。
- 1回で受益者が『50人』以上になる
- 自己信託を繰り返し行い受益者が多数になる
- 受益権の分割が禁止されていない
例えば企業が委託者兼受託者となり、事業の収益・資産を信託財産とする受益権を投資家へ販売したとします。
受益権を分割して販売すると、50人以上の投資家が受益者となるケースもあるでしょう。この場合、自己信託登録をしなければいけません。
7.自己信託は自分で財産を管理できる制度
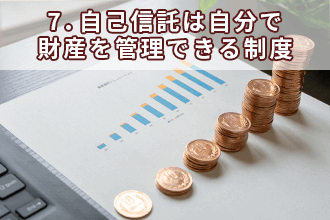
委託者と受託者が同一人物の自己信託は、財産の一部を信託財産として切り離し、管理できる制度です。生前贈与や企業の事業承継・新規事業の立ち上げなど、幅広く活用できます。
2007年から使えるようになった新しい制度で、これから利用されるケースが増えていくでしょう。複雑な部分もあるため、期待した効力を得るには、専門家へ相談しながら進めるのがおすすめです。
税金が関わる部分については『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続対策編






































