不動産を用いた相続税対策の具体的な方法と、メリット、デメリット、失敗例まで解説
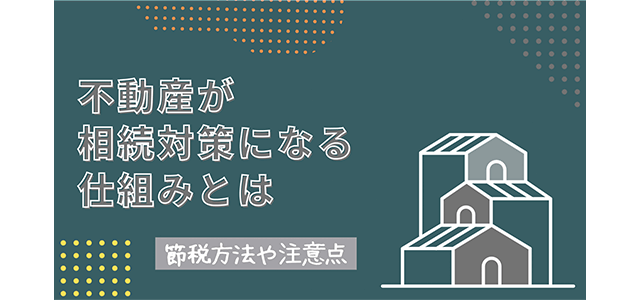
「相続税対策には不動産が有効」という話を聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、なぜそうなのかをきちんと理解している方は、意外と少ないものです。不動産ならどんな物件でも相続税対策になるわけではありません。場合によっては、不動産を所有していても相続税対策の効果がほとんどなかったり、逆にトラブルの種になったりすることもあるのです。
不動産による効果的な相続税対策のためには、なぜ不動産が相続税対策に有効なのかという基本を理解した上で、適切な不動産を購入・保有し、正しく管理していくことが肝心です。本記事では、相続税対策としての不動産について、基本からトラブル対策まで解説していきます。
この記事の目次 [表示]
- 1 1.不動産を用いた相続税対策の要点
- 2 2.土地の相続税評価額の求め方と価格水準
- 3 3.家屋の相続税評価額の求め方と価格水準
- 4 4.相続税対策として不動産を用いる方法
- 5 5.不動産賃貸経営の法人化による相続税対策
- 6 6.不動産を用いた相続税対策の失敗例5タイプと防止策
- 7 7.まとめ:相続税対策に不動産を活用したい場合は、必ず専門家への相談を
1.不動産を用いた相続税対策の要点
最初に、なぜ不動産が相続税対策になるのか、その理由のポイントを確認します。
1-1.相続税の課税の基準となる「相続税評価額」
相続税では、相続財産(課税対象になる遺産)ごとの「相続税評価額」(以下「評価額」といいます)を算出し、その合計額に基づいて税額を算定します。
相続財産には、現預金のほかに、株式・債券などの有価証券、不動産(土地・家屋)、貴金属、書画骨董、自動車など様々な種類がありますが、その種類ごとに評価額を求めるためのルールが定められています。
例えば、現金はもっともわかりやすく、額面金額=評価額となります。1億円の現金の評価額=1億円になるということです。預金も基本的には同様に口座残高=評価額となりますが、相続発生時点でまだ受け取っていない預金利息があれば、その分も加算されます。
では、不動産の場合はどうかといえば、下記のような基準を用いて評価額を求めるのが基本的な考え方です。
| 種類 | 詳細 | 基準 |
|---|---|---|
| 土地 | 相続税路線価が設定されている地域 | 相続税路線価 |
| 相続税路線価が定められていない地域 | 固定資産税評価額と評価倍率 | |
| 家屋 | 固定資産税評価額 |
1-2.不動産の相続税評価額は実勢価格よりも低いことが一般的
不動産が相続税対策として用いられる理由の1つ目は、一般的に、不動産では評価額が「実勢価格」(資産価値)よりも低くなることです。
「いま実際にその不動産を販売したら、いくらで売れるか」を、過去の取引事例などに基づいて推定した相場価格は、「実勢価格」と呼ばれます。不動産の資産価値を考える際は、「売ったらいくらになるのか」という実勢価格に基づいて考える必要があります。
一方、相続税評価額は、あくまで課税のためのルールに基づいて決められるもので、不動産が売買される際の価格とは、直接対応しているわけではありません。そして、路線価や固定資産税評価額に基づく相続税評価額は、一般的には実勢価格よりも低い水準となっています。
例えば、1億円の現金を持つ人が亡くなって相続となる場合、現金の評価額は1億円であり、その金額を基準に相続税が計算されます。一方、そのお金で実勢価格1億円の土地を購入して相続する場合、相続税路線価に基づく評価額は通常1億円よりも低く、例えば8,000万円となることがあります。結果として、課税される相続税も少なくなります。
もちろん、相続されたからといって、土地の実勢価格(=資産価値)に変化が生じるわけではありません。つまり、現金や預金を相続するのと比べて、同じ価値の資産をより少ない税負担で相続できることになります。
1-3.不動産を他人に賃貸すると、さらに評価額が下がる
不動産が相続税対策として用いられる理由の2つ目は、上記に加えて、土地や建物を人に賃貸している場合は、さらに相続税評価額を下げることができるためです。
これは資産を現預金で保有している人だけではなく、もともと土地を所有している人の場合にも有効です。その土地を他人に賃貸するか、賃貸住宅を建てて賃貸するなどすれば、より大きく評価額を下げることができます。
一方で、賃貸している不動産からは地代・家賃などの賃料収入を得ることができます。収入を得ながら相続税評価額を下げられるため、賃貸不動産を所有することは相続税対策の有力な方法となります。
1-4.「小規模宅地等の特例」が適用できれば、より大きな評価減も可能となる
不動産が相続税対策として用いられる3つ目の理由は、「小規模宅地等の評価減の特例」(以下「小規模宅地特例」といいます)という税制上の優遇制度が用意されていることです。
これは、相続された土地が一定の条件に当てはまる場合、50%(貸付事業用)または80%(居住用、事業用)の相続税評価額が減額される特例措置です。
(参考)小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう
2.土地の相続税評価額の求め方と価格水準
相続税評価額と実勢価格との差が、不動産が相続税対策に用いられる第一の理由だと説明しました。そこで次に、不動産の相続税評価額がどのように求められるのかを説明します。土地と家屋(建物)とで求め方が異なるため、まず土地の評価方法を説明します。
土地の相続税評価額の求め方には「路線価方式」と「倍率方式」とがあり、地域によってどちらを用いるのか決められています。
2-1.路線価方式による土地の評価
「路線価」とは、相続税や贈与税の算定に使用するために国税庁が算定・公表している土地の評価額です。路線価は、全国の主要な市街地、商業地、住宅街などの路線で定められています。
路線価の「路線」とは道路のことで、路線価はその道路に面している土地の評価額を、1平米あたりの価格で示します。

ただし、同じ道路に面している土地でも、土地の形状や周辺状況などが異なれば、その価値も異なってきます。そこで路線価方式の計算方法においては、土地の状況を考慮に入れて路線価を加減するための「補正率」と呼ばれる数値も定められています。
路線価方式における土地の評価額は、下記の式で求めます。
(補正がない場合は、補正率の項はなし)
最新の路線価は、国税庁ホームページ内の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
路線価の見方や、補正率などについてくわしく知りたい方は、下記の記事を参照してください。
(参考)【相続税路線価とは】調べ方・計算方法をわかりやすく解説!
2-2.倍率方式による土地の評価
路線価が定められているのは、全国の主要な都市部だけです。それ以外の地域にある土地は「倍率方式」によって相続税評価額を求めます。
倍率方式とは、土地の固定資産税評価額に、土地の地目ごとに定められた「倍率」を掛けて土地の評価額とする方式です。
倍率方式における土地の相続税評価額は、下記の式で求めます。
評価したい土地の倍率は、上で示した国税庁ホームページ内の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で確認できます。
なお、土地の固定資産税評価額は、市区町村(東京23区は都)が固定資産税の課税額を算定するために、土地ごとに「固定資産税路線価方式」または「標準宅地比準方式」により定めています。
具体的な数字は、市区町村から送付される納税通知書に記載されています。
引用:大阪市「固定資産税・都市計画税の通知書類」
2-3.土地の評価額の価格水準
相続税路線価も、固定資産税評価額を決めるための固定資産税路線価も「地価公示価格」(公示地価)を参照して定められています。
地価公示価格とは、国土交通省が毎年1月に公表している、全国26,000箇所の標準地における「自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格」(国土交通省「令和7年 地価公示の実施状況及び地価の状況」)です。
いわば、国土交通省が推定する「正常な取引における土地の実勢価格」だともいえるでしょう。
ただし、地価公示価格はあくまで理論上の推計値です。土地の取引価格は景気動向や不動産市況、土地の周辺状況など以外に、売り手・買い手の取引事情などによっても個別に大きく変動する可能性があります。
そのため、必ずしも地価公示価格=実勢価格となるわけではありませんが、平均的に見ればある程度実勢価格に近くなっていることが多いでしょう。
2-3-1.相続税路線価の価格水準は、地価公示価格の80%程度が目安
相続税路線価は、「1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途」に定めることとされています。
なお、相続税路線価は毎年7月に最新価格が公表されます。
(参考)国税庁:令和6年分の路線価等について
2-3-2.倍率方式の基準となる固定資産税評価額の価格水準は、地価公示価格の70%程度が目安
固定資産税評価額算定の根拠となるのは、固定資産税路線価(主に都市部)です。固定資産税路線価は、国土交通省が公表する地価公示価格の70%程度が目安とされています。なお、固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。
2-3-3.相続税評価額と実勢価格の関係
実勢価格、地価公示価格、相続税路線価、固定資産税路線価の価格水準を比較すると、下記のような順で、高額→低額になることが一般的です。ただし、これはあくまで目安です。地価の値動きによっては実勢価格が地価公示価格よりもずっと高くなることも、低くなることもあります。
そのため、土地の相続税評価額も、実勢価格の70%程度になることもあれば、90%程度になることもあります。

2-4.土地を賃貸している場合はさらに評価額が下がる
土地の相続税評価額は、その土地の使用状況によっても調整されます。使用状況には、大きく分けて下記の3種類があります。
| 自用地 | 所有者が居住や事業など自己のために使用している土地 |
|---|---|
| 貸宅地 | 所有者が他人に貸しており、借主が建物を建てて使用している土地 (借地借家法第2条に規定する借地権がある土地) |
| 貸家建付地 | 土地の所有者が貸家(賃貸マンション・アパートなど)を建て、貸家を他人に貸している土地 |
2-4-1.自用地の評価額
路線価方式、倍率方式ともに、自用地の場合が基準となっています。上述の計算式をそのまま当てはめて、評価額を計算します。
一方向のみ路線価400,000円の道路に接している250平米のA土地(補正なし)。
路線価400,000円 × 250平方メートル = 評価額1億円
2-4-2.貸宅地の評価額
貸宅地とは、他人(親族や同族会社以外)に貸して地代(借地料)を得ている土地です。貸宅地では、土地を借りている人(借地人)に「借地権」という権利が発生するため、土地の所有者が自由に土地を利用・処分することができなくなります。そのぶん、貸宅地は自用地よりも価値が低いと考えられるのです。そこで貸宅地では、自用地から借地権の分の価値を差し引く計算をして評価額を求めます。
ただし、日本には借地権の取引慣行がある地域とない地域があり、それぞれの地域で計算方法が異なります。まず、借地権の取引慣行がある地域(主に都市部)では、下記のように計算します。
借地権割合は地域によって異なり、30%から90%までの10%刻みで、いずれかの割合が地域ごとに設定されています。「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」では、A(90%)からG(30%)まで、7段階のアルファベット記号で借地権割合が記載されています。ただし、現在では借地権割合が80%や90%に設定されている地域はなく、実務上70%(C)が上限となっています。
A土地が貸宅地で、借地権割合70%の場合
1億円×(1-0.7)=3,000万円
一方、借地権の取引慣行のない地域での貸宅地の場合は、借地権割合は一律で20%と評価され、下記の式で評価額を求めます。
2-4-3.貸家建付地の評価額
貸家建付地とは、土地の所有者が、他人に貸すための家屋を建てている土地です。賃貸マンション・アパートをイメージすればよいでしょう。この場合は、その家屋を賃借する人に「借家権」という権利が発生します。
そこで、次の計算式により、自用地から借家権の分の価値を差し引きます。なお、賃貸割合とは、家屋の居住部分のうちどれだけ他人に貸しているかを示します。例えば5室の家屋で、1室は所有者が自分で使い、4室に賃借人がいる場合、賃貸割合は80%となります。
なお、借家権割合は現在、全国一律で30%とされています。
A土地が貸家建付地で、借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合80%の場合
1億円×(1-0.7×0.3×0.8)=8,320万円
3.家屋の相続税評価額の求め方と価格水準
自用家屋(被相続人が居住用・事業用として使っていた家屋)の相続税評価額は、下記の式で求めることとされています。つまり、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。
3-1.家屋の評価額の価格水準
家屋の固定資産税評価額は、「再建築価格に経年による減価分を補正した額」とされています。つまり、この建物をいま新築で建てたらこれくらいかかるだろうと想定される金額から、年月の経過で価値が落ちたと思われる金額分を引いて求めます。
補正率は工法などによっても大きく変わります。例として、木造住宅の場合、10年経過の補正率は0.6とされています。この場合、再建築価格が3,000万円なら、0.6を掛けた1,800万円が固定資産税評価額とされます。ただし、自治体や建物の維持管理状況などにより変動するため多少の幅があります。
3-2.貸家の評価額はさらに下がる
賃貸マンション・アパートなど、他人に賃貸している家屋を「貸家」といいます。貸家の相続税評価額は、下記の式で求めます。
賃貸割合が100%であれば、固定資産税評価額の70%が貸家の相続税評価額になります(現在、借家権割合は全国一律30%)。
貸家建付地に建つB建物は、固定資産税評価額が5,000万円で賃貸割合が100%の場合
5,000万円×(1-0.3×100%)=3,500万円
4.相続税対策として不動産を用いる方法
相続税対策として不動産を用いる具体的な方法について解説します。
いずれの方法も、準備や実行にある程度の時間が必要です。将来の相続を意識するようになったら、なるべく早くから取り組むことにより、より確実な相続税対策効果を得ることができます。
4-1.収益不動産の購入・管理による評価減
収益不動産とは、賃貸マンション・アパートや貸地など、収益目的で他人に賃貸する不動産のことです。不動産は貸家建付地や貸家としたほうが評価は低くなるため、「収益不動産」の所有・管理が相続税対策のために広く用いられています。
4-1-1.貸宅地か、貸家建付地か
同じ土地であっても、貸宅地と貸家建付地とでは、貸宅地にするほうが相続税評価は下がります。
しかし、貸宅地には借地権が借地人に帰属し、土地の所有者が自由に利用・処分できないなどのデメリットがあります。また、貸家建付地で賃貸住宅等から得られる家賃収入と比べて、貸宅地による地代収入はかなり低い水準であり、多くの場合、固定資産税がまかなえる程度といわれます。
他方で、貸主は借地契約の締結の際、借地権の設定に対する「権利金」を一時金として得られる場合があります(地域の慣習によって異なります)。また、貸宅地では地主が建物の管理をする必要なく、管理の手間も比較的少ないというメリットもあります。
貸家建付地は、土地の評価だけで見ると相続税評価の圧縮は貸宅地より小さくなりますが、家屋を含めて考えると貸宅地に近い圧縮割合になる場合もあります。ただし、賃貸住宅を建てるのにふさわしいのは、入居者ニーズがある地域だけです。
以上のように、貸宅地と貸家建付地には、それぞれメリット・デメリットがあり、また、地域のニーズなども関係するため一概にどちらが良いとは断言できません。
| 種類 | 相続税評価額の圧縮割合 | 収益性 (賃料収入) | 管理の手間 |
|---|---|---|---|
| 貸宅地 | 貸家建付地よりは高い | 低い | 少ない |
| 貸家建付地 | 貸宅地よりは低いが建物を含めれば、土地だけの場合より高くなる | 高い | 大きい(自主管理) 中程度(管理会社に委託) |
もともと所有していて自用地としている土地がある場合などは、それを貸宅地とすることが選択肢になる場合もあります。
一方、相続税対策のために新規に収益不動産を購入する場合は、より収益性の高い賃貸マンション・アパートなどが選ばれるケースが多いでしょう。
4-1-2.収益不動産購入時の借入金残債は、相続時に相続財産から差し引かれる
収益不動産を購入する場合、通常は、購入資金を金融機関から借り入れ、毎月の賃料収入から返済していきます。
相続時に被相続人(亡くなった人)名義の借入金の残債がある場合、その残債は原則的に相続人に引き継がれます(団体信用生命保険加入などにより残債が返済される場合を除く)。相続税の計算上、この残債額は相続財産から差し引かれます。これを「債務控除」といいます。
例えば、預金や不動産などの相続財産の評価額が2億円、借金の残債が5,000万円だとすると、1億5,000万円が相続税の計算対象になるということです。亡くなった人に借金があれば、結果的に相続税は圧縮されることになります。
4-1-3.収益不動産(土地付きアパート)の購入による相続税対策の例
収益物件として、土地付きのアパートを購入して相続税対策をする場合の例を見てみましょう。なお、以下は財産評価の考え方を示すための単純化した例であり、金利、手数料、諸経費、所得税、固定資産税などを考慮した収益シミュレーションではないことに注意してください。
4-1-3-1.(1)相続前の資産の状況
4-1-3-2.(2)相続税対策として以下の内容で収益不動産を購入
- 法定相続人:子3名(基礎控除額4,800万円)
- 土地付き木造アパート2億円を預金から1億円+融資1億円の資金で購入
土地:購入価格(実勢価格)1億3,000万円。相続税路線価1億400万円
家屋(木造アパート、建築費7,000万円) - 銀行からの借入額:1億円
- 融資返済総額:1億2,000万円(元金+利息)
- 毎月の家賃収入から諸経費、税金を差し引いた金額で、融資返済と修繕費をまかなうと仮定する
4-1-3-3.(3)相続発生時の資産と相続税評価額
| 相続財産 | 内容 | 時価(実勢価格) | 相続税評価額 |
|---|---|---|---|
| 預金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
| 土地 | 貸家建付地 相続税路線価1億400万円 借地権割合70% | 1億3,000万円 | 8,216万円 (=1億400万円×(1-0.7×0.3×1.0)) |
| 建物 | 貸家 建築費7,000万円 固定資産税評価額は建築価格の50%、賃貸割合100% | 5,000万円 (減価償却で2,000万円分価値低下) | 2,450万円 (=7,000万円×50%×(1-0.3)) |
| 借入金(債務) | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
基礎控除後の遺産総額:1億666万円-4,800万円=5,866万円
一方、収益不動産購入せず、2億円の預金のままで相続した場合は、以下のようになります。
基礎控除後の遺産総額:2億円-4,800万円=1億5,200万円
以上から、他の条件を考慮せず法定相続人の子3名が法定相続分での遺産分割をしたと仮定すると、相続税額(概算値)はそれぞれ下記のようになります。
| 預金のみの場合 | 収益不動産を購入した場合 | |
|---|---|---|
| 相続財産評価額 | 2億円 | 1億666万円 |
| 相続税の基礎控除後の課税相続財産額 | 1億5,200万円 | 5,866万円 |
| 相続税(子3人の合計) | 2,460万円 | 730万円 |

相続税は各人の取得した課税価格が高くなると税率も高くなる超過累進課税であるため、課税価格が高額になるほど、大きな相続税の圧縮効果が見込めます。
4-1-3-4.(4)資産価値の変化
一方、相続した資産の価値(実勢価格)はどう変化しているでしょうか。
上記例では、土地の実勢価格は変化しない、建物は経年による減価で5,000万円(帳簿価格)になっている、と仮定しています。その場合、相続した資産の価値は次のとおりになります。
預金1億円+土地1億3,000万円+建物5,000万円-借入残債1億円=1億8,000万円
購入した建物の価値が経年で減ってしまったため、預金のみで相続した場合に比べて、相続された資産の価値は減っています。
ただし、ここで注意していただきたいのは、収益不動産は保有を続ければ毎年家賃収入を生むという点です。そしてその収益により、借入の残債を返済していきます。
相続人が引き継ぐ2億円の債務は、アパートを保有していれば今後得られる家賃収入で相殺されるため、他の資産を取り崩すことなく、いずれはゼロになります。
それを考慮すれば、相続された資産の実質的な価値は、上記で示された1億8,000万円よりもかなり大きな金額として評価できるはずです。
また、現在の不動産市況では、特に都市部や人気エリアの土地の価格が上昇傾向にあります。そのため、土地がまったく値上がりしないと想定するのは、やや非現実的です。実際には実勢価格が値上がりすることにより、資産価値が増えている可能性も十分に考えられます。
このように、収益不動産を用いることで、結果としてより大きな資産を、より低い評価額で相続することができる可能性があるのです。
4-2.小規模宅地特例の適用による評価減
「小規模宅地特例」(小規模宅地等の評価減の特例)とは、相続財産に、亡くなった人が自宅、事業用宅地、または貸付事業用宅地として使っていた土地がある場合に、一定の要件に該当すれば、相続税評価額が80%または50%減額されるという特例措置です。
例えば、路線価での評価額が1億円の自宅土地に、小規模宅地特例が適用できたとすると、評価額は2,000万円と大きく圧縮されます。結果として、相続税額も相当に圧縮されます。
4-2-1.小規模宅地特例には、土地と相続人の両方に要件が定められている
小規模宅地特例は「対象となる土地」と「相続人」の両方に要件が定められています。
まず、対象となる土地の要件、減額の割合、適用できる限度面積をまとめると、下記のようになっています。
| 名称 | 内容 | 減額割合 | 限度面積 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人の自宅が建っている土地 | 80% | 330平米 |
| 貸付事業用宅地等 | 被相続人が賃貸事業で使っていた土地 | 50% | 200平米 |
| 特定事業用宅地等 | 被相続人が賃貸以外の事業で使っていた土地 | 80% | 400平米 |
| 特定同族会社事業用宅地 | 同族会社に貸し付けて事業で使っていた土地 | 80% | 400平米 |
また、対象となる土地ごとに、相続する人に対する要件も細かく定められています。

例えば、自宅土地(特定居住用宅地等)の場合、配偶者が相続する場合は必ず要件に該当します。配偶者以外の相続人が小規模宅地特例を適用するには、相続開始前から同居し、申告期限まで居住を継続するなどの厳格な要件があります。
また、賃貸マンション・アパートなどが建つ土地(貸付事業用宅地等)の場合は、相続人がその土地を相続税の申告期限まで保有し、かつ賃貸事業を続けていること、などの要件があります。
小規模宅地特例は、適用できれば非常に効果が大きな相続税対策となりますが、適用要件が厳密に定められているため、保有する土地や相続人の状況と、適用の可否をあらかじめよく確認しておく必要があります。相続が発生してから適用できないことがわかっても、変更はできないので、心配な方は、早めに相続専門の税理士に相談したほうがいいでしょう。
(参考)小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう
4-3.不動産の組み替えによる評価減
相続税対策に不動産を用いる場合、「不動産の組み替え」「資産の組み替え」などと呼ばれる方法もよく用いられます。これは、現在所有している不動産を売却して買い替えたり、建て替えたりすることで、相続税対策効果をより高めようとする方法です。
これにはいくつものバリエーションがあります。
4-3-1.賃貸ニーズが低い地域の土地を売却し、ニーズが高い地域の不動産を購入

賃貸住宅の購入・管理は相続税対策に効果がありますが、どの地域でも可能というわけではありません。入居者の賃貸ニーズが低い場所では、失敗のリスクが高くなります。
遊休土地(自用地)を所有している人が賃貸住宅を建設して相続税対策を検討した際、その地域の賃貸ニーズが低いことが判明した場合は、その土地を売却し、得られた資金で賃貸ニーズが高い地域にある賃貸マンション・アパートなどを購入します。すると、元の土地を自用地として相続するより、評価減となる可能性があります。
4-3-2.自宅を売却し、評価額の低い不動産に組み替える

都心に一定の敷地面積を持つ老朽化した自宅がある場合、相続税評価額は高額になり、結果として相続税の負担も大きくなることがあります。このような建物・土地を相続することで、相続人は相続税の負担に苦慮するという場合もあります。そのような事態を避けるためには、相続発生前に、自宅を評価額が減額される不動産に組み替えておく方法が考えられます。
例えば、自宅を売却して、タワーマンション住戸を購入し、そこに転居するという方法です。タワーマンションは実勢価格(資産価値)と比べて、相続税評価額が50%程度となることもあるため、相続税を大きく圧縮できる可能性があります(ただし、近年は通達改正などにより効果が以前より限定的になっています)。
また、自宅を売却すると、譲渡所得の3,000万円特別控除の特例や、10年以上所有している自宅を売却した場合に適用できる譲渡所得の軽減税率の特例、特定の居住用財産の買換え特例(前2特例との併用は不可)などがあり、所得税の課税面でも有利になっています。
ただし、元の自宅に小規模宅地特例の適用ができる場合、土地が最大80%の評価減となるため、組み替えたほうが相続対策として有利かどうかは慎重に検討する必要があります。
4-3-3.自宅建物を、賃貸併用住宅に組み替える

自宅建物が老朽化しているのであれば、賃貸併用住宅に建て替えるという方法も考えられます。例えば、4階建てのマンションに建て替えて、自分たちはその1フロアに住み、他のフロアは他人に賃貸するといった形です。
被相続人と家族だけが住む住宅の場合は、土地も建物すべて自用での評価となりますが、賃貸併用にすれば、他人に貸している分の土地は貸家建付地として、また貸している建物の部分は貸家として、それぞれ評価額を下げることができます。
ただし、賃貸ニーズがある地域であることが前提になります。また、建て替えには費用がかかるため、得失を慎重にシミュレーションする必要があります。
4-3-4.小規模宅地特例が100%適用できる土地に組み替える
自宅などの土地に小規模宅地特例が適用できれば、80%という大きな評価減が可能です。ただし、小規模宅地特例が適用できるのは、特定居住用宅地の場合で、最大330平米です。
例えば、自宅の土地が600平米だとすれば、270平米分には適用できません。このような場合、自宅土地を売却して地価がより高い地域に、小規模宅地特例の適用範囲内となる面積の土地に組み替える方法があります。
例えば、600平米の自宅土地の相続税評価額が2億円だとした場合、その土地を売却して、相続税評価額が倍の地域で300平米の土地(2億円)を購入して、新たな自宅とします。
元の土地の場合、330平米分に小規模宅地が適用できるとすると、その部分の評価額は(2億円×330/600)×0.2=2,200万円、適用できない部分の評価額は(2億円×270/600)=9,000万円となるので、全体の評価額は1億1,200万円になります。
一方、新しい土地では、300平米すべてに小規模宅地特例が適用できるため、2億円×0.2=4,000万円の評価額となり、7,200万円もの評価額圧縮が可能となります。
5.不動産賃貸経営の法人化による相続税対策
収益不動産を所有するということは、言い換えれば不動産賃貸事業を経営するということです。この不動産賃貸事業の経営を、不動産オーナー個人ではなく会社を設立しておこなうことを本記事では「不動産法人化」と称します。
会社法人には株式会社や合同会社などの種類があります。以下、本記事では株式会社を前提に説明しますが、合同会社などでも基本的な考え方は同じです。
不動産法人化により、不動産オーナー個人が収益不動産を所有・管理する場合と比べて、相続税対策としての効果をより増強させることができる場合があります。反面、不動産法人化にはデメリットや注意点もあり、実施には慎重な検討が必要です。
5-1.法人の不動産賃貸経営への関わり方の3パターン
法人がどのように不動産賃貸経営へ関わるのかについては、次の3つの運営形態があります。
5-1-1.管理委託方式

会社と個人が不動産管理委託契約を締結し、会社が不動産の管理業務をおこなう方式です。不動産の所有形態は個人のままで、会社は不動産の管理業務のみを受託します。
なお、「不動産管理会社」という用語は、広義には所有方式やサブリース方式も含みますが、狭義には本項の管理業務受託のみを指します。
5-1-2.サブリース方式

個人が所有する収益不動産の所有名義はそのままにして、会社が賃借する方法です。会社は賃借した不動産を、入居者に転貸します。入居者から得た賃料の一部を会社の運営費用にあて、残りを個人に賃借料として支払います。
5-1-3.所有方式

不動産管理会社が法人として不動産を所有する形です。もともと個人(被相続人)が所有していた不動産を、法人に売却して移転する場合もあれば、法人が金融機関から融資を受けて新規に不動産を購入する場合もあります。
また、収益不動産の土地と建物をあわせて法人が所有する場合もあれば、土地は個人所有で、建物だけを法人の所有とする場合もあります。
なお、不動産などの資産を保有・管理することを目的とする会社は「資産管理会社」とも呼ばれます。
5-2.法人化のメリット
法人化によるメリットは、大きく分けると次の4点にまとめられます。

以下、それぞれの概要を確認します。
5-2-1.税目の違いによる税率の差
個人で収益不動産を所有・管理する場合は、家賃収入から経費を差し引いて得られた所得は原則として不動産所得として所得税の課税対象となります。不動産所得は総合課税の対象となり、他の所得と合算して税額が計算されます。
所得税は課税される所得金額が上がるにつれて段階的に税率が上がる超過累進税率を採用しており、課税所得金額4,000万円以上の部分は45%の最高税率が適用されます。住民税10%とあわせると55%の税率となります。
一方、不動産法人化で得られる家賃収入(益金)から経費(損金)を差し引いた所得は、法人税等の対象となります。
資本金1億円以下の中小法人の場合、法人税は、年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分は23.2%の、2段階となっています。その他、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税をあわせた実効税率(各種税目を合算した実質的な税負担率)は、所得額によっても異なりますが33~34%程度になります。
不動産オーナーの所得の内容(不動産所得のみか、給与所得を併有するかなど)や、他の所得金額を合わせた総所得金額によって適用される税率が大きく異なるため、不動産法人化を検討すべき所得水準は一概にはいえません。また、前述した3パターンのうち、どのパターンを採用するかによっても異なります。
例えば、不動産オーナーが賃貸用建物を法人に譲渡し、その敷地を法人に貸し付けたとした場合、仮に不動産オーナーの所得が不動産所得のみであれば、不動産の純収入(不動産収入から必要経費を差引き、減価償却費相当額を加算したキャッシュフロー)が1,800万円以上にならないと、法人化のメリットは現れにくいでしょう。
あわせて、法人には損金として計上できる範囲が広いことや、所得が赤字になった場合に繰り越せる期間が長いなど、税務処理上のメリットがあります。
5-2-2.所得の分散による相続財産の抑制と課税圧縮効果
被相続人が収益不動産を個人所有していると、得られた不動産所得は、(費消されなければ)被相続人の資産として蓄積されていきます。つまり将来の相続財産が増加し、そのぶん、相続税額が増加する要因となります。
一方、法人所有の場合、益金(家賃収入)は、法人内部や法人の役員となっている推定相続人に役員報酬が支払われる形で分散され、被相続人が役員報酬を受け取らなければ相続財産が増加することはありません。
5-2-3.所得の分散による所得税の圧縮効果
法人の役員報酬に対しては所得税が課税されますが、給与所得控除及び基礎控除(合計所得金額2,500万円以下の場合)という非課税枠があるため課税上有利になります。
また、複数の推定相続人がいる場合には、例えば、1人に3,000万円の給与を支給するのと比べて、3人の役員に1,000万円を分散して支給するほうが、所得税の超過累進課税の税率が低くなります。これも所得分散による課税圧縮効果です。給与所得控除及び基礎控除が3人分適用されることもその効果を高めます。
なお、サブリース方式や管理委託方式など、法人が直接不動産を保有しない方式の場合は、不動産の所有者(被相続人)の受け取り分が発生するため所有方式と比べると効果は低くなりますが、所得分散による課税の圧縮効果は一定程度得られます。
5-2-4.相続財産の内容の変化による相続税圧縮の効果
収益不動産を個人所有する場合、相続が発生するとその不動産は相続財産となります。
一方、法人で不動産を所有している場合、相続が発生したときに相続財産となるのは不動産ではなく、被相続人が株主となっている法人の自社株式になります。自社株式の相続税評価方法は、財産評価基本通達178~189の7(取引相場のない株式の評価)によりますが、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式があり複雑なため、本記事では割愛します。
会社の損益や純資産の状況、承継タイミングなどによっては不動産を直接相続する場合の相続税評価額より評価額が低くなる場合もあります。
また、株式は不動産と比べて分割が比較的容易であるため、毎年少しずつ生前贈与するといったこともでき、贈与税の非課税枠を活用しながら有利に移転することが可能です。
なお、不動産管理法人を被相続人ではなく、推定相続人が設立する方法もあります。その場合は、法人が金融機関から融資を受けて、被相続人が所有する不動産を法人が買い取る形とすることが一般的です。その後、法人が家賃収入から融資を返済していきます。どちらが良いかは、一概にはいえません。
5-3.法人化のデメリットや注意点
法人化のデメリットや注意点は、以下の3点です。

以下、それぞれの概要を確認します。
5-3-1.法人設立や維持に手間とコストがかかる
法人の設立時には、登記費用、登録免許税及び不動産取得税などの諸費用がかかります。また、法人の決算・申告に際しての税理士報酬や法人住民税の均等割などは、たとえ決算が赤字であっても支払い・納付が必要です。
その他、社会保険料納付など、法人の維持のためにおこなわなければならない事務作業が発生します。
法人化についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
(参考)法人化のメリット・デメリットを解説!節税できるって本当?
5-3-2.法人が不動産を取得して3年経たないと評価額が高くなる
自社株の評価において、会社が保有する不動産は(個人所有と同様に)路線価などの相続税評価額で算定されるのが原則であり、その評価額が自社株の評価額に反映されます。
ただし、相続の発生(課税時期)から3年以内前に法人が取得した不動産は、「通常の取引価額」(時価=実勢価格)で評価されることとなります(財産評価基本通達189の4)。そのため、自社株の評価額も相応に上昇します。
つまり、法人が不動産を取得してから3年を超える時間が経たないと、相続税対策としての効果が損なわれるのです。
5-3-3.法人が土地を所有していると小規模宅地等の特例が適用できない
法人が所有する土地に対しては、小規模宅地等の特例は適用できません。ただし、個人が所有して法人に貸し付けている土地は、一定の要件を充たせば、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用が可能となります。
6.不動産を用いた相続税対策の失敗例5タイプと防止策
不動産を購入すれば、必ず相続税対策がうまくいくわけではありません。よくある代表的な失敗例を5つ採り上げ、防止策とともに解説します。
6-1.相続税が思ったほど圧縮されなかった
不動産が相続税対策になる根底には、相続税評価額が実勢価格よりも低く評価されることがあります。しかし、実勢価格と相続税評価額にどの程度の乖離があるかは、地域やタイミングによって異なります。
土地の路線価にしても、必ず実勢価格の80%程度になるわけではありません。場合によっては、実勢価格と相続税評価額があまり変わらないこともあり得るのです。
一方では、不動産を購入する際には不動産業者に支払う手数料や不動産取得税、登録免許税など諸費用がかかりますし、保有期間中は固定資産税がかかります。そういった費用を含めて考えると、不動産を購入してもあまりメリットがなかったというケースも少なくありません。
そのような事態を防ぐには、実勢価格と路線価に十分な乖離があるか、よく確認してから不動産を購入する必要があります。基本的に路線価と実勢価格との乖離が大きくなるほど、相続税対策の効果が大きくなります。不動産会社のいうことを鵜呑みにせず、必要に応じて不動産鑑定士などの専門家に依頼して、調査しましょう。
6-2.不動産賃貸経営が失敗に終わった
収益不動産の保有が、相続税対策に効果を発揮することはよくあります。他方で、収益不動産はただ保有していればいいというものではなく、不動産賃貸業という事業を営むという側面もあります。通常は融資を受けて物件を購入し、賃料収入で融資を返済したり、定期的に必要となる大規模修繕費をまかなったりします。
もし空室率が高まるなどして想定していた賃料収入が得られなければ、借金返済のために資産を切り崩さなければならないこともあります。場合によっては、不動産を売却しても補填できないほど赤字が膨らんでしまうこともあります。
まず、地域に賃貸需要があるかどうかを入念に確認する必要があります。その上で、地域ニーズに即した住宅を建てることや、建物が古くなっても入居率を維持するために管理や修繕に力を入れることが必要です。
6-3.相続後に遺族が不動産賃貸経営に失敗
収益不動産について、被相続人が存命中はうまく不動産賃貸経営ができていたものの、相続後に承継した家族が経営できなくなるというケースもあります。夫が管理していた賃貸アパートを妻が相続したものの、心身に不調があるため賃貸経営ができずに、結局経営破綻してしまうといったケースです。
相続人が高齢である場合は特に、賃貸不動産を相続してきちんと経営できるかどうかは、相続人本人の意向も確認しながら、慎重に検討する必要があります。
その上で、もし賃貸不動産を相続させるなら、適切な管理会社に管理を委託するとか、信託契約を活用するといった方法も検討します。状況によっては、相続税対策としては不利になるとしても、不動産を売却して現預金で相続したほうがよいこともあります。
6-4.租税回避行為として指摘を受けた
近年、タワーマンションの相続において路線価による相続税評価が税務署から否認されたことに対し、納税者が提訴して敗訴した事例が複数報道されています(平成29年2月15日東京高裁判決(平成28年(行コ)第59号)、令和4年4月19日最高裁判決(令和2年(行ヒ)283・103併合))。
相続税の圧縮だけを目的とした経済合理性のない不動産購入や業務実態のない法人化などは、租税回避行為とみなされるリスクが高くなります。
収益不動産の購入や保有があくまで経済行為として合理的な説明ができるものであるかを常に確認しましょう。相続発生から10年くらい前など、なるべく早い時期から取り組むこともポイントです。また、相続税にくわしい税理士のチェックも欠かせません。
6-5.相続人の間で遺産分割争いが発生
不動産は簡単に分割することができません。相続人が3名いるのに、相続財産の不動産が1軒といった場合、遺産分割が紛糾する恐れがあります。共有持分にすることも可能ですが、それは次の世代への相続など将来に禍根残すケースが多くなります。
遺産分割争いを防ぐ方法の1つは、遺言を残すことです。どうしてそのような遺産分割にしたのか、自分の気持ちを丁寧に遺言に記せば、それに対して異議を唱える相続人は少ないものです。あわせて、不動産は分割や共有が難しいことを前提にして、生命保険なども活用しながら、なるべく公平な遺産分割を意識するとよいでしょう。
7.まとめ:相続税対策に不動産を活用したい場合は、必ず専門家への相談を
相続税対策としての不動産活用は、実際に多くの富裕層や資産家が取り組んでいることであり、きちんと準備をして適正な形で進めれば、効果も得られます。
ただし、不動産ならなんでもいいということではありません。どのような不動産を保有し、どのように承継していくかによって、資産保全や次世代への資産承継の内容が大きく変わってきます。
また、やり方によっては税務署からの指摘を受けるリスクもあります。
これから不動産活用を検討される方はもちろん、現在の不動産賃貸経営が正しいのかを確認したい方も、一度相続税にくわしい専門税理士法人にご相談いただき、相続税対策の方向性を確認なさることをおすすめします。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続対策編







































