暦年課税とは│相続時精算課税制度との比較・デメリットも解説
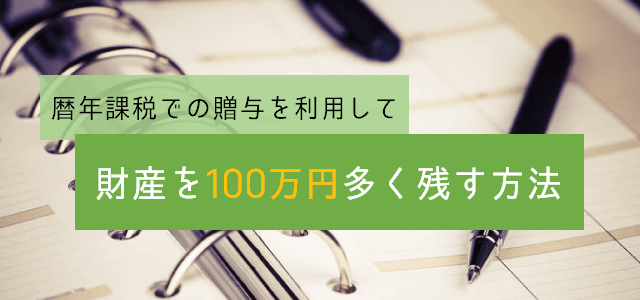
財産を贈与してもらったとき、特に何も手続きをしなければ「暦年課税」により贈与税が計算されます。
また、選択することで「相続時精算課税」制度により贈与税を計算することもできます。
暦年課税では、1月1日から同じ年の12月31日までに贈与された財産の合計額が110万円を超えない限り贈与税がかからないため、その仕組みを利用して相続税対策が可能です。
暦年課税には、メリットもあればデメリットもあります。そのため、生前贈与による相続税対策をするときは暦年課税の特徴を理解するだけでなく、もう1つの課税方法である「相続時精算課税」とどちらが有利であるかを入念に検討することが大切です。
そこで今回は、暦年課税の特徴やメリットとデメリットに加え、相続時精算課税制度の特徴とそれぞれの課税方法が向いている人の特徴などを、相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
なお、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与を対象に、相続時精算課税制度の改正が予定されています。ここでは、改正施行後の内容もあわせてお伝えします。
動画でも暦年贈与と相続時精算課税制度の税制改正により変更点について解説しています!
この記事の目次 [表示]
1.暦年課税とは1年間に受けた贈与に課税される方法
暦年課税とは、贈与した額に対する課税方法のことを指し、1年間に受けた贈与に課税されるというものです。ここでいう「1年間」とは毎年1月1日から12月31日までを指し、この間に贈与された財産が贈与税の課税対象となります。まずは暦年課税のメリットとデメリットをみていきましょう。
1-1.暦年課税のメリット
暦年課税の主なメリットは、以下の2点です。
- 年間110万円の基礎控除が使える
- 何度でも贈与できる
1-1-1.年間110万円の基礎控除が使える
暦年課税の場合、年間で贈与された財産の総額から基礎控除額110万円が差し引かれた残りに贈与税がかかります。そのため、年間の贈与額が110万円であれば贈与税はかかりません。
また、基礎控除の110万円は、贈与を受けた人1人に対する1年ごとの金額です。たとえば、3人に贈与する場合、年間330万円まで非課税で贈与できます。
1-1-2.何度でも贈与できる
暦年課税には、基礎控除額110万円を適用できる回数に制限がありません。そのため、複数年にわたって財産を非課税で贈与できます。
たとえば、贈与できる年数が10年であった場合、受贈者(財産を贈られる人)1人につき1,100万円まで非課税で贈与できます。受贈者が3人であった場合、非課税で贈与できる財産の額は、10年間で最大3,300万円です。
1-2.暦年課税のデメリット
暦年課税のデメリットは、以下の2点であると考えられます。
- 多額の贈与には向かない
- 暦年課税を行う度に手続きを行わなければならない
1-2-1.多額の贈与には向かない
年間で贈与された財産の額が110万円を超えると、贈与税がかかります。そのため、1回あたりの贈与額が1,000万円や2,000万円などである場合、多額の贈与税が課せられる可能性があります。
1-2-2.暦年課税を行う度に手続きを行わなければならない
毎年110万円以内の財産を複数回にわたって贈与する場合、その都度贈与契約書を作成する必要があります。贈与契約書を作成しなければ「定期贈与」とみなされる恐れがあるためです。
定期贈与とは「1年ごとに110万円を10年間にわたって贈与する」のように、まとまった財産を分割して贈与することです。定期贈与と見なされると、最初の年に一括で財産を贈与したことになります。
たとえば、1,000万円の財産を100万円ずつ10年間にわたって贈与するとしましょう。定期贈与と見なされると、1,000万円−110万円=890万円に贈与税がかかります。定期贈与とみなされないようにするためには、10年間にわたって毎年贈与契約書を作成しなければならず、手間がかかります。
1-3.暦年課税での贈与税の計算方法
暦年課税の場合、贈与税は以下の手順で計算をします。
- 1年間の贈与額を合計する
- 年間の合計贈与額から基礎控除を差し引き基礎控除後の課税価格を求める
- 基礎控除後の課税価格に贈与税率をかける
贈与税額の具体的な計算方法は、以下の通りです。
- 贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率−控除額
贈与税の税率は「一般贈与財産(一般税率)」と「特例贈与財産(特例税率)」で異なります。
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上※である人が、父母や祖父母などの直系尊属から財産を贈与されたときの贈与税を計算する際に用いられます。一般税率は、兄弟間や夫婦間など特例税率に該当しない贈与をしたときの税率です。※2022年(令和4年)3月31日以前の贈与については、20歳以上。
特例税率と一般税率の速算表は、以下の通りです。
〇特例税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
〇一般税率
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
ここで、モデルケースを用いて贈与税額をシミュレーションしてみましょう。
例】年間で1,000万円の財産を贈与されたときの贈与税額を計算します。
〇特例税率が適用されるケース
40歳の子供が、父親から現金1,000万円を贈与された場合は、特例税率を用いて贈与税を計算します。同じ年にほかに贈与は受けていない場合、基礎控除後の課税価格と贈与税額は以下の通りです。
- 基礎控除後の課税価格:1,000万円-110万円=890万円
- 贈与税額:890万円×30%-90万円=177万円
計算の結果、1,000万円の現金を贈与された子供は、177万円の贈与税を負担することになります。
〇一般税率が適用されるケース
16歳の子供が祖父から1,000万円の現金を贈与される場合、一般税率が適用されるため、基礎控除後の課税価格と贈与税額は以下の通りとなります。
- 基礎控除後の課税価格:1,000万円-110万円=890万円
- 贈与税額:890万円×40%-125万円=231万円
一般税率が適用される場合の贈与税額は、231万円となりました。このように、年間の贈与額が同じであっても、特例税率と一般税率のどちらに該当するかで贈与税額が異なることがあります。
2.暦年課税の申告方法
暦年課税の場合、贈与税の申告と納税はどのように行うのでしょうか。申告が必要になるケースや申告時期、申告方法をみていきましょう。
2-1.贈与税の申告が必要な場合
暦年課税の場合、贈与税の申告が必要になるのは、年間の贈与額が基礎控除の110万円を超えており、税負担が発生するときです。また、贈与税を申告・納税するのは、財産を贈与された人です。
年間贈与額が110万円以下であれば、贈与税を申告する必要はありません。ただし「住宅取得等資金の非課税の特例」などの特例や非課税措置で贈与税がかからなくなるのであれば申告が必要です。
2-2.贈与税の申告時期
贈与税の申告は、財産を贈与された翌年の2月1日〜3月15日までです。納税も、3月15日までに済ませなければなりません。
申告期限を過ぎたあとでも申告・納税はできますが、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。贈与税の負担を軽減する特例が適用できなくなる場合もあるため、申告と納税は必ず期限内に済ませましょう。
2-3.贈与税の申告方法
贈与税を申告する場合、所定の申告書を作成して住所地を管轄する税務署に持参または郵送をします。申告書の書き方や税額の計算方法などの不明点がある場合は、税務署に出向いて担当者に相談するのも方法でしょう。
また、e-Tax(電子申告)を利用することで税務署に申告書を持参したり郵送したりしなくても、贈与税を申告できます。
3.暦年課税の申告書類の作成方法
贈与税を申告するときは「贈与税の申告書」を記入する必要があります。ここでは、贈与税申告書の記入方法や提出時に必要な添付書類をみていきましょう。
3-1.贈与税申告書の記入方法
暦年課税を適用する場合は、贈与税申告書の第一表を記入しましょう。申告書は、最寄りの税務署または国税庁のホームページから入手できます。
贈与税の申告書を手書きで作成する場合、以下の手順で記入をします。
- 提出する税務署や提出日、申告する年を記入する
- 申告する人の住所、マイナンバー、生年月日、職業を記入する
- 「Ⅰ暦年課税分」の特例贈与財産分または一般贈与財産分に、贈与者の氏名や住所、続柄、財産を取得した年月日、取得した財産の明細、財産の価額などを記入する
- 【合計欄】に暦年課税分の課税価格の合計額や基礎控除額、税額などを記載する
取得した財産の明細には、現金や不動産などの贈与された財産の種類や財産の所在地などを記載します。
贈与税の申告書は、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成できます。確定申告書等作成コーナーを利用すると、贈与者の氏名や生年月日、取得財産などを画面の指示に沿って入力することで簡単に申告書の作成が可能です。
贈与税申告書の詳しい書き方や作成方法は、以下の記事または国税庁ホームページの「贈与税の申告」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(参考)贈与税申告完全マニュアル・申告書記入から添付書類まで徹底解説
3-2.贈与税を申告するときに必要な添付書類
暦年課税を適用して贈与税を申告する場合、以下の添付書類が必要です。
- 本人確認書類:「マイナンバーカード」または「番号確認書類+身元確認書類」
- 番号確認書類:通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
- 身元確認書類:運転免許証・身体障害者手帳・パスポート・在留カードのいずれか
- 贈与財産の価額を証明する書類:土地の評価証明書など
贈与税の申告書を税務署の窓口に提出する場合、本人確認書類を提示することで添付を省略できます。また、e-Taxで申告をする場合、本人確認書類の提出は必要ありません。
贈与財産の価額を証明する書類は、提出が義務づけられているわけではありませんが、土地や建物などが贈与されたときに添付をすることがあります。
4.暦年課税と相続時精算課税制度の違い
贈与税の課税方法には、暦年課税のほかに「相続時精算課税」があります。相続時精算課税制度は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者がそれぞれ以下の要件を満たすときに利用できる制度です。
- 贈与者:贈与をした年の1月1日時点で60歳以上である直系尊属(父母または祖父母)
- 受贈者:贈与を受けた年の1月1日時点で18歳(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)以上の子供または孫
(参照:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」)
相続時精算課税制度には、2,500万円の特別控除があります。相続が開始されるまで何度贈与しても、2,500万円までは贈与税がかかりません。その代わり贈与財産は、相続税の課税対象財産に加えられます。
特別控除額2,500万円を超える贈与財産には、一律20%の贈与税がかかりますが、相続税を計算するときに支払った贈与税額が控除される仕組みです。
相続時精算課税制度の概要やメリット、デメリットなどは、下記記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
(参考)相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!
5.相続時精算課税制度を検討するときに知っておきたいポイント
相続時精算課税制度は、以下の3点も踏まえて検討することが重要です。
- 相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻せない
- 贈与者が異なるのであれば相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる
- 相続税を計算するときに小規模宅地等の特例は使えない
5-1.相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻せない
相続時精算課税を一度選択すると、贈与者の相続が開始されるまで自動で継続して適用されます。途中で暦年課税に戻すことはできません。
また、2023年(令和5年)までの贈与では、相続時精算課税の基礎控除額110万円が適用できません。暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが有利かをよく考えたうえで利用することが大切です。
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度を選択した場合でも受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除額が適用できます。この基礎控除額は、2,500万円の特別控除額や暦年課税の基礎控除額とは別のものとして扱われます。
5-2.贈与者が異なるのであれば相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる
相続時精算課税制度は、すべての贈与者に対して適用されるわけではありません。異なる人から財産を贈与される場合は、相続時精算課税制度と暦年課税を併用できます。
長男が、祖父と父親から生前贈与を受けるケースで考えてみましょう。長男が祖父からの財産贈与について、相続時精算課税制度を選択した場合、制度が適用されるのは祖父と長男とのあいだで行われる贈与のみです。父親から長男に対する贈与には、相続時精算課税制度は適用されず暦年課税で贈与ができます。
5-3.相続税を計算するときに小規模宅地等の特例は使えない
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地を相続する場合、所定の要件を満たすと土地の相続税評価額が一定の限度面積まで50%または80%減額される制度です。
たとえば、被相続人の住居が建っている土地を配偶者が相続する場合、330㎡まで土地の相続税評価額が80%減額されます。 仮に土地の面積が200㎡、相続税評価額が6,000万円であった場合、小規模宅地等の特例を適用できると土地の評価額を1,200万円まで減額できます。
小規模宅地等の特例を適用できるのは、原則として相続や遺贈(遺言書によって特定の人に財産を送ること)によって取得した土地です。 相続時精算課税制度を利用して贈与された土地については、相続税を計算するときに小規模宅地等の特例を適用できません。
(参考)No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
6.暦年課税か相続時精算課税、どちらを選べば有利か
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与を対象に、相続時精算課税制度の改正が行われます。
この改正前については、一般的には、次のような考え方で有利判定の整理がされていました。
配偶者や子に「将来的に値上がりが期待できる財産」や「収益が発生する不動産等」を贈与する場合には、相続時精算課税制度を利用するのが有利で、それ以外のケースでは、暦年課税を利用し毎年コツコツを贈与していく方が有利。
但し、税制改正後、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度を選択した場合でも受贈者1人あたり年間110万円の基礎控除額が適用可能となります。さらに、この基礎控除額は、暦年課税の基礎控除額とは別のものとして扱われ、また、2,500万円の特別控除額の計算や相続財産への加算対象にもなりません。なお、税制改正後、暦年贈与は、相続開始前7年以内(現行3年以内)の贈与額の全てが持ち戻し加算の対象となります。
そのため税制改正後は、基礎控除額の年間110万円以下の贈与であれば暦年課税よりも相続時精算課税制度を利用した方が有利という結論になります。
但し、税制改正前の考え方が無効になるというよりは、税制改正前の考え方は以前として有効なのですが、それに加え、相続時精算課税制度のメリットが新たに加わったというイメージとなります。
なお、以下のような方は、暦年課税のまま相続対策を行った方が有利になる場合もありますので、注意が必要です。どちらが有利になるかは、資産状況や、いつ相続が発生するか、また実際に行う相続対策の内容によって変わって来て、特に税制改正後はその判断は難しくなっています。
〇子の配偶者や孫など、推定相続人以外の方(遺言書により遺贈を受ける場合や生命保険の受取人になっている場合等は除く)
〇次のすべての条件を満たす方
- 財産が多額にある(限界税率10%以上※)
- 7年以上健在(相続が発生しない)見込み
- 相続税と贈与税の税率差をつかって暦年課税による対策を行う
- 上記の税率差による対策効果が税制改正前の考え方による対策効果を上回る
※限界税率については、相続財産や相続人の数により異なりますが、例えば、遺産総額8000万で子供3人の場合の限界税率は11%となります。さらに詳しく知りたい方は、「相続税の税率は何%か。控除額とは?計算手順や早見表も解説」を参照下さい。
7.暦年課税を使った相続対策は専門の税理士に相談しよう
暦年課税が適用される場合、1年間で贈与された金額が受贈者1人あたり110万円以下であれば、贈与税はかかりません。10年や20年など長期にわたって財産を贈与できる人や、相続人以外の受贈者が複数人いるときは、暦年課税を適用したほうが相続財産を圧縮しやすいでしょう。
一方で、短期間に多額の財産を贈与したい場合や、将来的に価値が上がる財産を贈与するときなどは、相続時精算課税制度を適用したほうが有利な場合があります。
相続時精算課税制度を選ぶと暦年課税には二度と戻せないため、家族構成や保有財産の状況などに応じて慎重に判断しなければなりません。そこで生前贈与による相続対策を検討している方は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
相続税専門の税理士法人チェスターでは、相続税申告書の作成や申告業務だけでなく、生前の相続対策についてもご相談が可能です。少しでも多くの財産を大切な家族に引き継ぎたいと考えている方は、税理士法人チェスターまでお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































