負担付贈与とは?通常の贈与との違いは?税務やデメリットについて
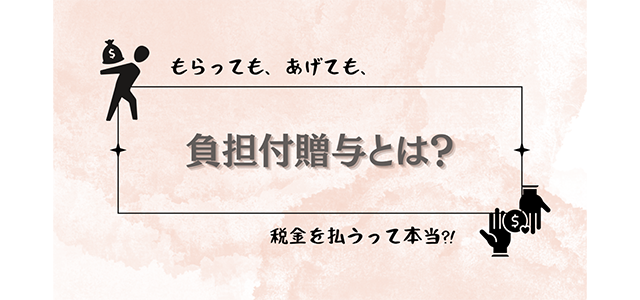
負担付贈与とは、財産を贈与する代わりに、受贈者が一定の負担(住宅ローンなどの残債の返済)をすることを条件とする贈与契約のことです。
負担付贈与は受贈者に条件を提示できる上に、履行されなければ契約解除できるというメリットがあるため、相続対策として活用されることもあります。
しかし、贈与者に譲渡所得が出る場合は所得税が課税されるなど、贈与者に税負担が生じるなどのデメリットもあるため注意が必要です。
この記事では、負担付贈与と通常の贈与の違いはもちろん、課税関係・メリット・デメリットについて解説しますのでぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.負担付贈与とは?具体例を元に解説
負担付贈与(読み方:ふたんつきぞうよ)とは、財産を贈与する代わりに、受贈者(贈与された人)に一定の債務を負担させることを条件とした贈与のことです。
負担付贈与の具体例として、不動産を贈与する代わりに、その不動産の住宅ローンの残債を受贈者が負担するケースが挙げられます。

負担付贈与は、土地や建物を贈与する代わりに、住宅ローンの残債や借金を返済するという内容の契約をするのが一般的です。
また、自分の飼っているペットの世話を引き継ぐことを条件に現金を贈与するなど、贈与する財産と付与される負担は多岐に渡ります。
1-1.負担付贈与と通常の贈与の違い
負担付贈与と通常の贈与の一番の違いは、「負担(債務)」があるか否かです。
通常の贈与は負担がないため、贈与時点で贈与契約が終了します。
しかし、負担付贈与は贈与後にも負担(債務の履行)が残るため、贈与契約は継続されます。
受贈者(贈与された人)は負担(債務を返済する義務)が残りますし、贈与者(贈与した人)には負担付贈与の契約内容が履行されるかを見届けます。
この他にも、税務において以下のような違いがあります。

1-2.賃貸物件の贈与は法的に負担付贈与に該当する
賃貸物件を贈与する場合、受贈者がその賃貸物件の入居者に対する敷金の返還義務(負担)を引き継ぐこととなります。
賃貸物件の贈与は法形式上は「負担付贈与」に該当することとなりますが、この敷金の返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、一般的にこの敷金返還債務を承継させる意図が贈与者・受贈者間においてなく、実質的に負担付贈与に当たらないとされています(「賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係」)。この場合、贈与者から引継ぎを受けた敷金相当額については、贈与税の課税対象となりません。
2.負担付贈与における課税について
負担付贈与では、贈与者に所得税が課税される可能性があります。
また、通常の贈与とは違い、譲渡所得が出る場合は贈与者に所得税や住民税が課税されます。
国税庁「負担付贈与に対する課税」にも、その旨が明記されています。
2-1.受贈者には贈与税が課税される
負担付贈与では、贈与財産の価額に注意を要します。
土地や借地権、家屋などの不動産の負担付贈与である場合、評価額は相続税評価額ではなく、贈与時の時価となりますのでご注意ください。ここでいう時価とは、贈与時の通常の取引価額に相当する金額となります。
贈与税が課税されるのは、贈与財産の時価から債務を差し引き、さらに基礎控除(年間110万円)を差し引いた後の価額です。その基礎控除後の価額に贈与税の税率を乗じて、贈与税額を計算します。

なお、贈与税が課税される場合は、負担付贈与がなされた翌年の2月1日~3月15日までの間に、贈与税の申告・納付を行うこととなります。
詳しくは、「贈与税は誰が払う?いくら払う?計算方法・非課税の特例も解説」や「贈与税申告にも申告期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について」をご覧ください。
2-1-1.親子間の負担付贈与の節税ポイント
親子間の負担付贈与の場合、相続時精算課税制度を活用すれば、贈与税の節税に繋がります。
相続時精算課税制度とは、原則「60歳以上の父母(もしくは祖父母)」から「18歳以上の子供(もしくは孫)」に対して、生前贈与をした際に選択できる贈与税の課税方式のことです。
相続時精算課税制度には、累計2,500万円の特別控除があり、超過した贈与財産については贈与税の税率が一律20%となります。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた贈与財産の価額(年間110万円の基礎控除額は含まれません。)は、贈与者の相続財産の価額に持ち戻して相続税が課税されますのでご注意ください。
詳しくは「相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!」をご覧ください。
2-2.贈与者には所得税等が課税される(譲渡所得が出た場合のみ)
負担付贈与を行った際に譲渡所得(譲渡益/利益)が出る場合は、贈与者に所得税等が課税されます。
具体的には、贈与財産の購入時の価額よりも債務の方が多い負担付贈与を行った場合などに、所得税等が課税されます。

なお、譲渡所得として所得税が課税される場合は、資産を譲渡した年の属する年の翌年2月16日~3月15日までの間に、譲渡所得の申告をしなくてはなりません。
詳しくは、国税庁「譲渡所得の申告期限」をご覧ください。
3.負担付贈与の課税シミュレーション
シミュレーションモデルを元に、負担付贈与をした場合の課税について確認していきましょう。
父親が15年前に土地を1,000万円で購入し、現在の価値(時価)は3,000万円に増加しているとします。
そして父親には1,200万円の借金があるため、土地を贈与する代わりにその借金を子供が肩代わりする、負担付贈与をするとします。

このシミュレーションモデルでは、受贈者である子供に贈与税が課税され、贈与者である父親にも所得税等が課税されます。
3-1.受贈者(子供)には贈与税が課税される
受贈者である子供は、父親から時価3,000万円の土地の贈与を受けていますが、負担として1,200万円の借金を負担することとなります。
そのため、差額の1,800万円は父親からの贈与とみなされ(みなし贈与)、子供には贈与税を払う義務が生じることになります。

贈与税の計算方法は、原則的な課税方法である暦年課税によるものとし、親子間の贈与であるため特例税率が適用されます。
そのため、(贈与財産3,000万円-負担1,200万円-基礎控除年間110万円)×特例税率45%-控除265万円=贈与税額4,955千万円となります。
3-2.贈与者(父親)には所得税等が課税される
贈与者である父親は、1,200万円の借金が帳消しになるので、その借金で土地を売却したという扱いになります。
また、もともと1,000万円で取得した土地を1,200万円で売却したという視点で見ると、父親には200万円の譲渡所得が生じたことになるため、所得税が課税されます。

このシミュレーションモデルでは、15年前に土地を購入しているため、所有期間5年超えの「長期譲渡所得」として、税率20.315%(所得税15.315%/住民税5%)を乗じることとなります。
4.負担付贈与のメリット
負担付贈与には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?確認していきましょう。
4-1.受贈者に何らかの負担をしてもらえる
負担付贈与の1つ目のメリットは、受贈者に何らかの負担をしてもらえることです。
例えば、居宅を贈与する代わりに生活の負担になっていた住宅ローンの返済を負担してもらう、土地を贈与する代わりに介護をお願いするなど、その負担は多岐に渡ります。
贈与の条件として負担をお願いできるため、言い出しにくい負担も交渉しやすくなります。
近い将来贈与を考えている場合は、負担付贈与の活用を検討されると良いでしょう。
4-2.受贈者が負担を履行しなければ贈与契約を解除できる
負担付贈与の2つ目のメリットは、受贈者が負担を履行しなかった場合、贈与契約自体を解除できることです。
もちろん、受贈者が負担を履行しないからといって、すぐに契約解除はできません。
予め一定の期間を定めた上で催促をし、それでも履行されない場合に限り、贈与契約の解除が可能となります。
予め贈与契約書に詳細を記載しておけば、言った・言わないのトラブルに発展することもありません。
5.負担付贈与のデメリット
続いて、負担付贈与のデメリットについて確認していきましょう。
5-1.受贈者が負担を履行しないリスクがある
負担付贈与の1つ目のデメリットは、受贈者が負担を履行しないリスクがあることです。
負担付贈与をしても、受贈者が必ずしもその義務を果たしてくれるとは限りません。
受贈者が負担を履行しない場合は、贈与契約そのものを解除することで、贈与財産の返還を求めることができます。
しかし、財産の返還にも応じない場合は、裁判で争うこととなってしまいます。
5-2.不動産等の負担付贈与は税金の負担が大きい
負担付贈与の2つ目のデメリットは、不動産等の負担付贈与は、税金の負担が大きいことです。
受贈者には贈与税が課税されますが、贈与時の時価が評価額となります。
通常の贈与の場合の相続税評価額は時価の8割相当額です。このため、評価額が時価となる負担付贈与は受贈者の負担する贈与税額が高くなります。
また、通常の贈与では贈与者に税金は課税されませんが、負担付贈与では譲渡所得として所得税等が課税される可能性があることも確認しておきましょう。
6.負担付贈与契約書の作成方法!各項目の書き方
負担付贈与は口頭でも成立しますが、負担付贈与契約書の作成を強くおすすめします。
しかし、通常の贈与契約書とは異なり、「契約を解除できる項目」や「解除された場合の取扱い」など、記載すべき内容が多岐に渡ります。
この章では、建物を負担付贈与した場合の、負担付贈与契約書の書き方についてご紹介します。
通常の贈与契約書の書き方について、詳しくは「【雛形つき】贈与契約書とは?書き方・生前贈与の注意点を解説!」をご覧ください。
6-1.前文(前置きとなる文章)
まずは前文(前置きとなる文章)に贈与者と受贈者の名前が記され、贈与契約を締結したことを明記します。

6-2.贈与内容や財産内容
第1条の項目では、贈与者はその所有する建物を受贈者に贈与し、受贈者はこれを受諾したことを確認します。
さらに、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など、建物を特定されるための詳細を記載します。

6-3.所有権移転登記に関する内容
第2条の項目では、贈与者は受贈者に対して、いつ建物を引き渡して所有権移転登記手続きを行うのかを記載します。
また、建物を引き渡す際の状態など、建物の所有権移転登記手続きに必要な費用の負担者などを記載します。

6-4.税務に関する内容
第3条の項目では、建物に課税される固定資産税について、所有権移転登記までの分を贈与者、それ以降の分を受贈者の負担とすることを記載します。
第4条の項目では、受贈者が贈与を受ける負担として受贈者が債務を承継することを記載します。

6-5.契約が解除された場合の取扱い
第5条の項目では、贈与者が契約を解除することができるいくつかの場合について記載します。
そして第6条では、負担付贈与契約が解除された場合、受贈者が建物を引き渡し、所有権移転登記手続きをすることを記載します。

6-6.後文と署名捺印
後文にて、この契約を証するために、負担付贈与契約書2通を作成し、それぞれが1通ずつを所持すると記載します。
そして負担付贈与契約を取り交わした日付と、贈与者と受贈者それぞれの署名捺印を行います。

7.負担付贈与を行う際の注意点
負担付贈与を行う際には、いくつか注意点があるので知っておきましょう。
7-1.負担の一部が履行されていると負担付贈与を解除するのが難しい
負担付贈与では、受贈者が負担を履行しない場合は、負担付贈与契約を解除することができます。
しかし、負担の一部が履行されている場合、双方の合意がなければ、原則として契約解除ができなくなります。
契約解除ができなければ、贈与財産の返還がなされず、裁判に発展することも考えられます。
7-2.負担付死因贈与を行う場合は契約書の作成を
負担付死因贈与とは、贈与者の死亡を事由として履行される、負担付贈与契約のことです。
負担付死因贈与を行う場合は、受贈者が負担を履行するか否かがより重要になりますので、必ず負担付死因贈与契約書を作成しましょう。
そして受贈者が契約書に書かれたことを遂行する「死因贈与執行者」を任命し、その旨を契約書に記載しておくと良いでしょう。
詳しくは、「負担付贈与、負担付死因贈与及び負担付遺贈を行う際の留意点」をご覧ください。
8.まとめ
負担付贈与は、財産の贈与の条件として受贈者に一定の負担をさせることができます。
しかし、受贈者の贈与税が高額になる場合や贈与者に所得税等が課税される場合があります。
負担付贈与を検討されている方は、税理士に相談した上で、徹底的な税務シミュレーションを行われることをおすすめします。
8-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、相続税と贈与税を専門とする税理士事務所です。
贈与税の節税に繋がる特例や控除の適用シミュレーションはもちろん、どうすれば相続対策になるのかといったアドバイスも提案させていただきます。
負担付贈与をご検討中でご不明点がある方は、まずはお気軽にお問合せください。
>>【公式】税理士法人チェスターに相談する
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































