公正証書遺言がある場合の相続登記手続きの流れは?必要書類や注意点を紹介
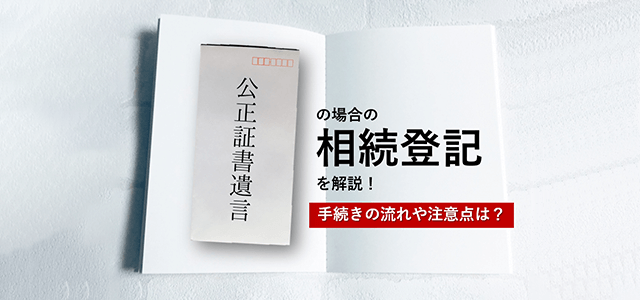
この記事の目次 [表示]
公正証書遺言と相続登記申請の基礎知識
遺言は、公正証書遺言のほかに、主なものとして自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。
公正証書遺言が他の遺言と大きく違うのは、公証役場の公証人が作成している点です。公証人が作成することや証人2名が立ち会うこと、公証役場に原本が保管されることなどから偽造などの不正がなく、自筆証書遺言などよりも信頼性が高いものとされています。
公正証書遺言とは
公正証書として作成された遺言を公正証書遺言といいます。
公正証書は、公証役場で公証人が作成します。法的な信頼性が高く、後に紛争が起きてしまった際には、証拠能力をもつ書面です。遺言書だけでなく、家族信託に関する契約書や売買契約書、贈与契約書なども公正証書で作成することができます。
協議離婚における養育費に関する取り決めなども、公正証書にすることがしばしばあります。
相続の定めと遺言の役割
法定相続人の相続順位や法定相続分などは、民法で定められています。通常は、この定めに従って相続人が決まり、法定相続分をもとに遺産分割協議をするなどして、相続の手続きが行われます。
ただし、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していた場合は、民法の定めよりも遺言の内容が優先されます。遺言者は、相続人や相続財産をあらかじめ指定しておくことができるのです。
公正証書遺言でできること
遺言書の内容は民法の定めに優先されるため、相続が発生してから遺言書の存在が明らかになると、相続人らの間で、遺言書の真偽をめぐる争いが起きてしまうこともあります。このため、自筆証書遺言や秘密証書遺言については、偽造などの不正を防ぐために、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
公正証書遺言は公正証書として作成されているため、偽造などの不正のないものとして認められ、真偽を争うことなくすみやかに相続手続きを開始することができます。
公正証書遺言の保管場所
公正証書遺言ができあがると正本と謄本が遺言者に交付され、原本は公証役場で保管されます。正本と謄本は遺言者が保管することになりますので、金庫などの安全な場所で大切に保管してください。
信頼できる人に謄本を預けたうえで、遺言者が正本を保管するのもよい方法といえます。謄本を預けておくことによって、遺言者が亡くなっても公正証書遺言があったことが明らかになり、相続時に混乱することを防ぐことができます。
また、正本や謄本を紛失してしまった場合でも、原本は公証役場に保管されているので、公証役場で再交付してもらうことができます。
公正証書遺言と検認手続き
遺言書がある場合、自筆証書遺言など(ただし「自筆証書遺言の保管制度」を利用して法務局に自筆証書遺言を預けていた場合をのぞく)については、偽造などの可能性もあるため、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
しかし、公正証書遺言の場合は検認手続きが不要なので、そのまま相続手続きにすすむことができます。相続登記申請においても、公正証書遺言は検認手続きを経ずにそのまま添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の場合の相続登記申請のメリット
公正証書遺言の中で不動産の相続について記載しておくと、遺産分割協議をする必要がなくなるため、手続きがスムーズに進められます。また、遺言者が不動産を誰かに託したいと思っている場合は、その意志のとおりに相続させることができます。
公正証書遺言の場合の不動産の相続は、家庭裁判所の検認手続きが必要ないことや、相続登記申請に必要な添付書類が少なくて済むなどのメリットもあります。
相続登記申請を行わない場合に生じるデメリット
2021年9月現在、相続登記は特に期限が定められているものではありません。しかし、2021年4月に不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続不動産の取得を知ってから3年以内の登記を義務化する規定が施行されます。
相続登記が義務化されると、期限までに正当な理由なく相続登記申請を怠った場合、最高で10万円の過料が科されます。
また、相続が発生すると、相続の承認や放棄の手続きには3か月以内、相続税の納税については10か月以内という定めがありますので注意してください。
これらのほかに、長期間相続登記申請を行わないでいると以下のようなデメリットが生じる場合もあります。
不動産を処分(売却)することができない
不動産は、亡くなった人の名義のままでは売却などの処分をすることができません。同様に、不動産を担保にして融資を受けることもできません。相続した不動産について何らかの契約をしたい場合には、相続登記をしておかなければなりません。
次の相続が発生したときの手続きが煩雑になる
相続人が不動産の相続登記をしないままで亡くなってしまった場合、次世代の相続人は遡って二重の相続手続きをする必要が生じます。これを何世代も繰り返してしまうと、どんどん法定相続人が増えてしまい、手続きは非常に煩雑なものとなります。
不動産を売却したいとか担保にしたい事由が発生したときに、大変なことになってしまうのです。
他の相続人が勝手に相続登記をしてしまう可能性
公正証書遺言で不動産を相続しても、登記をせずに亡くなった人の名義のままにしておくと、他の相続人が勝手に相続登記をすることが可能になってしまいます。
なお、相続登記に関しては、勝手に他の相続人だけの登記名義とする申請をすることは事実上不可能ですが、法定相続分の割合で、法定相続人全員を共同の登記名義人とする内容の申請であれば、法定相続人いずれか1名から行うことができます。
そのため、勝手に共同登記名義人となった相続人のうちいずれか1名だけで、相続登記をして不動産を売却してしまうようなことは、他の相続人の書類を偽造するなどの犯罪を伴うような行為を行わない限りは不可能です。
公正証書遺言の場合の相続登記申請の手続きの流れ
公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが不要なので、すみやかに相続登記申請をすることができます。また、公正証書遺言の場合の相続登記申請は、通常の相続登記申請よりも添付書類が少なくてすむ利点があります。
相続登記申請の、基本的な手続きの流れは以下のようになります。
1 相続する不動産の登記事項証明書を取得する
2 被相続人と相続人の戸籍謄本や住民票、相続する不動産の固定資産評価証明書など、相続登記申請書に添付する必要のある書類を揃える
3 相続登記申請書を作成する
4 相続登記の申請をする
相続登記の申請は、以下のように行います(郵送でも可能です)。
- 相続する不動産の所在地を管轄している法務局へ
- 相続登記申請書と添付書類を提出し
- 同時に登録免許税を納付する(郵送の場合は申請書に収入印紙を貼付しておく)
公正証書遺言の場合の相続登記申請に関するQ&A
公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが不要ですから、公正証書遺言の正本または謄本をそのまま相続登記申請の添付書類として使用することができます。公正証書遺言があれば、通常必要とされる遺産分割協議書は不要です。
Q.相続登記の申請人は?
A.公正証書遺言がある場合の相続登記は、その不動産を承継した相続人が申請人となります。
他に相続人がいたとしても当該不動産を相続する人でなければ、申請人にはなれません。
公正証書遺言で遺言執行者が指定されていた場合、特定財産の承継を記載した遺言(「A不動産を長男に相続させる」といった内容の遺言)については遺言執行者が相続登記の申請人になることができます。
Q.相続登記申請の添付書類は?
A.公正証書遺言による相続登記申請は、一般的な相続登記申請に比べると、遺産分割協議書や相続関係を証明するための戸籍類を添付する必要がなくなるため、添付書類が少なくてすみます。
公正証書遺言の場合の相続登記申請書に添付する書類は以下のとおりです。
- 公正証書遺言の正本または謄本
- 被相続人(遺言者)の死亡が記載されている戸籍謄本
- 被相続人(遺言者)の住民票の除票または戸籍の附票
- 不動産を取得する相続人(複数名であれば全員)の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人(複数名であれば全員)の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
Q.相続登記申請の登録免許税は?
A.登録免許税とは、不動産などの所有権の登記に対して課税されるものです。相続登記も相続による所有権の移転ですから、相続登記申請をするときは、あわせて登録免許税を法務局に納付しなければなりません。
相続登記の登録免許税を求める計算方法は「対象となる不動産の固定資産税評価額×0.004」です。仮に、固定資産税評価額が1,000万円として計算すると、登録免許税は4万円(1,000万円×0.004)となります。
固定資産評価証明書は相続登記申請の添付書類でもありますので、固定資産税評価額を確認したうえで計算してください。どのようにして登録免許税を納付するかについては、登録免許税に相当する額の収入印紙を登記申請書に貼付したうえで、相続登記を申請することが一般的に行われています。
Q.相続登記の申請先は?
A.相続登記は、相続する不動産の所在地(住所地)を管轄している法務局に申請します。法務局は区市町村ごとにあるわけではありませんので、対象となる不動産の住所地について、どの法務局が管轄しているのかを調べる必要があります。
法務局のホームページをみると管轄の案内が載っています。また「住所地+法務局」で検索することでも管轄している法務局を調べることができます。
Q.相続登記申請を専門家に依頼した場合の報酬費用は?
A.相続登記申請を専門家に依頼する場合、通常は司法書士に依頼します。司法書士に依頼した場合に支払う報酬は、およそ5万円~10万円程度といわれています。相続の内容が複雑な場合や関係する相続人が多い場合など、事情によっては報酬も変動することがあります。
報酬の他に実費が必要になります。主な内訳は、登録免許税・相続する不動産の登記事項証明書を取得する費用・戸籍謄本類の交付手数料及び定額小為替の発行手数料・郵便代などです。不動産の筆数や関係する相続人の人数が多い場合には実費も増えることになるため、数千円~数万円まで、内容に応じた費用がかかります。
相続登記申請について相続人間でトラブルが発生した場合には、司法書士では対応できないため、弁護士に依頼して解決する必要が生じます。弁護士費用については、数十万円といわれていますが、相続財産の額に応じて費用も変わりますので事前に確認しておくとよいでしょう。
なお、弁護士に法律相談をするだけの場合は、相談料として30分ごとに5,000円(税別)程度を目安としておいてください。
公正証書遺言の場合の相続登記申請の注意点
公正証書遺言による相続登記申請は、検認手続きが不要なことや添付書類が少なくて済むなどの利点があります。しかし、公正証書遺言による相続であっても、事情によっては相続手続きが複雑になってしまうことがありえます。
法定相続人が遺留分を主張したケース
遺言書の内容は原則として民法の相続の定めに優先しますが、被相続人の配偶者と直系卑属(子や孫)・直系尊属(親や祖父母)については、相続財産に対して最低限の取り分が保障されています。これを遺留分といいます。
配偶者と直系卑属は法定相続分の2分の1、直系尊属は法定相続分の3分の1が、遺留分として認められています。
公正証書遺言は信頼性の高い遺言書ですが、それでも遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害する内容であっても、ただちに遺言そのものが無効になるわけではありませんし、相続登記申請は問題なくできますが、遺留分を侵害された法定相続人は、侵害された遺留分を請求することが可能となります。
なお、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に連絡する前に、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。
専門家に希望する遺言の内容を伝えることで、上記のような遺留分請求のリスクやトラブルを未然に回避できることがあります。公証人との調整も専門家に委ねることができますので是非ご検討ください。
相続人が複数いて必要書類がスムーズに揃わないケース
一つの不動産を複数の相続人が共有して相続する場合、必要書類がなかなか揃わないこともありえます。このような場合には、相続人のいずれかが申請人になれば相続登記申請をすることは可能です。ただし、申請人ではない相続人は、登記識別情報通知を受け取ることができません。
後に不動産を売却することになった場合などに、登記識別情報が揃わないと余計な手続きが必要になります。共有する不動産の相続登記を申請する際には、相続人全員が申請人となって手続きをしておくことをおすすめします。
第三者へ遺贈する旨の公正証書遺言があったケース
被相続人は公正証書遺言で、相続人ではない第三者に不動産を遺贈すると指定することもできます。このような場合、相続ではなく「遺贈」といい、遺贈を受ける第三者を「受遺者」といいます。
受遺者へ不動産を遺贈する旨の公正証書遺言があった場合は、その不動産の名義を被相続人(遺言者)から受遺者へ変更する登記をすることになります。ただし、遺贈する旨の公正証書遺言が存在することを知らない相続人がいると、相続人が受遺者よりも先に、自身に相続登記をして不動産を売却してしまうことも起こりかねません。
受遺者は、第三者へ遺贈する旨の公正証書遺言が存在することを相続人に伝え、遺贈による所有権移転登記をしなければなりません。遺贈による所有権移転登記のことを「遺贈登記」といいます。
公正証書遺言によるものであっても、相続登記と遺贈登記では、手続きに異なる部分があります。
申請者が変わる
第三者へ遺贈する旨の公正証書遺言があった場合の遺贈登記は、受遺者と相続人全員が共同で申請しなければなりません。このとき、遺言執行者が選任されていれば、受遺者と遺言執行者が共同で申請することになります。
遺言執行者が選任されていない場合において相続人全員が申請に協力してくれないと、遺贈登記の申請をすることができなくなってしまいます。受遺者は、相続人に対して登記義務の履行を求める訴えを起こして協力させるか、または家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう手続きが必要になります。
添付書類が変わる
遺贈登記申請と相続登記申請は、添付書類に異なるものがあります。また、遺言執行者がいる場合といない場合でも、それぞれ添付書類が異なりますので、注意してください。
遺言執行者がいる場合の遺贈登記の添付書類は以下のとおりです(このうち、遺言執行者の印鑑証明書以外のものは、原本の還付をしてもらうことができます)。
- 公正証書遺言の正本または謄本
- 登記済権利証または登記識別情報
- 遺言者の死亡が記載された戸籍謄本
- 遺言者の住民票の除票または戸籍の附票
- 遺言執行者の印鑑証明書
- 受遺者の住民票
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
遺言執行者がいない場合の遺贈登記の添付書類は以下のとおりです(このうち、相続人の印鑑証明書以外のものは、原本の還付をしてもらうことができます)。
- 公正証書遺言の正本または謄本
- 登記済権利証または登記識別情報
- 遺言者の死亡が記載された戸籍謄本
- 遺言者の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 受遺者の住民票
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
登録免許税が変わる
相続人以外の人に対する遺贈登記の場合、相続登記とは登録免許税の計算方法が変わります。相続登記では「対象となる不動産の固定資産税評価額×0.4%」でしたが、遺贈登記については「対象となる不動産の固定資産税評価額×2%」となり、相続登記よりも高額になりますので、注意してください。
固定資産税評価額が1,000万円の不動産の場合の登録免許税は、相続登記では4万円となり、遺贈登記では20万円となります。
まとめ
公正証書遺言の場合の相続登記申請は、検認手続きも不要で、公正証書遺言の正本または謄本がそのまま添付書類にできるため、ご自身で申請する際には負担の少ないものといえます。
ただし、相続関係が複雑な場合や相続人の人数が多い場合、遺言の内容に納得がいかない場合などでは、準備が煩雑になってスムーズに進まないことや、トラブルになってしまうこともありえます。
相続登記の申請についてお困りのことがあれば、まず司法書士や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
また、公正証書遺言の場合は、できれば遺言書を作成する前に、その内容について司法書士や弁護士に相談してみることで、トラブルを事前に防ぐことができる場合が多々あります。
遺言者が自身の希望する内容を専門家に話してみれば、それがトラブルになる可能性のある内容であれば、専門家は適切な助言をしてくれます。
公正証書遺言を作成するためにも、公証役場との連絡や打ち合わせなどが必要になります。専門家がその手助けをしてくれる場合もあります。まず専門家に相談して遺言の内容をよく考えてから公正証書遺言を作成することを、あわせておすすめしておきます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































