親の財産管理をするには?任意後見、法定後見、家族信託などの違い
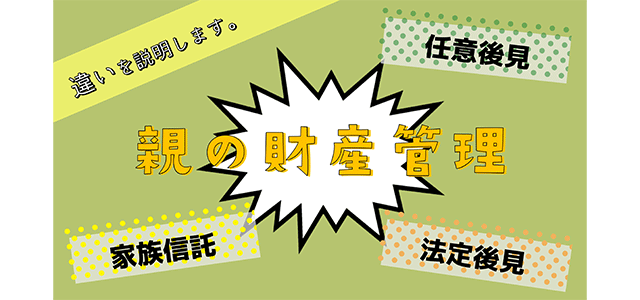
親の財産管理をするには『任意後見制度』『法定後見制度』『家族信託』などを利用できます。それぞれどのような違いがあるのでしょうか?銀行で行える代理人の手続きも押さえておきましょう。親が認知症になる前に、早めの対策が必要です。
この記事の目次 [表示]
1.親のお金を守る対策を考えよう
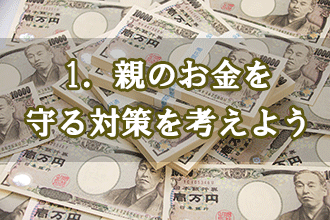
親が築いてきた財産を守るためには、あらかじめ対策を考えておかなければいけません。年齢を重ね認知症になれば資産を自由に動かせません。また、親本人が自由にいつでも使える状態にしておくと、意図せずお金を失う恐れもあります。
1-1.認知症になった後は資産が実質的に凍結
認知症になった親の資産は、実の子どもであっても勝手に動かせません。口座が凍結された状態になるため、親本人の暮らしのために使う目的だったとしても利用できなくなります。
資産の持ち主である親が認知症になると、法的に有効な契約を行うための意思表示が難しい状態と判断されるからです。例えば一人暮らしの親が認知症になったため、老人ホームへの入所を考えているとします。
入所するのに必要なまとまった金額を用意するために実家を売却しようとしても、所有者である親自身が契約できないため、売却は不可能です。親のために現金を用意しようと思っても、できない状態といえます。
1-2.詐欺や無計画な使い方にも注意が必要
年齢とともに認知能力や判断能力が衰えた場合には、詐欺に注意が必要です。被害者が高齢者の架空請求や勧誘販売のトラブルなども増加傾向とされています。
自ら判断し買い物をしているとしても、判断力が低下していると計画性のないお金の使い方をしてしまいがちです。年金支給日に全額使い切ってしまうケースや、同じものを何個も買ってしまうケースもあるでしょう。
親の判断能力不足によってお金を失わないよう、注意する必要が出てきます。
2.認知症になる前に始められる「任意後見制度」

認知症になる前にできる対策として代表的なのが『任意後見制度』です。認知能力や判断能力が落ちる前に、親が自分で後見人を選べる仕組みといえます。ただし、任意後見制度では『取消権』がない点に注意しましょう。
2-1.万が一に備え、自分で後見人を選べる
任意後見制度の特徴は、判断能力があるうちに、親本人が後見人を選べる点です。親が信頼して財産を預けられる家族や専門家を後見人に指名できます。
法定後見制度でも候補者を立てられますが、最終的に後見人を決めるのは家庭裁判所です。親の意向や希望があるとしても、その通りにかなえられるとは限りません。
親本人の意思を最大限尊重したいと考えているなら、任意後見制度を検討するとよいでしょう。
2-2.任意後見人は取消権を持てない
後見人を親が選択できる点は、任意後見制度のメリットです。しかし『取消権』がない点はデメリットといえるでしょう。
取消権とは、法定後見制度を利用したときに認められている権利です。本人が単独で法律行為を行った場合には、取消権を行使し契約を取り消せます。
任意後見制度では、任意後見人が本人の代わりに法律行為を行う代理権は認められていますが、取消権は認められていません。
そのため、本人が単独で大きな契約を結ぶといった法律行為を行わないよう、配慮が必要です。
3.銀行で代理人の手続きをしておく
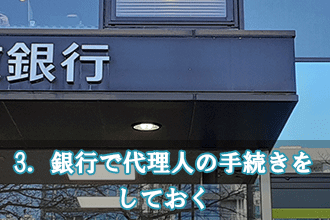
親が口座を開設している銀行で、『代理人』の手続きをしておくのもよいでしょう。手続きしておけば、代理人として親に代わって口座を管理できます。
3-1.代理人カード
親が高齢になると、銀行口座の暗証番号を忘れてしまう・キャッシュカードをなくしてしまうといった事態もあり得ます。そうなると、子どもが親の代わりにお金を引き出すといった対応を取れません。
『代理人カード』を作成しておけば、親本人の代わりに子どもがお金を引き出せます。手続きをするのは、口座の名義人である親本人です。
通帳やキャッシュカードのほかに、本人確認書類や届出印を窓口に持参し手続きしましょう。銀行から代理人カードが発行されたら、口座の管理をする子どもが受け取ります。
代理人カードを持っていれば、窓口はもちろんATMでの出金も可能です。
3-2.代理人指名手続
『代理人指名手続』をしておくのもよいでしょう。手続きは親本人のみでできます。代理人に指名する人が銀行に出向く必要はありません。
口座の名義人である親本人が手続きしておけば、認知症になり施設への入所金が必要な事態となっても、あらかじめ指名されている代理人が親の口座から出金できます。
定期預金の解約といった手続きも、代理人による実施が可能です。まとまった資金が必要なときにも、親本人の資産で対応できます。
4.「家族信託」「民事信託」という方法も

『家族信託』や『民事信託』を利用し、家族のみで親の財産を管理する方法もあります。不動産の活用といった積極的な運用も可能です。成年後見制度では実現できない、柔軟な管理ができます。
4-1.家族に財産の管理を任せられる
家族信託を利用するメリットとして、家族に財産の管理を任せられる点が挙げられます。これまで大切に築き上げてきた財産を信頼できる人に任せたいと親が考えているなら、家族信託はぴったりの仕組みです。
信託銀行や裁判所を介さず、家族間のみで自由に契約内容を決められるのもポイントといえます。決まりごとの多い制度では、親が希望する通りに管理できないかもしれません。
しかし家族信託による柔軟な財産管理であれば、親の意思を反映しやすいでしょう。
4-2.第二受託者を選任できる
万が一のときに備え『第二受託者』を選べるのも、家族信託の特徴です。家族信託の受託者が死亡した場合、親は新たな受託者を選ばなければいけません。
しかし高齢で判断能力に衰えが見られる場合、新しく受託者を選ぶのが難しいケースもあるでしょう。そこであらかじめ第二受託者を決めておきます。
また信頼して財産の管理を任せた受託者が、資産を使い込むケースもないとはいえません。このようなときに第二受託者がいれば、受託者を止める働きを期待できます。このようなトラブル発生時の対策としても役立つ仕組みです。
4-3.財産を守るだけでなく柔軟な管理が可能
柔軟に財産を管理できる家族信託を利用すると、親の財産を犯罪被害から守れます。家族信託を使えば、親の預金の名義を子ども名義に変更できるからです。
日々の暮らしに必要な支払いを子どもが管理できるため、振り込め詐欺といった犯罪の被害を未然に防げます。加えて財産を子ども名義にすることで、相続税対策も実行しやすいでしょう。
例えば不動産の買い替え・賃貸物件の建て替え・借入によるアパートの建設などが代表的です。
4-4.任意後見制度との併用も可能
ただし家族信託には『身上監護権』がありません。そのため介護サービスの利用契約や老人ホームの入所契約など、生活や医療・介護など身の回りに関わる契約を家族ができない状態です。
親が元気なうちは問題ないでしょう。しかし高齢になり認知症やその他の病気で判断能力が衰えた場合には、代わりに契約などの法律行為を担える人が必要です。
また『年金受取口座』や『農地』『借地権』など、一部の財産は信託財産に入れられません。家族信託だけで全てをカバーできないときには、代理権のある任意後見制度と併用すると解決できます。
5.既に認知症の場合はどうなる?
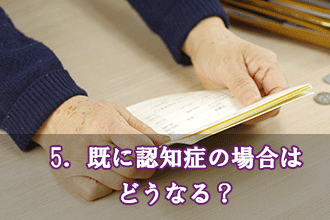
既に親が認知症を患っているなら、利用できるのは『法定後見制度』です。家庭裁判所に選任された後見人による、より手厚い支援を受けられます。ただし家族信託や任意後見制度を利用する場合と比較し、財産の使い道が制限される点はデメリットです。
5-1.「法定後見制度」を利用する
親が既に認知症なら、財産管理のためにできるのは法定後見制度の利用です。認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人に後見人を付け保護します。
判断能力に応じて『補助』『保佐』『後見』の3種類に分類される制度です。任意後見制度とは異なり、親は既に認知症のため、後見人を自分で選べません。
家庭裁判所に後見人の推薦はできますが、相当ではないと判断される可能性もあるでしょう。その場合、家庭裁判所が選任する弁護士や司法書士が後見人になります。
5-2.資産の使い道が限定される
任意後見制度であれば、あらかじめ後見人に財産管理について任せたいことを決めておけます。家族信託なら財産を子ども名義にすることで、積極的な運用も可能です。
一方、法定後見制度を利用すると、資産の使い道は狭い範囲に限定されます。親本人のための利用として、扶養家族の生活費・親の債務の弁済・後見人の職務遂行に必要な費用などには使用可能です。
ただし、あくまでも財産の持ち主は親のため、領収書やレシートを保管し厳密に管理しなければいけません。不適切な支出があれば、解任措置や刑事告発の可能性があります。
そのため親がたくさんの資産を持っている場合でも、その資産を生かした運用はできません。
5-3.専門家に依頼する場合は費用が発生
後見人として弁護士や司法書士が選任されると、毎月報酬が発生します。基本報酬の目安は『月2万円』です。
ただし管理財産の量によって管理の煩雑さが異なるため、基本報酬の金額が変わります。目安として、財産が1,000~5,000万円なら『月3~4万円』、5,000万円を超えるなら『5~6万円』に設定されるケースが多いでしょう。
一度後見制度を利用すると、基本的に制度の利用はやめられません。親が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。
6.認知症になる前と後で管理方法が異なる

高齢になった親の財産管理の仕方は、認知症になっているかいないかで異なります。認知症になった後なら、法定後見制度を利用しましょう。家庭裁判所が選任した後見人による管理が行われます。
認知症になる前であれば、親が自分で後見人を選ぶ任意後見制度の利用が可能です。家族信託で財産の運用を実施し、相続税対策にも取り組めます。
相続税対策を計画的に実施するなら、『税理士法人チェスター』に問い合わせるとよいでしょう。
『成年後見制度』については下記もご覧ください。
「成年後見制度」を制度をわかりやすく解説!どんな制度?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































