相続登記は権利証ナシでもできる!【プロが解説】理由と必要な事例
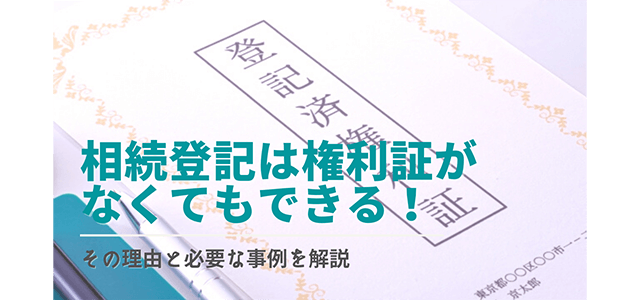
この記事では、権利証や登記識別情報とは何か、その存在意義等について解説した上で、権利証等がなくても相続登記ができる理由、相続登記の手続に必要となる添付書類の内容、さらに例外的に権利証等が相続登記で必要となる事例等について解説しています。
この記事の目次 [表示]
相続登記は権利証がなくてもできる
権利証(登記済証、登記済権利証)とは? 登記識別情報との関係
権利証とは、所有権移転や抵当権設定等の登記手続が完了した後に、平成17年頃まで登記所(法務局)から交付されていた書面のことをいいます。登記済証、登記済権利証と呼ばれることもあります。
この権利証ですが、平成16年に不動産登記法が改正され、平成17年頃から各登記所で順次発行されなくなりました。現在は全国どこの登記所においても発行されていません。現在は、権利証に代わるものとして、登記識別情報という12桁の英数字を組み合わせた情報が通知されるようになっています。その役割については後ほど解説しますが、権利証とほとんど変わりません。
登記識別情報は、登記手続が完了した後に交付される登記識別情報通知書という書面に記載されています。
ただし、この登記識別情報は、次に登記手続を行うまで使用しませんので、登記識別情報が記載された箇所が袋とじになっており、または登記識別情報が記載された箇所の上にシールが貼られており、外部からはその英数字が確認できないようになっています。
なぜ権利証が廃止されて登記識別情報が発行されるようになったかというと、権利証という書面では、平成16年の不動産登記法の改正によって導入された不動産登記のオンライン申請に馴染まなかったからです。
なお、既に発行済みの権利証は、これまでどおり登記申請の際の添付書類として利用しますので、引き続き大事に保管するようにしてください。
権利証や登記識別情報は、主に登記手続の際の本人確認の手段として利用されます。 具体的には、不動産の譲渡に伴う所有権移転登記や、借入の際に行う抵当権設定登記等の手続をする際に、添付書類として提出を求められます。
なぜ権利証や登記識別情報の提出を求められるかというと、これらの権利に関する登記をすると、現在登記名義人となっている人は不動産の権利を失うなどの不利益を受けることになるため、きちんと本人の意思に基づいて登記申請がなされているか(登記名義人に成りすました人からの登記申請ではないか)を確認しなければならないとされているからです。
そこで、このような権利に関する登記の申請について、登記名義人(登記義務者)と新たに登記上の権利を取得する人(登記権利者)との共同申請を求めるとともに、権利証等や印鑑証明書を提出させることによって、登記義務者の本人確認を厳重に行っているのです。
なお、権利証等の提出がなぜ本人確認に繋がるかというと、通常、不動産の登記名義人は、権利証等を厳重に保管・管理しているはずですので、権利証を所持していたり登記識別情報を知っている人は登記名義人だろうという推認が働くからです(もっとも、権利に関する登記を申請する際には、権利証や登記識別情報のほかに、印鑑証明書等の提出も求められますので、権利証等を無くしたとしても直ちに不動産の名義が変えられてしまう心配はありません。)。
登記手続と権利証の関係について
権利証や登記識別情報は、既述のとおり、不動産の譲渡に伴う所有権移転登記や、不動産を担保にして借入をする際に行う抵当権設定登記等、権利に関する登記手続に必要となります。
これに対して、相続を原因とした所有権移転登記手続を行う場合は、原則として権利証等の提出が必要とされていません。その理由を以下で解説します。
相続登記で権利証の添付が不要な理由
相続登記で権利証や登記識別情報の添付が不要な理由として、相続登記は不動産を取得した相続人が単独で申請することが認められている点が挙げられます。
なぜ相続登記について単独申請が認められているのかというと、相続は、売買等と異なり、被相続人が亡くなったことを原因として財産の承継が生じますので、登記名義人である被相続人の意思を確認する必要がないからです。
また、そもそも登記名義人である被相続人は既に亡くなっていますので、被相続人の意思は確認できません。
そこで、相続登記を受け付ける登記所としては、登記名義人である被相続人が死亡した事実を、被相続人が死亡した旨の記載がある戸籍謄本等によって確認すれば足り、登記手続の共同申請を求めたり、権利証や登記識別情報を使った本人確認を行う必要はないとされているのです。
相続登記に必要な書類一覧
次に、相続登記に必要な書類について解説します。
繰り返しとなりますが、相続登記を申請するにあたり、原則として権利証の提出や登記識別情報の提供は不要とされています。
しかし、例外的にいずれかの提供が必要とされることがあります。その場面や理由等については、本記事の最後で解説します。
相続登記を申請する際、その添付書類として、主に相続が発生したことと、誰がどのように不動産を相続するのかを証明するための書類が必要となります。
以下のとおり、誰がどのように相続するかによって、必要な書類も少しずつ異なってきますので、順番に見ていきましょう。
法定相続分で相続登記をする場合
まず、相続人が法定相続分で相続する場合に必要となる書類は、以下のとおりです。権利証や登記識別情報の提出は、原則として求められません。
② 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等一式
③ 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)または戸籍の附票
④ 相続人全員の戸籍謄本(相続が発生した後に取得したもの)
⑤ 相続人全員の住民票(本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
⑥ 相続する不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
なお、戸籍謄本の原本を返還してもらいたいときは、原本と一緒に、戸籍謄本のコピー又は相続関係説明図を提出してください。
また、登記申請書を作成するにあたっては、不動産の登記事項証明書が必要となりますので、必ず取得するようにしてください。
遺産分割協議により相続登記をする場合
一般的に多い相続の形態は、遺産分割協議による相続になります。遺産分割協議は相続人間の話し合いにより相続人の中で誰が相続するかを決めて、遺産分割協議書を作成します。
この場合、前記の法定相続分で相続登記をする場合に必要な書類(①~⑥)に加えて、以下の書類が必要となります。
⑧ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたものでなくて良い)
また、前記①~⑥の書類のうち、⑤の住民票が必要なのは不動産を相続する人の分のみとなります。
なお、こちらの場合も、権利証や登記識別情報の提出は求められていません。
遺言書により相続登記をする場合
遺言書により相続登記をする場合、法定相続人に相続させる場合と、それ以外の場合(遺贈する場合)とで必要書類が大きく異なります。
・遺言書により法定相続人に相続させる場合
まず、遺言書により法定相続人に相続させる場合(「相続させる」旨の遺言、または特定財産承継遺言と呼ばれます。)に必要となる書類は、以下のとおりです。
(2) 被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの)
(3) 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)または戸籍の附票
(4) 不動産を取得する相続人の戸籍謄本(相続が発生した後に取得したもの)
(5) 不動産を取得する相続人の住民票(本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
(6) 相続する不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
(7) 遺言書
上記のとおり、遺言書がいわゆる「相続させる」旨の遺言である場合は、相続登記に権利証の提出または登記識別情報の提供が求められておりません。
なお、遺言書が自筆証書遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は、別途家庭裁判所での検認手続が必要になりますのでご注意ください。
・遺贈する場合(遺言執行者がいる場合)
次に、不動産が遺贈された場合(法定相続人以外の第三者に遺贈されるケースが多いです。)に必要となる書類は、遺言執行者がいるかどうかによって異なります。
しかし、いずれの場合であっても、権利証または登記識別情報が必要となりますのでご注意ください。
まず、遺言執行者がいる場合、前記の遺言により法定相続人に相続させる場合に必要な書類((1)~(3)、(5)~(7))に加えて、以下の書類が必要となります。
(9) 遺言執行者の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
また、前記(1)~(3)、(5)~(7)の書類のうち、(5)の住民票は、遺贈により不動産を取得する人の分が必要となります。
・遺贈する場合(遺言執行者がいない場合)
次に、遺言執行者がいない場合に必要となる書類は、以下のとおりです。
(ⅱ) 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等一式
(ⅲ) 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)または戸籍の附票
(ⅳ) 相続人全員の戸籍謄本(相続が発生した後に取得したもの)
(ⅴ) 遺贈により不動産を取得する人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
(ⅵ) 相続する不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
(ⅶ) 遺言書
(ⅷ) 権利証または登記識別情報通知書(被相続人が不動産を取得したときに発行されたもの)
(ⅸ) 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
以上のとおり、遺言書に不動産の遺贈が含まれる場合、その遺贈に基づいて所有権移転登記手続をするためには、権利証または登記識別情報が必要となります。
このように、遺贈する旨の記載が遺言書にある場合は、登記手続に必要となる書類も非常に複雑となりますので、相続登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。
相続登記で権利証の添付が必要な事例
①被相続人の最終の住所と登記記録上の住所の一致を証明できない場合
次は、例外的に相続登記で権利証や登記識別情報が必要となるケースについて紹介します。
まず、被相続人の最終の住所と登記記録上の住所の一致を証明できないケースです。
相続登記を受け付けた登記所としては、被相続人とされている人物が不動産の登記名義人と同一人物であることを確認する必要があります。仮にこれらが同姓同名の別人物ですと、誤って赤の他人が所有する不動産の名義を変更させることになってしまうからです。
具体的な確認方法は、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票を提出させて、名前や本籍だけでなく住所も一致していることを確認します。
しかし、住民票の除票等の保存期間が経過しているなどして、住所の一致を証明できる住民票の除票等を取得できないケースがあります。
このような場合、権利証の提出があれば、被相続人と登記名義人を同一人物であると扱って良いとされています。権利証は登記名義人が保管していたはずですので、相続人がそれを所持していれば、登記名義人=被相続人だろうと考えられるからです。
②遺贈を原因とする所有権移転登記を行う場合
次に権利証等の提出が必要なケースとして、前に触れましたとおり、遺言書で不動産を遺贈するケースが挙げられます。
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を無償で譲る処分(遺言による贈与)のことをいいます。
遺贈を原因とする所有権移転登記は、通常の相続登記とは異なり、登記権利者と登記義務者とが共同して登記申請しなければならないとされています。ここでいう登記権利者は、遺贈により不動産を取得する人を指し、登記義務者は、遺言執行者または共同相続人全員(遺言執行者がいない場合)を指します。
この場合、登記義務者の本人確認が必要となりますので、権利証または登記識別情報の提出が必要となります。
相続登記で権利証がない場合の解決方法
では、遺言書で不動産が遺贈されたケースであるにもかかわらず、権利証や登記識別情報がない場合はどうすれば良いでしょうか。
このような場合であっても、権利証等による本人確認に替えて、登記所が登記名義人の登記記録上の住所に宛てて本人限定受取郵便(登記名義人が法人の場合は書留郵便)を送付し、登記申請があったことを知らせると共に、当該申請内容が真実であることを申し出るように促して本人確認を行う制度(事前通知制度)が用意されています(不動産登記法第23条第1項、第2項)。
また、司法書士等の資格者代理人や公証人が登記義務者の本人確認を行い、その情報(本人確認情報)を提供する方法もあります(同条第4項)。
以上のとおり、権利証がお手元になくても直ちに遺贈の登記ができなくなるわけではありませんので、諦めずに司法書士等の専門家にご相談ください。
まとめ
権利証は、相続登記において基本的には必要な書類ではありません。もし、相続が開始してから権利証が見つからないことに気付いたとしても、慌てずに司法書士などの専門家に相談してみましょう。
しかし、この記事で紹介しましたとおり、例外的に権利証が必要となる場合もあります。特に、遺言書に遺贈する旨の記載がある場合は、大変複雑な手続きになることが予想されますので、ご注意ください。
不動産は大きな財産ですから、登記手続は法務局によって厳正に行われています。もし書類に不備や不足があれば補正や取下が必要になります。そうなると時間や労力が余計にかかってしまい、ご自身の負担も大きくなります。専門家に依頼して、速やかに正確に相続登記をするのも、よい方法といえるでしょう。
また、相続登記が終わると新しい登記識別情報が交付されます。将来、不動産を売却するとか担保に入れることがあれば、この新しい登記識別情報が必要になります。ぜひ大切に保管しておいてください。
司法書士へのご相談は相続専門【司法書士法人チェスター】へ ››
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































