保存行為として行う相続登記を解説!相続人の1人からの申請、死者名義にする場合も
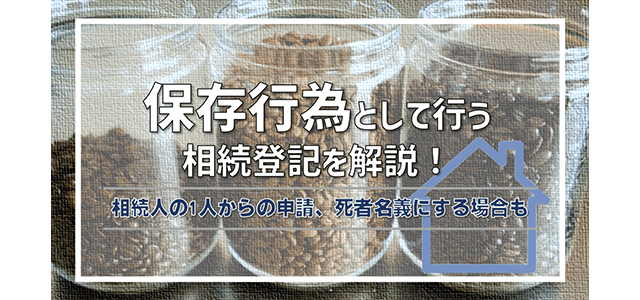
法律には保存行為という概念があります。簡単にいうと、財産の変更や処分をせずに、現状を維持するための行為を言います。たとえば、家の雨漏りを修繕するような行為は、建物の現状を維持するために必要な行為で、保存行為に当たります。
家を単独で所有している場合、その所有者は、家を売ったり、他人に貸したり、雨漏りを修繕することができます。
他方、複数の人で家を共有している場合、売るにも貸すにも共有者全員(または共有者の持分の過半数)の同意が必要となるなど、様々な制約があります。
しかし、家の雨漏りを修繕するなど、財産の現状を維持するために必要で他の共有者の不利益にならないような行為は、保存行為として共有者の一人が単独で行うことができるとされています。
この保存行為ですが、相続登記が保存行為として行われることがあります。
では、保存行為として行われる相続登記とは、どのような相続登記のことを指すのでしょう。
順を追って説明していきます。
この記事の目次 [表示]
相続登記の基礎知識
保存行為として行われる相続登記について解説する前に、まず、相続登記の基礎知識について解説します。
相続登記には、大きく分けて、民法で定められた法定相続分のとおりに登記する「法定相続登記」、話し合いにより遺産の分配方法を決めて登記する「遺産分割による相続登記」、遺言がある場合の「遺言に基づく相続登記」の3つがあります。それぞれ詳しく見ていくことにしましょう。
①法定相続登記
民法では、相続人となる人、順位、それぞれの相続割合が定められています。
たとえば、Aさんが亡くなられて、その配偶者Bさんと、子供のCさんとDさんの合計3人が相続人である場合、その相続割合は、配偶者が半分(2分の1)、子供たちが2分の1を2人で分け合うので、各4分の1、すなわち分母をそろえると、配偶者4分の2、子供各4分の1となります。
この民法で定められた相続割合を変更せずに、そのまま登記することを「法定相続登記」といいます。
②遺産分割による相続登記
上記の例で、配偶者BさんがAさん名義の不動産にこれからも居住し続けるので、家の名義はBさんの単独名義にしたい、という場合はどうでしょうか。
この場合には、Bさん、Cさん、Dさんの3人で「土地と建物は、Bが取得する」という内容の遺産分割協議をします。すなわち、Cさん、Dさんが自分の権利を譲る形にするわけです。
蛇足ですが、この譲る行為を「相続を放棄した」と表現する場合がありますが、相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをして、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がずに最初から相続人でなかった旨の審判を受ける制度です。法律用語としては、遺産分割で権利を譲ることは相続放棄とは言いません。
さて、この遺産分割協議の結果を「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名押印(実印)したものを添付して相続登記すると、Bさんの単独の名義にすることができます。
③遺言に基づく相続登記
上記の例で、Aさんが生前に「土地と建物はBに相続させる」という内容の遺言を遺していた場合には、その遺言書を添付して相続登記することで、遺言書どおりのBさんの単独名義にすることができます。
この場合には、CさんとDさんの協力は必要とせずに、Bさんが単独で相続登記をすることができます。
保存行為として行う相続登記とは
では、「保存行為」として行う相続登記とはどのような場合をいうのかについて説明していきます。
通常の相続登記との違い
不動産登記の申請には「申請人」が必ず存在します。それは登記申請の当事者です。自分で登記申請する場合には登記申請書に印鑑を押します。司法書士に依頼する場合には、登記申請委任状に印鑑を押し、司法書士が「申請代理人」として申請します。
つまり、不動産名義を取得する当事者が申請書(または司法書士への委任状)に登場する必要があります。これを相続に当てはめると、登記名義を取得する相続人全員が申請人になるのが原則です。
ただし、1つだけ「保存行為なら当事者のうちの1人から申請していいですよ」となっています。
相続登記申請の場合は、法律で定められた相続割合に従って、そのまま現状維持の状態を登記簿に反映するのならば、相続人のうちの1人からの申請で登記してもよい、ということになっています。
すなわち、法定相続登記の場合、通常の相続登記とは異なり、単独で相続登記を申請することができます。
保存行為としての法定相続登記の一例
まず前提として、先ほどのAさんがお亡くなりになり、配偶者がBさん、子供がCさん、Dさんの場合、相続分は先ほど確認したとおり、Bが4分の2、CとDがそれぞれ4分の1です。
この場合に、それぞれが別々に自分の持分についてだけ相続登記することはできません。
ですから、保存行為として法定相続登記をBさんが申請する場合には、必ず「4分の2 B、4分の1 C、4分の1 D」と全員の持分を登記簿に反映させる必要があります。そうすると、「勝手に自分以外の人の分を申請していいの?」という疑問があるかと思います。
しかし、それこそが「保存行為」を意味するものなのです。法律で決まっている割合なのだから、それをそのまま変更せずに登記したとしても誰も不利益はないでしょう、というのが法律の考え方です。
保存行為としての相続登記に関する注意点・デメリット
権利に関する不動産登記を申請すると、登記識別情報(所有権を取得したことを証する情報が記載された書面のことです)が通知されます。この登記識別情報が通知される条件は、「申請人自らが登記名義人となる場合」です。
では、上記の保存行為により他の法定相続人の持分まで登記するとどうなるでしょう。
申請人は、保存行為として申請した相続人のうちの1人です。「申請人自らが」「登記名義人になる」という2つの条件を満たすのは、申請した相続人だけです。すなわち、他の相続人は登記名義も権利も取得しますが、登記識別情報は手に入れることはできません。
この場合に、他の相続人の権利が否定されることはありませんが、次に売却する際などには、登記識別情報の提供が必要となります。他の相続人は登記識別情報を所持していないので、別の手続き(司法書士による本人確認情報の作成や公証人による本人確認など)が必要になるため、別途司法書士等に支払う報酬が必要となることがあります。
法定相続登記を選ぶと良いケース
では、保存行為として法定相続登記を申請するメリットは何かというと、他の相続人の協力を得ることなく、相続登記をすることができる、という点です。
たとえば、他の相続人に認知症の方がおられる場合や行方不明の場合などです。この場合、本人が意思を表示できなくても、他の相続人が保存行為として相続登記を申請すれば、相続登記自体はできるからです。
ただ、法定相続登記ができたとしても、その後売却するような場合にはやはり、共有者である他の相続人の協力が必要となります。
認知症の方や行方不明者がいる場合には、それらの方の売却意思の表示が必要となりますから、そのままでは売却まではできないことになります。
なお、共有者に認知症の方がいれば、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらったり、行方不明の方がいれば、不在者財産管理人を選任してもらったりすることで、認知症の方や行方不明者の方の代わりに売却の手続に協力してもらうことはできます。しかし、時間と手間のかかる手続きを要します。
保存行為としての相続登記を事例で紹介
法定相続登記をする際に保存行為として他の相続人の名義も含めて登記ができることはお話ししたとおりですが、ここではもう1つ「死者名義の相続登記」というものをご紹介します。
相続人に死者がいる場合の申請書の記載内容
前提となるケースですが、たとえばAさんが亡くなられ、相続人が配偶者のBさんと子供のCさん(一人っ子)である場合とします。相続登記をしないまま、Bさんも亡くなられた場合を想定してみましょう。下記のとおりです。
① A 平成25年3月10日 死亡
② B 令和3年5月9日 死亡
このような事例では、Aさんが亡くなられた時の相続人とその相続分が、Bさん2分の1、Cさん2分の1となっており、さらにBさんが亡くなられたので、Bさんが相続した2分の1は令和3年5月9日にCさんのものになります。
結果的には、Cさんがすべての権利を1人で取得することになるので、AさんからCさんへ直接相続登記ができそうにも思えます。ところが、これはできず、2回に分けて登記手続をしなければなりません(特に一人っ子の場合)。
では、申請書はどのような記載になるでしょうか?
≪1件目≫
原 因 平成25年3月10日相続
相 続 人 (被相続人 A)
住所
持分2分の1 亡B
住所
(申請人)持分2分の1 C
→Bさんは死亡していて申請人にはなれないため、Cさんが保存行為として法定相続登記をします。
≪2件目≫
原 因 令和3年5月9日相続
相 続 人 (被相続人 B)
住所
持分2分の1 C
→これにより、1件目のBさんの2分の1もCさんに移転するため、この不動産はCさんが単独で所有することになるわけです。
余談ですが、数年前までは、1回の申請でCさん名義に変更する相続登記をすることができていました。
Bさんが亡くなられていたとしても、CさんはBさんの相続人なのだから、Aさんの相続については、Bさんの権利も義務も引き継いだCさんが、Bさんの相続人の地位とAさんの相続人の地位の2つの肩書を記載して遺産分割協議書を作成することにより可能だったのです。
しかし、現在はこのような登記申請は受け付けられません。
一人っ子の場合は、実質一人で決めただけであり、協議(話し合い)にはならないだろう、というのが禁止された理由です。
死者名義への相続登記を行う場合の取り扱い
死者名義で相続登記をする場合、土地についての登録免許税が免除される特例があります。
上記の例では、1件目で2分の1ずつ登記しましたが、Bさんの2分1についての土地の登録免許税が免除されます。
たとえば、土地の評価額が1,000万円、建物の評価額が500万円であるとすると、通常は足したもの(1,500万円)に1,000分の4を掛けますので、6万円が登録免許税(印紙代)となるのですが、土地についてはBさんの2分の1分が免除されますから、土地500万円、建物500万円で1,000万円に1,000分の4をかけたもの、つまり4万円が登録免許税(印紙代)となります。
この場合には、免除の根拠条文として、「租税特別措置法第84条の2の3第1項適用」と申請書に記載しましょう。
まとめ
今回ご紹介したケースは、頻繁に起こりうるケースではありませんが、保存行為として他の相続人の協力を得ることなく単独でできる相続登記があり、また死者名義への相続登記をする場面もあるということを知っていただければ幸いです。
相続登記に関するご相談については司法書士法人チェスターで承っております。
お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































