共有持分の相続登記を解説!申請書作成時のポイント、注意点、書類サンプルも
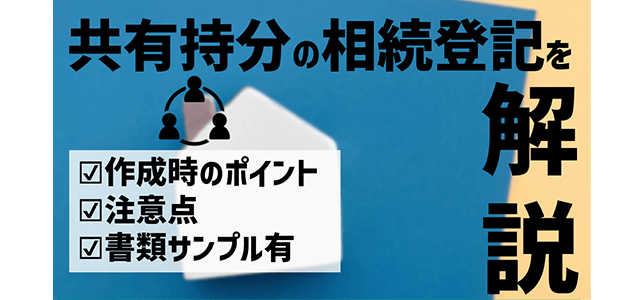
不動産を所有する形態は必ずしも1人の名義(単有)とは限りません。他の人と割合を決めて持ち合う形態(共有)も多くあります。今回は、共有にまつわるお話をしていこうと思います。
この記事の目次 [表示]
共有持分とは
不動産が共有状態になる経緯としては、たとえば夫婦がお互いに資金を出して不動産を購入する場合に、不動産の売買代金が3,000万として、ご主人が2,000万円、奥さんが1,000万円を支払ったとすると、不動産登記をする場合には「持分3分の2がご主人、持分3分の1が奥さん」の状態で登記されます。
共有持分とは、土地のこの場所から3分の2の部分がご主人、残り3分の1の部分が奥さん、という意味ではありません。物理的な割合を指すのではなく、不動産全体をそれぞれの持分割合で所有していますよ、という意味です。つまり、観念的な持分ということになります。
1人で所有する単有の場合と違って、ほかの人の権利があるため、売却したり賃貸に出したりする際に、自分だけの考えで勝手に決められないという、意思決定に制限がかかることが大きな特徴となります。
不動産が共有状態である場合に、単有の場合と比較してどのような不都合が生じてきたりするのか、また、相続登記にどのような手続きが必要になるのかなどについて触れていきます。
共有状態の不動産に関する注意点
不動産が共有状態である場合に、他の共有者の持分も含めてその不動産を売却したいと考えたとしても、他の共有者も同じ考えでないと売却することができません。
他方、法律上は、自分の持分だけを売却することは可能です。ただ、果たして自分の持分だけを売却することは可能でしょうか。
ご自身が不動産を購入する場合に、誰かの持分だけを購入し、知らない誰かと共有状態になることができるでしょうか。持分だけを購入するような専門業者もあるようですが、普通一般の方はそのような持分だけを購入したりはしません。
ですから、共有状態の不動産の売却を考えたときには、共有者全員の意思決定のもとで売買契約を締結しなければ、実際には不動産を処分することは困難なのです。
簡単に言えば、共有状態とは「自分の持ち物ではあるけれども、自分だけの意思では自由にできない状態」ともいえるわけです。
共有者の一人が不動産を売却したいと考えている一方で、他の共有者が不動産の売却に同意してくれない場合、他の共有者が自分の持分を買い取ってくれるなら良いのですが、他の共有者が譲渡代金を準備しなければならず、簡単ではありません。
そこで、不動産の共有状態を解消する一つの方法として、土地の場合ですが、「分筆」という方法があります。これはある程度広さのある土地であれば、検討できる方法です。
たとえば、甲土地が持分2分の1がA、持分2分の1がBであった場合に、甲土地を甲1、甲2と2つの土地に分筆します。そうすると、2つの土地に分かれるのですが、この状態では、甲1土地の所有者がA、甲2の土地の所有者がBとなったわけではないのが注意点です。
今どうなっているかというと、甲1土地は持分2分の1がA、持分2分の1がBとなっており、甲2土地も同様です。これを、それぞれの持分を「交換」という原因を使って、持分移転することによって、甲1土地が所有者A、甲2土地が所有者Bといった単有状態の土地を2つ作ることができるのです。
なお、分筆登記の手続きは、土地家屋調査士という国家資格者に依頼することができます。
このように、一度不動産を共有状態にしてしまうと、どのような形をとっても費用がかかったり、時間がかかったりします。不動産を購入する際や、誰が相続するかを決める際、不動産が共有状態になることにより、将来的にどのような不都合が生じるのかを十分に考えたうえで共有状態にすべきかどうかを決めるべきです。
現実的な話をすれば、夫婦共有で購入した場合でも、将来離婚した時には何らかの共有解消方法を考えなければならなくなったりします。
共有持分でも相続登記は必要
共有状態の不動産があるとします。たとえば、父Aが2分の1、母Bが2分の1の状態で、Aさんが亡くなられた場合には当然持分の2分の1だけに相続が発生します。この2分の1を遺産分割によって、母Bと子供がCDいたとして、3人で協議の結果2分の1をCとすることができます。
持分は他の共有者に名義変更すると良い?
上記の例で、子Cに父A持分2分の1を相続させることにする場合があります。その背景には、将来母Bが亡くなった場合にCDで話し合い母の2分の1もCにすることで、結果的にC2分の1、C2分の1すなわち単独所有(単有)になるわけです。
Cが親と同居している場合や実家を継いでいく場合、あるいは母が亡くなった時点で売却するような場合にはこのように移していくのもひとつの方法です。
また、父Aが亡くなった時点で、母にその2分の1を相続することにすれば、そこで母持分2分の1、母持分2分の1すなわち単独所有(単有)となるため、母Bに移しておくのでもよいと思います。
ただ、母はすでに高齢だという場合に、認知症になった時には自宅を売却して施設に入所する可能性もあるというようなことを考えた場合には、母Bは認知症になった後では成年後見人の選任なくして不動産を売却することができなくなるため、その点も考えておくべきでしょう。
私道の共有持分が相続対象である場合も登記が必要
不動産を購入する場合に、自宅の土地と建物のほかに私道部分やごみステーションの土地を近隣の所有者と共有で取得することがあります。登記名義を取得しておかなければそこの土地を使用できないことになります。つまり、自宅部分の土地建物は単有で、私道やごみステーションは数人の方との共有状態であるわけです。
このようなケースはかなりありますが、実際に居住していても、自宅部分以外の共有部分については所有している感覚がなく、相続が発生した場合には相続登記を忘れてしまうこともあります。売却するとなった場合に相続登記を忘れていたことに気づくこともあるのです。
これが売却せずに後の世代まで相続登記を忘れたまま自宅の土地建物だけを名義変更していった場合には、いずれとても面倒なことになりますから、最初の相続時に忘れずに相続登記をしておきたいところです。
もれなく相続登記をする方法としては、不動産所在地の市区町村で「名寄帳」を取得します。これはたとえばAさんが甲市で所有している不動産を全部知りたいという場合には、甲市役所でAさんの「名寄帳」を取得すればもれなく把握することができます。
共有持分の相続登記申請書を作成する際のポイント
共有持分だけの所有権移転登記を申請する場合には、少しだけ通常の所有権移転と異なってきます。具体的に登記申請書の記載方法について見ていくことにしましょう。
①登記の目的
現在の登記簿の記載が、「持分2分の1がA、持分2分の1がB」である場合で、Aさんが亡くなって、遺産分割協議の結果、配偶者のBさんに亡Aさんの持分を移転するという例で考えていきましょう。
まず登記の目的は、通常単有の場合には「所有権移転」と記載しますが、この場合は、所有権全体を移転するのではなく、Aさんの持分だけを移転しますから「A持分全部移転」とします。忘れがちなのが「全部」というワードです。これでAさんの持っている2分の1をすべて移転しますよ、というのがわかります。
なお、原因の欄には、「令和3年6月10日相続」、つまり被相続人が亡くなった日を書いてから「相続」と記載します。
②相続人
次に、相続人という箇所に誰がAさんの持分を相続するかを記載するのですが、単有の場合には「(被相続人A) 住所 B」と記載するのですが、ここは持分移転なので、
「(被相続人A) 住所 持分2分の1 B」というように氏名の前に承継する持分を記載します。
共有持分の相続登記における登録免許税
不動産登記を申請する場合には、法律で定められている税率で登録免許税(印紙代)を納めます。所有権移転登記の場合には、不動産価格に所定の税率をかけて登録免許税額を算出します。この不動産価格は、役所が発行する固定資産評価証明書に記載されている不動産の評価額のことを指します。
登録免許税の計算・単独所有時との比較
相続の場合の登録免許税の税率は、1,000分の4となっています。仮に1,000万円の土地の相続であれば4万円が登録免許税(印紙代)となります。では、持分だけの移転の場合も同じなのでしょうか。
持分の場合は、不動産価格に持分をかけて持分の評価額を算出します。つまり、「不動産価格×持分割合×1,000分の4」となりますから、2分の1の移転であれば、1,000万円の不動産の場合、1,000万円×2分の1=500万円、これに1,000分の4の税率をかけて2万円となります。
共有持分の相続登記に関する一括申請
所有権移転登記を申請する場合に、複数の不動産の所有権移転や持分移転を同時にすることがあります。
たとえば、土地と建物があり、土地は父の単有名義で建物は父と母の2分の1ずつの共有名義というケースで、父が亡くなったので父の権利についてのみ相続登記を申請する場合です。ここではそのような場合の申請方法に触れていきます。
相続関係が、被相続人A、配偶者B、子CDで解説していきます。
所有権移転と持分全部移転を一括申請するケース
甲土地の所有がA単有、丙建物がA 2分の1、B2分の1という場合に、Aが令和3年5月30日に亡くなって、BCDで遺産分割協議の結果、母Bに相続登記をする場合の記載方法を見てみましょう。
登記の目的は「A持分全部移転及び所有権移転」
原因は「令和3年5月30日相続」
相続人が「(被相続人)住所 持分後記のとおり B」
というように記載します。
目的の欄は、所有権移転(単有)と持分(共有)移転を併記します。相続人の欄の持分は不動産ごとに異なるため、氏名の前には書きません。
では、後記とはどこに記載するのでしょうか。これは不動産の表示のところを指します。
丙建物の不動産表示を記載した箇所の最後に(持分2分の1)と記載します。甲土地は単有なので不動産表示の最後には何も記載しません。
持分が異なる不動産の持分全部移転を一括申請するケース
上記で説明した例が、単有名義の不動産と共有名義の不動産でしたが、甲土地がA2分の1、B2分の1、乙土地がA3分の2、B3分の2、丙建物がA5分の3、B5分の2となっている場合に上記の相続が発生した場合の相続登記の申請方法は次の通りです。
「登記の目的」A持分全部移転
「原因」令和3年5月30日相続」
「相続人」(被相続人)住所 持分後記のとおり B」
上のケースとは登記の目的が異なるだけです。そして、不動産ごとに持分が異なるので、持分の記載は、各不動産の表示欄の最後に記載します。
まとめ
一般的には共有状態というのはあまり良い状態とはいえませんが、やはり購入する際には資金繰りの関係や税金の優遇措置などを考えた場合に共有状態が生じることはやむをえません。
今回の解説では、相続関係が良好な場合を想定したお話になっていますが、実際には相続人間の関係性が悪く、遺産分割が難航するなどの状態は多く見られます。そのような場合にはできるだけ権利関係はシンプルなほうが良いです。
持分移転の場合の申請書の記載方法につきましては、今回ご紹介したルールで作成していただければ十分ご自身でもできると思います。
記事を参考に共有状態をなるべく円満に解消していただければ幸いです。
共有持分の移転登記手続きを含む不動産登記手続きのご相談は、ぜひ司法書士法人チェスターまでお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































