遺言より遺留分が優先される!請求方法や時効などプロが解説
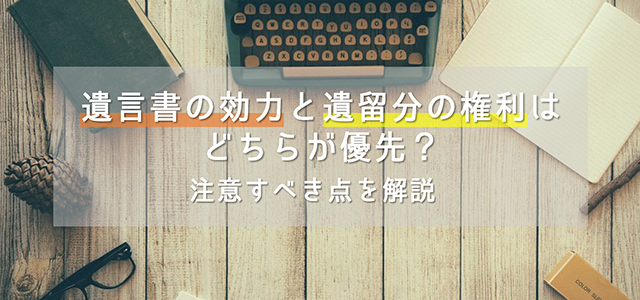
遺言書にはどのような効力があるのでしょうか?有効な遺言書にどこまで従わなければいけないのか確認しましょう。また法律に定められている遺留分についても解説します。遺留分を請求できるケースや、遺留分の時効についても見ていきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.遺言書の内容は絶対従うべき?
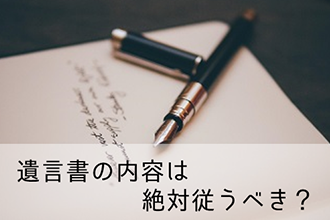
被相続人によって遺言書が作成されていた場合、その内容には絶対に従わなければいけないのでしょうか?遺言書の持つ効力について紹介します。
1-1.そもそも遺言書が有効になる要件とは
遺言書は自分の好きな形式で書いても、正式なものとは認められません。例えば被相続人がエンディングノートを用意しており、その中に遺産分割について記載があったとしても、それだけでは法的な効力は持たないのです。
有効な遺言書は、民法が規定する下記の3種類です。
- 自筆証書遺言:法律で決められたルールにのっとって自筆で作成
- 公正証書遺言:公証人と証人2名が立ち合い、内容を確認してもらいながら作成
- 秘密証書遺言:遺言内容を明かさず、遺言書の存在のみ公証人に証明してもらう
遺言書の作成には多くのルールがあります。例えば自筆証書遺言では作成日の記載が必須で、自書で記さなければいけません。スタンプで押されている場合には無効です。
1-2.遺言と異なる遺産分割は場合により可能
有効な遺言書がある場合でも、相続人全員がその内容に納得していない場合には、遺言書と異なる内容で財産を分けられます。遺言書と異なる遺産分割をするのに必要なのが『遺産分割協議』です。
遺産分割協議の実施方法に、法的な決まりはありません。ただし相続人全員が参加することは必須条件です。たとえ遺産分割協議で決定した内容でも、相続人が欠けている状態で決定した内容は無効とされます。
また遺産分割協議で決定した内容は『遺産分割協議書』にまとめましょう。必須ではありませんが、作成しておくことでトラブル回避に役立ちます。
2.相続があるときに知っておきたい遺留分
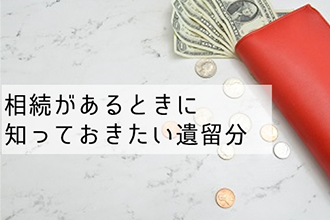
相続には遺留分という、最低限受け取れる財産が認められています。遺言書と遺留分の内容が異なる場合には、どのように扱われるのでしょうか?
2-1.遺留分とは?遺言書とどちらが優先?
被相続人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が最優先です。法律でも遺産分割のルールが定められていますが、基本的には遺言書の内容が優先されます。
ただし被相続人に近しい相続人には、最低限の遺産分割が認められる『遺留分』があります。遺言書で定められている遺産分割が遺留分を侵害する割合になっている場合には、『遺留分侵害額請求』が可能です。
遺留分を持っている相続人は、権利を行使することで最低限の遺産を相続できます。
2-2.遺産分割協議との違い
遺言書と異なる割合で相続する際に用いる点で、遺留分と遺産分割協議は同じです。しかし遺留分を請求できるのは、あくまでも遺留分に対する権利を侵害されているときに限ります。
一方、遺産分割協議は、相続人全員が合意できる割合で遺産分割できるよう話し合う場です。全員が合意しているのであれば、遺留分に関係なく遺産分割できます。
ただし一度納得し署名捺印した後に遺留分を請求するには、遺産分割協議のやり直しが必要です。再び相続人全員の合意を得られれば、遺留分を受け取れます。
2-3.遺留分侵害の遺言自体は無効にならない
遺留分は、遺言書に記載されている内容より優先されます。だからといって、遺留分を満たしていない遺言書が無効というわけではありません。
遺言書自体は有効のため、遺留分を持つ相続人が遺留分侵害請求をしなければ、遺言書通りの遺産分割が実行されます。遺留分の請求があった場合にも、遺留分が差し引かれた後は、遺言書で指定された人が取得します。
3.遺留分は誰がいくら請求できるの?
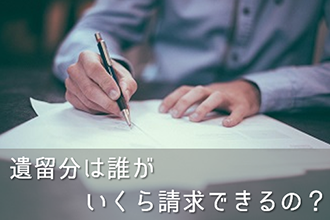
遺言書の内容よりも優先される遺留分は、誰が請求できるのでしょうか?権利を持つ人と、いくらまで請求できるのか計算の仕方を解説します。
3-1.配偶者や子ども、直系尊属が権利を持つ
法定相続人の中でも遺留分を請求できるのは『配偶者』『子ども』『直系尊属(父母・祖父母など)』に限られます。同じ法定相続人でも、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
また子どもの持つ遺留分侵害請求権は、代襲相続も認められています。親より先に子どもが亡くなっている場合には、その子どもが相続人となり遺留分を請求できるのです。代襲相続できる人物が複数いる場合には、遺留分を人数で均等に分けます。
3-2.遺留分の割合の計算方法
請求できる遺留分は、直系尊属かそれ以外かで相続財産全体に対する割合が異なります。相続人が直系尊属のみの場合には、相続財産全体の1/3を請求可能です。
配偶者や子どもが相続人なら、相続財産の1/2を遺留分として請求できます。相続人が複数いるときには、遺留分に法定相続分をかけて計算しましょう。例えば配偶者の法定相続分は1/2のため、1/2×1/2=1/4と計算できます。
また遺留分を計算し、実際に相続を受けた価額の方が大きい場合には、遺留分侵害額の負担があるかもしれません。このとき遺贈を受ける受遺者が相続人なら、財産の価額から遺留分を差し引いた金額が負担額の上限です。
4.自分の相続分が明らかに少ない場合

遺言書で示された遺産分割方法では、明らかに遺留分に満たないというケースもあるでしょう。そのようなときの対処方法をあらかじめ知っておけば、スムーズに手続きできるはずです。
4-1.遺留分侵害額の請求をする
本来であれば受け取れるはずの遺留分さえ相続できない内容の遺言書であれば、遺留分侵害額を請求しましょう。遺留分のある相続人には、遺留分侵害額請求権が認められています。
遺留分は遺言書の内容より優先されますが、自ら請求しなければ受け取れません。相続したいなら必ず請求しなければいけない点に注意しましょう。
似た言葉に『遺留分減殺請求権』があります。こちらは2019年の法改正以前に設けられていた規定です。遺留分侵害で贈与・遺贈された財産の返還を求められる権利ですが、現物返還が原則でした。法改正を機に金銭請求に変更されています。
4-2.時効があるため早めに手を打つ
遺留分侵害額請求権には時効があります。権利を持つ相続人が『被相続人の死亡』『自分が相続人であること』『遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと』を知ってから1年たつと時効です。
また仮に相続の開始や遺留分侵害について知らなくても、相続開始から10年が経過すると請求できません。この10年は『除斥期間』といい、この期間を過ぎると請求は不可能です。
そのため遺留分の請求をするときには、できるだけ早めに実施しましょう。その際、遺留分に加えられる生前贈与の範囲に注意が必要です。
相続人への生前贈与は相続開始前10年間、それ以外の第三者への生前贈与は相続開始前1年間に行われたもののみが対象です。
5.遺留分侵害額請求はどのように行うか
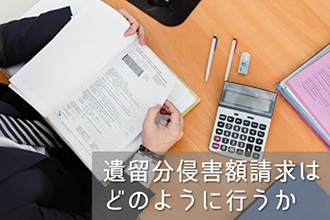
法的に実施方法の規定がない遺留分侵害請求権ですが、確実に請求するにはポイントがあります。また請求しても解決しない場合の対処法も確認しましょう。
5-1.内容証明郵便で請求
遺留分侵害請求を実施するときには『内容証明郵便』を利用しましょう。相手方に請求の意思を伝えれば成立するため、口頭で伝えるだけでも、メールや手紙で送っても構いません。
ただしこのような方法では、時効を過ぎてから相手方に「知らなかった」と言われてしまう可能性があります。確かに伝えた・メールや手紙が届いたという証拠がないため、請求の事実を誰も証明できないのです。
内容証明郵便であれば、郵便の内容が郵便局に記録として残り、受け取ったことも証明されます。相手方の言い逃れを防げる方法です。
5-2.未解決の場合は調停の申し立て
請求に対して当事者間の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所での調停を利用できます。裁判所が間に入り、双方の事情聴取や資料提出を元に、解決案の提示や助言をするのです。
ただし調停での話し合いでも決着がつきそうにないと調停委員会が判断すれば、調停は不成立となり、その後は訴訟で決着をつけることになります。
6.遺留分は放棄もできる。放棄する理由や方法
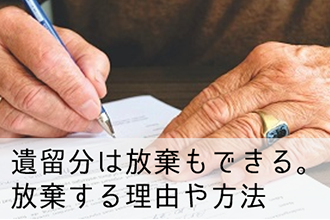
相続放棄は実際に相続が始まるまでできません。しかし遺留分はあらかじめ放棄することもできます。遺留分の放棄が役立つシーンや、手続きの仕方を解説します。
6-1.権利を放棄することでトラブル対策になる
遺言書に遺留分を侵害するような遺産分割方法を記載するときには『遺留分放棄』を組み合わせましょう。被相続人が生前に話を通し、合わせて手続きすることで、トラブルを未然に防げます。
例えば事業を継がせるため、長男に全財産を相続させるケースなどで有効です。事業の継続に土地や建物など全財産が必要な場合、あらかじめ他の兄弟姉妹に遺留分放棄をしてもらうことで、問題を避けられます。
相続争いを避け、親類関係を良好に保つのにも役立つ方法です。
6-2.放棄に応じてもらえたら裁判所の許可を得る
遺留分放棄は当事者間だけではできません。放棄をするかは権利を持つ人の自由意思に基づくため、強要はできないからです。そこで家庭裁判所に申し立てを行い許可を得ます。
申し立ては被相続人と申立人の戸籍謄本など、必要書類を用意し手続きしましょう。ただし手続きをしても、下記の三つの基準を満たしていなければ認められません。
- 放棄が自由意思に基づくものであること
- 放棄の理由に合理性・必要性があること
- 遺留分の代わりになる資金援助などがあること
放棄には特段のメリットはありません。そのため家庭裁判所では放棄が妥当なものであるかチェックし、判断を下すのです。
7.遺留分侵害額請求は時効に注意しよう

法定相続人の中でも、配偶者・子ども・直系尊属には遺留分が認められています。遺留分は最低限相続が認められている財産のことです。他の贈与や遺贈により侵害されていると、侵害されている分の請求ができます。
ただし時効が定められているため、請求する場合には早めに実施しましょう。請求の意思を相手方に伝えるだけで成立します。内容や受け取りの証明ができる内容証明郵便を使うと、間違いなく請求が可能です。
慣れないことが多く難しいと感じるなら、遺産分割対策も実施している『税理士法人チェスター』へ問い合わせてみるとよいでしょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい
「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。
さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。
チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































