相続登記を放置するリスク/いつまでに行うべきか解説
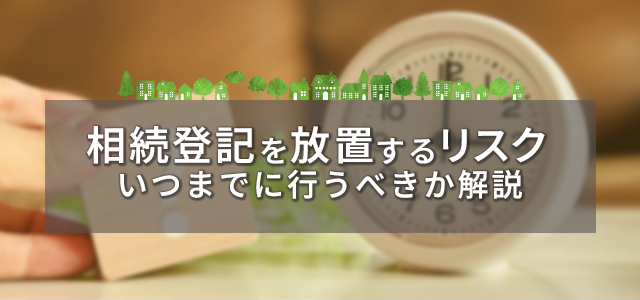
相続登記の意義とは
相続した不動産の登記をするためには費用もかかりますし、一から必要な書類を集めるのも大変です。それなら放っておこうと考えられる方も多いのではないのでしょうか。それでは、相続登記は何のためにしなければいけないかを考えてみましょう。
相続登記の意義とは、登記をすることで対抗力を得ることができるということです。対抗力とは、この不動産は自分のものだということを、
自分以外の第三者に対して主張できる効力
です。また、法務局の登記簿という公的な帳簿に所有者として記載されることで、所有者であることを対外的に公示し、取引の相手方が所有者を確認できることから取引の安全を図ることができます。
もし相続登記をしなければ、登記簿上は不動産の名義が亡くなられた方の名義のままで残ってしまいます。それでは現在誰がこの不動産を実質的に所有しているかは登記簿を見てもわかりません。そこで、登記簿を見た第三者に対しても、その不動産が自分のものであることを主張するために、相続登記をすることが必要になります。
相続した不動産を売却しようとしたときや、相続した不動産を担保としてお金を借りようとしたとき、不動産業者や金融機関から、まず登記簿上の所有者が誰であるかを必ず確認されます。
取引の安全を図る必要性は、不動産取引や銀行取引をする際にももちろん当てはまります。登記簿以外の他の書類で自分が相続人だと主張しても、不動産に関する取引をする際には、その登記の有無が最も重要視されます。
少なくとも不動産を売却したり不動産を担保としてお金を借りたりする際には、前提として必ず相続登記を行わなければなりません。
相続登記せずに放置するリスク
次に、相続登記をせずに放置するとどのようなリスクがあるかを考えていきましょう。
①不動産の売却や担保の提供ができない
不動産の売却をしたり、不動産を担保にして銀行からお金を借りたりするためには、前提として必ず相続登記をする必要があります。取引を行う時点で相続登記をすればいいと考えられる方も多いとは思いますが、取引の直前となってすぐに相続登記ができるとは限らないので、前もって準備をしておく必要があります。
相続登記をするためには、戸籍謄本などの書類を集め、他に相続人がいる場合には相続人全員から書類に署名・捺印をしてもらう等した上で、法務局に登記申請をしなければなりません。
登記が完了するまでには、通常、書類を集め始めてから早くとも1ヶ月程度時間がかかります。被相続人が本籍地を何度も移していたり、本籍地が遠方であったりした場合は、それらの本籍地のある市区町村役場で戸籍謄本を取得しなければなりませんので、さらに多くの時間がかかります。そのため、もし直ぐにお金が必要になった場合でも、前提となる相続登記が完了するまでに数ヶ月以上要してしまい、取引のタイミングを逸してしまうことすらあります。
不動産を売却するおすすめのタイミング
不動産を売却するにはおすすめのタイミングがあります。特に相続税の課税対象となる方は参考にしてください。
不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税の課税対象になります。譲渡所得とは、売却代金から不動産の取得費と譲渡費用(不動産を売却するのに要した経費)を差し引いた金額です。譲渡所得に、所有期間に応じた税率をかけて算出された金額が、譲渡所得税となります。
相続財産を売却する場合、納付した相続税額の一部を取得費として計上できる場合があります。その要件の一つとして、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却しなければならないという期間の制限があります。
そうすると相続税の申告期限が10ヶ月なので、相続が開始してから3年10ヶ月以内に不動産を売却する必要があります。相続税の課税対象になっている場合は、遅くともこのタイミングで売却することをお勧めします。
なお、譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が異なることにもご留意ください。不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合、長期譲渡所得となって税率が低くなります。この所有期間は、不動産を取得した日から引き続き所有していた期間をいいますが、相続により取得した不動産については、原則として被相続人が不動産を取得した日が起算点となります。
もし、被相続人が不動産を購入した代金より高く売却することができる見込みがある場合は、所有期間が5年を超えているかどうか売却する前に必ず確認するようにしてください。
②相続人の増加で権利関係が複雑化する
未分割の遺産が存在する場合、これを放置すると、相続人が亡くなるたびに更に相続人が増えていってしまう場合があります。遺言が存在しない場合、相続登記をするためには、相続人全員の共有名義にするか、遺産分割協議を行って不動産を取得する相続人を決める必要があります。
遺産分割協議とは、相続財産を誰が取得するのかを、相続人全員で話し合って決めることです。遺産分割協議を行って合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成したうえで、取得者の名義にするため、相続登記をする必要があります。その際には、遺産分割協議書に法定相続人全員が署名のうえ実印で押印し、法定相続人全員の印鑑証明書の添付も必要となってきます。
遺産分割協議が面倒なため、相続人全員で売却しようと考えるかもしれません。しかし、その場合であっても、不動産を売却する際には、相続人全員が売主となって契約をすることになりますので、いずれにせよ相続人全員の実印による押印も印鑑証明書も必要となってきます。
つまり、いずれにせよ相続財産に対しては相続人全員が権利を持っているため、相続人全員で契約を行ったり、相続人全員の同意が必要となったりします。
世代が進むほど権利関係は複雑化しやすい
相続財産は、親が亡くなるとその子へ、その子が亡くなると孫へと、どんどん権利が承継されていきます。被相続人に子や両親がいない場合、権利は兄弟姉妹へ承継されます。そして更に権利を承継した方が亡くなると、場合によってはその配偶者や子へと承継されてしまうケースもあります。
相続登記をせずに何世代も放置してしまうと、その不動産の所有者が何十人と増えていき、どんどん権利関係は複雑化していきます。そうなると、いざ不動産を売却しようとしても、一度も会ったことのない親戚と同じ不動産の相続人として、全員で話し合いをしなければならなくなることもあるでしょう。
そうなってきますと、遺産分割協議をしようとしたり、不動産を売却したりしようとしても、相続人全員の同意が得られる可能性は低くなってきます。相続人全員の同意を得られなければ、不動産を売却できるタイミングを逸してしまう上、相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てざるを得なくなり、その結果、何年もかけて調停成立に至った後に相続登記をしなければならないという事態も起こり得ます。
③相続人の判断能力低下で遺産分割協議が困難になる
相続人が増えていくにつれて、判断能力が低下している相続人が出てくる可能性が高くなってきます。遺産分割協議をするためには、相続人に法律行為をするのに十分な判断能力があることが必要となります。このような判断能力を、事理弁識能力ともいいます。
認知症などで判断能力を欠く常況にある方がいらっしゃる場合、その方との間では遺産分割協議はできません。遺産分割協議をするためには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、その方の代理人となる成年後見人を選任してもらった上で、その後見人に、代理人として遺産分割協議に参加してもらわなければならなくなります。
④相続登記の必要書類が準備できなくなる
相続登記をするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本などが必要となります。
戸籍謄本の保存期間は現在150年に延長されましたが、もともとは80年の保存期間でした。戸籍の附票や住民票除票の保存期間も現在は150年ですが、従来は5年しか保存期間がありませんでした。
そのため、何世代も前に亡くなった方の名義がそのまま残っていると、相続登記をするために必要な書類が通常の方法で準備できなくなる可能性があります。一般的に、必要な書類が準備できない場合は、上申書などの特殊な書類をご自身で作成して法務局に提出する必要があり、ご自身で対応することが困難な場合、司法書士等の専門家にお願いする必要が生じてきます。
⑤他の相続人に不動産を処分されるおそれがある
相続登記を放置してしまうと、他の相続人に不動産を処分されてしまう可能性もあります。せっかく相続した不動産があるにもかかわらず、他の相続人の行動によっては不動産の権利を失ってしまう可能性があるのです。
どういったケースで権利を失ってしまうのか確認しましょう。
共有持分の譲渡が行われたケース
まず、他の相続人が不動産の共有持分を譲渡してしまう可能性があります。
被相続人が不動産を所有していた場合、相続が開始すると、相続人が法定相続分に従ってその不動産を共有する状態となります。仮に被相続人が、相続人の一人に不動産を相続させる旨の遺言を残していた場合、同相続人が不動産を単独で取得することになると、同相続人は被相続人の相続開始時に遡って不動産の所有権を単独で取得することになります。
しかし、この遺言の内容に基づく相続登記を怠っていると、遺言が存在することを知らない第三者は、相続人が共有持分を有していると信頼してしまいます。悪意のある相続人は、この信頼を利用して、遺言により不動産を単独で取得した相続人がいるにもかかわらず、登記がされていないのをいいことに、自分に相続した持分相続権があると偽って、その持分を、事情を知らない第三者に譲渡することができてしまうのです。
このような本来有しない共有持分の譲渡ができてしまうことは、既に遺産分割協議が成立していた場合も同様に当てはまります。仮に遺産分割協議により自分が単独で取得したとする相続登記を放置してしまうと、他の相続人が法定相続分について相続登記をして、他の相続人自身の持分を第三者に譲渡してしまうことが可能です。
速やかに相続登記をしていれば、その権利関係が登記簿によって公示されますので、その登記を無視して勝手に不動産を第三者に譲渡することはできません。
因みに、従前は、相続人の一人に不動産を相続させる旨の遺言が存在する場合には、相続登記をしていなくても、不動産を単独で取得したことを第三者に対して主張することができました。しかし、近年の民法改正により、遺言が存在する場合であっても、相続登記と持分移転登記の先後によって優劣が決せられるようになりましたのでご注意ください。
借金の返済が滞り、不動産を差し押さえられたケース
他の相続人が借金をしていてその返済が滞ってしまった場合、その相続人の債権者に不動産を差し押さえられる可能性もあります。差押の登記がされてしまうと、不動産を売却しようと思っても、差押の登記を抹消しないことには売却することができません。
借金をしていた相続人に弁済能力がなければ、不動産を売却する相続人は差押の登記を抹消してもらうために、いったんその借金を肩代わりしなければならない可能性もあります。
法定相続による相続登記を代位登記で行われたケース
相続登記は代位登記でされる場合もあります。代位登記とは、債権者代位権に基づいて登記をすることです。
債権者は、債務者名義の財産にのみ差押をすることができますので、不動産が被相続人名義のままではこれを差し押さえることはできません。したがって、債権者は、債務者名義の相続登記が完了していないと債務者の財産たる不動産を差し押さえることはできません。
それでは債務を負った相続人自身が相続登記をしない限り、債権者は被相続人名義の不動産を差し押さえられることは無いのではないかと思われるかもしれません。しかし、債権者は、相続人である債務者に代わって、その相続登記を申請することができる場合があります。このとき、債権者が相続登記を行うに際して、相続人の承諾は必要とされていませんので、たとえ当該債務者において悪意が無くても不動産を差し押さえられてしまうことがあるのです。
相続登記は3年以内の申請が義務化される
これまで、相続登記は義務とされていませんでした。しかし、相続登記がされていない不動産が数多くあり、その不動産を所有している相続人がわからない、いわゆる所有者不明土地の増加が社会問題となっています。
こうした所有者不明土地問題を受け、2021年4月21日に改正不動産登記法が成立しました。その内容は、不動産を取得した相続人について、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付けるというものです。また、違反者へは10万円以下の過料の罰則が設けられました。
相続登記義務化の施行日
相続登記義務化の施行日は2024年4月1日です。
なお、同日以降に相続する不動産だけでなく、同日より前に相続してまだ相続登記をしていない不動産も相続登記義務化の対象となります。経過措置により、施行日の前に相続した不動産については施行日から3年以内に相続登記を申請すればよいことになります。
相続登記は書類の収集等に相当の時間と労力を必要としますので、なるべく早く専門家である司法書士に相談しましょう。
相続税申告に合わせて相続登記するのも一つの方法
相続が発生し、被相続人の相続財産が基礎控除を超える場合は相続税を支払わなければなりません。相続税には基礎控除があり、相続財産が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生しません。しかし、その控除額を超えるような場合は、原則、相続税を支払わなければなりません(実際には、他にも特例や税額控除がありますので、相続税が課税されない場合もあります)。
税金を支払うには申告期限があり、相続税の場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。相続税の申告に必要な書類と、不動産の相続登記に必要な書類は似たような書類が多くあります。相続税の申告期限にあわせて、不動産の相続登記を済ませてしまうことも一つの方法です。
まとめ
相続登記を放置していると思いもよらないリスクが生じる可能性があります。2024年4月1日以降は相続登記が義務化され、相続から3年以内に申請しなければならなくなりました。
適切なタイミングで登記をすることは、相続された方の負担軽減にもなります。相続登記のタイミング・方法などで疑問があれば、相続手続きを専門に扱う司法書士法人チェスターにご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































