遺産分割協議のやり直しは可能!時効・5つの具体例・手続きを解説
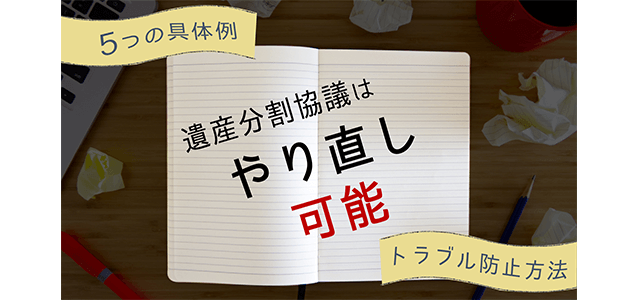
遺産分割協議は、原則としてやり直しできません。しかし、協議が無効になる場合や相続人の同意を得られた場合など、やり直しが認められる事情がある場合に限り再審議できます。
ただし、不動産分割協議のやり直しには不動産登記の名義変更や贈与税の発生など、事前に把握しておきたいポイントがあることを覚えておきましょう。
相続人とのトラブルを未然に防ぐためにも、遺産分割協議の具体的な手順と注意したいポイントを理解することが大切です。
この記事の目次 [表示]
1.遺産分割協議のやり直しに時効はない-いつでも検討できる
相続人全員の同意のもと、遺産分割協議のやり直しを希望する場合「時間が経っているから」との理由で断念する必要はありません。理由として、遺産分割協議のやり直しの行為自体に時効や期限がないからです。
ただし、詐欺や強迫があったとしてやり直しを求める場合は、主張できる期間が決まっています。これは売買契約や遺言といった法律行為全般に通じる原則のため、分けて考えなくてはなりません。
また、協議をやり直す以前に財産を譲渡していた場合は、他の相続人への賠償が必要です。
なぜなら、本来は共有するべき財産を独断で処分したことになるからです。
2.遺産分割協議をやり直す4つの手順
遺産分割協議をやり直すには、以下の手順に沿って行います。
遺産分割協議をやり直す4つの手順
- 相続人全員を集めて話し合いの場を設ける
- 必要書類を用意して遺産分割協議書を作成する
- 贈与税や譲渡所得税などの税金を算出する
- 所有者を変更する場合は不動産登記の名義を変更する
遺産分割協議のやり直しは、当初の遺産分割協議以上に複雑な手続きが絡んでくるため、専門家に任せることが無難です。
「単なるやり直しだから」と、税金や登記を意識しないまま手続きを進めてしまうと、あとから申告漏れを指摘されてペナルティを課される可能性もあります。
2-1.相続人全員を集めて話し合いの場を設ける
遺産分割をやり直す場合、相続人全員の合意が必要になるため、全員が集まれる場を設けます。再協議の時点で死亡している相続人がいる場合は、死亡した人の相続人全員の参加が必要です。ただし、全員の合意があっても、すでに遺産分割で確定した相続財産を相続人から取得した第三者の権利は保護されます。
たとえば不動産を例にすると「当初の遺産分割協議で相続した不動産を、その後に第三者へ売却した」場合、遺産分割協議のやり直しを主張して取り戻すことはできません。
また、相続人全員の同意が得られない場合、または遺産分割協議に無効や取消事由が存在する場合は、訴訟手続による解決を図ります。
2-2.必要書類を用意して遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議のやり直しに必要な書類は、基本的に当初の遺産分割協議と同じです。
遺産分割協議のやり直しに必要な書類
- 遺産分割協議書
- 相続手続き依頼書
- 相続同意書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人の住民票
- 被相続人の住民票または除かれた戸籍の附票
- 相続登記申請書
- 車検証
- 車庫証明書
- 株式名義書換請求書などの書類
遺産分割協議書は「誰がどの財産を取得するのか」が重要で、とくに財産は正確に記載する必要があります。
不動産の場合は登記事項証明書の記載通りに、預貯金の場合は銀行名・支店名に続けて「定期預金及び普通預金全額」のように記載します。
遺産分割協議書が複数枚に渡る場合は、割印の漏れがないよう注意が必要です。
相続同意書とは、特定の遺産の分割方法に相続人全員が同意していることを証明する書類で、預貯金の払い戻しで銀行に提出したり、車の名義変更で運輸局に提出したりします。
特定の遺産を先行して分割したい場合にのみ必要になる書類のため、遺産全体の分割方法が記載されている遺産分割協議書がある場合は不要です。
除かれた戸籍の附票とは、被相続人の住民票の移り変わりを記録した書類を指します。
やり直しに際し追加で必要となる書類はあるのか、あるいは以前の書類は再利用できるのかなどは、専門家である司法書士や税理士に相談を検討してください。
2-3.贈与税や譲渡所得税などの税金を算出する
遺産分割協議をやり直した場合でも、税法上は新たな財産の移転とみなされるため、税理士にあらためて税金の算出依頼を行います。
遺産分割協議のやり直しによる再分割は、新たな財産の移転とみなされるため、贈与税や譲渡所得税が課税されます。
遺産分割協議のやり直しにより財産の移転が生じ、新たに財産を取得した相続人が対価を支払わない場合は贈与税の対象となり、反対に対価を支払う場合は、譲渡所得税の対象となります。
また、相続財産に不動産が含まれ名義変更が生じる場合は、不動産取得税と登録免許税が必要です。
2-4.所有者を変更する場合は不動産登記の名義を変更する
遺産分割協議をやり直した結果、不動産の所有者に変更が生じる場合は、司法書士に不動産の所有権移転登記(不動産の名義変更)を依頼します。
対象不動産について、すでに当初の遺産分割協議にもとづく不動産登記がなされている場合は「合意解除を原因とする所有権抹消登記」が必要です。
所有権抹消登記が完了すると登記名義人が被相続人に戻るため、再協議の内容をもとにあらためて「相続」を原因とする所有権移転登記を行います。
3.遺産分割協議をやり直すときの注意点-手間や費用を知っておく
遺産分割協議のやり直しの可否は、かかる手間や費用を理解したうえで、総合的に判断する必要があります。
遺産分割協議をやり直すときの注意点
- 不動産登記のやり直しが必要
- 贈与税や譲渡所得税の申告・納税が必要
- 遺産分割調停または審判による遺産分割はやり直し不可
- 相続税申告専用の協議書をすすめる税理士に注意
遺産分割協議のやり直しが相続人全員の合意を前提としている以上、やり直しに伴う注意点も相続人全員での共有が必要です。
3-1.不動産登記のやり直しが必要
遺産のなかに土地・家屋などの不動産がある場合には、不動産の所有権移転登記を行います。当初の遺産分割協議により決めた内容にて所有権移転登記をしている場合、そのまま新たな名義人への所有権移転登記が認められないため、一時的に所有権抹消登記が必要です。
また、遺産分割協議のやり直しに際して相続すべき不動産が新たに発覚した場合は、当該不動産について所有権移転登記を行います。
以下の流れは「課税価額2000万円の土地において、当初の遺産分割協議のあと名義変更し、そして再協議の結果、別の相続人名義となったケース」です。
上記事例における不動産登記の流れ
- 当初の遺産分割協議にもとづき、「相続」を原因とする所有権移転登記
申請人:当該不動産を取得する相続人
登録免許税:8万円
- 遺産分割協議のやり直しに伴い、「合意解除」を原因とする1.の所有権抹消登記
申請人:再協議に参加した相続人全員
登録免許税:1000円
- 再協議の結果にもとづき、「相続」を原因とする所有権移転登記
申請人:新たに当該不動産を取得する相続人
登録免許税:8万円
3-2.贈与税や譲渡所得税などの申告・納税が必要
遺産分割協議のやり直しは「贈与税や譲渡所得税など本来必要ないはずの税金を払ってもなお、やり直しの価値があるか」を見極める視点が必要です。
遺産分割協議のやり直しは、税法上は一旦確定した資産が移転したとみなされます。
当初の遺産分割協議により相続人Aが相続した財産を、再協議にて相続人Bが相続する場合、BがAに対価を支払っているならば「譲渡所得税」が、対価を支払っていないならば「贈与税」が課せられます。
たとえば、課税価額2000万円の土地のケース。
仮に、遺産分割協議のやり直しにより、取得する相続人が変わった場合、課される税額は以下のとおりです。
なお、譲渡所得税の税率は保有期間(相続の場合は被相続人が取得してからの期間)で変わるため、保有期間は5年超(長期譲渡所得といいます)とします。
| 贈与税 | 譲渡所得税 | |
|---|---|---|
| 対価を支払った場合(売却益500万円) | - | 75万円 |
| 対価を支払っていない場合 | 695万円 | - |
参考:贈与税の計算と税率(暦年課税)、長期譲渡所得の税額の計算|国税庁
3-3.遺産分割調停または審判により遺産分割した場合はやり直し不可
当初の遺産分割が、協議ではなく調停や審判によって行われていた場合は、遺産分割のやり直しは原則できません。調停や審判による遺産分割は、各相続人の意向を踏まえたうえでの裁判所による公的手続きです。
そのため「相続人全員が合意している」との理由だけで覆すことは許されません。
ただし、調停や審判に本来参加すべき相続人が不参加であった場合は、手続きが違法であると判断され、遺産分割のやり直しが可能です。
3-4.相続税申告専用の協議書をすすめる税理士に注意
当初の遺産分割協議を各相続人にとって納得できるものとし、やり直さなくても済むように、正しい知識を持った税理士に相談が重要です。
誤った情報をもとに遺産分割協議書の作成を急がせる税理士の言葉を鵜吞みにしてしまうと、意図しない遺産分割となり、結果的にやり直しへとつながります。
以下のような税理士のアドバイスは明確に誤りであるため、注意が必要です。
- 相続税の申告期限内に遺産分割協議をまとめないと、税額軽減の特例が受けられない
- 取りあえず相続税申告用に簡易な遺産分割協議書を作り、正式な遺産分割協議書は、後日作り直せばよい
確かに、配偶者による相続税の軽減や小規模宅地等の軽減措置は、相続税の申告時に遺産分割協議が完了していることが前提です。
しかし「申告期限後3年以内の分割見込書」を同時に提出することにより、申告期限後3年以内の遺産分割協議完了を条件に、軽減措置が受けられます。
参考:相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続|国税庁
内容の中身にかかわらず相続人全員の同意がある以上は、正式な遺産分割協議書です。
そのため、後日に作成した遺産分割協議書は「遺産分割協議のやり直し」とみなされ、不動産登記の抹消や贈与税の課税が発生します。
4.相続人とのトラブルを防ぐためにできること
遺産分割協議に臨むにあたり、相続人とのトラブル防止の意識は、協議の円滑な進行や仕切り直しのリスク軽減につながります。
相続人とのトラブルを防ぐためにできること
- 不動産がどのくらいあるのかを把握する
- 当事者同士で密にコミュニケーションをとる
- すぐに弁護士に依頼して争うのは避ける
4-1.不動産がどのくらいあるのかを把握する
不動産は、どのような権利関係の不動産がどれほど存在しているのかをすべて洗い出し、相続人全員で情報を共有しておきます。
数値化されている金銭と比較して、不動産はトラブルにつながる要素を多く含んでいるからです。
不動産の特性によりトラブルに発展する事例
- 被相続人が複数の土地を所有していた場合
- 単一の不動産を複数の相続人で共有する場合
- 土地と建物の所有者が別になった場合
複数の土地を相続した場合、筆数(不動産登記上の土地の単位)や敷地面積を基準に分割することにより、それぞれの土地の評価額の違いで不公平感が残ります。
とくに土地を必要とする相続人がいない場合、評価額にもとづいてすべて売却や換金をして分割する方法(換価分割)が一般的です。
共同で単一の不動産を相続する場合は、当該不動産の処分や管理について、相続人の間の意思の統一が難しくなります。
共有ではなく特定の相続人が単独で相続し、本来の持ち分にあたる価額分を金銭で補填(代償分割)するのも手です。
被相続人の土地に相続人の建物が存在し、遺産分割協議の結果、土地と建物の所有者が別になってしまうと、土地の使用権を巡って対立が生じます。
建物の所有者が土地も相続し、同じく代償分割による補填により、利用権を巡る対立を避けられるでしょう。
4-2.当事者同士で密にコミュニケーションをとる
故人の遺志を確認する手段が限られる以上、相続人の間のコミュニケーションは被相続人が生きていたとき以上に必要です。
お互いに何を考えているのか分からなければ、誤解が生まれてしまいます。
連絡をこまめに取り合って、遺産分割協議を全員が納得する形で終わらせる1つのゴールを目指して、話を進めることが重要です。
また、遺産分割協議の場で話し合うべき事項をあらかじめ書き出しておき、順に確認しながら進めるとスムーズに進みます。
生前の被相続人との距離感や相続人の間のしがらみから生じる負の感情を、遺産分割協議の場に持ち込むことは避けましょう。
4-3.安易に弁護士に依頼して争うのは避ける
遺産分割協議に専門家の同席を希望する場合は、相続人が共同で依頼することにより、無用なトラブルを避けられます。
法律が絡むことだからと個人が代理人として弁護士を立てると、他の相続人は警戒心を抱いて態度を硬くさせてしまうため、おすすめしません。
やむを得ない事情がない限り、遺産分割協議は相続人同士がお互いに連絡を取り合い、相続人本人の出席が無難です。
それでもなお手続きや法律の解釈に不安が残るのであれば、相続人全員による専門家への立会い依頼により、トラブルを防ぎながら安心して協議を進められます。
司法書士の場合は権利関係のアドバイスを受けながら不動産登記も同時に依頼できたり、税理士の場合は相続税や贈与税の軽減措置のアドバイスを受けられたりします。
5.遺産分割協議がやり直しになる具体例-5つのケースで解説
遺産分割協議がやり直しになるさまざまなケースを押さえておくことにより、いざ同じ事態に遭遇した際に適切な対応が取れます。
相続人全員の同意といった典型例も含め、遺産分割協議がやり直しになるケースは以下の5つです。
遺産分割協議がやり直しになる具体例
- 協議が無効や取り消しになる原因が存在した場合
- 相続人全員がやり直しに同意をした場合
- 遺産分割協議書に載っていない遺産が発覚した場合
- 存在しないはずの遺言が見つかった場合
- 手続が進まないことで遺産分割できない場合
5-1.協議が無効や取り消しになる原因が存在した場合
遺産分割協議が無効や取り消しになる原因が存在した場合は、相続人の一部が重大な問題を抱えているケースが多く、当該相続人の問題解決を優先する必要があります。遺産分割協議の成立要件である「相続人全員の同意」が欠けていた場合は、協議は無効になり、やり直しです。
相続人全員の同意が欠けていたとして無効になるケース
- あとから婚外子の存在が発覚し結果的に相続人の一部を除外した合意となった
- 制限行為能力者(精神上の障害により判断能力に欠けるとされた者)が成年後見人(制限行為能力者に代わって財産を管理する者)を介することなく同意した
無効の場合は、法律上当然に最初からなかったことになるため、主張するための期限はありません。また、遺産分割協議の同意内容に錯誤(重大な勘違い)があった場合は、取消の主張が可能です。
たとえば「負債がないと信じて相続放棄をしなかったが、あとから多額の負債が見つかった」とのケースが一例です。
さらに、遺産分割協議が詐欺や強迫によって行われた場合は、取消を主張できます。
無効と違って、取消の原因となる意思表示は取消を主張するまでは有効なものとして扱われ、主張できる期間にも制限があるため注意してください。
| 原因となった意思表示 | 追認できるときから5年 | 行為の時から20年 |
|---|---|---|
| 錯誤 | 勘違いに気付いたときから5年 | 共通 |
| 詐欺 | 騙されていたことを知ったときから5年 | |
| 強迫 | 自由な意思を取り戻してから5年 |
5-2.相続人全員がやり直しに同意をした場合
相続人全員の同意によるやり直しの場合には、追加費用や課税のリスクを相続人全員で共有することにより、想定外のトラブルを避けられます。
当初の遺産分割協議の時点ではお互い納得していたとしても、あとから事情が変わって「別の分割方法が良かった」と思うことはあるはず。
遺産分割協議が相続人全員の同意で成立する以上、やり直しも全員の同意が必要です。
仮に、当初の遺産分割協議からやり直しの間までに亡くなっている相続人がいる場合は、当該相続人の相続人全員が同意しなくてはなりません。
5-3.遺産分割協議書に載っていない遺産が発覚した場合
遺産分割協議後に新たに遺産が発覚した場合に備えて、新たに見つかった遺産の分割方法や帰属先を決めておきましょう。
当初の遺産分割協議時には相続人の誰もが認識していなかった遺産が、後日新たに発覚したケースがあります。
この場合は新たに見つかった遺産についてのみ、別途遺産分割協議が必要です。
新たに遺産が発覚するたびに遺産分割協議を行う手間をなくせるため、あらかじめ「協議後に新たに遺産が発覚した場合は、法定相続分に従って分割する」といった文言を盛り込んでおくと安心でしょう。
5-4.存在しないはずの遺言が見つかった場合
遺産分割協議後に、存在しないと思っていた遺言書が見つかった場合には、遺産分割協議の内容が覆る可能性を想定しておきましょう。
遺言は被相続人の最後の意思表示であるため、記述内容は最大限に尊重されるべきであり、遺言に反する遺産分割協議は無効となるのが原則です。
とくに「遺言内容と異なる遺産分割協議は認めない」との文言があったり、相続人以外の第三者への遺贈が含まれていたりした場合は、無効となる可能性があります。
さらに、遺言の内容と遺産分割協議の内容に大きな差があり「遺言の存在を知っていたならば、協議内容には同意しなかった」と認められる場合は、錯誤(さくご)の観点で取消を主張できます。
ただし、以下の事情が認められる場合は、当初の遺産分割協議が有効なものとして扱われます。
遺言があっても遺産分割協議が有効となる条件
- 遺言の内容と遺産分割協議の内容に、大差がない
- 第三者の権利を侵害しない
- 遺言の内容を確認してもなお、相続人全員が遺産分割協議の内容に納得している
- 遺言執行者(選任されている場合のみ)が反対していない
遺言の影響を完全になる排除はできませんが、遺産分割協議書に「後日遺言が発見された場合でも、第三者の権利を侵害しない限りその内容に拘束されない」との文言を盛り込むのも有効です。
5-5.手続が進まないことで遺産分割できない場合
相続人の一部が、遺産分割協議の内容を履行するために必要な手続きを行わない場合は、調停や審判手続きにより遺産分割を進めることになります。
たとえば、不動産を特定の相続人が取得し他の相続人に補償する代償分割において、取得した相続人が名義変更の登記を怠っているケースが一例です。
たとえ取得した相続人の怠慢によるものであっても、他の相続人が一方的に遺産分割協議をなかったことにはできません。
したがって、手続きを先に進めるには、家庭裁判所における調停や審判によることになります。
6.遺産分割協議はやり直し可能-悩んだときはいつでも相談を
遺産分割協議のやり直しは、リスクを認識したうえで相続人全員が同意しているのであれば、積極的に検討すべきです。
病気や事故、災害などによって当初の遺産分割協議のときと事情が変わってしまうことは多々あります。遺産分割協議の内容に拘束されてしまうと、柔軟さを欠くことになり相続人の生活を脅かしかねません。
一見ハードルが高い遺産分割協議のやり直しも、専門家のサポートを受けることにより、安心して臨むことが可能です。
税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人である強みを活かして、遺産分割協議のやり直しについての相談から協議への立会い、税に関するアドバイスまでを全面的にサポートします。遺産分割協議のやり直しについての相談は、税理士法人チェスターにお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































