遺産分割協議書は必要か?不要か?作成しないリスクや作成方法
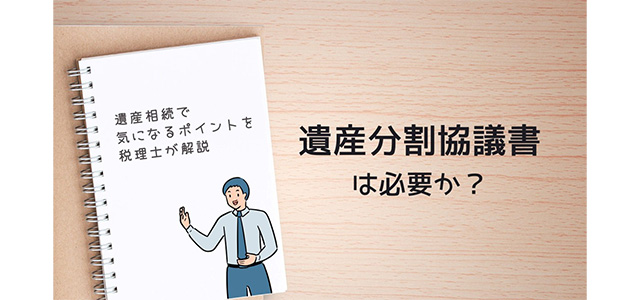
「遺産分割協議書は必要?不要?」
「作成しないとどんなデメリットやリスクがあるの?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、遺産分割協議書が必要か不要かは、被相続人の財産内容やどのような相続手続きが必要なのかで異なります。
ただし、遺産分割協議書は多くの相続手続きで提出を求められる書類で、作成しないとデメリットやリスクがあるのも事実です。
「遺言書がない」&「法定相続人が2人以上いる」など一定のケースでは、遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。
この記事の目次 [表示]
1.遺産分割協議書とは?どうして作成が必要なのか
遺産分割協議書とは、遺産分割協議において法定相続人全員が合意した遺産の分割方法を記載した書類のことです。
被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が2名以上いる場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、「誰が・どの財産を・どれだけ・どのように相続するのか」などを詳細に決めなくてはなりません。
遺産分割協議は、民法第907条に基づき被相続人が遺産分割を禁止していない限り可能で、法定相続人が全員参加して合意をすることで成立します。この合意内容を書面化したものが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、法律で作成を義務付けられている訳ではありません。
しかし、遺産分割協議において決めた遺産の分割方法に、相続人全員が合意していることを証明できるため、様々な相続手続きで遺産分割協議書の提出を求められます。
詳しくは、「【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説」でも解説しております。
1-1.遺産分割協議書が必要とされる相続手続きと提出先
遺産分割協議書の提出が必要とされる、代表的な相続手続きと提出先は以下の通りです。
| 相続手続き | 提出先 |
|---|---|
| 預貯金や株式の解約や名義変更 | 金融機関 |
| 相続税の申告 | 税務署 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 法務局 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局等 |
なお、これらの相続手続きをする際でも、遺産分割協議書の作成が不要となるケースもあります。
そのため、遺産分割協議書が必要か不要かは、個別に判断をすることとなります。
\\CHECK//
グループに所属する司法書士や行政書士と共に、さまざまな相続ニーズにワンストップで対応が可能です。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
2.遺産分割協議書が必要なケース
遺産分割協議書が必要となるのは、主に以下の4つのケースです。
上記のケースに該当する場合は、なぜ遺産分割協議書の作成が必要なのでしょうか?確認していきましょう。
2-1.遺言書なし&法定相続人が2人以上
遺産分割協議書が必要なのは、被相続人が遺言書を残しておらず、さらに法定相続人が2名以上いるケースです。
このケースの場合、法定相続人全員で遺産の分割方法について協議をする必要があるため、原則として、その協議について合意した遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書を作成しておけば、後で「言った・言わない」という水掛け論に陥りにくく、当事者間における認識のズレも起きにくくなります。
後々のトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
詳しくは、「遺産分割の進め方を解説。書面に残すときに気を付ける点を把握しよう」をご覧ください。
2-2.不動産を換価分割・代償分割する
遺産分割協議書が必要なのは、不動産を換価分割や代償分割するケースです。

換価分割をする場合は、不動産を換価することや売却代金の分割割合を、遺産分割協議書に記載する必要があります。
また、代償分割をする場合は、誰が誰に対して代償金をいくら支払うのかを、遺産分割協議書に記載することが求められます。
詳しくは、「【換価分割とは】遺産分割協議書の書き方・税金を税理士が解説」や「【代償分割とは】代償金の決め方・相続税について税理士が解説」をご覧ください。
2-3.相続税の申告義務がある
遺産分割協議書が必要なのは、相続税の申告義務があるケースです。
この理由は、税務署に提出する申告書には、相続財産の分割等に関する書類として、遺産分割協議書や遺言書の添付を求められるためです。

なお、相続税額の軽減に繋がる「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」などの特例を適用する際には、遺産分割が成立していることを証明するために、遺言書や遺産分割協議書の提出が必須となります。
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」ですので、この期限までに遺産分割協議書を作成しましょう。
詳しくは、「相続税を申告するための必要書類をプロが解説!【一覧表付】」や「【相続税の申告書の添付書類・必要資料】綴じ方、入手方法も解説」をご覧ください。
2-4.相続登記の義務がある
遺産分割協議書が必要なのは、相続登記の義務があるケースです。
この理由は、法務局に提出する相続登記申請書には、遺産分割協議書や遺言書の添付を求められるためです。

令和6年4月1日から相続登記の義務化が施行され、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはなりません。
正当な理由なく期限内に登記手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料に処される可能性がありますのでご注意ください。
詳しくは、「【不動産相続時の必要書類一覧】取得方法や法務局に提出する手順を解説」をご覧ください。
3.遺産分割協議書が不要なケース
遺産分割協議書が不要な事例は以下のとおりです。
上記に該当しないケースでは、基本的に遺産分割協議書を作成する必要があると考えてください。
3-1.遺言書に従って遺産分割をする
遺産分割協議書が不要なのは、遺言書に従って遺産分割をするケースです。
この理由は、法的に有効な遺言書がある場合は、原則としてその遺言に従って遺産分割がなされるためです。

ただし、法定相続人全員と遺言執行者の合意があれば、遺言と異なる遺産分割、つまり遺産分割協議による遺産分割に切り替えることができます。
遺言とは異なる遺産分割をする場合は、遺産分割協議書の作成が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、「遺言書と異なる遺産分割は可能!遺産分割協議の注意点」をご覧ください。
3-2.法定相続人が1人だけ
遺産分割協議書が不要なのは、法定相続人が1人だけのケースです。
法定相続人が1人であれば、被相続人の遺産を単独で相続することとなるため、遺産分割協議自体が不要です。
相続手続きでは、被相続人との関係が分かる戸籍謄本を提出することで、相続関係を証明することとなります。
詳しくは、「一人っ子相続の注意点は?メリット・デメリットと相続税対策も解説」をご覧ください。
3-3.法定相続分で遺産を分割する
遺産分割協議書が不要なのは、法定相続分で遺産分割するケースです。
法定相続分とは、民法第900条で定められた、法定相続人が有する相続分の割合のことで、主に遺留分や相続税を計算する際に用いられます。

法定相続分で遺産分割をする場合は、相続関係を証明できる書類だけで相続手続きができるため、遺産分割協議書の提出は求められません。
詳しくは、「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
3-4.遺産が現金や預貯金のみ
遺産分割協議書が不要なのは、遺産の内容が現金や預貯金のみのケースです。
遺産が現金のみの場合、相続手続きは不要ですので、遺産分割協議書を提出する必要はありません。
また、金融機関での相続手続きは、金融機関が指定する書類に法定相続人全員が署名捺印をして提出すれば、遺産分割協議書の提出は不要とされています。
4.遺産分割協議書を作成しないとどうなる?デメリットやリスク
遺産分割協議書には、法定相続人全員で決めた遺産の分割方法に、全員が合意していることを第三者に証明する役割があります。
そのため、遺産分割協議書を作成しないと、以下のようなデメリットやリスクがあります。
4-1.金融機関での相続手続きが煩雑になる
遺産分割協議書を作成しないと、金融機関での相続手続きが煩雑になるというデメリットがあります。
預貯金の払い戻しや解約などの相続手続きは、金融機関が指定する書類(例:相続に関する依頼書、相続届など)などに法定相続人全員の署名捺印があれば、遺言書や遺産分割協議書の提出は不要とされています。
しかし、複数の銀行に預貯金口座がある場合などは、金融機関毎に書類を準備して、すべての書類に法定相続人全員の署名捺印をしなくてはなりません。
相続手続きが煩雑になりますので、複数の金融機関で相続手続きをされる場合は、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
4-2.相続人同士のトラブルに発展しやすい
遺産分割協議書を作成しないと、相続人同士のトラブルに発展するリスクがあります。
例えば、遺産分割協議書を作成せずに口頭で合意をした場合、明白な証拠がなければ、「言った言わない」の水掛け論に発展する可能性があります。
相続人同士のトラブルを回避するためにも、遺産分割協議書を作成して相続人全員の合意を得ておくことが大切です。
4-3.相続関係が複雑になるリスクがある
遺産分割協議書を作成しないと、相続関係が複雑になるリスクがあります。
例えば、法定相続人の口約束だけで遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しないまま放置している間に、相続人の誰かが亡くなったとします。
このように、短期間に相続が連続して発生することを、数次相続と呼びます。
一次相続の遺産分割協議書がない状態で二次相続が発生した場合、二次相続に係る法定相続人は、被相続人が、一次相続でどれだけの遺産を相続したのかを把握することが困難です。
結果として、一次相続の法定相続人と二次相続の法定相続人で、相続トラブルに発展することが考えられます。
数次相続について、詳しくは「数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点」をご覧ください。
5.遺産分割協議書を作成できる人は?誰に依頼すれば良いの?
遺産分割協議書を作成しないデメリットやリスクは多いため、遺産分割協議をしたのであれば、遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。
遺産分割協議書を作成できる人は以下の通りで、それぞれメリットとデメリットがあります。
- 相続人
- 専門家(弁護士・司法書士・税理士・行政書士)
- その他(信託銀行や公証人)
相続人が自分で遺産分割協議書を作成すれば、費用がかからないというメリットがありますが、作成ミスや不備があると相続手続きで使えませんし、作り直す手間もかかってしまいます。
遺産の内容が現金や預貯金のみで、なおかつ相続人同士の関係性が良いのであれば、相続人が自分で作成しても良いですが、それ以外のケースは専門家に依頼されることをおすすめします。
詳しくは、「遺産分割協議書を作成できる人は?自分で作る?専門家に依頼する?」をご覧ください。
5-1.遺産分割協議書の作成は専門家に依頼がおすすめ
遺産分割協議書の作成は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家への依頼がおすすめです。
この理由は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士の基本報酬の範囲内に、遺産分割協議書の作成費用が含まれていることが多いためです。
なお、専門家によって対応できる相続手続きの内容が異なるため、どの専門家に依頼すべきかは以下のフローチャートを基に見極めましょう。

一般的な相続であれば、相続手続きのサポートを依頼する専門家は、税理士や司法書士です。
報酬の目安については、「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」や「相続登記にかかる司法書士の報酬はいくら?その他の費用の相場も徹底紹介」をご覧ください。
6.遺産分割協議書を自分で作成する方法・流れ
遺産分割協議書を作成する流れは、以下のとおりです。
遺産分割協議書の提出が必要とされる相続手続きの中で、最も期限が早いのは相続税申告です。
申告書の作成などもありますので、相続開始から8ヶ月以内には、遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。
詳しくは、「遺産分割協議書を自分で作成する方法!流れや書き方【ひな形・文例付き】」もご覧ください。
6-1.遺言書の有無を確認
まずは以下のような方法で、被相続人が法的に有効な遺言書を残していたか否かを確認します。
- 自宅や銀行の貸し金庫などを確認する
- 法務局に遺言書保管事実証明書の交付の請求をする
- 公証役場の遺言検索システムを利用する
自宅や貸し金庫などで自筆証書遺言書が発見された時は、変造・隠匿を防ぐために、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければいけません。
ただし、法務局で保管されていた自筆証書遺言や、公証役場で保管されていた公正証書遺言が見つかった場合は、検認手続きは不要です。
詳しくは、「遺言書の検認は必要?欠席できる?流れ・費用を税理士が解説」をご覧ください。
6-2.法定相続人の調査・確定
遺言書がなければ遺産分割協議をすることとなりますので、協議に参加する法定相続人の調査・確定をします。
法定相続人は民法で優先順位が定められています。家族構成によって誰が法定相続人になるのかが異なります。

法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて調査します。
なお、連絡先が不明である推定相続人がいる場合は、戸籍の附票を取り寄せたうえ、現在の住所を確認するなどして連絡先を把握します。
未成年者の相続人には特別代理人の選任が必要となり、判断能力が乏しい人(認知症・知的障害など)には後見人を付ける必要があります。
詳しくは「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」をご覧ください。
6-3.相続財産の調査・確定・評価
法定相続人の調査・確定と並行して、遺産分割協議の対象となる、被相続人の相続財産の調査・確定・評価します。
相続財産とは、被相続人が死亡時点で所有していた財産に属した一切の権利義務のことで、プラスの財産やマイナスの財産のことを指します(民法第896条)。

相続財産の調査では、遺品やエンディングノートなどを参考に、被相続人が生前に取引のあった銀行・証券会社・保険会社・不動産会社などを確認して相続財産を確定していきます。
ネット銀行の預金・ネット証券会社の有価証券・仮想通貨・電子マネーの残高など「デジタル遺産」は見落としやすい資産ですので注意が必要です。
詳しくは、「相続財産とは?具体例で相続財産に含まれるもの含まれないものを解説」をご覧ください。
6-4.遺産分割の協議
法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が・どの財産を・どのくらいの割合で・どのような方法で相続するかを話し合って決定します。
なお、相続放棄をした法定相続人は、遺産分割協議には参加できません。

何らかの事情で意見がまとまらず、遺産分割協議が不成立の場合は、家庭裁判所で遺産分割調停の申立てをします。
なお、令和5年4月1日以降は、相続開始から10年経過後の遺産分割においては、特別受益や寄与分の主張が原則としてできなくなり、法定相続分等による遺産分割がなされることとなります。
詳しくは「相続開始から10年経過後の遺産未分割の取扱い~民法改正による見直しが施行~」をご覧ください。
6-5.相続人全員の合意に基づき遺産分割協議書を作成
遺産分割協議で決めた分割方法に、法定相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。
以下は税理士法人チェスターが公開している、遺産分割協議書のひな形を用いた記載例ですので参考にしてください。

遺産分割協議書には、法律で定められたテンプレートや様式はありませんが、客観的に「どのような遺産分割をするのか」が分かるように記載しなくてはいけません。
遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「【ひな型付】遺産分割協議書の書き方とは?基礎から応用まで詳しく解説」をご覧ください。
7.遺産分割協議書についてよくある質問Q&A
遺産分割協議書の作成において、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。
7-1.遺産分割協議なしで相続登記はできる?
遺産分割協議書なしで相続登記ができるのは、遺言書に従って遺産分割する場合や、法定相続分で遺産分割する場合に限定されます。
法定相続分で遺産分割をすると、不動産は必然的に法定相続人全員の共有名義となり、権利関係が複雑化するためおすすめしません。
特別な理由がない限りは、換価分割や代償分割などを活用して、遺産分割協議書を作成した上で相続登記をしましょう。
7-2.遺産分割協議書を後で作成することはできる?
遺産分割協議書の作成自体に期限はないため、後で作成することもできます。
ただし、後回しにしている間に、次の相続(二次相続)が発生したり(上記4-3.参照)、法定相続人の考えが変わったりする可能性も考えられるため、遺産分割協議が成立したら速やかに作成されることをおすすめします。
なお、相続税申告や相続登記には期限が設けられているため、申告義務や申請義務がある場合は期限までに必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
7-3.ゆうちょ銀行の相続手続きで遺産分割協議書は絶対に必要?
ゆうちょ銀行では、遺産分割協議書がなくても相続手続きが可能です。
ただし、法定相続人全員の署名捺印がなされた、「貯金等相続手続請求書」の提出を求められます。
ゆうちょ銀行の相続手続きでは、貯金の払い戻し先はゆうちょ銀行のみです。相続手続きのために何度か訪問しなくてはならないなど、一般的な銀行の相続手続きとは異なる点がいくつかあります。
事前準備をした上で、しっかりと相続手続きを進めましょう。
7-4.遺産分割協議書に捨印は必要?
遺産分割協議書に捨印をするか否かは、法定相続人の判断に委ねられます。
捨印とは、軽微な記載ミスがあった場合に訂正印として利用できるように、余白部分に予め押印しておくことです。
自分以外の人に修正をしてもらえるというメリットがあるものの、意図しない修正を加えられるリスクがあるのも事実です。
捨印は必要不可欠ではありませんので、相続人同士の関係性などを考慮して捨印するか否かを判断しましょう。
詳しくは、「遺産分割協議書の捨印や訂正印の正しい押し方|図でわかりやすく解説」をご覧ください。
8.まとめ
遺産分割協議書が必要か不要かは、ケースによって判断が異なります。
「遺言書がない」&「法定相続人が2人以上いる」ケースでは、相続手続きが煩雑になることが考えられますので、原則として遺産分割協議書を作成されることをおすすめします。
税理士法人チェスターは、年間3,000件以上の相続税の申告実績を誇る、相続税に強い税理士法人です。
グループに所属している司法書士法人チェスターと共に、遺産分割協議書の作成など、さまざまな相続手続きのお手伝いを承ります。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































