共有名義の相続登記を徹底解説!トラブルを防ぐ方法/メリット・デメリット
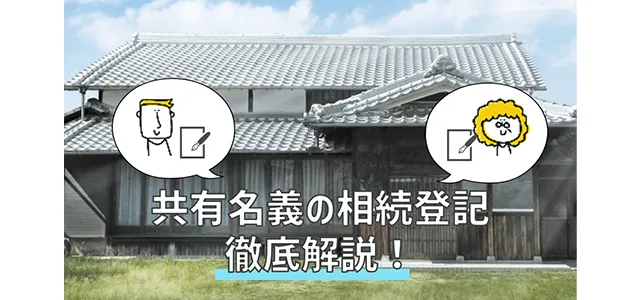
この記事の目次 [表示]
共有名義の相続登記とは
相続登記をする際には、相続人全員が協議し、被相続人の不動産を誰が取得するか決定します。
このとき二人以上で不動産を共有することがあります。これを共有名義の相続登記といいます。
また、相続人がそれぞれ、民法で定められた法定相続分に応じた共有持分を相続したときも共有名義の相続登記となります。
父が亡くなり、母と二人の子が相続人になる場合、母は2分の1、二人の子はそれぞれ4分の1の持分で不動産を共有します。
共有名義でも単独名義と同様に相続登記が必要
共有名義であっても、単独名義と同様に相続登記は必要となります。相続登記を行うと、共有者全員に登記識別情報通知書が発行されます(委任状や遺産分割協議書等の提出が必要です)。
登記識別情報は以前の登記済権利証に代わる制度で、この登記識別情報の発行をうけることにより不動産の共有者であることが証明されます。
共有持分という考え方
不動産の共有持分を有する状態とは、どのような状態なのでしょうか。
例えばある土地についてAが3分の2、Bが3分の1の割合で共有している場合、Bは土地の3分の1しか使用することができないわけではありません。
上記の例で、Bは自己の持分に基づいて土地の全てを使用することができます。
ただし、Aも同じように土地の全てを使用することができるので、Bが土地全体を占拠してAが全く使用できない状態にすることはできません。
また、Bは土地全体の売却や改良(畑を宅地に変える等)を一人で勝手に行うことはできません。共有者であるAとの協議が必ず必要となります。なお、自己の持分のみであれば、自由に売却することができます。
私道の共有持分を相続したときも登記申請は必要?
住宅団地に面した私道は、その私道を使用する人によって共有されていることがあります。
多くの人によって共有されているときは、一人当たりの持分はかなり少ないこともありますが、この私道の共有持分についても、相続登記は必要です。
被相続人が所有していた土地とその土地に接する私道の持分があるときは、どちらも相続登記をしないと、その後土地を売却することができません。被相続人の所有していた土地だけを売却すると、買主が私道を使用することができないからです。
共有名義の相続登記を行う理由
共有名義の相続登記を行う理由は、相続人間で協議がまとまらなかったため、やむを得ず共有名義にする場合と、相続人間で協議の上、共有名義にした場合と二通りあります。
遺産分割の方法に制約はないので、共有名義にすることに全員が納得していれば、共有名義の相続登記を行うことに何ら問題はありません。
共有名義の相続登記を行える人
共有名義を取得することになった相続人全員と、その相続人から委任を受けた第三者が、共有名義の相続登記を行うことができます。委任を受ければ誰でも相続登記を申請することができますが、相続登記申請書類に委任状の添付が必要です。
ただし、業として相続登記を代理申請することができるのは、司法書士や弁護士といった資格者に限られています。このことは法令等で定められており、違反すると罪に問われることもあります。
債権者代位登記によるトラブル
被相続人が借金を残して亡くなった場合に、債権者が被相続人の所有する不動産を差し押さえることがあります。
このとき不動産の名義が被相続人のままでは、差押えの登記ができません。
この場合、債権者は、「債権者代位権」という権利を行使して、強制的に相続登記を行うことができます。
相続人からの委任を受けずに例外的に相続登記ができるのです。この場合、法定相続分の割合で登記がされるため、不動産が共有になってしまうことがあります。
相続登記がなされた旨は、相続人の一人に通知されるだけであり、相続人に登記識別情報が通知されることもありません。
そのため、相続人の知らないうちに不動産が共有状態になります。
その後の遺産分割や売却が困難になることもあります。なぜなら債権者代位権を行使して相続登記された不動産は、既に差し押さえられていることも多く、被相続人の債務を完済しなければ、不動産の処分自体ができないからです。
共有名義の相続登記を行う手順
まず、相続人の範囲を確定します。相続人の範囲を確定するために、戸籍を取得する必要があります。また、相続人全員の現住所を登記する必要があるので、住民票の写しも取得します。住民票の写しについては戸籍の附票に代えることもできます。
次に、相続する不動産について調査します。
相続する不動産について漏れなく調査するため、不動産の存在する役所の税務課で『名寄帳』を取得します。またすべての不動産について法務局で登記簿謄本を取得します。
相続人と不動産の調査が終わったら、法務局に提出する登記申請書を作成します。
一般的な内容の登記申請書の記載方法については、法務局のホームページで公開されています。
最後に、申請書と添付書類を漏れなく法務局に提出します。このとき登録免許税を納めます。登記申請を受け付ける法務局は、不動産の所在地により管轄が分かれています。
管轄は法務局のホームページで調べることができます。
遺産分割後に名義変更する方法
相続人全員で遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書を作成し、各自が署名押印します。押印は実印で行い、印鑑証明書を添付します。印鑑証明書の期限は特に設けられていないので、過去に取得した印鑑証明書を添付することも可能です。
ただし、印鑑証明書は遺産分割協議に納得したという意思を担保するという側面もあるので、遺産分割協議書に署名押印した日に近い印鑑証明書を取得する方が、相続人間の後のトラブルを防止するという意味でも望ましいです。
共有名義の相続登記を行うメリット・デメリット
共有名義の相続登記について、メリットもあればデメリットもあります。被相続人の所有する不動産の状況や、相続人同士の人間関係などを念頭に、これらのメリットやデメリットを検討する必要があります。
共有名義の相続登記のメリット
一番の大きなメリットは、相続人間の公平さが図れることです。
民法で定められた法定相続分の割合は、相続人間の公平を趣旨として定められているため、共有、特に法定相続分で共有すれば、相続人から不平不満が出にくくなります。
遺産分割協議が紛糾すると、相続登記がなされないまま徒に時間が過ぎてしまい、相続人の一人が亡くなって次の相続が発生してしまうこともあります。一旦法定相続分で共有名義の相続登記を行えば、腰を据えて遺産分割協議を行うこともできます。
共有名義の相続登記をおすすめするケース
不動産を共有名義にすると、後述するように、売却や管理の方針について共有者間で意見が合わず揉めることがありますので、あまりお勧めできません。
しかし、不動産の評価額が極めて高い場合は、相続人の一人が単独で不動産を相続すると、不動産を取得しない相続人に対して高額の代償金を支払わなければなりませんので、共有名義にせざるを得ないと考えられます。
また、共有名義にしておくと、不動産を譲渡するためには、共有者全員の同意が必要となります。
たとえば、被相続人が所有していた土地が先祖代々引き継がれてきた土地であり、相続人間で今後も土地を維持する意向がある場合には、共有名義の相続登記をして良いと思われます。そうすれば、共有者の一人が単独で不動産を譲渡することはできませんので、先祖代々引き継がれてきた土地を守ることができます。
共有名義の相続登記のデメリット
共有名義の相続登記のデメリットは、メリット部分の裏返しでもありますが、不動産の売却が難しくなる場合があることです。
共有者のうちの一人でも売却に同意しないときは、売却の話は頓挫します。不動産の売却には共有者全員の同意が必要だからです。
また、共有者の一人に不動産の管理を任せてしまい、他の共有者は普段何もしないのに、不動産の売却や賃料の分配だけは執拗に求めてこられるといったことも多々あります。
固定資産税の支払いを原因としてトラブルが生じるケースもあります。
固定資産税の支払通知は、代表者一人に対して送付されますので、事実上代表者が固定資産税全額を支払うことになります。
代表者が他の共有者に固定資産税の一部の負担を求めても支払いを拒否されたり、逆に賃料の分配を求められたりすることがあります。
このように、不動産を共有名義にすると、売却や管理の方針について共有者間で意見が合わず、揉めることがあります。
単独名義にしてしまえば、誰からも口を挟まれることなく管理や処分をすることができるようになります。
また、共有者の一人に相続が発生した場合、その相続の内容にもよりますが、共有持分が更に細分化されてしまうことがあります。3分の1の持分を有する共有者が亡くなり、その配偶者と子二人が法定相続分で相続したとなると、配偶者は6分の1、子はそれぞれ12分の1の持分を取得することになります。他人の相続にはコントロールが及びませんので、意図せず共有者が増えてしまうことがあるのです。
前述したように、不動産の売却には共有者全員の同意が必要です。したがって、共有者に相続が発生して共有者がさらに増えれば、同意を得なければならない当事者が増えることになりますので、売却等の手続きが難しくなるのです。
共有名義の相続登記で問題が生じるケース
父が亡くなり、土地と建物について母と三人の子が法定相続分で相続をした場合、母は2分の1、子はそれぞれ6分の1の持分を取得します。このようなケースで、更に数年後に土地と建物を売却しようとしたときに、問題が噴出することがあります。
まずは、母が認知症を患ってしまった場合です。
不動産を売却する際は必ず母親本人に売却の意思があることが必要であり、その意思確認が必要です。
認知症の程度によりますが、意思確認できない場合は、成年後見人を選任する必要があり、手間と時間がかかりますし、不動産だけでなく母の財産がすべて成年後見人によって管理されることになります。
不動産を売却する意向があるようでしたら、母が認知症を患う前に、母が不動産を相続しない旨の遺産分割協議をまとめておく必要があります。
共有者の一人に相続が発生した場合にも注意が必要です。
共有者の一人が死亡してしまった場合、不動産の共有持分は共有者の相続人に承継されます。たとえば、上記の例で子の一人が死亡してしまい、子の配偶者と2人の子が相続した場合、配偶者は12分の1、子はそれぞれ24分の1の共有持分を取得します。
共有者が増えれば、不動産の売却時に同意を得なければならない当事者も増えてしまいます。持分が少ないからといって無視することはできず、同意を得なければならないことに変わりはありません。
共有者が海外に移住していたり、珍しいケースでは収監中といったケースもあります。この場合は迅速に共有者の意思を確認することができませんので、不動産の売却に支障が生じることがあります。
さらに、共有者の一人が行方不明になってしまった場合も問題です。
共有者の一人が行方不明だとしても、その共有者の同意なくして不動産を売却することはできません。この場合、不在者財産管理人の選任を裁判所に依頼する必要があります。そうすると、不在者財産管理人(弁護士等の専門職が選任されることが多いです。)に報酬を支払う必要がありますし、時間もかかってしまいます。
共有名義の相続登記のトラブルを防ぐ方法
共有名義の相続登記によるトラブルを防ぐには、被相続人の死亡前、死亡直後、遺産分割協議の段階、それぞれのタイミングにおいて採れる手段があります。ここではその手段について詳しく解説します。
①遺言書にて遺産分割の内容を具体的に記す
まず、被相続人が遺言書を遺すことにより、共有名義の相続登記によるトラブルを予防することができます。
遺言書には、不動産の分割方法を具体的に定めることができます。つまり、相続人の一人に単独で不動産を相続させるように定めることで、不動産の共有状態を避けることができます。この場合、相続人間で不公平が生じないように、不動産を取得しない相続人には他の財産(預金等)を相続させるよう遺言書に記しておきましょう。
また、遺言書を作成しておくことで、後に遺産分割協議の必要もなくスムーズに登記ができます。
以下では、遺言書を作成する注意点について簡単に解説します。
遺言書は、被相続人が自分で作成し、自宅で保管しておいても構いません。
しかし、自宅で保管しておくだけでは、相続人が遺言書を発見できず、遺言書の存在に気づかないまま遺産分割協議が行われてしまうことがあります。
また、自宅で保管しておくだけでは、被相続人の死亡後に相続人の誰かが遺言書を改ざんしてしまう危険もあります。
そこで、令和2年7月10日から、法務局で遺言書を保管するサービスが始まりました。
被相続人が自筆で書いた遺言書を法務局に持参し、手数料を払って保管してもらうというものです。
このサービスを利用すれば、法務局が遺言書を保管するため、相続人による改ざんのおそれはなくなります。ただし、法務局では、遺言書の形式面のみチェックされて、具体的な内容についてはチェックされないことに注意が必要です。
少しお金はかかりますが、公正証書遺言を作成する方法もあります。
公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。通常は、司法書士等の専門家と相談しながら遺産分割の内容を決定し、これを遺言書の条項に適切に反映させた上、公証人と二人の証人の面前で作成します。手数料を支払えば、公証人に自宅に来てもらうこともできます。
公証人が本人確認を行いますので、「筆跡が違う」「意思能力が不十分な状態で誰かに書かされた」などと遺言の有効性が争われるリスクを回避することができます。
遺言書は公証役場で保管されますので、相続人による改ざんや隠蔽のおそれはなく、安心です。
また、公正証書遺言であれば、裁判所による検認手続が不要となります(法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も同様に不要です。)。
公正証書遺言を作成していれば、不動産を共有状態にさせることなく、確実に相続人の一人に不動産を取得させることができます。共有名義にすることによるトラブルを未然に防ぐ最も効果的な方法だといえます。
公正証書遺言の作成について疑問点等ありましたら、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。
②生前に不動産を売却する
不動産は、前述したとおり、遺言書を作成することによって一人の相続人にその権利の全部を相続させることができます。
一方、各相続人には遺留分という最低限の取り分が認められます。したがって、不動産を取得した相続人は、他の相続人に対して相当額の金銭を支払わなければならないことがあり得ます。
ここでもし被相続人が有する財産が不動産のみだった場合、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して支払う金銭を工面できないことがあります。このような場合、不動産を換価して分割する必要が生じます。もし直ぐに売却できない不動産だった場合は、一旦共有名義にしなければならない事態も生じ得ます。
不動産を生前に売却していれば、遺産は現預金のみとなります。そうすれば、相続人は揉めることなく現預金を公平に分配すれば良いことになります。また、遺産が現預金のみであれば、仲が悪くてあまり相続させたくない相続人がいた場合であっても、遺言書を作成することにより、その相続人には遺留分相当額のみ相続させれば良いのです。
このようにして不動産が共有名義になることを回避する方法もあります。
③相続放棄を行う
相続放棄とは、相続財産全部について放棄する旨を裁判所に申請する手続きのことです。
相続放棄により、相続人は最初から相続を受けなかったことになるため、共有者を減らすことができます。
しかし、相続放棄は、相続財産全部について放棄することになるため、一部の財産についてだけ放棄をすることはできません。不動産だけ相続放棄をして、その他の現預金などは相続したいという希望は認められないのです。
そもそも、相続放棄は、相続人の意思によって行うものであるため、他の相続人がこれを強制することはできません。もし相続放棄をさせることができる関係にあれば、相続人の一人が単独で不動産を相続することに同意してくれるはずであり、遺産分割協議書への調印にも応じてくれるでしょう。
確かに相続放棄をすれば共有名義となるリスクを回避することができますが、相続人に相続放棄をさせることに期待すべきではありません。
④換価分割や代償分割を行う
換価分割とは、相続した不動産を売却し、お金に換えて、相続人間で分配する方法です。
お金に換えることにより、より公平に遺産を分割することができるため、よく使われている方法の一つです。
不動産を換価してしまえば、その後共有者の一人が不動産を管理する必要もなくなりますし、共有者間で賃料を分配する必要もなくなります。固定資産税の負担割合等について共有者間の調整も要しません。つまり、相続手続を完結させてしまうことで、トラブルの種をなくすことができるのです。
仮に遺言書が遺されていなかった場合であっても、安易に共有名義による相続登記をせず、不動産を換価して分割してしまうことをお勧めします。
不動産を換価する場合、相続した不動産の名義人を誰にするかがポイントです。
相続人全員の名義にしても構いませんが、売却時に全員が売却手続きに関与しなければならないため、手続きがスムーズに進まないこともあります。
相続人が2~3人と少人数であり、全員が近くに居住していたり、施設入所等で身動きの取れない相続人がいない等、売却手続きの負担が少なくて済むケースであれば、相続登記の直後に売却をするための共有名義の相続登記を行っても問題ありません。
相続人の代表者一人の名義にする場合は、代表者一人に売却手続きの負担がかかりますが、売主が一人のため、手続きはスムーズに進みやすいです。ただし、相続人の代表者が売却代金を受け取って、他の相続人全員に分配するときに注意が必要です。
相続人代表者から各相続人に対する贈与とみなされ、贈与税がかかることがあるのです。そのため、遺産分割協議書に換価分割であることを明記します。贈与ではなく相続分の分配であることを税務署に証明する必要があるからです。
次に、代償分割とは、不動産などの現物を相続人のうちの一部の人が取得する代わりに、他の相続人に対し金銭で支払うというものです。分割が難しい不動産を取得した者が、不公平な部分を金銭で補います。
亡くなった夫が4000万円の価値がある不動産を所有しており、法定相続人が妻と二人の子のケースでは、協議により妻だけがその不動産を相続した場合、妻が子に対しそれぞれ1000万円ずつ支払うことになります(子の法定相続分はそれぞれ4分の1)。
代償分割をするにはある程度の金銭を用意しなければならないため、金銭を用意できるかどうかが一つのポイントとなります。
また不動産の評価額を適正に出さなければ、他の相続人の同意が得られないおそれがありますし、不動産の価額と支払う金額が不均衡であれば贈与とみなされ、贈与税が課せられるおそれもあります。
上記のケースで、実際は不動産に2000万円の価値しかないのに、子に1000万円ずつ支払った場合、本来の法定相続分より多い500万円については贈与とみなされてしまうことがあります。不動産の評価額を適正に判断し、贈与にならないよう注意する必要があります。
⑤現物分割により不動産の分割を行う
現物分割とは、遺産を換価せずにそのまま分割する方法のことをいい、遺産分割の原則的な分割形態とされています。現物分割によれば、不動産が共有名義となる事態を回避することができます。
たとえば、二つの不動産を二人の相続人で分ける場合、いずれの不動産も共有名義とせずに、各相続人が単独で一つずつ不動産を相続します。
また、一筆の土地を分筆して分ける方法も認められ、これも現物分割の一種とされます。
現物分割は、各相続人がそれぞれ取得を希望する不動産が異なる場合に適した分割方法といえます。しかし、不動産の評価額に差がある場合や、不動産の評価額に争いがある場合には、代償金を巡って紛争が長期化するおそれがあります。
また、一筆の土地を分筆して分割することもできますが、分筆することにより不動産の評価額が下がることがありますので注意が必要です。
⑥信頼できる司法書士に相談する
司法書士は相続登記手続きに関するプロフェッショナルであり、相続人の人数、相続する不動産の状況(立地、地積、使用状態)、相続人の人間関係など相談者の事情を踏まえた上で、最適な相続の方法をアドバイスすることができます。
一口に相続登記といっても杓子定規に行えばよいというものではなく、相談者の数だけ相続の問題があります。全く同じ状況の家庭は世の中に二つと存在しないからです。
特に共有名義の相続登記はトラブルに発展する可能性があるため、信頼できる司法書士にアドバイスを求め、慎重に判断することが必要といえます。
共有名義の相続登記を解消する方法
相続人で共有名義にしてしまった相続登記を解消するには、まず、共有者と協議をしてみることが大事です。
共有持分を持ちたくない人がいる場合には、共有者間で持分譲渡契約や贈与契約を結ぶことにより、共有者を減らすことができます。
たとえば、相続人A、B、C、Dが一つの不動産を4分の1ずつの割合で共有している場合、そのうちBがAに持分を譲渡すれば、Aの持分が4分の2、CとDの持分が4分の1と、共有者を三人に減らせます。さらにAがCからも持分を譲渡してもらえれば、Aの持分が4分の3、Dの持分が4分の1となります。
このように持分を譲渡してもらうことで共有状態を解消することができます。ただし、Aには持分を買い取るための資金が必要になります。
共有者が持分の譲渡に応じない場合は、裁判所の手続きを利用することもできます。法定相続による相続登記をした場合は遺産分割調停、遺産分割協議を経て相続登記をした場合は共有物分割調停を申し立てることになります。ただ、いきなり裁判所に調停を申し立てると、共有者間の争いが決定的となるでしょう。極力協議によって解決するように努力しましょう。
調停とは、調停委員の立会いの下、裁判所内で話し合う手続きです。
訴訟とは違い、話し合いの場を設けて円満に解決するという趣旨の手続きであるものの、調停がまとまれば判決とほぼ同じ効力を持つ調停調書を作成してもらえます。
ただし、調停手続は必ずしも裁判所に出頭する義務がないため、当事者に調停に応じる意向が無い場合、調停が不調に終わってしまうこともあります。また、あくまで話し合いでの解決を目指す手続ですので、話し合いができる相手でなければ効果がありません。
調停で解決できない場合は、遺産分割調停であれば自動的に審判に移行し、共有物分割調停であればあらためて地方裁判所に訴訟を提起することになります。
審判や訴訟の場合、裁判所が当事者から提示された証拠をもとに合理的な分割方法を定めることになるため、必ずしも当事者の希望通りの分割方法にはなりません。
共有名義の相続登記に関する疑問と解答
共有名義の相続登記には数多くの論点が詰まっています。
専門家であっても一筋縄ではいかないこともある分野です。最後に共有名義の相続登記に関するよくある疑問について解説します。
①遺産分割前に相続人の一人が相続放棄をすると他の相続人の共有持分は増える?
共有名義の一人が相続放棄をした場合、その共有者は最初から相続人にならなかったことになるので、残された相続人の持分は基本的に増えます。しかし、相続関係によっては、共有持分が増えない相続人もいます。
たとえば、夫婦と二人の子の家族構成で、父が亡くなった場合、母は2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつの共有持分を取得します。ここで、母が相続放棄をしたときは、子の共有持分はそれぞれ2分の1に増えます。他方、子の一人が相続放棄をした場合は、母の共有持分は2分の1のまま変わらず、子の共有持分は2分の1に増えます。
なお、上記の例で、二人の子がいずれも相続放棄をした場合、第二順位の相続人である父の両親が共有持分を取得することになります。もし父の両親が既にお亡くなりであれば、第三順位の相続人である父の兄弟が共有持分を取得することになります。
②共有名義の不動産にかかる固定資産税は誰が支払う?
共有名義の不動産にかかる固定資産税は共有者全員の持分に応じて支払うのが基本です。Aが3分の2、Bが3分の1で共有している場合はその持分割合に応じて固定資産税を支払わなければなりません。
しかし、自治体の税務課からの請求の通知は、相続人の代表者に送られます。自治体としては、税金を払ってくれるなら誰が支払ってくれてもよいし、また分割して請求することによる手間を省けるからです。
共有名義の不動産の場合、一番多くの持分を持っている共有者に課税通知が送付されているようです。
同じ持分の場合は被相続人と親等が近い者に送付されているようですが、こちらも自治体によって取扱いはさまざまです。
③共有名義の相続登記にかかる登録免許税はどれくらい?
共有名義による相続登記をする場合であっても、登録免許税の計算は一筆の不動産について行います。不動産の価額×0.4%という計算方法は変わりません。価格1,000万円の土地であれば、4万円の登録免許税を支払います。
④共有名義の相続登記は三人以上でも行える?
共有名義による相続登記は、三人だけでなく、それ以上の人数でも行うことができます。
法定相続分どおりに相続登記を行う場合には、共有者の一人が相続登記を申請することができます。また、相続人の一人に委任状を渡して、相続登記を委ねることもできます。
早めに専門家へ相談することでトラブル回避も
共有名義の相続登記は様々な問題を孕んでおり、一番平等だからとか協議をするのが面倒だからという理由により安易に法定相続分で共有名義にしてしまうと、後々多くのトラブルに見舞われる可能性があります。
共有名義による相続登記を検討されているのであれば、その前に信頼できる専門家に相談してみてください。悩みや疑問があれば相続手続き専門の司法書士法人チェスターにお気軽にご相談ください。専門のスタッフが迅速かつ丁寧に問題に対処してまいります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































