成年後見人はどのように選ばれる?なれる人、手続きなどを解説
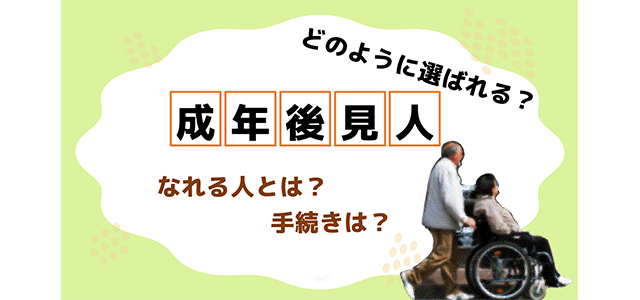
成年後見人は、自分の意思で十分な判断ができない人の代理人です。例えば認知症の相続人がいる場合、成年後見制度の活用で手続きをスムーズに進められます。成年後見制度を利用するメリット・デメリットや、家族信託について確認しましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続人の中に認知症の人がいたら?

相続が発生したとき、相続人の中には認知症の人がいるかもしれません。遺産分割協議は全ての相続人が合意しなければ無効となるため、思うように手続きが進まないでしょう。認知症の人に後見人がいれば、後見人を代理人とし手続きを進められます。
1-1.遺産分割協議は相続人全員が参加する
相続が発生すると、遺産の分け方を話し合う『遺産分割協議』を実施するケースが多いものです。相続人全員で話し合い合意することで、分配する割合が決まります。
ただし全ての相続人が集まって会議をする必要はありません。電話やメールで全員の意見を取りまとめ、遺産分割協議書を作成します。
作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。1通作成した遺産分割協議書を、相続人全員に順番に送って署名・押印してもらいます。
もしくは相続人の数だけ遺産分割協議書を作成し、それぞれに署名・押印してもらい回収する方法も可能です。
1-2.認知症の相続人は法定後見人が代理
認知症の相続人がいる場合、代理人として『成年後見人』が必要です。民法上の扱いとして、認知症の人は『意思能力のない者』とされます。
そのため、本人が遺産分割協議書に合意したと署名・押印したとしても無効です。これでは相続人全員の合意を取れません。そこで代理人として法律行為を実施できる成年後見人を選任します。
高齢化が進み、80代や90代で認知症と診断される人の割合が高いことは明らかです。遺産分割協議を実施する際には、成年後見人について知っておくと役立ちます。
2.成年後見人の種類
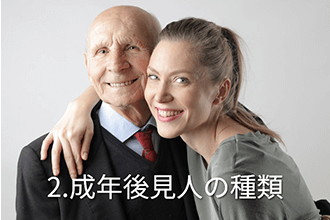
成年後見人には『法定後見人』と『任意後見人』の2種類があります。法定後見人は、判断能力が不十分と診断された後に行われる保護制度です。一方、任意後見人は判断能力が低下したときに備え、本人があらかじめ決めておくという点が特徴です。
成年後見人についてくわしく知るために、まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。
2-1.法定後見人とは
認知症や精神病をわずらい十分な判断能力が失われると、日常生活に必要な法律行為を満足にできない可能性があります。正しく判断できない結果、不必要な高額商品の購入を契約したり、詐欺に遭ったりする場合もあるでしょう。
判断能力の欠如により不利益を被ることがないよう適用される保護制度が『法定後見』です。判断能力の度合いによって『後見』『保佐』『補助』の3種類のうち、適切なものを選びます。
一度法定相続人が選定されると、本人の死亡時までその関係が続くのが原則です。
2-2.任意後見人とは
『任意後見』は、判断能力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備え、本人が決めた後見人と『任意後見契約』を結ぶ制度です。どのような判断を任せるかも、契約としてあらかじめ決めます。
遺産分割協議を始めとする法律行為や、受けたい介護や治療の実現、希望する財産の処分の実施などを依頼可能です。必ずしも利用しなければいけないものではなく、希望者のみが利用できます。
例えば資産を多く持っている人が活用すれば、将来認知症になったとしても、適切な相続税対策を実施できるでしょう。元気なうちに自分が必要だと思うことを実施できるよう準備する方法です。
2-2-1.必ず後見監督人がつく
契約書を結んでいたとしても、後見人が任意後見の範囲を超えて判断を下してしまう可能性があるかもしれません。そこで任意後見では必ず『後見監督人』を定める決まりです。
後見についての報告や、財産に関する書類を確認する役目です。また法定後見であっても、本人の預貯金や収入が多く財産管理が複雑になりやすい場合、サポートとして後見監督人が指定されるケースもあります。
3.成年後見制度を活用するには

成年後見人は勝手に決められるものではありません。制度の活用には、家庭裁判所への申立てが必要です。申立ての手順や、家族が成年後見人になる場合の課題を紹介します。
3-1.家庭裁判所に申立てをする
制度を利用するには『家庭裁判所への申立て』を行います。家庭裁判所は家庭内での紛争といった家事事件を扱う裁判所です。まずは調停を実施し、それでも解決しなければ審判や訴訟へと発展します。
成年後見人の選任も家庭裁判所の管轄です。家庭裁判所では申立ての理由・医師の診断書・面談などを通して、本人に最適な後見人を選任します。
法律上の課題や生活面での困難な事情がある場合、財産管理が複雑なケースでは、それぞれの分野に精通した専門職が成年後見人として選ばれる場合もあります。例えば弁護士・司法書士・社会福祉士などです。
申立てに必要な費用は、申立て手数料800円分と登記手数料2,600円分の『収入印紙』、3,700円分の『郵便切手』、裁判所から連絡がきたときに必要な『鑑定費用』10万円程度です。鑑定費用以外は数千円で足ります。
3-2.成年後見人は家族でもなれる?
申立書には成年後見人の候補者を記載する欄があります。下記に該当しなければ、家族が法定後見人になれる可能性もあるでしょう。
- 未成年者
- 成年後見人・保佐人・補助人などを解任されたことがある人
- 破産開始決定を受けたが、借金の免除を受けられていない人
- 成年被後見人に対して訴訟をしているかしたことのある人や、その配偶者や子どもなど
- 行方不明者
ただし、記載した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるわけではありません。ケースに応じて適切な後見人が指定されるため、専門職が選ばれるケースもあります。
また家族が成年後見人になると、親族間のトラブルに発展する可能性も考えられるでしょう。『毎月帳簿を見せろ』などと嫌がらせをする親族もいるかもしれません。
3-2-1.大きな負担となる可能性あり
家族でも成年後見人にはなれますが、大きな負担がかかる可能性があります。成年後見人になった家族は、本人の財産を代理人として管理しなければいけません。
さらに生活全般にわたって保護しなければならず、介護施設への入所契約といったことも行う必要があります。加えて1年に1回裁判所への報告も必要です。
報告書や財産目録の作成は、慣れるまで負担に感じる人もいるでしょう。サポートが多岐にわたることで、不満を感じた後見人とその他の親族との間で、関係が悪化する可能性もあります。
3-2-2.利益相反関係が発生する場合
後見人と被後見人が『利益相反』となる場合もあります。例えば子どもが母の後見人となっており、父の相続が発生するといったケースです。
それまでは子どもが後見人としてサポートしていても、利益相反関係になるときにはサポートできません。そこで家庭裁判所へ『特別代理人』の選任を求める申立てをします。
遺産分割協議に関しては、後見人に代わり特別代理人が本人の代理として手続きを進める仕組みです。ただし後見監督人が設定されている場合は、特別代理人の選任は要りません。
4.必要書類を準備する手順

家庭裁判所へ成年後見制度の申立てをするときには、さまざまな書類が必要です。書類を準備する手順を知ることで、スムーズに手続きを進めましょう。
4-1.ケアマネジャーなどが本人情報シートを作成
『本人情報シート』は、ケアマネジャーやケースワーカーなど福祉関係者に依頼し作成してもらう書類です。本人について日ごろからよく知る担当者に記入してもらいましょう。
提出は任意のため、福祉関係者との関わりがあまりないなら、無理に頼む必要はありません。例えば一度の面談をもとに作成された本人情報シートでは、適切な情報とはいえないからです。
また本人情報シートの作成には、手数料が発生する可能性もあります。
4-2.医師に診断書の作成を依頼
成年後見人の申立てには、本人の判断能力を示すために、医師の『診断書』も必要です。家庭裁判所指定の『診断書(成年後見制度用)』を作成してもらいます。
診断書の作成を依頼するときには、本人情報シートも医師へ渡しましょう。加えて家庭裁判所から精神鑑定の依頼があったときに、引受が可能かも確認します。引受の可否は『鑑定連絡票』に記入してもらいます。
4-3.申立書や親族関係図など必要書類を用意
必要な書類はほかにも複数あります。下記を全てそろえて家庭裁判所へ申立てましょう。
- 申立て書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票または戸籍附票
- 本人の成年後見等の登記がされていないことの証明書
- 健康状態についての資料
- 本人の財産に関する資料
書類はさまざまな場所で取得しなければいけません。戸籍謄本は本籍地での取得が必要ですし、保有している財産に合わせ不動産登記事項証明書や通帳のコピーなどを用意します。
全てそろえるのに時間がかかる場合も考えられるため、できるだけ早めに用意し始めましょう。
5.成年後見制度活用のデメリット
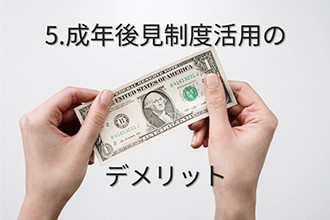
成年後見制度を利用すると、遺産分割協議発生時にスムーズに手続きできます。ただしメリットだけではありません。利用するために手間や費用がかかりますし、財産の管理に関する制限も気になる点です。
5-1.手間や月額2~6万円の費用がかかる
制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。そのためには複数の書類をそろえる手間がかかりますし、鑑定が不要でも調査に1~2カ月かかります。
弁護士といった専門職の成年後見人が選任されると、毎月報酬を支払わなければいけません。通常の後見事務のみを実施する場合『月額2万円』が目安です。
財産の保有状況によっては『月額6万円』というケースもあります。成年後見制度は原則として本人の死亡まで続くため、その間は報酬を支払い続けなければいけません。
後見人の解任ができるのは家庭裁判所のみです。解任するには不正行為といった相当の理由がなければいけません。予算オーバーによる後見人の解任は不可能です。
5-2.資産運用や相続税対策に制限あり
判断力が低下した人の生活を守るために設けられているのが成年後見制度です。そのため本人の保有する財産を維持・管理はできても、積極的な運用や相続税対策はできません。
例えば株式投資による運用や、子どもや孫への生前贈与、保有している土地への建物の建築などは不可能です。財産の有効活用や相続税対策を考えている場合には、他の制度を活用しましょう。
6.認知症になる前の対策には家族信託がある

後見人への報酬や、財産の運用・相続税対策の制限など、成年後見制度のデメリットを避けつつ、本人の財産を管理するには『家族信託』を検討するのがおすすめです。報酬が必要なく、資産運用にも取り組めます。
6-1.家族や親族が財産を管理できる
家族信託を利用すると、財産を管理するのは本人の家族や親族です。そのため報酬が発生することはまずありません。成年後見制度で毎月必要な2万~6万円の報酬が不要のため、経済的な負担が軽減されます。
利用するためには、まず家族内で家族信託の内容を話し合い、合意しなければいけません。合意した内容で契約書を作成し、財産の名義を親から子へ変更します。
このとき財産に不動産が含まれる場合は、法務局へ『信託登記』を申請します。信託財産の一覧である『信託目録』の作成も必要です。信託財産が現金や預貯金なら、財産管理に用いる専用口座も開設します。
実施するのに家庭裁判所への申立ては必要ありません。
6-2.資産運用など「資産を守る」以外も可能に
財産の管理について、本人と財産を任される家族の間で、柔軟に決められるのが家族信託の利点です。あらかじめ合意し契約書に記載があれば、積極的に運用しても構いません。
アパートの建設や株式投資などもできます。例えば本人がマンションを保有している場合、成年後見制度では老朽化していても修繕や建て替えができません。
家族信託であれば契約書の内容にのっとって、適切な工事を実施できます。信託財産の適切な運用ができる点がメリットです。
7.高齢化が進む昨今、理解が必須な制度

認知症で判断能力が低下すると、本人による法律行為は無効とされます。例えば遺産分割協議もそうです。合意し署名・押印したとしても、認知症の相続人がいると全員の合意を得られたとはいえません。
そこで利用を検討するのが成年後見制度です。家庭裁判所に選任された後見人が、本人の代理人として遺産分割協議に参加します。後見人がいれば遺産分割協議はスムーズに進むでしょう。
ただし報酬が発生する点や、財産の運用ができない点はデメリットです。資産運用や相続税対策を検討しているなら、家族信託を利用してもよいでしょう。
相続税対策についてくわしく知るには『税理士法人チェスター』への相談もおすすめです。
『法定後見制度』についてくわしく知るなら、下記もご覧ください。
【親が認知症に!】法定後見制度とは?申立と手続き。任意後見との違い
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































