葬儀費用の相場は200万円? 費用を抑える方法や補助金、費用の内訳を紹介
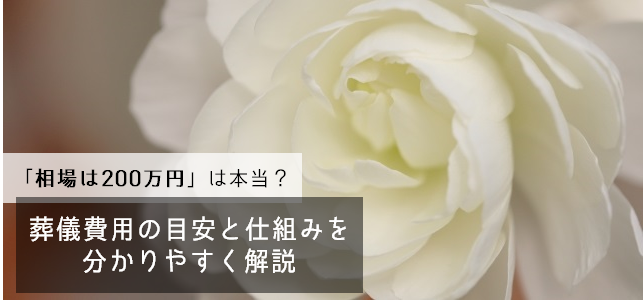
葬儀費用は何百万円もかかって価格の決まり方も不透明というイメージが定着しています。
亡くなった家族を真心込めて送りたいと思うものの、葬儀費用が高くついてしまうのではないかと心配にもなります。
この記事では、相続税を専門にしている税理士が葬儀費用の仕組みと目安をご紹介します。
葬儀費用の相場がどれぐらいなのか心配になっている人はぜひ参考にしてください。
なお、この記事では葬儀を仏式で行う前提で解説します。
この記事の目次 [表示]
1.葬儀費用は3つの要素で構成されている
葬儀費用は、主に葬儀一式費用、飲食接待費、寺院費用の3つの要素からなります。
これらの費用のうち支払額が最も大きなものは葬儀一式費用ですが、寺院費用のほうが高くなるケースもあります。
近年は亡くなる人が高齢化していて会葬者が少なくなっていることや、葬祭業への新規参入が相次いでいることなどから葬儀費用の相場は徐々に低下しています。
この章では、葬儀費用の相場をそれぞれの要素ごとに分けて解説します。
1-1.葬儀一式費用
葬儀一式費用は、お通夜から告別式まで執り行うための費用です。
火葬料、祭壇設営費、棺・骨壺などの費用のほか、葬祭場の使用料、霊柩車やマイクロバスの手配にかかる費用が含まれます。
葬儀一式費用の相場は、約30万円~140万円です。
1-2.飲食接待費
飲食接待費は、通夜振る舞いや精進落としなど会葬者に料理を出してもてなすための費用です。
遠方から来た親族の宿泊費や、香典に対する返礼品(香典返し)の費用を含めることもあります。
飲食接待費は会葬者の数によって大きく異なりますが、相場は約30万円~70万円です。
1-3.寺院費用
寺院費用は、寺院や僧侶に納めるお布施などです。葬儀では故人に戒名をつけますが、そのための戒名料が高額になることがあります。このほか、僧侶の送迎の代わりに手渡すお車代や飲食接待の代わりに手渡す御膳料も含まれます。
寺院費用の相場は、約20万円~100万円です。
2.葬儀の形式は多様になっている
以前に比べて葬儀の形式は多様になっていて、どのような形で故人を見送るかによって葬儀費用は大きく変わります。
葬祭業者によって呼び方が異なることもありますが、葬儀はおおむね一般葬、家族葬、一日葬、直葬の4つの形式に分類されます。
この章では、葬儀の形式ごとの費用(葬儀一式費用、飲食接待費、寺院費用の合計)の相場をご紹介します。
2-1.一般葬
一般葬は、町内会や会社関係など多くの会葬者を呼ぶお葬式をさします。通夜と告別式を2日間かけて執り行う、従来行われてきた一般的な葬儀の形式です。
一般葬を行うメリットは、生前にかかわりがあった多くの人が故人とお別れできることです。費用の面では、香典が多くなるため葬儀費用の実質的な負担が軽減される傾向があります。
一方、会葬者への接待など喪主や家族の負担が大きいことがデメリットです。また、他の形式に比べて葬儀一式費用や飲食接待費が多くなります。会葬者の数が事前に予想できず、予定よりも費用が多くなることもあります。
一般葬を行う場合の葬儀費用の相場は、約100万円~200万円です。
2-2.家族葬
家族葬は、家族や近親者だけで行うお葬式です。通夜と告別式を2日間かけて執り行いますが、会葬者が少ない分、費用を抑えることができます。
家族葬には、家族など親しい人どうしで落ち着いて故人をしのぶことができるというメリットがあります。会葬者に応対する家族の負担も比較的少なく済みます。
一方、葬儀に呼ばれなかった親族とトラブルになりやすいというデメリットがあります。思いがけず会葬者が多くなり、予定よりも費用が多くなることもあります。
このほか、葬儀が終わってから会社関係の弔問があり、対応が必要になる場合もあります。
家族葬を行う場合の葬儀費用の相場は、約30万円~100万円です。
2-3.一日葬
一日葬は、通夜を行わず告別式のみ執り行う葬儀の形式です。
高齢や遠方の親族でも参列しやすく、日程を短くしても故人を丁寧に見送ることができます。また、葬儀費用を抑えられるというメリットもあります。
デメリットとしては、葬儀が昼間の告別式だけになるため、故人とのお別れの機会が少なくなる点が挙げられます。会葬者の数によっては、家族葬より費用がかかる場合もあります。
一日葬を行う場合の葬儀費用の相場は、約50万円~100万円です。
2-4.直葬
直葬は、葬儀を行わずに火葬だけを行います。火葬の前に読経など簡単な儀式をする場合もありますが、会葬者を呼ぶことはありません。
会葬者を呼ばないため、喪主や家族の負担が最小限で済むというメリットがあります。
一方デメリットも多く、通夜や告別式を行わずに火葬してしまうため、故人とのお別れの時間が十分に取れません。訃報を知らされなかった親族とトラブルになるケースもあるほか、しばらくたってから葬儀を簡素にし過ぎたことを後悔する人もいます。
一日葬を行う場合の葬儀費用の相場は、約20万円~50万円です。
3.葬儀費用の相場は世間一般で言われているほど高くはない
葬儀費用は、地域の習わしや会葬者の数、家族と親戚の考え方によって大きく変わります。そのため、一概に相場がいくらということは困難です。
ここまでご紹介してきた葬儀費用の相場は、複数の民間の調査を参考にしました。
しかし、相続税申告の実務を通じて葬儀費用を見ると、実際の相場はかなり異なっています。
相続税を納めるいわゆる富裕層の人たちでも、葬儀に200万円近い費用をかけているケースはまれです。高い場合でも100万円程度に収まり、最近では50万円を下回るケースも増えています。
4.葬儀費用の負担を軽減するには
ここまでお伝えしてきたように、葬儀を行うためには数十万円~数百万円もの費用がかかります。
故人を手厚く葬りたいと思うものの、いくらでも費用をかけられる人は多くないでしょう。
この章では、葬儀費用の負担を軽減する方法をご紹介します。
残された家族に負担をかけないように、元気なうちから葬儀のあり方について話し合う機会があってもよいでしょう。
4-1.適切な葬儀の形式を選ぶ
葬儀費用は葬儀の形式によって大きく異なります。簡素な形式の葬儀を選んで会葬者を少なくすると、葬儀費用を抑えることができます。
しかし、費用だけを考えて葬儀を簡素にしすぎると、後になって「これでよかったのだろうか」と悔やむことになるかもしれません。葬儀に呼ばれなかった親族との関係が悪くなったという話も聞かれます。
故人の遺志を尊重しながら、遺族にとっても悔いの残らない方法で葬儀ができればよいでしょう。
4-2.相見積もりを取る
複数の葬祭業者から見積もりを取ること(相見積もり)も有効です。
葬儀が終わってから追加費用をめぐるトラブルが起きないように、見積書の内容を細かく見ることが大切です。特に、会葬者の人数は適切に見積もらなければなりません。
故人が亡くなってからでは、相見積もりを取って比較検討する時間はありません。生前の余裕のあるうちに見積もりを済ませておくとよいでしょう。
4-3.補助制度を利用する
遺族が生活保護を受けているなど困窮している場合は、生活保護法に基づく「葬祭扶助」を受けることができます。葬祭を行う前に市区町村役場または福祉事務所に申請します。
葬祭扶助の金額はおおむね20万円が上限となり、扶助を受けた場合は直葬を行うことが基本となります。
このほか、困窮者でなくても、健康保険から葬祭費・埋葬料などが支給されます。故人が加入していた健康保険の種類や居住地の自治体によって異なりますが、支給額は3万円~7万円です。
健康保険に加入している被保険者の扶養家族が亡くなった場合は、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。
なお、直葬を行った場合は、葬儀を行っていないとみなされて葬祭費が支給されない場合があります。
4-4.故人の遺産から支払う
葬儀費用は、喪主(遺族)が支払うことを前提に考えている人も多いかもしれませんが、故人の遺産から支払うこともできます。
葬儀費用を故人の遺産から支払う場合は、次のような点に注意が必要です。
- 銀行等に故人の死亡を知られると一定額を超える預金が凍結される
- 遺産を使うと相続放棄ができなくなる
- 遺産分割協議の前に遺産を使うと相続人の間でトラブルになる
銀行等に故人の死亡を知られると預金が凍結されますが、民法の改正により一定額まで払い戻しができるようになりました。詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
5.相続税の計算で葬儀費用はマイナスできる
相続税の計算では、遺産から葬儀費用を差し引くことができます。課税対象になる遺産の額を減らすことで、相続税が節税できます。
ただし、葬儀にかかわる費用をすべて差し引けるわけではありません。この章では、葬儀費用のうち遺産から差し引くことができるものとできないものをご紹介します。
5-1.遺産から差し引くことができるもの
相続税の計算で遺産から差し引くことができる葬儀費用は、主に以下のようなものです。
亡くなってから告別式が終わるまでの費用と考えて差し支えありませんが、納骨の費用が含まれる一方、香典返しの費用は含まれません。
- 遺体の捜索費用
- 遺体や遺骨の搬送費用
- お通夜にかかった費用
- 本葬にかかった費用
- 火葬や埋葬、納骨のための費用
- 寺院などに対するお布施
- 会葬御礼の費用
これらの費用でも遺産から差し引くことができるのは、故人の職業、財産その他の事情に照らしてふさわしいとされる範囲に限られます。
会葬御礼の費用は、別途香典返しをしている場合に限って遺産から差し引くことができます。香典返しをしていない場合は会葬御礼が香典返しとみなされ、その費用は遺産から差し引くことができません。
どのような葬儀費用が控除の対象になるか具体的な項目については、下記の記事を参考にしてください。
5-2.遺産から差し引くことができないもの
以下のようなものは葬儀費用として遺産から差し引くことはできません。
- 香典返しの費用
- 初七日以降の法要の費用
- 位牌、仏壇、墓地、墓石の購入費用
- 医学上、裁判上特別の措置(解剖など)に要した費用
香典は故人ではなく喪主に対して贈られるものであるため、香典返しの費用を遺産から差し引くことはできません。
位牌、仏壇、墓地、墓石は葬儀とは直接関係がなく相続税が非課税になる財産でもあるため、これらの購入費用を遺産から差し引くことはできません。
葬儀費用として控除できないものの具体例についても、下記の記事を参考にしてください。
5-3.相続税がかかる場合は事前に税理士に相談しておくのも一法
この章では、葬儀費用として相続税から控除できるものとできないものをご紹介しました。
相続税がかかることがあらかじめ分かっているのであれば、一連の葬儀に先立って信頼できる税理士を見つけておくとよいでしょう。
相続税は税理士に依頼して申告することが一般的とされるほど計算が難しい税目であり、申告が必要であれば、いつかは税理士を探す必要があります。
前もって信頼できる税理士を探して相談しておけば、一連の葬儀の際にとっておくべき領収書や控えておくべき金額などを指示してもらえるというメリットがあります。
6.まとめ
ここまで、葬儀にかかる費用の仕組みと目安をご紹介しました。
相続税申告実務の現場から見た感覚では、世間一般で言われている葬儀費用の相場は実際よりも高いと考えられます。また、葬儀費用は葬儀の規模や会葬者の数によって大きく変わるため、相場はあくまでも一つの目安としてお考えください。
葬儀費用は、相続税の対象となる遺産からマイナスすることができます。
相続税がかかることが見込まれる場合は、相続税に詳しい税理士に事前に相談しておくと心強いでしょう。
年間3,000件以上の相続税申告を行う税理士法人チェスターでは、相続税申告の際に集める資料や、必要な相続手続き等をまとめたチェックリストをご用意しております。無料でダウンロード頂けますので必要に応じてご活用ください。
【関連記事】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































