相続の相談はどこがいい?無料窓口8選を比較!選び方・費用相場をプロが解説
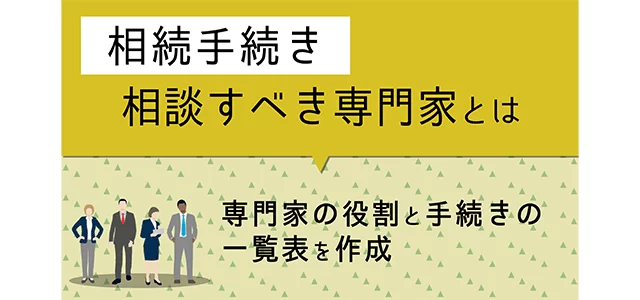
結論から言うと、相続についての相談先は、相談したい内容によって異なります。
- 遺産相続手続きに関する基礎的な内容
→ 市役所・区役所・税務署・法務局などの公的機関 - 個別の内容
→ 弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家
たとえば「相続税の申告や節税対策」は税理士、「遺産分割の揉め事」は弁護士、「名義変更や登記の手続き」は司法書士が担当します。
また、市区町村や専門家団体が無料相談窓口を設けていることも多く、まずは費用をかけずに状況を整理することも可能です。
この記事では、相続相談のおすすめ窓口・無料相談の活用方法・専門家に依頼する際の費用相場をわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続の基礎的な相談は【公的機関】
「まずは何をしたらいいの?」など、基礎的なことを確認したい場合は、まずは公的機関に相談しましょう。相談先は、相談したい内容や目的によって以下のように異なります。
| 相談したい内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続に関する基礎的な相談 | 市役所や区役所 |
| 相続税に関する基礎的な相談 | 税務署 |
| 相続登記に関する基礎的な相談 | 法務局 |
市役所・区役所・税務署・法務局は、何度でも無料で相続の相談ができます。
ただし、基礎的なアドバイスにとどまり、詳細はすべて専門家に相談するよう推奨されることは、念頭に置いておきましょう。
1-1.【市役所や区役所】相続に関する基礎的な相談
相続手続きに関する基礎的な内容に関しては、市役所や区役所に相談をしましょう。
区役所や市役所は公的機関なので安心ですし、何度相談しても無料です。
また、近年は相続に特化した専用窓口として、「おくやみコーナー」を設けている区役所や市役所も増えています。
死亡手続きを行うために、故人や遺族の状況に応じて必要な手続きを抽出し、申請書作成の補助・受付・関係する課への案内等、ワンストップサービスを提供する専用窓口のこと。自治体によって「ご遺族支援コーナー」や「おくやみ受付窓口」とも呼ばれている。
参考:政府CIOポータル「おくやみコーナー設置ガイドライン」
市役所や区役所では、弁護士や税理士による無料の法律相談や税務相談も実施されています。
開催される曜日や時間に制限があり、具体的なアドバイスはしてもらえませんが、気軽に専門家に相談ができます。
詳しくは「相続の相談が無料でできる窓口は?専門家の得意分野、相談範囲を確認」をご覧ください。
- 死亡に係る役所での相続手続き
- 役所に提出する申請書の作成サポート
- 戸籍謄本や印鑑証明書などの取得方法
- 相続が開始したが、まず何から始めるべきか分からない
- 遺産相続に関する基礎的な相談をしたい
ただし、「誰が相続人になるのか」や「遺産分割協議書の作成方法」などの個別の事案については、専門家に相談するよう案内されます。
1-2.【税務署】相続税に関する基礎的な相談
相続税に関する基礎的な内容に関しては、公的機関である税務署に相談をしましょう。
税務署では、正しい相続税申告・納付のため、一般的な相続税に関する基礎知識はもちろん、個別の事案の対面相談も可能です。
ただし、税務署に相続税の節税に関する相談はできません。
相続税の大幅な軽減を実現させるためのアドバイスや、二次相続を見据えた遺産分割アドバイスなどは、税務の専門家である税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「相続税の相談は税務署で可能│税理士との違いや予約方法等を解説」をご覧ください。
- 相続税の申告義務の判定
- 相続税の簡易的な計算方法
- 相続税の申告書の書き方
- 申告書に添付する必要書類の詳細
ただし、「どうすれば相続税を軽減できるのか」「この特例を適用する場合の遺産分割方法」など、相続税の軽減に関する内容は、専門家である税理士に相談するよう案内されますのでご注意ください。
1-3.【法務局】相続登記に関する基礎的な相談
相続登記に関する基礎的な内容に関しては、公的機関である法務局に相談をしましょう。
事前予約が必要となりますが、相続登記の申請に伴う書類の作成方法について相談できます。
ただし、法務局では「遺産分割協議がまとまらない」「相続人は誰なのか」など、個別の事情に応じた相談はできません。
あくまで相続等で取得した不動産に係る、相続登記の申請方法についての相談のみ対応が可能となります。
詳しくは「相続登記は専門家・法務局に相談すべき!メリット、費用、注意点も紹介」をご覧ください。
- 相続登記の申請書の書き方
- 相続登記の申請時に提出する必要書類
ただし、相続関係がシンプルで、なおかつ相続人全員が手続きに協力的であることが前提です。
関連する必要書類の収集や作成なども依頼する場合は、専門家である司法書士に依頼をしましょう。
2.相続の個別の相談は【各専門家】
「法定相続人は誰?」「故人の財産総額はいくら?」など、個別の相続の相談は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家にしましょう。
初回相談(30分~1時間)は無料であることがほとんどなので、まずは利用するのがおすすめです。無料相談でもしっかりとアドバイスをしてもらえますし、正式契約の締結を強制される訳ではありません。
まずはどのような相続手続きについて相談したいのかを整理した上で、適切な専門家に相談されることをおすすめします。
| 弁護士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 信託銀行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遺産相続トラブル | 〇 | × | × | × | × |
| 相続放棄の申述 | 〇 | × | 〇 | × | × |
| 相続税の申告・納付 | △ 日本税理士会に税理士登録が必要 | 〇 | × | × | × |
| 相続税の軽減対策 | × | 〇 | × | × | × |
| 不動産の名義変更 (相続登記) | △ | × | 〇 | × | × |
| 法定相続人や相続財産の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 遺産分割協議書の作成 | 〇 | △ 申告書に添付する書類のみ | △ 相続財産に不動産がある場合 | 〇 内容が定まっている場合 | × |
| 相続財産の運用 | × | 〇 | × | × | 〇 |
2-1.【弁護士】遺産相続トラブルや相続放棄など
遺産相続トラブルが起きている場合(トラブルが起こりそうな場合)や、相続放棄を検討している場合は、弁護士に相談をしましょう。
弁護士は、依頼者の権利保護のために、法律上の紛争解決や法的手続きなどをおこなう専門家です。
依頼者の代理人として相手方と交渉したり、話し合いがまとまらない場合は裁判所への調停や訴訟の手続きを担当したりすることができます。
なお、弁護士は相続登記や相続税申告書の提出などの代行業務も可能ですが、実務にくわしい弁護士は少数です。ただし、弁護士が税理士業務を行うためには日本税理士会に税理士登録を行う必要があります。
弁護士に相談するのは、あくまで法律関連の内容となります。
詳しくは、「弁護士に相談できる相続手続きや遺産相続のトラブル」や「遺産相続トラブルを裁判で解決!調停・審判の流れをわかりやすく解説」をご覧ください。
- 遺産分割協議でもめており解決をはかりたい
- 遺産分割調停や審判に移行したい
- 相続人の一部が遺産を使い込んだので責任を追及したい
- 遺言書に不審な点があり無効にしたい
- 不公平な遺言内容で遺留分侵害額請求をしたい
- 相続放棄の期限が迫っている
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、遺言書により遺留分権利者(配偶者や子など一定の相続人)が自己の遺留分を侵害された際に、遺留分を侵害している人に対して、侵害された遺留分相当の金銭の支払いを請求することです。
なお、相続をめぐるトラブルは、「法テラス」でも無料で相談できます。
国によって設立された法的トラブル解決の総合窓口なので、問題の解決に適した窓口を無料で案内してもらえます。
2-2.【税理士】相続税の軽減、申告・納付について
相続税の申告・納付はもちろん、相続税の軽減について知りたい方は、税理士に相談をしましょう。
税務に関する相談や税務申告書の作成は税理士の独占業務であり、原則として他の者がおこなうことはできません(法律上は弁護士も可能、弁護士が税理士業務を行う場合は税理士登録が必要)。
ただし、遺産分割を巡る相続トラブルが生じている場合に、相手方と交渉して遺産分割協議をまとめたりすることは税理士にはできません。
詳しくは「相続税に強い税理士の選び方」や「ネットに騙されないで!本物の相続専門の税理士を選ぶための3つのポイント」をご覧ください。
- 土地や家屋の評価額の算定
- 株式や非上場株式の評価額の算定
- 相続税の申告書や納付書の作成
- 相続税の軽減対策
- 相続税の軽減に繋がる遺産分割アドバイス
- 相続税の納税資金の相談
相続に係る税金は相続税だけではありません。被相続人の所得に係る所得税の準確定申告や、相続不動産の売却に係る譲渡所得税など、税金の種類も多岐に渡ります。
特に譲渡所得税については、「取得費加算の特例」「居住用不動産の3,000万円の特別控除」「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」など適用できる特例もあり、これらの適用要件は非常に複雑です。
税理士であれば、相続税のみならず遺産分割後に発生する税務に関する相談も可能です。
\\CHECK//
税理士法人チェスターでは、既に相続が発生している方の初回面談は無料です。お気軽にご相談ください。
>>【相続税専門】税理士法人チェスターに相談する
2-3.【司法書士】不動産の名義変更(相続登記)
相続不動産を取得した場合、相続登記が義務づけられますので、必ず司法書士に相談をしましょう。
司法書士は、法務局や裁判所に提出する書類の作成や代行を行う専門家です。
特に不動産の登記業務は司法書士の独占業務であり、原則として司法書士以外の者がおこなうことはできません(法律上は弁護士も可能)。
相続登記に係る遺産分割協議書の作成や法定相続情報一覧図の取得など、相続登記の関連業務も可能です。
また、司法書士は相続放棄の申述書の作成サポートや、成年後見人への就任などもできます。
詳しくは「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。
- 相続登記の申請
- 相続放棄の申述
- 遺産に不動産がある場合の遺産分割協議書の作成
- 成年後見人の選任手続き
- 不在者財産管理人の選任手続き
- 特別代理人の選任手続き
- 遺言書の検認手続き
検認とは、法務局での保管制度を使っていない自筆証書遺言などがあった場合に、相続人や受遺者が家庭裁判所でおこなう手続きです。
遺言書の有効性を判断するものではなく、遺言書の偽造や変造を防ぐ目的でおこなわれます。
詳しくは「遺言書の検認とは│必要なケースや手続き方法・費用を解説」をご覧ください。
\\CHECK//
すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
>>司法書士法人チェスターに相談する
2-4.【行政書士】必要書類の作成や収集
相続トラブルがなく、相続税申告や相続登記も不要であるものの、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書などの作成を専門家に依頼したい場合は、行政書士に相談をしましょう。
行政書士は、官公署(行政)に提出する書類作成や、権利義務に関する書類作成の専門家です。
相続の場面では、相続人の調査や遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更などをおこなうことが多いでしょう。
詳しくは「相続で行政書士ができることは何?メリット・司法書士との違いについて」をご覧ください。
- 戸籍収集や相続人の調査
- 法定相続情報一覧図の取得
- 相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成(内容は定まっているのが前提)
- 銀行や証券口座の解約・名義変更手続きなども依頼したい場合
上記の内容は、他の専門家でもおこなうことができますが、行政書士の報酬相場は他の士業に比べて低額となります。
弁護士・税理士・司法書士に依頼する内容がなく、必要書類の作成や収集のみを依頼したい場合は、行政書士に依頼を検討するとよいでしょう。
\\CHECK//
>>行政書士法人チェスターに相談する
2-5.【信託銀行】相続財産の運用や遺言信託
相続財産の運用を含め、全ての相続手続きを一任したい場合は、信託銀行に相談するのも選択肢の1つです。
ただし、信託銀行の行員が直接相続の手続きなどに関与することは少なく、税理士や司法書士などと提携して、手続きの取りまとめをおこなうことが一般的です。
また、信託銀行に依頼した場合には、士業の専門家に依頼するよりも費用が高額となる傾向にありますのでご注意ください。
- 被相続人が信託銀行の遺言信託を利用していた
- 相続財産の運用を検討している
被相続人が信託銀行の遺言信託を利用していた場合、まずはその信託銀行に被相続人の死亡を伝え、相談するのがよいでしょう。
信託銀行自体が各種手続きを代行してくれる場合もありますし、適切な専門家を紹介してくれることもあります。
なお、「遺言信託」とは信託銀行の商品名であり、一般的には、信託銀行が遺言書の作成支援や保管、遺言書の実現(「遺言の執行」といいます)をおこなうサービスを指します。
2-6.相続の相談をする専門家の選び方!相談先フローチャート
遺産相続の依頼先を、どうやって見分ければ良いのかが分からない方もいらっしゃるでしょう。
遺産相続の依頼先を見分けるためのフローチャートですので、参考にしてください。

相続手続きの相談をする専門家は、異なる士業が相互に連携をとっているか否かを確認しましょう。
この理由は、専門家によって代行できる業務内容が異なるためです。
例えば、相続税申告と相続登記の義務がある場合、税理士を探して相談した上で相続税申告の依頼をし、さらに司法書士にも状況を一から説明して相続登記の依頼をしなくてはなりません。
相互に連携を取っている専門家であれば、税理士に相続税申告の相談をすれば、相続登記などの業務は連携先の司法書士が対応してくれるため、相続人のみなさんの手間を省くことができます。
\\CHECK//
相続税専門の税理士法人チェスターをはじめ、グループに所属する司法書士法人チェスター・行政書士法人チェスター・法律事務所と共に、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応させていただきます。
すでに相続が開始されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
全国展開!税理士法人チェスターの拠点一覧はこちら
チェスターグループへのご相談はこちら
3.相続の相談を有効活用する方法
専門家に相続の相談をする際、初回の無料相談は30分~60分程度に限られていることが一般的です。
限られた時間を有効活用するためにも、できる限り以下のような資料を揃えていきましょう。
最低でも、専門家に何を相談したいのかを具体的にメモにまとめておくと、初回の相談がスムーズになります。
詳しくは、「【相続手続きの必要書類一覧】効率的な集め方や入手方法を解説」をご覧ください。
また、予め相続手続きの流れや期限を把握しておくことも大切です。詳しくは「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。
3-1.親族関係がわかる資料
いかなる相談内容であれ、親族関係を口頭で説明するのは難しいため、親族関係がわかる資料を準備しておきましょう。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)や住民票の除票、相続人の戸籍謄本などです。
相続関係を簡略化して表した、以下のような簡単な相続関係説明図を作成しておくと、スムーズに相談が進みます(手書きなどで簡単に作成したもので問題ありません)。

出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」
詳しくは「【テンプレート付】相続関係説明図とは?目的や書き方、記載例を紹介」をご覧ください。
3-2.被相続人の遺産内容がわかる資料
相談内容が遺産分割・相続税申告・相続登記に関係するものである場合は、被相続人の遺産内容がわかる資料もあると話が進みやすくなります。
| 被相続人の遺産の内容 | 資料の例 |
|---|---|
| 不動産 |
|
| 預貯金 |
|
| 有価証券 |
|
| 自動車 |
|
| 借入金や貸付金 |
|
| 生命保険 |
|
| その他 |
|
財産内容については、財産目録を作成しておくとスムーズに相談が進みます。
詳しくは「財産目録とは?相続における作成目的・書き方【無料Excel書式&記載例付】」をご覧ください。
3-3.遺産の分割方法に関する資料
相談内容が遺産分割・相続税申告・相続登記に関係するものである場合は、遺産の分割方法に関する以下のような資料があると話が進みやすくなります。
- 遺言書があった場合:遺言書
- 遺言書がなかった場合:遺産分割協議書
遺産の分割方法は決まっているものの、遺産分割協議を作成していない場合は、遺産の分割方法について相続人間で合意した内容のメモや遺産分割案でも構いません。
詳しくは「遺産分割協議書を自分で作成する方法!流れや書き方【ひな形・文例付き】」をご覧ください。
4.相続の手続きを専門家に依頼した場合の費用相場
相続手続きの相談を行い、専門家に依頼した場合の費用目安についてまとめました。
初回相談は無料もしくは安価であることが多いので、初回の相談時に具体的な見積もりを依頼し、見積もりを確認したうえで、正式に依頼するかどうかを検討するとよいでしょう。
なお、いずれの専門家に依頼する場合でも、相談料や報酬などとは別に、交通費や出張日当・印紙税・その他役所へ支払う手数料などの実費が必要です。
4-1.弁護士の報酬
相続トラブルなどの相続手続きに関して弁護士に相談をした場合、相談料は30分あたり5,000円程度となることが一般的です(初回相談無料の事務所も増えています)。
正式に弁護士に依頼することとなった場合、着手金や報酬などが発生します。
弁護士の報酬は自由化されているため事務所によって異なりますが、日本弁護士連合会の旧報酬規程に基づいて設定されていることが多いです。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% | 16% |
| 300万円超~3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超~3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
着手金と報酬金は、依頼者が受け取る経済的利益に料率を乗じて計算します。
詳しくは「【遺産相続・遺産分割の弁護士費用】相場は?いつ誰が払う?」をご覧ください。
4-2.税理士の報酬
相続税申告などの相続手続きに関して税理士に相談した場合、初回相談料は無料としている税理士事務所がほとんどです。
初回の相談を経て、税理士に相続税の申告業務を依頼した場合、税理士の基本報酬は遺産総額の0.5~1.0%が相場です。
| 遺産総額 | 基本報酬の目安 |
|---|---|
| 5,000万円 | 25万~50万円 |
| 7,000万円 | 35万~70万円 |
| 1億円 | 50万~100万円 |
| 2億円 | 100万~200万円 |
| 3億円 | 150万~300万円 |
税理士の基本報酬の中には、財産目録や遺産分割協議書の作成なども含むのが一般的です。
なお、相続人や不動産の数が多い場合や、相続財産に非上場株式が含まれる場合などは、加算報酬が別途発生することがほとんどです。
詳しくは「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。
4-3.司法書士の報酬
相続登記などの相続手続きに関して司法書士に相談をした場合、初回の相談料は無料であることが多いです。
初回の相談を経て、実際に司法書士に依頼することになる場合の報酬は以下の通りです(実費は含みません)。
| 依頼する手続き | 費用相場 |
|---|---|
| 相続登記の申請 | 7万円~12万円程度 |
| 遺産分割協議書の作成 | 5万円~10万円程度 |
相続登記の申請については、不動産の数や評価額、法定相続人の数に応じて、報酬が追加・加算されるケースがあります。
また、戸籍謄本の収集も依頼する場合は、2万円程度が加算されることとなります。初回相談の時点で、必ず見積もりを出してもらいましょう。
詳しくは「相続登記にかかる司法書士の報酬はいくら?その他の費用の相場も徹底紹介」をご覧ください。
4-4.行政書士の報酬
相続手続きについて行政書士に相談した場合、初回の相談料は無料であることが多いです。
実際に、必要書類の作成や相続手続きの代行を依頼する場合の、行政書士の報酬目安は以下の通りです。
| 費用相場 | |
|---|---|
| 相続人調査 | 3万円~ |
| 相続財産調査・遺産目録作成 | 3万円~ |
| 戸籍等の公的書類取得の代行 | 2万円~ |
| 相続関係図の作成 | 2万円~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~ |
| 銀行口座などの解約 | 3万円~ |
| 自動車の名義変更 | 3万円~ |
いくつかの業務をまとめて依頼すれば、個別に依頼するよりも割安な金額で依頼できることもあります。
詳しくは、「行政書士の相続手続きの費用相場はいくら?メリットも解説」をご覧ください。
5.相続の相談についてのよくある質問
最後に、相続手続きに関するよくある質問を確認しましょう。
5-1.遺産が少なければ専門家に相談する必要はないですよね?
遺産の額が少なくても、遺産分割トラブルは生じます。兆候がある場合は、専門家である弁護士に早めに相談するほうがいいでしょう。
裁判所「令和3年度司法統計年報」によると、遺産分割事件で扱う財産額は5,000万円以下が全体の76.7%を占めています。
「兄は過去に自宅建築の費用を出してもらった」「妹は海外留学費用を出してもらった」など、生前に受けた利益をどう評価するのかなどを巡って争いとなる場合もあります。
他にも、被相続人と同居していた家族が、被相続人の財産を使い込んでいたのではないかという疑いから生じるトラブルなどもよくあります。
詳しくは「相続でもめる家族の特徴3つ!原因や予防対策・対処法を詳しく解説」をご覧ください。
5-2.遺言を残しておけばトラブルになりませんか?
遺言書があればある程度のトラブルを回避することはできるものの、絶対にトラブルに発展しないという保証はありません。
例えば、自筆証書遺言の場合、日付が記載されていないなど、遺言の書式に不備があり、法的に有効ではない遺言となっていることもあります。
また、残された遺言書の筆跡が明らかに被相続人のものとは違っていたり、遺言書を作成した日付が被相続人の認知症が悪化した後であったりと、遺言書に不審な点があることもあります。
さらに、遺言の内容が「長男に全財産を相続させる」など、遺留分を無視した、極端にかたよったものである場合にも、トラブルに発展する可能性があります。
詳しくは「【遺言トラブル11選】具体的事例と対応方法をプロが解説」をご覧ください。
5-3.相続税の申告期限までに納税資金が準備できない場合はどうなるの?
遺産総額が多額で相応の相続税を納税しなければならないものの、遺産の大半が不動産や非上場株式など現金以外であるため、相続税の支払いに苦労するケースはよくあります。
この理由は、相続税の支払い方法は、期限までの金銭一括払いが原則とされているためです。
取得した相続財産を換価して納税資金を準備したり、延納や物納などの納税方法を検討したりする必要があるでしょう。
必ず税理士に相談して、最適な方法を提案してもらいましょう。
5-4.専門家に相談したら、依頼しないとダメ?
無料相談などで相談しても、必ず依頼をしなければならないということはありません。
専門家のほうでも、そのように考えていることはほとんどありません。相談して、依頼の必要がないと思えば依頼しなくても大丈夫です。
また、相性が合わないと感じたら、他の専門家に依頼しても問題ありません。
5-5.海外が関わる相続の相談は誰にする?
海外が関わる「国際相続」は、複雑な法律や税制が絡むため、国際相続の経験が豊富な弁護士や国際税務に強い税理士に相談すべきです。
法的な問題は弁護士、相続税に関する問題は税理士に相談しましょう。現地の専門家と連携できるネットワークを持つ専門家を選ぶのが重要です。
6.相続手続きの相談はお悩みに合った専門家へ
相続手続きは、相続人がすべてご自分でおこなうこともできます。
しかし、相続に関する知識がない人がすべての相続手続きを行うと、非常に大きな労力と時間が必要であり、間違いがあるのではないかという不安がつきまといます。
専門家に依頼すれば、報酬などの費用はかかるものの、労力、時間、余計な心配をすべて無くすことができます。
実際に業務を依頼する場合は、相続実務の経験が豊富な専門家を選ばなければなりません。
とはいえ、必要な相続手続きにあわせて、それぞれの専門家を探して対応をするのは大変です。
相続手続きの相談をするのであれば、専門家同士が相互に連携を取っているグループを選択されることをおすすめします。
6-1.チェスターグループにご相談を
チェスターグループは、相続業務に特化した専門家集団です。
チェスターグループには、相続専門の税理士・司法書士・行政書士・弁護士はもちろん、不動産の売却等を取り扱う株式会社が揃っています。
すべての相続手続きをチェスターグループ内で完結でき、相続の相談にかかる時間や労力が最小で済みます。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































