内縁の妻が相続財産を受け取れるようにするには?遺留分や税金に注意
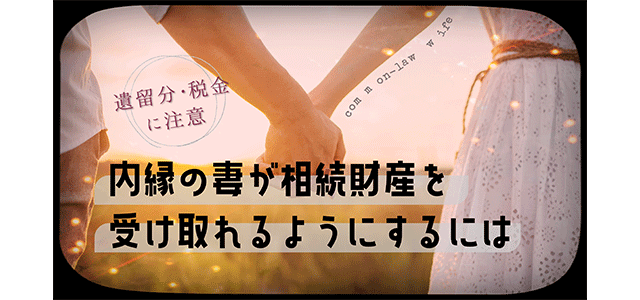
内縁の妻は法定相続人ではありません。そのためどれだけ長きにわたり連れ添っていたとしても、相続で財産を渡せないのが原則です。内縁の妻が財産を受け取るには、夫が生前の間に対策しましょう。生前贈与や生命保険・遺贈・死因贈与について解説します。
この記事の目次 [表示]
1.内縁関係でも相続人になれる?

法的な婚姻関係を結んでいないパートナー同士が『内縁関係』です。通常の夫婦と同様の生活実態があるケースでも、パートナーが亡くなった際の相続の扱いはまったく異なります。
1-1.内縁関係とは?
内縁関係は法律では定められていません。一般的には下記を満たしていると、内縁関係にあると考えられます。
- お互いに婚姻の意思があり、長い期間にわたって夫婦同然の共同生活をしている
- どちらの親族からも夫婦同然と扱われている
- 結婚式をしたり、仕事の関係者や友人など外部の人に配偶者として紹介したりしている
パートナーとの関係が内縁関係と認められる場合、法的な保護を受けられる可能性があります。例えば内縁の配偶者が死亡すると、一定の要件を満たすことで遺族年金の受給が可能です。
内縁の配偶者が亡くなったとき、住宅を賃貸しており賃借権を持っていると、残されたパートナーは賃借権を引き継げます。残されたパートナーは、亡くなった配偶者と同居していた住宅に住み続けられる仕組みです。
1-2.婚姻関係がないと相続人になれない
婚姻届を提出していない内縁関係であっても、遺族年金を受け取ったり、賃借権を引き継いだりできます。ただし内縁の配偶者が生前所有していた財産の相続に関しては、内縁関係のパートナーに権利はありません。
法定相続人と定められているのは『死亡した人の配偶者』『死亡した人の子ども』『死亡した人の直系尊属(父母や祖父母)』『死亡した人の兄弟姉妹』です。
ここで登場する配偶者は、あくまでも婚姻届を提出している法的な配偶者を指します。どれだけ長い期間を一緒に過ごしていても、晩年の介護を一手に引き受けていても、内縁関係では相続人になれません。
2.パートナーが相続財産を受け取れるケース

内縁の配偶者が死亡したとき、パートナーは原則として相続財産を受け取れません。ただし状況によっては、相続財産を受け取れる可能性もあります。
2-1.相続時点で配偶者の場合
内縁の配偶者が亡くなったときに、相続財産を引き継げるようにするなら、婚姻届を提出し法的な夫婦になるのが一つの方法です。『法的』に配偶者になれば、常に法定相続人として、財産を引き継ぐ権利が発生します。
配偶者が法定相続人になるために、婚姻期間の定めはありません。内縁の配偶者が死亡する直前に婚姻届を提出したとしても、相続発生時点で配偶者になっていれば相続の対象です。
2-2.ほかに相続人がいない場合
亡くなった内縁の配偶者に相続人がいない場合、パートナーは『特別縁故者』として扱われます。特別縁故者であれば、亡くなった配偶者の財産を受け取れます。ただし自動的に受け取れるわけではありません。
まずは相続人としての権利を主張する人がいないかどうか、待つ期間が設けられます。その期間に誰も現れなければ、清算後の財産は特別縁故者である内縁関係のパートナーが受け取れます。
ただし、相続人がいないと確定してから3カ月以内に『特別縁故者に対する財産分与』の申立をしなければいけません。加えて審判で特別縁故者と認められることも必要です。
3.生前贈与でパートナーに財産を残す
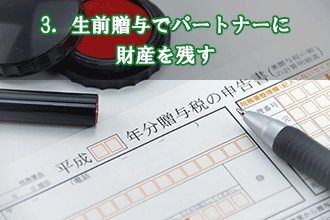
法定相続人ではない内縁関係のパートナーには、『生前贈与』を使い財産を残す方法もあります。税金の負担を抑え財産を渡すには、基礎控除額を把握しておきましょう。贈与契約書の作成についても解説します。
3-1.毎年基礎控除額までは贈与税がかからない
生前贈与を利用するなら、贈与税の基礎控除額について知っておきましょう。贈与には税金がかかり、贈与を受けた人に納税義務が課されます。
ただし贈与を受けた金額全てに対して課税されるわけではありません。毎年1月1日~12月31日に贈与を受けた金額から、基礎控除額『110万円』を差し引いた額に課税されます。
年に110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない仕組みです。
3-2.贈与契約書は必須
贈与は、贈与する人とされる人の『あげます』『受け取ります』という合意によって成立します。合意さえあればよいため、契約は口頭だけでも構いません。
ただし口頭のみの契約では、贈与があったと第三者に対して証明できません。そこで贈与契約の内容を明文化し『贈与契約書』を作成しましょう。
贈与の内容や日付などを記載し、贈与する人・される人それぞれが署名捺印をします。加えて公証役場で確定日付を取っておくと、確かにその日に作成したものと証明が可能です。
契約書は2通作成し、贈与する人・される人がそれぞれ保管します。
4.生命保険を活用しパートナーに財産を残す

『生命保険』を使う方法もあります。保険金は法定相続人が最低限受け取れる相続額である遺留分の計算に、原則として含めません。内縁関係のパートナーに財産を残しやすい方法です。
4-1.パートナーを受取人にできる保険に入る
財産を残すために生命保険を利用するなら、保険金の受取人に内縁関係のパートナーを指定できる保険を選びましょう。下記の条件を満たしていると、受取人に指定できます。
- 内縁関係のパートナー以外に戸籍上の配偶者がいないこと
- 同居期間が一定期間を超えていること
- 一定期間を同一生計で暮らしていること
ただし保険会社によって基準が異なる点に要注意です。ほかの条件が必要なケースもある上、そもそも受取人に指定できるのが戸籍上の配偶者に限定されているケースもあります。
審査を受けてみなければ指定の可否が分からない場合もあるため、まずは保険会社に問い合わせましょう。
4-2.原則、遺留分侵害額請求の対象にならない
法定相続人には、最低限保障される遺産取得分である『遺留分』があります。生命保険の保険金は、原則として遺留分の計算に用いる遺産に含まれません。
遺留分を請求される恐れがなく、基本的に全額内縁関係のパートナーに渡せます。ただし相続財産に対し保険金があまりにも多い場合には、遺留分の対象となるかもしれません。
例えば相続財産が100万円のみなのに対し、保険金が5億円もあるようなケースです。このような場合には、保険金も遺留分の計算対象です。受取人に指定されていても、全額を受け取れない可能性があります。
5.遺贈でパートナーに財産を残す
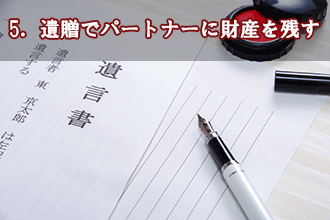
遺言によって財産を残す『遺贈』を利用してもよいでしょう。通常であれば、相続財産は法定相続人同士で分配されます。しかし遺言に遺贈の記載があれば、その内容に従って、パートナーは財産を受け取ることが可能です。
5-1.遺言を作成する
遺贈は遺言を残す人の意思のみで実施できる財産処分の方法です。相続人はもちろん、相続人以外にも財産を渡せるため、内縁関係のパートナーに対しても財産を残せます。
パートナーに遺贈で財産を渡すには、『遺言書』を作成しましょう。遺言書は本文を自筆で書く『自筆証書遺言』と、公証役場で作成する『公正証書遺言』の2種類がよく用いられます。
5-2.相続税に対する配慮が必要
残されたパートナーは、遺贈で財産を取得すると『相続税』を納めなければいけません。このときの納税額は、通常より20%高く設定されます。
法定相続人より税額が高くなりやすいため、納税に多額の資金を用意しなければいけないケースもあるでしょう。多額の財産を遺贈で残しても、税金の負担が重くなるだけという可能性もあります。
財産を受け取るパートナーの負担を考えた上で、遺贈を利用するか検討するとよいでしょう。
5-3.相続人に遺留分を請求される可能性がある
法定相続人が受け取れる遺留分を、内縁関係のパートナーに遺贈する金額が侵害している場合、相続人から『遺留分侵害請求』をされる可能性があります。
遺贈により侵害されている遺留分を請求するのは、相続人が本来持っている権利であり、止められません。ただし遺留分には下記の通り時効があります。
- 遺留分を侵害する贈与や遺贈を知ってから1年経過したとき
- 相続開始から10年経過したとき
また遺産分割協議で一度合意すると、時効を迎える前でも相続人全員が合意しなければ請求できません。
6.死因贈与でパートナーに財産を残す
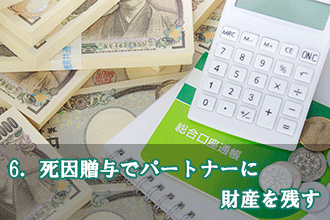
『死因贈与』を利用する方法もあります。あらかじめ合意していれば、亡くなった後に内縁関係のパートナーに財産を残せます。
6-1.双方の合意が必要な契約行為
家や土地・車など、今使っているものを死後にパートナーへ渡したいなら、死因贈与を使うケースが多いでしょう。死因贈与は『自分が死んだら家をあげる』といった内容の契約です。
贈与する人の死亡をきっかけに贈与が成立します。死後に財産を渡すという点では遺贈と同じですが、贈与する人・される人の間に合意がなければいけません。
パートナーには、あらかじめどのような財産を贈与するか伝えておきます。契約は贈与のため、作成するのは遺言書ではなく『贈与契約書』です。
口頭でも契約は成立しますが、契約書を作成しておくと第三者へも確かに贈与契約を結んでいると示せます。
6-2.負担付き死因贈与契約も
死因贈与の中には『負担付き死因贈与契約』もあります。契約が成立すると、贈与される人は負担をまっとうすることで贈与を受けられる仕組みです。例えば下記のような内容の負担付き死因贈与があります。
- 1,000万円を贈与する代わりに、身の回りの世話を続けてほしい
- 家を贈与する代わりに、リフォーム費用を負担してほしい
- 土地を贈与する代わりに、自分が死ぬまで無償で土地を管理してほしい
成年後見を利用するより自由度が高い仕組みのため、亡くなるまでに満たしたい希望がある場合に利用しやすいでしょう。贈与する人はいつでも契約を撤回できます。
ただし贈与される人が既に負担を履行しているときや、贈与する人が死亡してからは撤回できません。
7.財産を渡したい場合は計画的に対策を
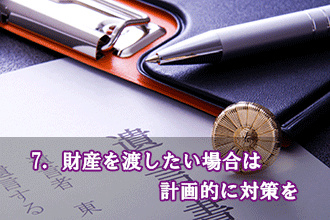
内縁の妻は法定相続人ではありません。そのため相続財産を受け取れないのが原則です。それでも内縁関係のパートナーに財産を残したい場合には、生前から準備を始めましょう。
生前贈与・生命保険・遺贈・死因贈与といった方法の利用が可能です。確実に財産を残せるよう、それぞれの方法で財産の渡し方を押さえておくとよいでしょう。
財産を引き継ぐと、相続税や贈与税が発生するケースもあります。どのくらいの負担がかかるかは『税理士法人チェスター』へ相談し、計算してもらうと確実です。
『内縁の妻』に財産を渡す方法については、下記もご覧ください。
内縁の妻と相続|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































