通帳で生前贈与の証明はできる?贈与契約書作成時の注意点・相続対策について解説
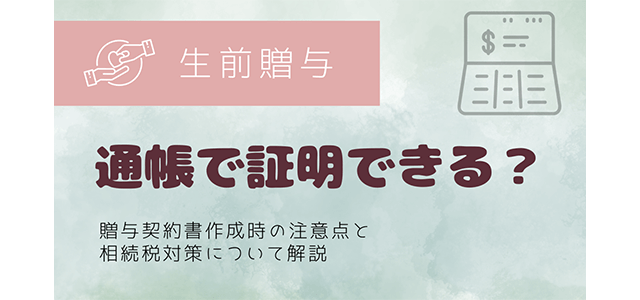
相続対策のために、存命であるうちに資産を贈与する「生前贈与」をする人は少なくありません。生前贈与をして相続税がかかる財産を減らすことで、税負担の軽減効果が期待できるためです。
生前贈与をするときに、子供や孫の名義で預貯金口座を開き、そこにお金を入金するケースがあります。しかし、子供や孫の名義で作った預貯金口座が「名義預金」と見なされてしまうと、生前贈与をしたことにはなりません。
今回は、名義預金とみなされるケースや生前贈与をする際の注意点などを、相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.生前贈与のために通帳を作っても相続対策とならないことがある
財産を贈与した人に贈与税が課せられるのは、1月1日から同じ年の12月31日までに贈与された財産の合計金額が、基礎控除額の110万円を超えるときです。そこで、相続対策を目的に生前贈与をする際は、贈与税がかからない範囲で財産を贈与する「暦年贈与」がよく用いられます。
暦年贈与とは、財産を受け取る人(受贈者)1人あたりの贈与額を年間110万円以内にして、毎年少しずつ財産を贈与する方法です。
暦年贈与をするために、子供や孫などの名義で預貯金口座を作って送金するときは、名義預金とみなされないようにすることが大切です。名義預金は、名義人と実際に所有している人が異なる預金を指します。
たとえば、父親が子供の名義で預金口座を開き、定期的に送金していたとしましょう。実際に預金口座を管理しているのが子供ではなく父親であれば、その預金は名義預金とみなされます。
名義預金と認定されると、口座内にあるお金は亡くなった人(被相続人)のものであると見なされて、相続税の課税対象となります。
1-1.名義預金は預金口座を管理する人のもの
相続税の課税対象となるのは、被相続人の名義となっている財産ではなく、実際に所有していた財産です。名義が異なる人のものであったとしても、実質的な所有者が被相続人であれば相続税の課税対象になります。
預金口座内にあるお金は、口座を管理している人のものです。自分自身で管理している他人名義の口座に送金をしても、単に財産の名義を変えただけと判断されるため、生前贈与は成立しません。
そのため、実質的に口座を管理する人が亡くなって相続が発生したとき、預金口座内のお金は相続財産とみなされます。
1-2.名義預金と見なされると相続税が課税される
名義預金を管理している人が亡くなった場合は、口座内のお金は相続財産となり遺産分割の対象となります。
また、名義預金も含めた相続財産の総額が、相続税の基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人)」を超えている場合は、相続税がかかります。
名義預金については以下の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。
(参考)名義預金の基礎知識と相続税が追加で発生する条件を解説
(参考)名義預金はばれる!贈与税ではなく相続税が課税される理由と対策
2.子供名義の口座を作って暦年贈与をするときのポイント
相続対策を目的に生前贈与をする場合、そもそも贈与契約が成立したと認められなければ、財産が移転したことにはなりません。また、贈与契約が認められたとしても、贈与の仕方を誤ると高額な贈与税が課せられることがあります。
そこで、子供や孫の名義で預金口座を作って暦年贈与をするときは、以下の点に注意をすると良いでしょう。
- 贈与契約書を作成する
- 同時期の贈与を避ける
- 未成年者への贈与をする場合も贈与契約は成立する
- お年玉であれば110万円を超えても非課税となる
なお、子供名義の口座で贈与税がかかるケースについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)子供名義の口座に贈与税がかかるケース|節税対策も解説
2-1.贈与契約書を作成する
財産を贈与した人(贈与者)と贈与された人(受贈者)の双方が正しく認識していなければ、贈与契約は成立しません。そこで、作成しておきたいのが「贈与契約書」です。
贈与契約書は、贈与が確実に行われたことを第三者に証明するために、贈与者と受贈者の間で交わす書類のことです。
生前贈与をする際に子供や孫などの名義の預金口座を作る場合、贈与契約書を作成して贈与の事実を書面に残しておきましょう。
また、お金を渡した記録が残るように、現金の手渡しではなく銀行振込で贈与すると、贈与の事実があったと客観的に認められやすくなります。
2-2.同時期の贈与は避ける
1人あたりの贈与額が、年間で110万円以内の贈与をする場合、同じ時期に贈与をするのは避けたほうが良いでしょう。毎年同じタイミングで同じ金額の贈与をし続けていると「定期贈与」とみなされる恐れがあるためです。
定期贈与とは、毎年一定金額の贈与をすることが決まっている贈与のことです。たとえば「毎年100万円ずつを10年間にわたって贈与する」のような贈与契約は、定期贈与となります。
1年あたりで贈与額が100万円であれば、贈与税の基礎控除額である110万円を下回っているため課税されることはありません。
しかし定期贈与とみなされると、最初から100万円を10年間にわたって合計1,000万円を贈与する契約であったとみなされるため「1,000万円−110万円=890万円」に贈与税がかかります。
そこで、毎年110万円以下の財産を毎年贈与するときは、贈与するタイミングや贈与額を変えたうえで、その都度贈与契約書を作成し定期贈与とみなされないようにすることが大切です。
2-3.未成年者に贈与する場合は親権者の同意が必要
未成年者に贈与する場合は、親権者の同意を得られれば贈与契約は成立します。たとえば、孫に財産を贈与する場合、その親(贈与する人の子供またはその配偶者)の同意が必要です。
なお、財産を贈与された未成年者が、贈与の事実を知らなくても問題ありません。
未成年者に財産を贈与するときも、贈与の事実を証明できるようにすることが大切です。口約束ではなく、親権者が代理人となって贈与契約書を作成しましょう。
また、お金は金融機関の口座に振り込んで履歴を残し、贈与された事実が証明できるようにすることが大切です。
2-4.一般的に妥当な金額であればお年玉に贈与税はかからない
孫や甥、姪などにお年玉を渡す場合、社会通念上相当と認められる金額であれば、贈与税の課税対象にはならないとされています。
そのため、親族や知人の数が多く年間で受け取ったお年玉の金額が110万円を超えたとしても、1人当たりの贈与額が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税はかかりません。
ただし、お年玉として渡す金額が、常識から考えて余りにも高い場合は、贈与税がかかる可能性があります。お年玉として渡す金額の判断が難しい場合は、税理士や最寄りの税務署に相談をすると良いでしょう。
3.贈与契約書を作成するときのポイント
贈与契約書を作成するときは、信頼性を高めることが大切です。そのためには、以下の点を意識すると良いでしょう。
- 署名と日付は自筆で記入する
- 必要な項目を漏れなく記載する
- 確定日付を取って立証力を高める
なお、贈与契約書を作成する方法について詳しくは、以下の記事でも解説していますのでご覧ください。
(参考)贈与契約書の書き方【保存版】様式・注意点を記載例付きで解説
(参考)贈与契約書を代筆で-本人が自署できない場合に不備のない契約書を作成する方法
3-1.署名と日付は自筆で記入する
贈与契約書はパソコンでも作成できます。しかし、すべてパソコンのみで作成された贈与契約書は、本人以外の人が作成したものではないかと疑われてしまいかねません。
そこで、パソコンを用いて贈与契約書を作成するとしても、署名と日付だけは自筆で記入するようにしましょう。
また、贈与契約書には贈与者の実印を押印することでさらに信頼性が高まります。
3-2.必要な項目を漏れなく記載する
贈与契約書に記載すべき項目は特に定められていませんが、以下の項目は記載しておくことをおすすめします。
- 贈与を行った日付
- 誰から誰に贈与されるのか
- 贈与する財産の種類
- 贈与された金額
- 贈与者と受贈者の住所・氏名
- 贈与の条件
- 贈与の方法
贈与する財産が不動産である場合、所在や番地を記載します。また、贈与契約書に収入印紙を転封しなければなりません。収入印紙代は、贈与された不動産の金額によって異なります。
財産を受け取る人が未成年であれば、受贈者名だけでなく親権者の氏名も記載しましょう。
3-3.確定日付を取って立証力を高める
贈与契約書を作成する時は、立証力を高めるために確定日付日を取ると良いでしょう。確定日付とは、証書や文書などがその日に存在していたことを証明するものです。
贈与契約書に確定日付があると、税務署から「家族で口裏をあわせて過去の日付で契約書を作ったのではないか」と疑われにくくなります。
確定日付は、公証人役場でもらうことが可能です。作成した贈与契約書を公証人役場に持参すると、公証人が内容を確認し、記載内容に問題がなければ、確定日付印が贈与契約書に押印されます。
確定日付の押印にかかる費用は、1件につき700円程度です。
4.子供名義の通帳を作るときの注意点
子供名義の通帳を作るときは、以下の点に注意しましょう。
- 親子の印鑑は別にする
- 子供名義の通帳は親が代理人として手続きする
- 口座の名義人が通帳を自由に使用できるようにする
4-1.親子の印鑑は別に
子供がまだ幼かったとしても、預金口座の届出印は両親とは別の印鑑にすることをおすすめします。子供と親の印鑑が同じであると、実質的には親の通帳であるとみなされやすくなるためです。
そのため、子供名義の預金口座を作る前に、子供の名前が入った印鑑を作っておくと良いでしょう。子供が育ち、口座を管理できるようになったら、預金口座の通帳とともに届出印を渡します。
4-2.子供名義の通帳は親が代理人として手続きする
子供が幼く自分自身で通帳を作ることができない場合は、両親をはじめとした法定代理人が代わりに作成することになります。
両親が子供の名義で通帳を作る際は、必要書類を準備して金融機関の窓口で手続きをします。口座開設の際に必要となる書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。
- 子供の本人確認書類:マイナンバーカード・健康保険証・住民票など
- 親権者の本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・住民票など
- 子供と親権者の関係を確認できる書類:住民票・戸籍謄本・母子手帳など
住民票や戸籍謄本などは、発行後6か月以内のものに限られるのが一般的です。また、健康保険証を本人確認書類として提出する場合、追加で他の本人確認書類の提出を求められる場合があります。
金融機関によっては、インターネットで口座を開設することも可能です。ただし、インターネットで通帳を作ると、紙の通帳は発行されないことがあるため、口座の開設後は口座を管理する専用ページから電子通帳の取引履歴を定期的にプリントアウトしておくと良いでしょう。
4-3.口座の名義人が通帳を自由に使用できるようにする
名義人である人が通帳の存在を知らないと、贈与契約は成立しません。通帳の存在を名義人に知らせないまま亡くなると、口座にあるお金は相続財産となってしまいます。
そのため、子供や孫の名義で通帳を作ったのであれば、名義人が自由に使用できるように口座の存在や保管場所を知らせておき、本人が自由に利用できるようにしておきましょう。
口座内にあるお金を子供が使ってしまわないか心配なときは「口座からお金を引き出すときは報告してもらう」「親が定期的に口座の残高を確認する」などの方法で対策することをおすすめします。
5.子供の通帳にお金を移して贈与税がかかるとき
子供の名義で作った通帳を本人に管理してもらっていても、贈与税がかかってしまうケースがあります。代表的な事例は、以下のとおりです。
- 預かっているものだと証明できない
- 贈与額があまりにも過大
5-1.預かっていたものだと証明できない
親族や知人から預かったお年玉を、子供の代わりに親自身の預金口座で管理していた場合、将来的に子供名義の預金口座に移したとしても、贈与ではないため贈与税はかかりません。
しかし、本来であれば子供のお金であることが証明できないと、税務署からは贈与とみなされて贈与税の課税対象になることがあります。
そのため、子供の代わりに預かっているお年玉については、親自身の口座に入金するのではなく、最初から子供名義の口座で管理しておくと良いでしょう。やむを得ず、一時的に親の口座に入金する場合は、契約書や覚書を作成し、子供からお金を預かっているという記録を残すことが大切です。
5-2.贈与額があまりにも金額が過大
子供に生活費や教育費を渡す場合、通常必要と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。国税庁は、贈与とはならない生活費や教育費について、以下の通りに定めています。
- 生活費:日常の生活に必要な費用や治療費、養育費など
- 教育費:学費や教材費、文具費など
※参考:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
生活費や教育費という名目であったとしても、贈与された金額が過大であった場合は贈与税の課税対象となってしまいます。
また、 贈与税がかからないようにするためには、生活費や教育費が必要となるタイミングでその都度贈与しなければなりません。必要でないタイミングで贈与したとみなされると、贈与税の課税対象となります。
加えて、生活費や教育費として渡したお金であっても、贈与された本人が預金をしたり株式や不動産などの購入資金に充てたりすると贈与税がかかります。 子供にお金を渡すときは、必ず生活費や教育費にあてるように念を押しておくと良いでしょう。
6.相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算される点に注意
相続が開始される前の一定期間内に、相続人へ贈与された財産は相続財産に加算され相続税の課税対象となります。 これを「生前贈与加算」といいます。
令和5年(2023年)までに行われた贈与で相続財産に加算されるのは、相続開始前3年以内に贈与された財産です。しかし、令和6年(2024年)以降は、相続財産に加算される贈与の期間が順次延長されていき、最終的に相続開始前の7年以内まで課税対象となります。
ただし、すでに支払った贈与税については、相続税額から控除されます。また、贈与税の配偶者控除を受けて贈与された財産については、相続財産に加算されません。
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上ある夫婦のあいだで、居住用の不動産またはそれを購入するための資金を贈与するときに利用できる制度です。この制度を適用した場合、贈与税の基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで贈与税がかからなくなります。
生前贈与加算の対象になるのは、相続や贈与(遺言によって特定の人に財産を贈ること)によって遺産を取得した人です。相続や遺贈によって財産を取得していない人に贈与された財産は、タイミングにかかわらず生前贈与加算の対象外となります。
たとえば、相続人が配偶者と長男、長女である場合、被相続人が生前に孫へ贈与していた財産は、生前贈与加算の対象外となります。
生前贈与加算について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相続開始前3年~7年以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?
7.生前贈与による相続対策は専門家に相談を
生前贈与をするために子供や孫の名義で通帳を作ったとしても、名義預金と認定されてしまうと贈与契約が成立しません。また、名義人である人に管理を任せていたとしても、贈与の仕方を誤ると多額の贈与税が課せられることがあります。
生前贈与の方法を間違えるとかえって高額な税負担が生じかねません。そこで、相続対策を目的に生前贈与を検討している方は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人チェスターは相続税を専門としており、一般のお客様だけでなく同業の税理士からも高く評価いただいています。
税理士法人チェスターの相続対策コンサルティングサービスでは、相続税の節税や納税資金、遺産分割のバランスを踏まえて、最適な対策方法をご提案させていただきます。生前贈与を用いた相続対策を検討されている方は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































