遺産分割協議書作成の費用は?誰に依頼すべきか・誰が払うかまで解説
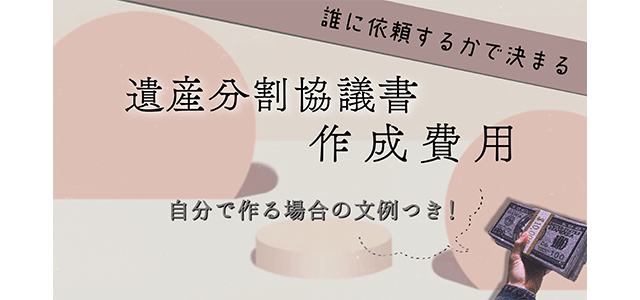
遺産相続が発生した際に、相続人が全員で遺産の分割割合を話し合った上で、その内容をまとめて作成する書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は相続人が自分で作ることも可能ですが、遺産の記載漏れやトラブルを防ぐために、士業者に作成を依頼することが一般的です。
遺産分割協議書を作成できる士業として、「弁護士、税理士、司法書士、行政書士」が挙げられますが、士業ごとに、遺産分割協議書の作成に関しておこなえる業務内容や、作成費用に違いがあります。今回の記事ではそれらについて解説します。
この記事の目次 [表示]
- 1 1.遺産分割協議書の作成ができる専門家ごとの費用相場
- 2 2.遺産分割協議書の作成費用は誰が払うのか
- 3 3.遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット・デメリット
- 4 4.遺産分割協議書は相続人が自分で作成もできる
- 5 5.まとめ:遺産分割協議書の作成には手間がかかる! 専門家に頼むなら費用の見積もりを
1.遺産分割協議書の作成ができる専門家ごとの費用相場
遺産分割協議書の作成が可能な士業は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士の4つです。この4つの士業は、それぞれ専門とする分野が異なっており、遺産分割協議書の作成を依頼する場合の費用相場も異なります。
一般的には、弁護士へ依頼する場合がもっとも高く、行政書士に依頼する場合がもっとも低くなります。
| 士業 | 依頼できる内容・特徴 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続人同士で遺産分割のトラブルがある場合などに、交渉や代理人として解決を依頼できる。またその内容を反映した遺産分割協議書の作成を依頼できる。 | 依頼者が受ける経済的利益による。 旧報酬規定に基づく場合が多い |
| 税理士 | 相続税の計算や税務署への申告を依頼できる。また、税務署への提出の必要がある遺産分割協議書の作成を依頼できる。 | 遺産総額の0.5%~1.0%(相続税申告)。 上記に遺産分割協議書作成も含まれる場合が多い。 |
| 司法書士 | 相続した不動産の名義変更(相続登記)手続きを依頼できる。あわせて、遺産分割協議書の作成を依頼できる。 | 相続登記だけなら、不動産1か所ごとに10万円前後。 遺産分割協議書作成も含めたパックで、15万円~25万円程度。 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成を依頼できる。 | 遺産分割協議書作成だけなら3~5万程度 必要書類収集なども含めて合計10万円程度。 |
なお、士業者への依頼した場合に支払う対価としては、「費用」のほかに、「報酬」という言葉もよく用いられます。両者は似ていますが、厳密にいえば、「費用」と「報酬」とは異なります。
「報酬」は、士業者に行ってもらった業務に対して支払う対価です。それに対して「費用」は、相談料や着手金、必要経費(出張日当、交通費、印紙代、切手代)等も含めて、依頼者が士業者に対して支払うお金全体を指します。
ただし、特に厳密に区別されずに用いられる場合もあります。
では、以下それぞれの士業についてくわしく見ていきましょう。
なお、以下で示す費用等の例は、特に断りがない限り消費税を含まないものです。
1-1.弁護士に依頼する場合の費用相場
2004年3月まで、弁護士の費用(報酬や着手金)は日本弁護士連合会が作成した報酬規定により一律に定められていました。同年4月以降は自由化され、弁護士ごとに自由に費用を決めることができるようになりましたが、現在でも、旧報酬規定を元に費用を設定している弁護士や法律事務所が多いようです。
したがってここでは、旧報酬規定を、弁護士費用の相場としてご紹介します。
▼日本弁護士連合会旧報酬規程による着手金、報酬の例(訴訟事件や家事審判事件などの場合)
| 経済的利益 | 着手金(最低10万円) | 報酬額 |
|---|---|---|
| 300万以下 | 8% | 経済的利益の16% |
| 300万超~3000万以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超~3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
弁護士費用は、依頼者が受ける「経済的利益」により変動することがわかります。
なお、「着手金」は、実際に依頼をする場合に最初に支払う費用であり、その前に「依頼するかどうかを決めるために相談する」場合にも、30分で5,000円程度の法律相談料が発生することが一般的です。
また、依頼後は、切手代や交通費、裁判を起こす場合は、裁判所に納める印紙代や予納金、出張が必要な場合は、日当といった実費が別途発生します。弁護士に支払う様々な費用については下記リンクをご参考ください。
(参考)日本弁護士連合会ホームページ 弁護士費用(報酬)とは
1-1-1.弁護士に依頼したほうがいい場合
遺産分割協議では、相続人間での意見の対立やトラブルが生じることはよくあります。小さなトラブルであれば、当事者同士の話し合いで解決できますが、紛糾して当事者同士での話し合いでは解決がつかない場合や、深刻化して法的措置に移行しそうな場合は、弁護士に代理人になってもらって、交渉したほうがよいでしょう。
弁護士は、まず相談や交渉により話をまとめようとします。それができなければ、調停、審判という流れで遺産分割協議を進め、できる限り訴訟(裁判)に持ち込まないようにして、なるべく費用が安くて迅速に解決できる手段を取ります。
一般的に、訴訟になると弁護士費用も跳ね上がるので、裁判にならないように折り合いをつけることが得策です。
1-1-2.遺産分割協議書作成を依頼する弁護士の探し方
弁護士や法律事務所によっては相続の相談は受けていない、あるいは得意ではないというケースもあります。ホームページなどで相続にくわしい旨をうたっている法律事務所を探すとよいでしょう。
また、各地域の弁護士会が設けている「弁護士紹介センター」などの紹介窓口や、国が全国に設けている「法テラス」を利用するのもよいでしょう。
(参考)東京弁護士会 弁護士紹介センター
(参考)法テラス
1-2.税理士に依頼する場合の費用相場
税理士に相続税の計算、相続税申告書の作成、申告業務を依頼した場合、税理士報酬は遺産総額の0.5~1.0%が相場です。そのプランの中に、遺産分割協議書の作成を含むのが一般的です。
たとえば、相続財産総額が7,000万円未満なら、税理士へ支払う費用は45万円程度になります。
(参考)相続税申告の税理士報酬・相場の実態と税理士選びのポイント|税理士法人チェスター
1-2-1.税理士に依頼したほうがいいケース
税理士の専門業務は、税金の計算や申告です。また、税理士は相続税申告がある場合の遺産分割協議書の作成もおこなうことができます。
一定額以上の相続財産がある場合、相続税の申告が必要となります。
税理士は相続税申告が必要な際に依頼をすることがおすすめです。相続税申告自体はご自身でおこなうこともできますが、不動産の評価が必要な場合や、遺産総額が大きい場合、様々な特例を活用したい場合、多額の生前贈与があった場合など、難しい申告になることも少なくありません。
また、遺産分割の内容が相続税額に影響を与える場合もあります。
そのため、相続税申告が必要な場合は、遺産分割協議書作成も含めて、税理士に依頼することが一般的です。
なお、相続税申告を税理士に依頼し、遺産分割協議書作成は、たとえば行政書士に依頼するなどと、別々に依頼するより、一括で依頼したほうが、一般的には総費用は低くなります。
1-2-2.遺産分割協議書作成を依頼する税理士の探し方
相続税の計算や申告は、税の分野の中では「資産課税」というジャンルになります。資産課税は専門性が高いため、税理士なら誰でもくわしいというわけではありません。
相続税申告や遺産分割協議書作成を依頼する税理士を探す場合は、ホームページなどで「相続専門」を掲げている税理士事務所に依頼することをおすすめします。
税理士法人チェスターでは、年間の相続税申告件数が2200件を超えており、高額の相続税申告や複雑な贈与があるケースなどにも対応しています。税務調査率も低く、安心してご依頼頂ける代表的な相続専門の税理士法人です。
1-3.司法書士に依頼する場合の費用相場
相続財産に不動産が含まれている場合に関係してくるのが司法書士です。司法書士は遺産分割協議書の作成もおこなうことができます。
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合の費用は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本など必要書類の取得代:不動産1箇所につき5,000円以内
- 不動産の調査費用:1件400円程度(把握できている場合は不要)
- 登録免許税:不動産の固定資産税額の0.4%
- 司法書士への登記報酬
日本司法書士連合会が平成30年に行った「報酬アンケート」によると、相続登記の司法書士報酬の全体平均値は6~8万円、低額者10%の平均が3万~5万円、高額者10%の平均が9万~12万円とされています。
(参考)報酬に関するアンケート(2018年1月実施)日本司法書士連合会
上記は報酬額なので、実費を含めた費用の相場は、10万円程度です。
なお、以上は、相続登記に限って依頼する場合です。上記に加えて、遺産分割協議書の作成も依頼する場合は、遺産分割協議書作成費用が必要になります。
司法書士によっては、「不動産登記パック」などの名称で、遺産分割協議書の作成と相続登記手続きをまとめて受けている場合もあります。
その場合、パック費用の目安は15万円~25万円程度です。
1-3-1.司法書士へ依頼したほうがいいケース
相続で不動産を取得した際に、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更します。この変更登記を「相続登記」と呼びます。相続登記申請は、現在は義務ではありませんが、2024年4月から義務化されます。
不動産の相続登記をおこなうのは相続をした本人ですが、司法書士、または弁護士が代理をできます。ただし、登記実務に精通している弁護士は少なく、また弁護士報酬は高額であるため、一般的には司法書士へ手続きを依頼します。
1-3-2. 遺産分割協議書作成を依頼する税理士の探し方
司法書士の探し方も弁護士と同様で、相続にくわしいことをホームページなどで示している事務所を探すのがよいでしょう。
お住まいの地域の司法書士会から紹介を受けることもおすすめです。相続において、不動産は相続財産に含まれていることが多く、相続登記は頻繁に行われています。ため、弁護士や税理士が司法書士と提携していることもよくあります。
司法書士法人チェスターでは、税理法人チェスターと連携してスムーズな相続登記と相続税申告を行っています。遺産に不動産が含まれる相続は、相続税申告も含めて、一元的に事務処理ができる司法書士を選びましょう。
(参考)司法書士法人チェスター
1-4.行政書士に依頼する場合の費用相場
行政書士とは、行政機関に提出する書類や、権利を表す書類の作成を代行できる業務です。
弁護士や司法書士と異なり、トラブルの交渉、代理や登記は扱えません。その分、相続人調査や遺産分割協議書の作成だけなら比較的安価で依頼できます。
費用相場は遺産分割協議書の作成だけなら3~5万円程度、相続人調査なども依頼する場合では、10万円程度(相続人の人数等に応じて)です。
1-4-1.行政書士へ依頼したほうがいいケース
行政書士は弁護士のように訴訟や交渉、司法書士のように登記を扱えるわけではありませんが、遺産分割協議書の作成や、相続人調査を安価で引き受けてくれます。金融機関等に口座解約の書類を依頼して解約の代行をおこなうほか、必要書類のアドバイスなども可能です。トラブルが予想されず、相続税申告や不動産登記もない場合には、行政書士への依頼が検討されます。
1-4-2. 遺産分割協議書作成を依頼する税理士の探し方
ホームページ検索などのほか、地域の行政書士会に連絡をすると、行政書士を紹介してもらえる制度があります。行政書士は費用が安価ですが、相続手続きをメイン業務としていない場合もあるので注意しましょう。
2.遺産分割協議書の作成費用は誰が払うのか
士業に遺産分割協議書の作成を依頼する場合、「誰が」費用を支払うのかは、士業によって異なります。
2-1.弁護士に依頼した場合
弁護士費用は、弁護士に依頼をした本人が支払います。もし、トラブルが紛争化していて、相続人がそれぞれ別の弁護士を代理人とした場合、それぞれの相続人が支払います。
2-2.税理士、司法書士、行政書士に依頼した場合
弁護士以外の士業に依頼するのは、遺産分割協議が紛争化していないケースのため、相続人間で話し合って支払います。相続人同士で分割して費用を払う場合もあれば、代表者がまとめて支払うこともあります。遺産分割の相続分に応じて必要費用も分割することもよくあります。
3.遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するメリット・デメリット
遺産分割協議書は相続本人が作成しても問題ないものです。専門家への依頼を検討する場合は、そのメリット、デメリットを比較した上で、依頼をしたほうがいいかどうかを決めましょう。
3-1.遺産分割協議書作成を専門家に依頼するメリット
遺産分割協議書の作成を士業に依頼をすることのメリットには、以下のようなものがあります。
3-1-1.ミスのない書類作成、手続きができる安心感がある
法律書類を書き慣れていない人が書類作成をすると、思わぬところでミスが生じて、後々、トラブルのタネになることがあります。士業者に任せれば、ミスのない書類作成や手続きができる安心感があります。
3-1-2.相続人の関係が悪いような場合もまとめやすくなる
ご家庭によっては、相続人同士の関係が悪く、顔も見たくないということもあります。あるいは遠方に住んでいて疎遠となっているケースもあります。そのような場合でも、専門家が間に入れば、スムーズに遺産分割協議がまとめやすくなります。
3-1-3.代償分割、換価分割などの難しい手続きも任せることができる
相続財産が現金だけであれば、遺産分割は容易です。
しかし、相続財産の中心が不動産で、現預金が少ない場合などは、相続人間で分割することが難しいことがあります。そういったケースで、不動産を相続する人がその代償として他の相続人に現金を支払う方法が「代償分割」です。また、不動産を売却して、現金化してから遺産分割をする方法が「換価分割」です。
これらの複雑な方法を利用したい場合は、専門家の力を借りたほうがよいでしょう。
3-1-4.相続人調査、相続財産調査も依頼できる
遺産分割協議書は相続人全員が参加する必要があります。しかし、そもそも「誰が相続人なのか」がわからない場合もあります。
たとえば、以下のような場合です。
- 被相続人(亡くなった人)に、複数の婚姻・離婚歴がある
- 複数の養子がいる
- 婚外子がいる
- 相続放棄をする相続人がいる(相続放棄をすると相続権が移動し、別の親族が相続人となるケースがあります)
- 代襲相続がある
また、被相続人の本籍地が何度も変更になっていた場合などは、戸籍を集めるだけでも大変です。さらに、被相続人が資産家だった場合、どこにどれだけの財産があるのかを調べるのも手間取ることがあります。
一方、遺産分割協議書は、基本的に相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに作成する必要があるので、調査にかけられる時間は限られています。
こうした場合には、専門家に相続人調査、戸籍収集、財産調査などを依頼することで、早急に資料が揃い、遺産分割協議を進めることが可能となります。
3-1-5.財産の分割や、不動産相続登記の手続きなども依頼できる
遺産分割協議書の作成を依頼すると、単純に書類を作るだけではなく、実際に財産を分割する手続き(現金の分配や口座の解約、場合によっては不動産会社の紹介など)も行ってくれます。また、司法書士なら不動産登記も依頼できるので安心です。
3-1-6.遺産分割内容や相続税対策のアドバイスをもらえる
遺産分割は必ずしも法定相続分のとおりに進める必要はありません。相続人間で納得すれば、相続分は柔軟に変えることができます。法定相続分通りにしないことで、相続税が節税できることもあります。相続にくわしい税理士に相談すれば、分割の内容や取得する相続財産内容に応じた相続税対策のアドバイスももらえます。
3-1-7.相続税申告が必要な場合は、申告書作成もあわせて頼める
相続税申告が必要な場合には、税理士に依頼をすると申告書作成もセットで行ってくれます。もちろん、相続税額の計算なども依頼できるので安心です。
3-2遺産分割協議書作成を専門家に依頼するデメリット
専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することには、デメリットもあります。
3-2-1.費用がかかる
記事内で既に触れているとおり、専門家に依頼をする以上は費用が発生します。
3-2-2.信頼できる専門家の探し方がわからない
相続に関しては、今回紹介している士業の他に、信託銀行や不動産会社なども窓口となり、様々な情報を発信しています。情報が多すぎて一体どの専門家が信頼できるのか混乱してしまう場合があります。
3-2-3.相続人の間の不信感が増す場合もある
遺産分割をめぐって、相続人間で意見の対立などがあった際に、「良かれ」と思って早くから弁護士などの専門家に相談をすると、他の相続人が「身内の話に弁護士を呼ぶなんて」と、態度を硬化させて、逆にトラブルが深刻化してしまう場合があります。
士業者に依頼するのであれば、その依頼をすること自体について、相続人間での合意を取ってからにしたほうがベターです。
4.遺産分割協議書は相続人が自分で作成もできる
遺産分割協議書は、専門家に依頼をしなくても自分でも作成できます。ご自身で作る場合のポイントは以下のとおりです。
4-1.遺産分割協議書作成前の準備
遺産分割協議書の作成には大前提として以下の2つの特定を行っておく必要があります。
- 相続人全員の特定
- 相続財産の特定
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるほか、相続人間で分割する相続財産がどんな内容で、いくらあるのか特定する必要があります。
相続財産は亡くなられたご家族(被相続人)が遺した現金や預貯金、不動産や有価証券、貴金属類はもちろんのこと、住宅ローンなどの債務も含まれることに注意しましょう。高額の債務がある場合には相続放棄も視野に入れる必要があります。
4-2.遺産分割協議書の書き方を図でチェック
遺産分割協議書の書き方は以下の記載例をご参考ください。


遺産分割協議書はインターネットでダウンロードできる無料の書式も、多数公開されています。作成時には相続人の遺した相続財産をミスなく記載する必要があるため、注意しましょう。
4-3.自分で遺産分割協議書作成する際のポイントと注意点
自分で遺産分割協議書を作成する場合には、以下のポイントに留意してください。
- 住民票や戸籍謄本を参照し被相続人の情報を入れる
- 法定相続人全員の名前を入れる
- 誰がどの財産を相続するか明確に記載する
- 後日判明した財産をどうするのか記載する
- 法定相続人の人数分作成し保管する旨を記載する
- 法定相続人全員の住所と氏名を直筆で記載する
- 法定相続人全員の実印を押印する
また、記載する財産については、財産の種類ごとに、下記の注意点を押さえておきましょう。
- 預貯金は、通帳に照らして、銀行名、支店名、預金種目、口座番号を記載する
- 不動産は、土地と建物に分けた上で登記簿謄本の記載事項とまったく同じように記載する
- 有価証券などは、証券などに照らしてその内容を記載する
- 自動車は、車検証に照らして、名義人、自動車登録番号、車台番号を記載する
- 債権、債務は、借用証などに照らしてその内容を記載する
4-4.遺産分割協議書作成の保管法や活用法
遺産分割協議書の作成を終えたら、正しく保管・活用しましょう。
4-4-1.遺産分割協議書の保管方法
遺産分割協議書は、「相続人全員分の原本」を作成し、各自が原本を保管することが一般的です。相続人全員分の原本を作成するというのは、「全員分の原本のコピー」を作ることとは違うので注意してください。
4-4-2.遺産分割協議書が求められる場面
一般に、遺産分割協議書は以下の場面で提出が求められます。
- 相続された不動産の相続登記(法務局)
- 相続税申告(税務署。小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減などの特例を適用する場合は必須)。
- 相続された査定額100万円超の自動車の名義変更(陸運局)
- 遺産分割協議後のトラブルによる再協議時
なお、金融機関における被相続人の口座の解約時に遺産分割協議書が求められることがあります(ホームページなどには必要と書いてあります)が、実際にはなくても対応してもらえます。
5.まとめ:遺産分割協議書の作成には手間がかかる! 専門家に頼むなら費用の見積もりを
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、手間や時間、ミスをするリスク等を考えると、通常は、専門家に依頼することがおすすめです。
専門家に依頼すれば作成費用がかかりますが、具体的にどれくらいの費用がかかるのかは、見積もりを依頼して正確に把握しましょう。
税理士法人チェスターでは、遺産分割協議書の作成だけではなく、相続税申告や不動産の相続登記についてもグループ一丸となって対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































