遺言執行者は単独で相続登記可能!【法改正あり】手続き方法も解説
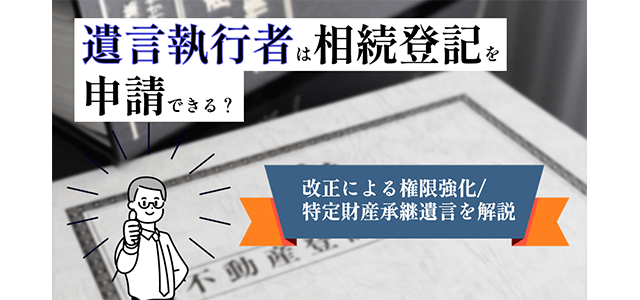
遺言執行者に関する基礎知識
遺言書を残したとしても、誰が遺言書の内容を実現してくれるのでしょうか。
ご自身の思いを託して遺言書を作成しても、死後に自らその内容を実現することはできません。その思いをきちんと実現させるために、実行してくれる人が必要になります。
ご自身に代わって遺言の内容を実現させるために、遺言執行者がいます。
ここでは、遺言執行者について詳しく解説します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や必要な手続きを行う者をいいます。
遺言書は、相続法に定められた方法に従っていれば、どのようなことを書くかは自由です。しかし、法律で定められた事項に限ってのみ効力が発生します。
そのため、遺言によって実現できることも限定されています。
遺言でできることは、身分に関すること、相続に関すること、財産の処分に関することなどに限られています。
具体的には、主に以下の通りです。
- 子供の認知
- 未成年後見人の指定等
- 相続人の廃除および廃除の取消し
- 相続分の指定等
- 特別受益の持戻の免除
- 遺産分割方法の指定等
- 5年以内の遺産分割の禁止
- 相続人の担保責任の指定
- 遺留分滅殺方法の指定
- 遺贈
- 寄付行為
- 信託の設定
- 遺言執行者の指定等
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金の受取人の指定や変更等
遺言執行者は相続開始後、遺言の内容の中に具体的な手続きがあれば、相続人などと協力して相続手続きを進めていきます。
遺言執行者が行う手続きは、子供の認知の届出、相続人の廃除または廃除の取消しの請求、預貯金の払い戻しや分配、株式や不動産の名義変更、寄付などがあります。
遺言者は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託できます。
遺言執行者がいないときや亡くなったときは、利害関係人は、家庭裁判所に請求して、遺言執行者を選任してもらうことができます。利害関係人とは、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者などをいいます。
遺言執行者を選ぶメリット
遺言執行者は、法律上、必ず選ばなければならないと定められてはいません。
しかし、遺言執行者がいない場合、遺言の内容を実現するために、物の引渡しや不動産の登記、預貯金の払戻しや解約などといった手続きや届出を、相続人がすることになります。
相続人同士の利害が対立し相続が速やかに進まないと予想される場合や、相続財産が多く手続きが複雑になる場合は、遺言執行者がいることで遺言の実現がスムーズに進みます。
また、相続人の誰かが勝手に相続財産を処分してしまう恐れがあるような場合、遺言執行者がいれば、相続財産を勝手に処分されることは許されません。このような場合、遺言執行者の存在が大きな意味を持ちます。
遺言で、子供の認知や相続人の廃除または廃除の取消しをする場合は、必ず遺言執行者を指定しなければなりません。これらは、相続において、相続人と利害が対立するため、遺言執行者を指定するよう定められています。
遺言執行者を選ぶ方法
遺言執行者は以下の方法で選ぶことができます。
- 遺言で指定するか、遺言で第三者に指定を委託する
- 利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する
遺言書において選ぶケース
遺言執行者は、遺言によって指定することができます。遺言によって第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。
また、遺言執行者の死亡または辞退に備えて、予備の遺言執行者を指定しておいたり、予備的に第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。
遺言執行者は、複数人の指定ができます。遺言執行者は自然人に限らず、法人でも構いません。遺言執行者が複数の場合には、その任務の執行は、過半数で決めます。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示していた場合は、その指示に従います。
遺言執行者の指定は、権利であって、義務ではありません。つまり、遺言執行者を指定せずに遺言書を作成することもできます。遺言執行者を指定していなかったからといって、遺言が無効になることはありません。
未成年者及び破産者は、遺言執行者となれませんので、これらの者を指定しても無効となるおそれがあります。未成年者または破産者に該当するかどうかは、遺言書の作成時ではなく、遺言者の死亡時で判断します。
つまり、遺言書の作成時に、遺言執行者と指定した者が未成年者であっても、遺言者の死亡時に成人していれば、遺言執行者の指定は有効となります。
遺言執行者は司法書士や弁護士などの専門家である必要はなく、友人、知人、相続人から選ぶことも全く問題はありません。
しかし、手続きが複雑な場合や、相続人同士が揉めている場合などは、司法書士や弁護士などといった専門家を遺言執行者に選任した方が望ましいといえます。
家庭裁判所において選ぶケース
遺言による遺言執行者の指定がない場合や、指定された者が辞退や死亡していた場合は、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に対して、遺言執行者の選任の申立てができます。
申立人は、遺言執行者として特定の候補者を希望できます。よくあるパターンは、相続人や司法書士、弁護士などです。
希望の候補者が必ず選ばれるとは限りませんが、家庭裁判所は、候補者の意思を確認し、遺言執行者として適任であるか否かを判断して、特段の事情がなければ、候補者が選任されることが一般的です。
希望の候補者の記載がない場合は、家庭裁判所が、適当な弁護士などを裁判所の職権で選任します。
遺言執行者を選ぶ際の注意点
遺言者が生前に遺言執行者を選ぶ際には、注意が必要です。
どのような人物を遺言執行者に指定するかによって、遺言の内容が速やかに執行されるかどうか、明暗が分かれます。
遺言執行者には、相続人や受遺者がなることは可能です。ただし、財産を多く受け取った相続人や受遺者は、それ以外の相続人との間に軋轢が生じやすいので、遺言執行者として適正かどうか疑問が残ります。
また、遺言により指定された人や家庭裁判所に選任された人は、遺言執行者になることを拒むことができます。手続きが煩雑な場合や時間的な余裕がない人は、選任されても拒むかもしれません。
また拒まなかったとしても、専門知識が乏しく遺言の内容を実現するだけの力量がない人だった場合、遺言執行者に指定したメリットがありません。
遺言書で選ぶ場合であっても、家庭裁判所に希望する場合であっても、遺言執行者になってもらいたい方には、前もって相談し承諾を取っておいた方が望ましいでしょう。
遺言執行者の権限強化と相続登記の可否について
2018年7月に相続法の改正があり、配偶者居住権の創設や遺産分割に関する見直しなど、相続に関するルールが大きく変更されました。この改正法は、既に全面的に施行されています。
中でも、遺言執行者の権限強化(明確化)は、相続法の重要な改正内容の1つです。そこで、遺言執行者の権限を改正前後で比較しながら説明するとともに、遺言執行者による相続登記の可否について解説します。
遺言執行者の権限を改正前後で比較
改正前の相続法では、遺言執行者が就任を承諾しても、相続人にその事実を通知することは義務づけられていませんでした。そのため、特に遺言執行者と遺言の内容に不満を持つ相続人との間でトラブルが発生することがありました。
また、遺言執行者は相続人の代理人とみなすと規定されていましたが、その権限については規定されていませんでした。
このように、遺言執行者の権限が明確ではなく、相続人との間でトラブルが生じることがあったため、2018年7月の相続法の改正で、遺言執行者の権限が明確化されました。
まず、改正前の遺言執行者の権限について解説します。
改正前の遺言執行者の権限
• 遺言執行者の立場や遺言執行者がした行為の効力が明確でなかった
改正前相続法は、遺言執行者を「相続人の代理人」と定めていました。
この点について、遺言執行者が選任される際に、相続人は遺言執行者に代理権を授与しません。また、遺言は遺言者が作成するので、本来は「遺言者の代理人」という性質を持つはずです。
しかし、法律上は「相続人の代理人」と規定されていましたので、遺言執行者が誰の意思に基づいて職務を行なえばよいかが明確ではなく、トラブルが生じることがありました。
• 遺贈の履行の権限が明確でなかった
遺贈とは、遺言によって特定の人に財産を与えること(贈与すること)をいいます。遺贈を受ける人は相続人に限られず、血縁関係のない人も含まれます。
改正前相続法は、遺贈を誰が履行すれば良いかが明確ではありませんでした。判例は、遺言執行者が遺贈に基づいて所有権の移転登記を行うべきとしていましたが、相続法には規定されていませんでした。
なお、後述する特定財産承継遺言がある場合(特定の財産をある相続人に承継させることを内容とした遺言)、改正前相続法では、遺言執行者に登記権限がなく、不動産を相続する相続人が単独で相続登記をすることになっていました。
• 復任権の要件が厳しかった
改正前は、やむを得ない事由がある場合に限って復任が可能でした。
遺言執行者は、遺言者が信任に基づいて遺言によって指定するか、家庭裁判所が選任するものなので、第三者に任務を任せることは望ましくないと理解されていました。そのために、やむを得ない事由がある場合に限ってのみ第三者に任務を行わせることができるとされていました。
次に、改正後の遺言執行者の権限について解説します。
改正後の遺言執行者の権限
遺言執行者の権限について相続法改正によって見直された主な点は以下の通りです。
- 遺言執行者の立場や、遺言執行者による行為の効力が直接相続人に生じることが明確化された
- 遺言執行者の義務、権限等が条文上明確化された
- 遺贈の履行ができることが明確になった
- 自由に復任できるようになった
- 遺言執行者の立場や、遺言執行者による行為の効力が直接相続人に生じることが明確化された
まず、遺言執行者を相続人の代理人とみなすとする規定は削除され、遺言執行者の行為は相続人に直接効力を生じる旨の規定が新設されました。
また、遺言執行者は、遺言の内容を実現する義務を負うことが明確にされました。
これらにより、遺言執行者は相続人の要望に応じることなく、あくまで遺言者の意思に従ってその職責を果たせばよいことが明確となりました。
なお、遺言執行者がその就任を承諾したときは、遅滞なく相続人にその旨を通知しなければならないことになりました。
通知をすることで、相続人は、「遺言があり、遺言執行者がいて、遺言の執行が始まった」ことを、相続のはじめの段階で知ることができるようになりました。
• 遺言執行者の義務、権限等が条文上明確化された
改正相続法は、遺言執行者の立場を強化するために、その権限や義務を条文で明確化しました。 たとえば、特定財産承継遺言がある場合に、その財産が不動産であれば、遺言執行者は遺言の内容に従って相続登記をする義務を負います。
また、その財産が銀行の預金であれば、遺言執行者は預金を解約して払い戻した上、遺言の内容に従って分配する義務を負います。
このように、遺言執行者には相続登記をする権限や預金の解約を申し入れる権限が条文上付与されています。
また、遺言執行者がいる場合は、相続人は、勝手に相続財産を処分したりなどの、遺言執行者の執行の妨げとなる行為ができません。この規定に違反して行った行為は無効になります。
このことも改正相続法に明確に定められました。ただし、善意の第三者には対抗できません。
このように、遺言執行者は、遺言の内容を滞りなく実現するために、その権限と義務が明確になりました。
• 遺贈の履行ができることが明確にされた
改正相続法では、遺言執行者がある場合には、「遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」と明文化されました。
これにより、受遺者(遺贈を受けた人)にとっては、遺贈の実現を求める相手が明確になりました。遺言執行者がいれば遺言執行者に、遺言執行者がいなければ相続人に履行を求めます。
また、遺贈が不動産で遺言執行者がいる場合は、遺贈による所有権移転登記は、受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として共同申請により行います。
• 自由に復任できるようになった
遺言執行者は、遺言者が遺言で禁止していない限り、自己の責任で第三者に任務を任せることができるようになりました。
相続法改正後は「やむを得ない事由」がなくても、遺言執行者の責任や裁量で復任できます。復任をするにあたり、相続人や受遺者の同意は一切不要です。
遺言執行者は相続登記を申請できる?
前に述べましたが、相続法改正前は、特定の不動産を特定の相続人に相続させるという内容の遺言(特定財産承継遺言)の場合、その不動産の相続登記は、その特定の相続人が、単独で相続登記ができました。
そのため、遺言執行者は、相続登記の手続きをする権利はなく、義務も負わないとされていました。
一方、相続法改正後は、特定の不動産を特定の相続人に相続させるという内容の遺言がある場合、遺言執行者が相続人に代わって相続登記の申請を単独ですることが可能となり、特定の条件にある相続財産については、遺言執行者による相続登記の申請ができるようになりました。
どのような場合でも相続登記の申請ができるわけではなく、特定の条件を満たした場合にだけできるようになりました。
特定の条件とは、遺言書に、特定の相続不動産を特定の相続人に相続させると記載し、遺言執行者を指定している場合です。このような遺言を「特定財産承継遺言」といいます。
このような遺言がある場合、遺言執行者は、その相続人に代わって、相続登記の申請を単独ですることができます。
なお、特定の不動産を相続した相続人も、相続法改正後も引き続き、単独で相続登記を申請することができます。
特定財産承継遺言とは
特定財産承継遺言とは、遺産の分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言のことをいいます。
具体的には、「自宅の土地と建物は長男◯◯に相続させる」などを記載した遺言のことを言います。
なお、特定財産承継遺言は相続人のみを対象とするもので、相続人以外の第三者を対象とするものは遺贈となります。
遺言執行者は預貯金の払戻/解約も行える?
前に述べましたように、改正相続法は、銀行の預金を対象とする特定財産承継遺言がある場合、遺言執行者がその預金の解約や払戻しをする権利があることを明確にしました。
遺言執行者は、特定財産承継遺言の内容が預金の場合には、預金の解約および払戻しの申入れをすることができます。
なお、「〇〇銀行の預金債権のうち、500万円をAに相続させる」といったように、預金の一部のみを対象とする遺言の場合は、特定財産承継遺言としての法律で求められている要件を満たさないため、遺言執行者は預金の解約の申入れをする権限を有さないとされています。
遺言執行者の相続人に対する通知義務
改正相続法では、遺言執行者の相続人に対する通知が義務化されました。遺言の執行を開始したときは、遅滞なく、相続人に通知しなければなりません。
遺言執行者が、遺言の内容を伝えずに遺言の執行を進めると、特に相続によって財産を取得しない相続人との間で、トラブルが生じてしまうおそれがあります。そのため、遺言執行者は相続人に対して、必ず遺言の内容を伝えなければいけません。
遺言執行者への妨害行為の対応を比較
遺言執行者が遺言の執行をしようとすると、妨害行為をする人が出てくる場合があります。妨害しようとする人は、相続分に不満がある相続人や、他人への遺贈に不満を持った相続人などです。
たとえば以下の事例があったとしましょう。
父親(母親は既に他界)が亡くなりました。相続人は息子1人です。父親は公正証書遺言を作成していました。相続財産は自宅と郊外にある土地です。
公正証書遺言には、「自宅は長男に相続させる。土地はAさんに遺贈する」との記載があり、遺言執行者に父親の知り合いの司法書士が指定されていました。
父親は晩年一人暮らしで、身の回りの世話をしてくれていた方へのお礼として、郊外に持っていた土地を遺贈しました。
父親が亡くなって、息子は遺言書を確認して驚きました。
相続財産は全て自分が相続すると思っていたのに、郊外にある土地がAさんに遺贈されていました。息子は事業を営んでいましたが、経営が苦しく、相続が開始したら、父親の土地を売却して、事業を立て直そうと考えていました。
買い手も既に見つけています。
困った息子は、遺言執行者に無断で、自宅と郊外にある土地の相続登記を済ませ、土地を売却し、買い手への所有権移転の登記まで済ませました。
このように、遺言執行者に無断で相続登記をし、不動産売却をするなどの妨害行為が行われた場合、改正前後でどのような対応の違いがあるのでしょうか。
改正前の対応
改正前は、「遺言執行者がある場合」には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないと定められてはいましたが、相続人が執行を妨げた場合、その妨害行為の効果は明文化されていませんでした。
「遺言執行者がある場合」に、相続人が遺言の執行を妨げる行為をした事例について、裁判所は、「相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である」との判決を出していました。
この「無効」という効果は、第三者への対抗要件(所有権移転登記をしていた、等)を備えていなくても、誰に対しても主張できる、絶対的無効だと一般に解釈されていました。
しかし一方で、「遺言執行者がない場合」にも、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為については、無効とはならず、先に対抗要件(所有権移転登記をしていた、等)を備えた者が遺贈の対象となった目的物を取得するとされた判例も存在していました。
つまり前述した事例では、「遺言執行者がある場合」は、息子による郊外の土地についての処分行為は絶対的に無効であり、Aさんは所有権移転登記をしていなくても息子による処分行為の無効を主張することができ、郊外の土地を取り戻すことができます。
この場合、遺言執行者は、土地を取り戻し登記も元に戻した上で、遺贈を受けたAさんへ土地の所有権移転登記をします。
反対に、遺言執行者がない場合は、郊外の土地を息子から購入した第三者が先に所有権移転登記を具備してしまっていますので、Aさんは遺贈によって取得した土地の権利を第三者に主張できないという解釈でした。
第三者にとっては、遺言執行者がいなければ、対抗要件を備えることによって確定的に権利を取得することができます。
他方、遺言執行者がいれば、たとえ遺贈の目的とされていることを知らず、きちんとお金を払って購入して対抗要件を備えても、いつまでも売買契約の無効を主張されるリスクが残り、非常に不安定な立場となっていました。
改正後の対応
改正相続法では、遺言執行者の遺言の執行を妨げてした行為の効果について、無効であることが明文化されました。
ただし、同時に、善意の第三者(事情を知らない第三者)に対抗することができないということも規定されました。
遺言執行者の遺言の執行を妨げてした遺贈の目的物についての処分行為は、原則無効となりますが、事情を知らない第三者に対しては処分行為の無効を主張できません。つまり、遺言執行者があっても、遺贈を受けた者が先に対抗要件を備えなければ、第三者によって遺贈の目的物を取得されてしまう可能性があります。
遺言執行者としては、遺贈がなされた相続財産があれば、速やかにその対抗要件を具備させる責任がある、という趣旨に法改正がおこなわれたと言えます。
前述の事例では、第三者が妨害行為であることを知らなければ、第三者が先に対抗要件を備えている以上、土地を取り戻すことができませんし、登記を元に戻すことはできません。
なお、第三者が事情を知らなかったことについて過失が無いことまで要求されていません。
つまり、第三者がもう少し注意を払っていれば、遺言の内容などに気付くことができたとしても、第三者が先に対抗要件を具備していれば、不動産を確定的に取得することになります。
このように、相続法が改正されて、遺言執行者に素早い対応を求められるようになりました。
もしご自身が遺言執行者に指定されていれば、早い段階で、司法書士事務所などの専門家に相談されることをお勧めします。
遺言執行者の権限強化に関する注意点
遺言執行者の権限強化に関する法律改正は、2019年7月1日に施行されました。
遺言書の作成の日や相続が開始した日、遺言執行者が就任した日によって、対応は変わってくるのでしょうか。また、相続人と遺言執行者との関係について、注意すべきことはどういったことなのでしょうか。
ここでは、遺言執行者の権限強化に関して注意すべき点について解説します。
①施行日と遺言執行者の就任日/遺言作成日の関係
今回の改正法の原則は、相続の開始が2019年7月1日より前であれば旧法、2019年7月1日以降であれば改正法で対応することになります。しかし、例外があるので注意しなければなりません。
例外①:遺言執行者の権利義務と通知義務
相続の開始が2019年7月1日より前であっても、遺言執行者に就任した日が2019年7月1日以降の場合、改正法が適用されることになります。遺言執行者は、相続人へ通知をする義務が発生し、遺贈の履行は遺言執行者のみ行うことができます。
例外②:特定財産承継遺言に基づく登記申請など
遺言執行者が特定財産承継遺言に基づいて登記申請などをする権限があるのは、遺言書の作成が2019年7月1日以降の場合のみとなっています。つまり、相続の開始が2019年7月1日以降であっても、遺言書の作成が2019年7月1日より前であれば、遺言執行者は登記申請をする権限がありません。
特定財産承継遺言の対象となった預金の払戻しや解約などをする権限についても同様です。
例外③:遺言執行者の復任権について
改正法では、遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができるようになりました。しかし、相続の開始や遺言執行者の就任日が2019年7月1日以降であっても、2019年7月1日より前に作成された遺言書には適用されません。 したがって、2019年7月1日より前に作成された遺言書により指定された遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合に限り、第三者にその任務を行わせることができます。
このような場合は、非常に専門的になりますので、遺言執行者の問題に強い、司法書士事務所などの専門家に相談されることをお勧めいたします。
②遺言執行者の権限強化に対する相続人の姿勢
相続法改正前は、不動産を相続人の一人に相続させる旨の遺言を遺していた場合、遺言執行者は相続登記の手続きをすることはできず、取得した相続人自身が手続きをする必要がありました。
また、金融機関によっては、遺言執行者による解約や払い戻しの請求に応じないこともあり、金融機関でトラブルになるケースがよくありました。
また、遺言書の内容に不満を持っている相続人との間でトラブルとなり、遺言内容の実現が困難となるようなケースも少なくありませんでした。
改正相続法では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定され、遺言執行者があくまで遺言者の意思(遺言)に基づいて行動すれば良いことが明確になりました。
さらに、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と明文化されました。
これらの改正により、相続人との間の軋轢やトラブルを防ぐことができるようになり、遺言の円滑な実現ができるようになりました。
遺言執行者の権限強化(明確化)によって、相続人の権利が以前より悪くなるわけではありません。反対に、煩雑な手続きなどを遺言執行者が相続人に代わって対応してくれるようになったと言えます。
遺言執行者と相続人が協力していくことで、遺言の内容をより確実に、よりスムーズに実現していけるでしょう。
遺言による相続登記の申請方法
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言の3種類があります。
一般的に遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言と公正証書遺言がよく利用されます。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは、簡単に言うと、自筆証書遺言は自分で書けて費用がかからず証人が不要だという点、公正証書遺言は公証人という法律のプロが関わって作成しているので遺言書を相続法の要件に従って確実に作成できるという点です。
遺言書による相続登記の申請方法は、遺言書が特定財産承継遺言であれば、その遺言書を添付して相続登記を申請します。
有効な遺言書であれば、相続人による遺産分割協議は不要であり、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本などをたくさん取得する必要もありません。
遺言書による相続登記では、遺産分割協議による場合などと比べて、必要書類が少なく済みますが、自筆証書遺言、秘密証書遺言などは、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があるなど、公正証書遺言に比べて手続きが追加で必要となることがあります。
ただし、自筆証書遺言であっても、法務局の保管制度を利用されている場合は検認手続きが不要となります。
なお、遺言者が亡くなった後は、相続人等の利害関係者から、公証役場で公正証書遺言が保管されているかどうかを確認することができますので、遺言書が見当たらない場合は必ず確認するようにしましょう。
また、被相続人が法務局の保管制度を利用していた場合は、相続人などが遺言書を閲覧した際に他の相続人に通知される仕組みとなっています。更に、被相続人が予め指定した相続人1名に対して通知される制度も、近時、新たに導入される予定となっています。
遺言の種類によって手続きや提出書類が異なる
遺言が公正証書遺言か自筆証書遺言かによって、必要な手続や提出書類が異なります。
遺言書が自筆証書遺言なら、「検認」という手続きを行う必要があります。
検認は、家庭裁判所に遺言書や戸籍謄本などとともに検認申立書を提出することにより開始されます。申立書が受理されれば、家庭裁判所から相続人全員に対して呼出状が届きます。裁判所に行くと、一つの部屋に相続人全員が集まり、裁判官の前で遺言書を開封してその内容を確認する流れとなります。
なお、遺言書は必ず開封せずに提出するようにしてください。仮に開封してしまった場合でも、無理に封をしたりせずにそのままの状態で提出してください。
検認が終われば、遺言の内容に従って相続手続きを進めていきます。遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に従って手続きを進めていきます。
一方、遺言書が公正証書遺言なら、家庭裁判所の検認を行う必要はありません。
つまり、相続開始後にできるだけすみやかに遺言執行手続を開始したい場合は、検認が不要な公正証書遺言、もしくは遺言保管制度を利用した自筆証書遺言で遺言を作成しておくのが望ましいでしょう。
そして、相続登記(遺言に不動産を特定の相続人に相続させる旨が記載されている場合)を申請する際の提出書類として、遺言書が自筆証書遺言の場合は、当該遺言書に加えて、裁判所が発行する検認済証明書を提出する必要があります。
相続登記を申請する際に他に必要な書類は、
相続登記の必要書類と取得の仕方、期限を一覧でわかりやすく紹介で詳しく解説しておりますので、こちらをご参照ください。
まとめ
遺言執行者は未成年者や破産者でなければ就任することができます。
しかし、遺言執行者の権限や義務が明確化されたことで、責任の所在も明確となりました。自ら遺言執行者を引き受ける場合は、大きな決断と覚悟が必要になります。
遺言の執行という複雑な手続きを任せるなら、やはり司法書士などの専門家にその任務を依頼することが望ましいです。
さまざまな場面で、専門的な知識や法的な判断を駆使して、確実に遺言の内容を実現させることが可能となります。 また、遺言を作成する際も、司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
遺言執行者は中立的な立場で任務を行うことが重要です。生前に遺言書で遺言執行者を指定する場合には、相続人などではなく、利害関係のない専門家を選ぶことも検討されるべきです。
遺言書の作成や、遺言執行者による相続登記申請について不明な点があれば、相続手続き専門の司法書士法人チェスターにご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































