実家の農地相続にはルールがある?相続登記の流れ、土地活用方法など
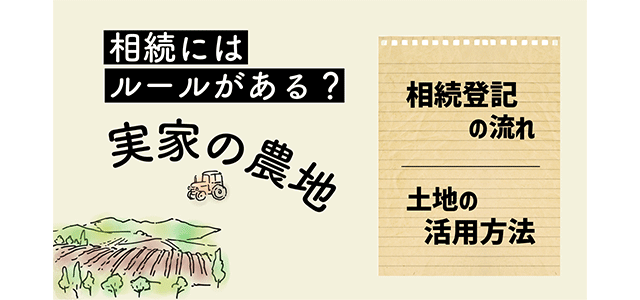
実家の農地を相続した場合、相続登記のほかに農業委員会への届け出も必要です。農地ならではの手続きがある点に注意しましょう。相続をスムーズに進められるよう、農地の分割の仕方や、農地転用の方法、相続税の猶予や免除についても紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.農地を含む財産を相続することになった場合

親が亡くなり相続の手続きをするとき、財産の中に農地が含まれているケースもあるでしょう。農地を相続する際にも、その他の財産の相続と同様に遺産分割協議が必要です。仮に農地が不要の場合でも、農地以外の財産のみの相続はできません。
1-1.遺言や遺産分割協議で相続方法を決める
農地を相続したら、通常の財産を分割する場合と同様に、『遺言』や『遺産分割協議』で相続方法を決定します。被相続人が遺言書を残しているなら、その内容にもとづいて分割しましょう。
遺言書を残していない場合や、遺言書とは異なる分割方法を採用したいケースでは、相続人全員で遺産分割協議を実施します。遺産分割協議で話し合っても合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる流れです。
裁判官や調停委員が間に入った話し合いでも合意できなければ、審判へ移行し裁判官の決定に従うことになります。
1-2.農地のみの相続放棄はできない
引き継いでも農業をするわけではないから、農地を『相続放棄』したいという人もいるかもしれません。相続放棄は被相続人に対する相続権を放棄することです。
最初から相続人ではないものと扱われるため、農地以外の財産も相続できなくなってしまいます。農地は不要だけれど、ほかの財産は引き継ぎたいと考えているなら、農地も同時に引き継がなければいけません。
農地として使用しない場合は、周りに迷惑をかけないよう最低限の管理をしながら保有し続けます。雑草の刈り取りや害虫などに注意しながら管理しましょう。
2.農地を上手に分ける方法の例

相続人が複数いる場合、農地をどのように分割すればよいのでしょうか?同じ程度の広さの土地があればうまく分割できるかもしれませんが、そうでないケースもあるはずです。
農地を農地のままで分割するのが難しいなら、『代償分割』や『換価分割』が向いています。
2-1.相続人の1人が農地を継ぎ、代償分割する
『農業を継ぎたい』『農地を活用したい』と考えているなら、代償分割を実施しましょう。
農地の引き継ぎを希望する相続人が農地を相続し、ほかの相続人は農地を引き継いだ相続人から、農地を分割したときの価値に相当する現金を受け取る方法です。
引き継いだ農地で自ら農業を行ってもよいですし、農業に取り組みたいと考えている人に管理を任せてもよいでしょう。
農業以外の用途にも使えるなら、農地以外の土地にする『農地転用』を行い、賃貸住宅や駐車場などとして土地を活用する方法もあります。
2-2.農地や宅地などとして売却する
農地を売却して得た利益を分割する『換価分割』という方法もあります。土地のまま等分するのは難しいですが、現金であれば簡単に計算して分割が可能です。
土地の評価額についてのトラブルや、特定の相続人が現金を用意しなければいけない負担を避けられるのもポイントといえます。
農地のまま売却すれば、地目変更にかかる手続きの手間がありません。農地だから受けられる控除や、税制面の優遇もあります。ただし農業を営む人や法人にしか売却できないため、一般的な宅地の売却より時間がかかります。
農地転用して売却する方法も有効です。場所によってはマンション用地として売却でき、高値が付くかもしれません。
3.農地転用するには

農地をほかの目的で使用するには、農地転用の手続きが必要です。必要な手続きは、農地の立地によって異なる点に注意しましょう。
3-1.調整区域にある農地の場合は許可が必要
相続した農地が、過度の市街化を抑えるために設けられている『市街化調整区域』にあるなら、転用には都道府県知事の『許可』が必要です。加えて農地の分類によっては転用できません。まずは農地の種類を確認します。
- 農用地区域:農業に利用すべき土地のため転用禁止
- 第1種農地:農業に条件のよい土地のため原則転用不可
- 第2種農地:ほかの土地への代替ができない場合に転用可能
- 第3種農地:市街地に近い場所にある土地で原則転用可能
第2種や第3種であれば、転用できる可能性が高いでしょう。許可を得るにあたり、建築主が農地の所有者なら『農地法第4条』の対象、農地の所有者と別の人であれば『第5条』の対象です。
3-2.市街化区域にある農地は届け出のみ
農地法第4条もしくは第5条の許可が必要なのは、市街化調整区域にある農地の場合に限られます。相続した農地が市街化区域にあるなら許可を得る必要はなく、『届け出』のみで構いません。
農地を管轄している農業委員会に事前の届け出をするだけで、農地からほかの目的へ転用できます。相続した農地を宅地に変更し住宅を建てる、賃貸物件を建て家賃収入を得るなど、農地転用で土地を活用しやすいでしょう。
4.農地を相続登記するには
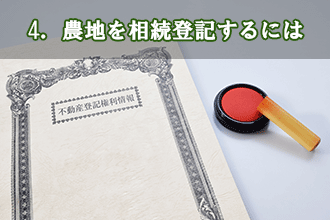
被相続人から農地を引き継いだなら『相続登記』が必要です。相続登記を実施するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?必要な書類や費用も確認します。
4-1.管轄の法務局で手続きを行う
取引の安全性を確保するため、不動産は所有者を登記するよう定められています。相続が発生し所有者が変わったときに行うのが相続登記です。
相続した農地の登記簿上の所有者を、被相続人から相続人へ名義変更します。相続登記ができるのは、不動産所在地を管轄する法務局です。
相続人の住所地と農地のある地域が離れている場合でも、農地のある地域の法務局で手続きしなければいけません。法務局は全国にありますが、相続登記の手続きをできる法務局は限定されています。
4-2.戸籍謄本や遺産分割協議書などを用意
相続登記の実施には下記の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票もしくは除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明
- 遺産分割協議書(作成した場合)
- 相続人の住民票
- 遺言書(ある場合)
- 委任状(代理人を立てる場合)
登記申請書とともに提出する書類は、『原本』が原則です。ただしそのほかの手続きで原本が必要なら、返還を請求できます。
返還を希望する場合には、『原本に相違ありません』と記載し押印した書類のコピーを用意しましょう。コピーを原本とともに提出すれば、原本を返してもらえます。
4-3.登録免許税を支払う
登記をするときには『登録免許税』の支払いが欠かせません。税金の対象となる課税標準は『固定資産税課税台帳』の価格です。固定資産課税明細書の『価格』もしくは『評価額』の部分に記載されています。
課税標準に『0.4%』をかけると、登録免許税の計算が可能です。100円未満の端数があるときには切り捨てた金額を、1,000円未満のときは1,000円を納めます。
相続登記を行う際の登録免許税には、免税措置もあります。ただし適用されるのはどれもイレギュラーなケースのみです。そのため免税されるのはごく一部に限られます。
4-4.専門家に依頼した場合は報酬も発生
手続きを『司法書士』や『土地家屋調査士』といった専門家に依頼すると、専門家への報酬も必要です。報酬の金額は依頼先によって異なります。3万円台〜6万円台など幅があります。
ただし手続きが複雑な場合は追加料金がかかるため、報酬はより高額です。例えば、これまで何世代も相続登記が行われていない農地の登記が該当します。相続人が多く、資料の取り寄せだけでも大きな手間が発生するからです。
また相続する不動産が多い・不動産ごとに相続人が異なる・相続登記を申請する法務局が多いといったケースも、報酬が高くなりやすいでしょう。
相続登記は自力でもできますが、確実に実施するには専門家への依頼が向いています。
5.相続登記をしたら農業委員会に届け出る
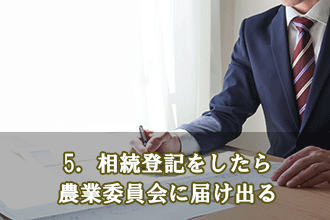
農地の相続手続きは、登記だけでは完了しません。相続登記が終わったら、農業委員会への届け出が必要です。届け出には期限もあるため注意しましょう。
5-1.10カ月の期限内に手続きを行う
農業委員会へ届け出をする期限は、農地の権利を取得したと知ってから『10カ月』以内です。相続時にはさまざまな手続きがあるため、10カ月はあっという間に過ぎてしまいます。忘れずに手続きしましょう。
届け出をせずにいると、10万円以下の過料が科されるケースもあります。多忙でなかなか手続きできない場合には、『行政書士』に依頼するとよいでしょう。
5-2.届出書と登記事項証明書が必要
届け出に必要な書類は『届出書』と『登記事項証明書』です。届出書には下記を記載しましょう。
- 取得した人の氏名・住所
- 土地の所在地
- 権利を取得した日
- 権利を取得した事由
- 取得した権利の種類及び内容
- 農業委員会によるあっせん等の希望の有無
遺言や遺産分割協議にもとづき分割済みで、相続登記も実施しているのであれば、農地を取得した人が届け出ます。遺産分割協議で合意できておらず、農地を引き継ぐ相続人が未定なら、相続人全員の名義で手続きしましょう。
協議で合意した後、農地を相続すると決まった人が届け出ます。
6.農地の評価額と相続税
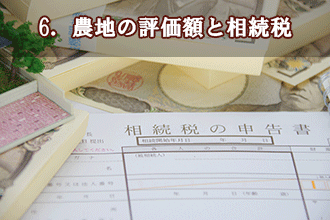
相続が発生すると、相続税が発生するケースもあるでしょう。農地の相続税額はどのように計算するのでしょうか?
6-1.4種類の区分で評価方法が異なる
農地の相続税は、4種類の区分ごとに算定方法が異なる複雑なものです。まずは相続税を算定する農地が、下記の4種類のうちどれに該当するか、国税庁の『財産評価基準書』のサイトで確認しましょう。
サイト上部から相続を開始した年を選び、該当する農地の場所を選択すれば、区分が分かります。それぞれの税額は以下の方法で算定可能です。
| 農地の種類 | 相続税の算定方法 |
|---|---|
| 純農地 | 倍率方式:農地の固定資産税評価額×評価倍率 |
| 中間農地 | |
| 市街地農地(右のいずれかで計算) | ①宅地比準方式:(農地を宅地とした場合の1平方mあたりの価額-1平方mあたりの造成費)×地積 ②倍率方式:農地の宅地としての固定資産税評価額×宅地の評価倍率 |
| 市街地周辺農地 | 市街地農地であるとした場合の価額の80%相当 |
中でも市街地農地の計算では、固定資産税評価額や評価倍率に宅地のものを用いる点に要注意です。想定外の大きな負担が発生するかもしれません。
参考:財産評価基準書|国税庁
6-2.納税猶予と免除
農地の相続税は『納税猶予』を受けられる可能性があります。被相続人から引き継いだ農地で相続人が農業を営む場合に限り、要件を満たすと相続税の猶予を受けられる仕組みです。
被相続人が農業もしくは特定貸付けを行っており、以下のいずれかに該当する農地であれば、猶予を受けられるでしょう。
- 相続で取得し遺産分割が完了している農地
- 贈与税納税猶予の対象であった農地
- 相続の年に被相続人から一括贈与を受けた農地
猶予された相続税は、相続人の死亡・相続人から後継者への一括贈与・指定の区域内にある農地で農業を20年継続といった場合に免除されます。これ以外のケースで農業をやめると、利子税+相続税を支払わなければいけません。
『納税猶予』について詳しくは下記もご覧ください。
農地の相続税は納税猶予の特例を利用すればゼロになる?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
7.農地の種類、区分を確認しよう

農地を相続するときには、種類や区分ごとに扱いが異なる点に要注意です。同じ農地でも立地によっては転用できず、相続税の税額も変わります。
特に相続税の算定は複雑です。区分ごとに適用される算定方法が異なるため、専門家に計算を任せた方が安心でしょう。実績豊富な『税理士法人チェスター』であれば、相続税の算定も依頼できます。
加えて、相続税も農業委員会への届け出も、相続を知ってから10カ月以内に手続きしなければいけません。専門家の力を借りれば、スムーズに手続きできるでしょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































