相続放棄申述書の書き方。押印に使える印鑑、放棄の理由の選び方など
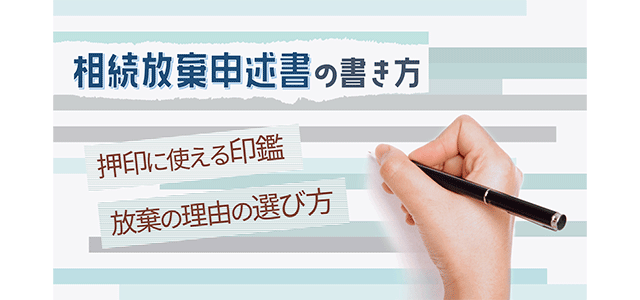
相続放棄申述書は相続放棄に必須の書類です。一度の手続きで正確に書類を作成し提出しなければいけません。自力での作成が難しそうと感じるなら、専門家に任せる方法もあります。そのためにも正しい書き方を確認し、早めに書類の準備をしましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続放棄申述書はどんな書類か
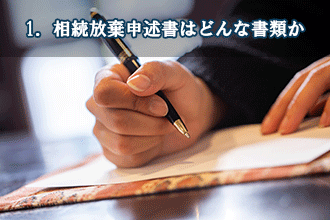
被相続人の死亡を知っても、その財産を引き継がず『相続放棄』するケースもあります。そのために必須なのが、家庭裁判所への『相続放棄申述書』の提出です。自力での作成が難しそうと感じるようであれば、専門家に依頼してもよいでしょう。
1-1.相続放棄のために家庭裁判所に提出する
相続放棄は、被相続人の死亡時にさかのぼり、相続権を消滅させる手続きです。被相続人の持つ全ての財産や負債を引き継ぎません。
この手続きを行うには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄を認めてもらう必要があります。正しく申述書を作成し、家庭裁判所へ提出しましょう。
その後『照会書』が届くため、回答欄に記入して返送します。相続放棄が受理されると、家庭裁判所から『相続放棄申述受理通知書』が送られ、正式に相続放棄が認められる流れです。
申述書は相続放棄の手続きに欠かせない書類のため、必ず正確に作成しましょう。
1-2.書類作成は専門家に依頼すべき?
申述書の作成は自分でもできます。ただし、期限内に問題なく正しい申述書を作成するのは難しいかもしれません。加えて戸籍謄本といった書類も用意する必要があります。
手間と時間がかかるため、弁護士や司法書士に依頼してもよいでしょう。報酬は2万8,000円以上となっており、必要な手続きや書類が増えるほど高額になるケースや、パッケージ料金が設定されているケースもあります。
報酬のほかに郵送料や印紙代などの実費も必要です。専門家に依頼すると費用はかかりますが、書類の不手際により受理されないという事態を避けられます。
2.相続放棄申述書1枚目の作成方法
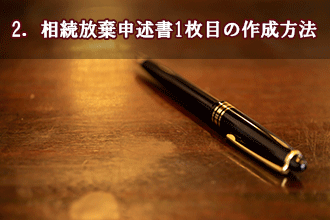
相続放棄申述書は2枚にわたる書類です。1枚目には申述人や被相続人の情報を記載するほか、収入印紙の貼付も必要です。それぞれどのように記載していくのか確認します。
2-1.800円分の収入印紙を貼る
1枚目の右上には収入印紙の貼付欄があります。ここには『800円分』の収入印紙を貼りましょう。200円印紙を4枚でも、400円印紙を2枚でも、その他の組み合わせでも構いません。
申述書の一番上の欄にありますが、収入印紙は最後に貼るのがおすすめです。万が一書き間違いが発生すると、一度貼り付けた収入印紙を貼り直さなければならず手間になってしまいます。
また、通常行う貼り付けた後の収入印紙への割り印は不要です。
2-2.裁判所名や日付を記入、記名押印をする
収入印紙の貼付欄の下には、『裁判所名』『日付』『申述人の記名押印』の欄があります。裁判所名に記載するのは、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所です。
『相続人の最寄りの家庭裁判所』ではない点に注意しましょう。申述書に『家庭裁判所』と記載されているため、東京・横浜・大阪など裁判所名のみ書きます。
日付は相続放棄の申述をする日にちを書き入れましょう。申述人の記名押印欄には、相続放棄をする本人の氏名を書き、印鑑を押します。印鑑は認印で問題ありません。
2-3.「申述人」欄に相続放棄する人の情報を記入
申述人欄には下記の通り複数の項目があります。裁判所から連絡が来る住所や電話番号でもあるため、正確に読みやすく記入しましょう。
- 本籍:住所地と同じ場合もありますが住所地ではない
- 住所:生活の拠点となっている住所
- 電話番号:平日の日中に連絡のつきやすい番号
- 氏名:申述人の氏名
- 生年月日:申述人の生年月日
- 職業:一般的な職業を記入(会社員・自営業・主婦など)
- 被相続人との関係:子・孫・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹・おいめい・その他から、当てはまるものに丸をつける、その他の場合はかっこ内に具体的な関係も記入
本籍は戸籍謄本の通りに、住所は住民票の通りに書き写せば間違いがありません。
2-4.「被相続人」欄に亡くなった人の情報を記入
被相続人欄は亡くなった人について記載する箇所です。下記の項目があるため、記入漏れのないよう全て書き入れます。
- 本籍:戸籍謄本に記載の本籍地通りに記載
- 最後の住所:被相続人が亡くなったときの住民票上の住所
- 死亡当時の職業:一般的な職業を記入(会社員・自営業・無職など)
- 氏名:被相続人の氏名
- 死亡日:相続が開始した日に関係するため、戸籍を確認し正確に記入
3.相続放棄申述書2枚目の作成方法
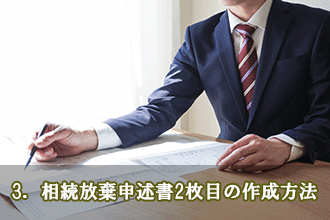
2枚目には『相続の開始を知った日』や『放棄の理由』『相続財産の概略』を記載する欄が設けられています。ケースによって記載する内容が異なる部分のため、記入例を参考にしつつ、自身の状況に合わせて書き入れましょう。
3-1.「相続の開始を知った日」を記入
相続の開始を知った日にちを記入したら、下記の選択肢からその日がどれに該当するか選びましょう。
- 被相続人死亡の当日:被相続人が亡くなった日に連絡があった場合
- 死亡の通知をうけた日:被相続人の死亡を郵便や電話などの通知で知った場合
- 先順位者の相続放棄を知った日:自分より前の相続順位の人が全員相続放棄し、自分が相続人と知った日
- その他:相続人となり3カ月以上たった後、被相続人に債務があると知ったというような、ほかに当てはまらないケース
被相続人の死亡と相続の開始を知った日が離れている場合は、通知された郵便や事実経過のメモで証明します。証明する書類がないなら、裁判所に説明ができれば問題ありません。
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から『3カ月』以内です。そのため相続放棄をすると決めたら早めに手続きしましょう。
3-2.債務超過など「放棄の理由」を記入
申述書2枚目には『放棄の理由』を記入する欄があります。選択肢が設けられているため、当てはまるものに丸をつけましょう。選択肢は下記の通りです。
- 被相続人から生前に贈与を受けている
- 生活が安定している
- 遺産が少ない
- 遺産を分散させたくない
- 債務超過のため
- その他
例えば、被相続人である親の事業を引き継ぐ相続人に遺産を集中させたいときには、『遺産を分散させたくない』へ丸をつけます。プラスの資産より負債の方が多いなら『債務超過のため』を選べばよいでしょう。
選択肢に当てはまらない場合は、『その他』に丸をつけ具体的な理由を簡潔に記載します。
3-3.「相続財産の概略」に把握できた内容を記入
放棄する財産を全て記載するのが『相続財産の概略』の欄です。被相続人が死亡した時点で持っていた資産を、負債も含め全て記載します。
正確な金額である必要はないため、『100万円』『50平方メートル』というように、おおよその数字で書けば問題ありません。申述する時点で判明している財産について全て記載しましょう。
相続する資産や負債が不明または無い場合には、空いている箇所に『不明』もしくは『無し』と書いておきます。
4.相続放棄する人が20歳未満の場合
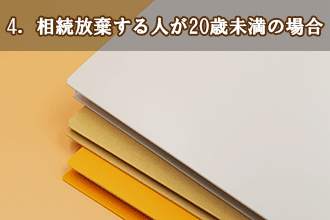
ここまで解説したのは、相続放棄する申述人が20歳以上の場合の記載例です。20歳未満の未成年の場合、『職業』の書き方が異なります。また『法定代理人等』の欄への記入が必要です。
4-1.職業や被相続人との関係の書き方
職業欄は成人なら『会社員』や『主婦』などと記載します。一方20歳未満の場合は、現在の教育課程に従い『小学生』『中学生』『高校生』と書きましょう。学年や学校名は不要です。
『被相続人との関係』欄や『本籍』『住所』『氏名』『生年月日』は、成人が申述書に記入する場合と同様に書けば問題ありません。
4-2.法定代理人は誰がなれるのか
未成年の場合は『法定代理人』が本人の代理として申述します。そのため『法定代理人等』の欄も記載しなければいけません。
法定代理人になるのは、『親権者』や『後見人』であるケースがほとんどです。どちらかであれば、選択肢に丸をつけ、『住所』『電話番号』『氏名』を記載します。
加えて『申述人の記名押印』も、法定代理人の氏名と印鑑を用います。また相続が発生したとき、申述人である未成年者に相続放棄をさせると、法定代理人である親権者が引き継ぐ財産が増えるケースがあります。
このように、申述人である未成年者と法定代理人の利益が相反するときには、未成年者の利益を守るため『特別代理人』も選ばなければいけません。
5.記入に迷いやすい部分について解説
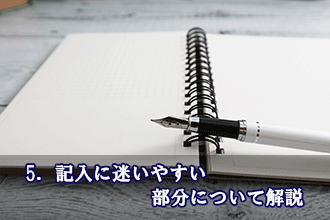
『添付書類』のチェック欄と、放棄の理由の『その他』の部分は、どのように記入すべきか迷いやすい部分です。どのように記入すればよいか、詳しく確認していきましょう。
5-1.添付書類は何にチェックすればよい?
申述に必要な書類を添付したら、その書類を添付書類の欄でチェックしましょう。必要な書類は、申述人と被相続人の関係によって異なります。
誰が申述人でも『被相続人の住民票除票』と『申述人の戸籍謄本』は必須です。加えて下記に記載する必要な書類を用意しましょう。
- 配偶者・子ども・孫:被相続人の死亡記載のある戸籍謄本・被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本(孫の場合のみ)
- 父母もしくは祖父母:被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・配偶者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本(祖父母の場合のみ)
- 兄弟姉妹もしくはおいめい:被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・配偶者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本・被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本・兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本(おいめいの場合のみ)
5-2.「放棄の理由」にある「その他」とは?
放棄の理由を記載する欄には、選択肢のほかに『その他』の項目があります。選択肢の中に当てはまる理由がないなら、その他を選び具体的な理由を書きましょう。
例えば、相続争いに巻き込まれるのが面倒と感じているなら、その他を選び『被相続人と疎遠であったため相続を辞退したい』と記載します。ほかにも『兄弟に遺産を譲るから』といった理由もあるでしょう。
理由は状況に合わせ率直に書きます。放棄の理由が相続放棄の可否に影響を与えることはありません。
6.期限を意識して早めに準備をしよう

相続放棄をするなら相続放棄申述書を提出しましょう。申述書は正確に書かなければならず、被相続人との関係性によって異なる添付書類も必要です。
申述書の提出期限は相続の開始を知ってから3カ月以内のため、できるだけ早い段階で準備を始めましょう。自力で書類の作成や収集をするのが難しいと感じるなら、弁護士や行政書士に依頼する方法もあります。
相続放棄を実施するときには、あらかじめ資産と負債を明らかにした上で、引き継げる資産がないか確認しましょう。相続財産が多数あると相続税の計算が必要になるケースもあります。
相続税について疑問に感じた点は『税理士法人チェスター』に相談しましょう。
『相続放棄の期限』について詳しく解説している以下もぜひご覧ください。
相続放棄の期限は「3ヶ月」!延長することはできる?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































