死後離縁とは?遺産相続はどうなる?申立て手続きの流れや注意点
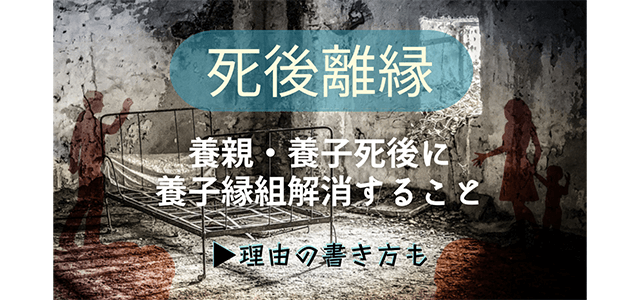
「死後離縁をするとどうなるの?相続権は?」
「死後離縁をしたら戸籍の記載や苗字はどうなるの?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論を言うと、死後離縁が認められると、養親と養子の親子関係や親族関係は解消されますが、すでに発生した養親や養子の遺産相続に影響はありません。
しかし、死後離縁後に養親や養子の親族の相続が発生した場合は相続権を失うため、代襲相続なども発生しないこととなります。
本稿では、死後離縁の基礎知識はもちろん、相続権や苗字などの取扱いについてまとめました。
死後離縁許可の申立て手続きの流れや、専門家に依頼した際の費用などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.死後離縁とは
死後離縁とは、養子縁組の当事者(養親や養子)のどちらか一方が死亡した後に、生存している当事者が死亡した当事者との養子縁組を解消する手続きのことです。
養子縁組の当事者のどちらかが亡くなっても、親子関係は消滅しません。
そのため、死後離縁を希望する場合は、生存している当事者が家庭裁判所に申立てをしなくてはなりません(民法第811条6項)。

出典:e-GOV法令検索「民法第811条」
死後離縁が認められると、養親と養子の親子関係のみならず、養親や養子の血族との親族関係も終了します(民法第729条)。
例えば、養親が亡くなって養子が死後離縁をした場合、養親の親である祖父母や養親の実子との親族関係も終了するということです。
死後離縁は生前に離縁が叶わなかった場合、亡くなった養親の親族との関係を断ちたい場合、旧姓に戻りたい場合など、さまざまな理由でおこなわれます。
養子縁組について、詳しくは「実子とは?養子縁組とは?相続における実子と養子の違い【具体例】」をご覧ください。
1-1.死後離縁と死後離婚の違い
死後離縁と似た手続きに死後離婚がありますが、両者には違いがありますので、混同されないようご注意ください。

養子縁組が成立した日から、養子は養親の法定血族(実子)として、相続権や祭祀継承などの法的な権利を得る代わりに、扶養義務なども負うこととなります。
そのため、死後離縁を選択すると法的権利を放棄することとなるため、家庭裁判所の許可が必要となります。
一方、死後離婚は、姻族関係終了は亡くなった配偶者の血族との親族関係を終了させることで、相続権や祭祀継承などの法的な権利などは関連しません。
そのため、家庭裁判所の許可は不要で、市区町村役場に「姻族関係終了届」などの必要書類を提出するだけで手続きが完了します。
詳しくは「姻族関係終了届の効果・メリット・提出期限など徹底解説」をご覧ください。
\\CHECK//
相続の専門家である弁護士・司法書士・税理士が、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応可能です。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
チェスターグループへのご相談はこちら
2.死後離縁をするとどうなるの?相続権は?扶養義務は?
死後離縁をすると、家庭裁判所が認めた日以降は相続権や扶養義務などの取扱いに影響があります。
この章では、死後離縁をするとどうなるのかといった、具体的な効果についてまとめましたので、参考にしてください。
2-1.死後離縁の前に発生している相続には影響なし
死後離縁をしても、すでに発生した相続に係る相続権には影響しません。
この理由は、死後離縁は当事者のどちらかが亡くなった日までさかのぼって、養子縁組を解消する手続きではないためです。
家庭裁判所の許可審判が確定し、市区町村役場に離縁届が受理された時点から死後離縁が成立するため、相続開始時点で養子縁組が成立していれば、法定相続人として遺産相続できます。

例えば、養親の相続が発生した場合、養子は第一順位の法定相続人として、養親の遺産を相続する権利(相続権)を有します。
その後、養子が死後離縁をしても、養親の相続開始日には法定相続人であったため、その相続権に影響はないということです。遺産分割協議にも参加できます。
養子がかかわる相続は、遺産相続トラブルに発展しやすい・通常の相続とは一部の取扱いが異なるなど注意ポイントがいくつかあります。
詳しくは「養子縁組の相続トラブルを回避する方法│事例や注意点を解説」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。
2-2.死後離縁の後に養親の代襲相続は発生しない
死後離縁をした後に養親の父母(祖父母)の相続が発生した場合、代襲相続は発生しません。
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その法定相続人の子が代わりに遺産を相続する制度のことです。

例えば、養父の父(祖父)の相続発生時において、すでに養父が亡くなっている場合、養父の代わりに養子(孫)が養父の父(祖父)の遺産を代襲相続します。
しかし、死後離縁が成立した時点で、親子関係も親族関係は解消されます。
そのため、死後離縁の後に、養子が養親の代襲相続人として、養祖父や養祖母の遺産相続をすることはありません。
代襲相続について、詳しくは「代襲相続は養子縁組でも発生する!要件や代襲相続人、相続税について解説」をご覧ください。
2-3.死後離縁の後は養親や養子の血族との相続関係が解消される
死後離縁をした後は、養親や養子の血族との相続関係も解消されます。
例えば、養子縁組をした養親に実子がいる場合、法的に実子と養子は兄弟姉妹として扱います。
すでに養親が亡くなっており、その後子どもがいない実子の相続が発生した場合、兄弟姉妹である養子は第三順位の法定相続人となります。

しかし、養親が死亡した後に養子が死後離縁をし、その後に養親の実子の相続が発生しても、養子が実子の遺産を相続することはありません。逆に、実子が養子の遺産を相続することもなくなります。
先述した通り、代襲相続も発生しませんので、実子の子や養子の子が代襲相続人となることもありません。
詳しくは「【独身の相続】法定相続人は誰?今からできる対策も解説」をご覧ください。
2-4.死後離縁の後は親族間の扶養義務も消滅する
死後離縁をした後は、相続権のみならず、親族間の扶養義務も消滅します。
扶養義務とは、自力では生活が困難な親族を経済的に援助する義務のことです。
扶養義務者は配偶者・直系血族・兄弟姉妹であり、これらの人が経済的な支援が困難な時は、家庭裁判所の審判によって3親等内の親族が扶養義務者となります(民法第877条)。

例えば、養親に実子がいた場合、その実子は養子にとって法律上の兄弟姉妹となります。
養親が亡くなったあとも死後離縁しなかった場合、養子が実子の扶養義務を負ったり、実子が養子の扶養義務を負ったりします。
しかし、死後離縁した場合は親族関係が解消されるため、親族間の扶養義務も消滅します。
扶養義務について、詳しくは「扶養義務者とは?範囲や負っている義務の内容や対象者の範囲を解説」をご覧ください。
2-5.死後離縁の後は遺族年金の受給権もなくなる
死後離縁が成立すれば、養親と養子の親族関係が終了するため、遺族年金の受給権もなくなります。
遺族年金の受給権の失権について、法律で以下のように定められているためです。
| 遺族基礎年金 | 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなったとき(国民年金法40条3項一) |
|---|---|
| 遺族厚生年金 | 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき(厚生年金法63条1項四) |
つまり、養子縁組中は遺族年金の受給権があったとしても、死後離縁が成立した時点から遺族年金を受け取ることはできなくなります。
遺族年金について、詳しくは「遺族年金とは?誰がいくらもらえる?条件・手続き方法も解説」をご覧ください。
3.死後離縁をする前に知っておきたい5つの注意点
死後離縁をする前に知っておきたい注意点は、以下のとおりです。
3-1.死後離縁をすると養子の氏(苗字・姓)は原則として復氏する
死後離縁をすると、養子の氏(苗字・姓)は原則として復氏します。
この理由は、民法第816条において、「養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。」と定められているためです。
ただし、養子縁組の日から7年経過後に死後離縁をし、なおかつ死後離縁の日から3ヶ月以内に市区町村役場に届け出た場合は、養子縁組中の氏を引き続き称することができます(民法第816条2項)。

死後離縁に期限はありませんので、どうしても養子の氏を使いたいものの、要件を満たすことができない場合は、養子縁組の日から7年経過するのを待っても良いでしょう。
なお、養子の子の氏は当然に変更しないため、養子である親と同一の苗字を称したいときは、家庭裁判所で「子の氏変更許可」の手続をとる必要があります。
3-2.養親や養子の遺産を相続したくない場合は相続放棄を
養親や養子の遺産を相続したくない場合は、死後離縁ではなく相続放棄を検討しなくてはなりません。
相続放棄とは、被相続人の財産や権利を一切相続しないことを指します。
相続放棄を選択した場合、法的には「はじめから法定相続人ではなかった」と扱うため、マイナスの財産(未払金や借金などの債務)を返済する義務もなくなりますが、プラスの財産(不動産や現金などの資産や権利)も相続できなくなります。

相続放棄が選択されるのは、被相続人が債務超過でその返済義務を相続したくない場合や、他の法定相続人との遺産分割トラブルを避けたい場合です。
相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述をしなくてはなりません。
相続放棄について、詳しくは「【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!」をご覧ください。
3-3.死後離縁の申立てができるのは養子縁組の当事者のみ
死後離縁の申立てができるのは、原則として養子縁組の生存当事者である養親か養子のみです。
養親や養子の親族が、相続関係に納得いかないから等の理由で、代わりに死後離縁の申立てを行うことはできません。
なお、養子本人が15歳未満の場合は、単独で死後離縁の申立て手続ができません。この場合は、養子の法定代理人(実父母等)が死後離縁の申立て手続きを行います。
3-4.死後離縁が認められないこともある
死後離縁をするためには家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが、理由が不純であると判断された場合は、死後離縁が認められないこともあります。
例えば、養親からの相続や贈与によって多額の利益を得たにも関わらず、養親の親族の扶養義務から免れるためだけに、死後離縁の申立てをした場合などが該当します。
ただし、相続や贈与を受けているからといって、必ずしも不許可になるとは限りません。
場合によっては家庭裁判所から審問の機会が設けられ、背景にどのような事情があるのか聞き取ったうえで審判する場合もあります。
死後離縁が認められない可能性がある場合は、必ず専門家である弁護士に相談をしましょう。
3-5.死後離縁が認められると撤回できない
死後離縁の申立てをして家庭裁判所に認められると、撤回はできなくなります。
死後離縁の申立てをする前に、死後離縁をしたことによる不都合はないか慎重に検討しましょう。
加えて、死後離縁は亡くなった養親または養子の親族との関係にも影響します。
特に、遺産相続や家の継承といった問題がある場合は、親族同士でもよく話し合って決めましょう。
4.死後離縁の申立て手続きの流れ
死後離縁の手続の流れは、以下のとおりです。

裁判所「死後離縁許可」もあわせてご覧ください。
4-1.家庭裁判所に死後離縁許可の申立てをする
まずは管轄の家庭裁判所に、死後離縁許可の申立てを行います。
具体的には、死後離縁許可の申立書に必要書類を添付して、家庭裁判所に提出することとなります(申立書の書き方や必要書類は次章で解説します)。
申立先:申立人の住所地を管轄する家庭裁判所
家庭裁判所の開庁日は、基本的に平日のみとなります。窓口で直接提出できない場合は、郵送での提出でも問題ありません。
管轄の裁判所は、裁判所「裁判所の管轄区域」から検索していただけます。
4-2.家庭裁判所における審理を受ける
次に、家庭裁判所における審理を受けます。
具体的には、裁判官が死後離縁許可を認めるか認めないかを判断する(審判を下す)ために、申立人に以下のような照会がなされます。
- 書面による照会
- 参与員の聞き取り
- 審問(直接事情を尋ねる)
死後離縁許可の申立てから1ヶ月以内に審理がありますので、裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしましょう。
裁判官が審判を下すと、死後離縁の許可・不許可に関わらず、結果の連絡があります。
なお、死後離縁が認められた場合は、申立書の提出から約1ヶ月後に、家庭裁判所から審判書謄本が送付されます。
審判書謄本とは、申立てに対する審判の結果が記されている書類ですので、大切に保管しておきましょう。
4-3.確定証明書の交付を申請する
死後離縁が確定した後は、確定証明書の交付を申請しましょう。
確定証明書とは、審判が確定したことを証明する書類のことで、市区町村役場に届出をする際に提出を求められます。
確定証明書の交付申請用紙は家庭裁判所に備え付けてありますので、必要事項を記入し、150円分の収入印紙を貼って提出しましょう。
郵送で確定証明書の交付を申請する場合は、返信用封筒と110円切手を同封します。
ただし、審判書謄本が発送されてから2週間は、確定証明書を受け取れませんので、この点にはご注意ください。
4-4.市区町村役場に養子離縁の届出をする
さいごに、申立人の本籍地または住所地の市区町村役場に、養子離縁届を提出すれば、死後離縁は完了です。
なお、養子離縁届を提出する際には、以下の必要書類の添付も求められます。
- 審判書謄本
- 確定証明書
基本的には上記の書類で届出できますが、養親と養子の戸籍謄本の提出を求められる場合もあります。
詳細は自治体によって異なるため、あらかじめ問い合わせておくと安心です。
5.死後離縁許可の申立書の書き方
死後離縁許可の申立書の書き方は、以下の通りです。
引用:裁判所「家事審判申立書(別表第1事件)」
死後離縁許可の申立書は、裁判所「死後離縁許可の申立書」からダウンロードしていただけます。
5-1.死後離縁許可の申立書に記載する理由の書き方
死後離縁許可の申立書の2ページ目にある申立ての趣旨や理由については、以下を参考に記載しましょう。

出典:裁判所「家事審判申立書(別表第1事件)」
申立ての理由には、「元の姓に戻したい」や「養親の家族間でトラブルがあった」といった内々の事情を記載する必要はありません。
理由に記載すべきポイントは、以下の3点です。
- 養親と養子縁組関係にあり、養親に育てられて15歳以上を迎えた事実
- 養親が亡くなった事実
- 養子縁組を解消したい意志
申立書の書き方に不安がある場合は、専門家に相談されることをおすすめします。
5-2.死後離縁許可の申立書に添付する必要書類
死後離縁の申立ての必要書類は、以下のとおりです。
- 死後離縁許可の申立書
- 養親と養子それぞれの戸籍謄本(除籍謄本)
- 収入印紙800円分(1人あたり※)
- 連絡用の郵便切手(裁判所により異なる)
※養親2人と離縁する場合は合計1,600円必要
なお、死亡している当事者の戸籍謄本は、死亡の記載があるもの(除籍・改製原戸籍)となります。
連絡用の郵便切手は、裁判所により金額や内訳が異なります。事前に申立人の住所地を管轄する家庭裁判所のホームページで、金額を確認しましょう。
6.死後離縁の申立てにかかる期間
死後離縁の申立てにかかる期間は2ヶ月程度です。内訳は以下のとおりです。
| やること | 期間 |
|---|---|
| 申立書や必要書類の準備 | 約1週間 |
| 家庭裁判所の審判 | 約1ヵ月 |
| 審判の結果が出てから確定するまで | 2週間 |
| 役所での手続準備・養子離縁の届出 | 約1週間 |
死後離縁の申立書を提出してから、家庭裁判所の審判を受けるまでに約1ヶ月かかります。
事情があって早めに死後離縁を成立させたい人は、収入印紙や戸籍謄本の準備を早めに済ませておきましょう。
また、家庭裁判所から審判の結果が出たあと、2週間は申立人が結果に不服を申し立てるための期間が設けられています。
もし不許可となった場合はこの2週間で、不服を申し立てましょう。
7.死後離縁の費用はいくら?専門家に依頼した場合は?
自分で死後離縁許可の申立てをした場合、負担する費用は4,000~7,000円程度の実費のみです。
【郵便切手】管轄の家庭裁判所によって異なる
【戸籍謄本】450円(1通あたり)
【除籍謄本】450~750円(1通あたり)
【確定証明書の申請に必要な印紙】150円
戸籍謄本を取得する手数料は自治体によって異なりますし、郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なります。予め市区町村役場や家庭裁判所に確認されることをおすすめします。
なお、死後離縁の手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、上記の実費に加えて報酬・手数料が発生します。
7-1.司法書士に依頼する場合(司法書士費用)
死後離縁の申立て手続きのサポートを司法書士に依頼する場合、以下のような司法書士費用が発生します。
| 費用目安 | |
|---|---|
| 相談料 | 初回無料であることがほとんど |
| 書類作成費用 | 5万円程度 |
| 書類の代行収集 | 2万円程度+取得手数料(実費) |
司法書士の費用・報酬は自由化されており、各司法書士事務所によって取扱いが異なります。
初回相談は無料であることが多いため、この際に見積もりを出してもらうことをおすすめします。
司法書士について、詳しくは「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。
7-2.弁護士に依頼する場合(弁護士費用)
死後離縁の申立て手続きのサポートを弁護士に依頼する場合、以下のような弁護士費用がかかります。
| 費用目安 | |
|---|---|
| 相談料 | 30分あたり5,000円~ (初回無料の場合もあり) |
| 書類作成費用 | 10万円程度 |
| 書類の代行収集 | 2万円程度+取得手数料(実費) |
弁護士の費用・報酬も自由化されており、各弁護士事務所によって取扱いが異なります。
以前は「旧日本弁護士連合会報酬等規程」に基づいて弁護士の費用・報酬は一律化されていましたが、現在もこの規定を参考にしている弁護士事務所が多いのが実情です。
弁護士は司法書士よりも費用が高くなる傾向にあるものの、死後離縁だけでなく相続トラブルや遺産協議分割の代理人も依頼できます。
相続や身内間のトラブルにアドバイスをもらいたい人や、代理人を任せたい人は、弁護士への依頼を検討しましょう。
8.まとめ
死後離縁の申立てが認められれば、亡くなった養親や養子の血族との親族関係が解消されます。
ただし、すでに発生した相続に影響はありませんので、親族間の遺産相続トラブルをしたい場合は、相続放棄などを検討しなくてはなりません。
なお、死後離縁は一度認められると撤回できませんので、慎重に検討しましょう。
戸籍収集等の代行も含めて専門家に依頼したい方は、状況に併せて弁護士や司法書士に相談をしましょう。
8-1.チェスターグループにご相談を
チェスタ―グループは、相続業務に特化した専門家集団です。
相続に強い司法書士・弁護士・行政書士・税理士はもちろん、相続不動産の売却サポートを行う株式会社も揃っています。
あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能となりますので、相続の相談にかかる手間や労力を最小限に抑えることが可能です。
チェスターグループでは、すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
その他







































