公証役場で確実な遺言書の作成を。遺産の資料や証人の用意が必要
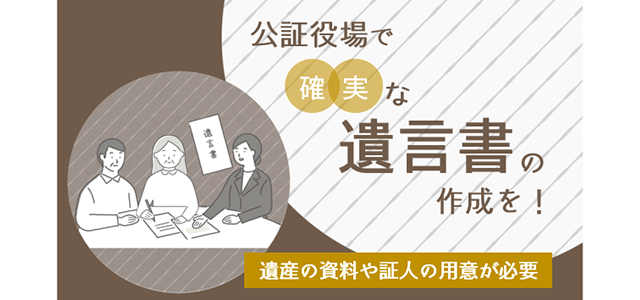
公証役場で確実な遺言書の作成を。遺産の資料や証人の用意が必要
遺言書を公証役場で作成すると、偽装や無効となる心配がなく確実です。ただし手続きをするには、必要書類を用意しなければいけませんし、打ち合わせや資料の準備なども必要です。スムーズに手続きするために、何を用意しなければいけないのか見ていきましょう。
1.公正証書遺言とは

公証役場で作成する遺言書を『公正証書遺言』といいます。自筆証書遺言と秘密証書遺言も遺言書として認められますが、公証役場を利用しない点が違いです。公正証書遺言ならではの特徴やメリットを確認します。
1-1.公証役場で作成する遺言書
公正証書遺言の一番の特徴は『公証役場』で作成・保管する点です。民法で定めている3種類の遺言方式の中で、最も安全性が高く確実な遺言書と考えられています。
役場というと、市役所や町役場など地方自治体の組織と混同している人もいるかもしれません。公証役場は『法務省』が管轄する国の機関です。属する組織が異なり、市役所や町役場とは関係ないため注意しましょう。
1-2.要件を満たす必要がある
正しく公正証書遺言を作成するには、下記の要件を満たさなければいけません。
- 証人2人以上の立ち会い
- 作成者が遺言の趣旨を公証人に直接口で伝える
- 口述の内容をもとに公証人が遺言書を作成し、読み聞かせ閲覧させる
- 遺言作成者と証人が署名押印する
これらの要件を満たすと公正証書遺言として認められます。ただし要件を満たしていても無効になる可能性があります。遺言作成者の病状が悪く判断能力が低下しているとみなされるケースです。
遺言書には期限がありません。万が一に備え、遺言作成者が健康な状態のうちに、できるだけ早いタイミングで作成しておくと安心です。
1-3.公正証書遺言のメリット
手続きの手間がかかる公正証書遺言には、メリットもあります。例えば遺言書が確かにあったことを認める『検認が不要』のため、家庭裁判所へ検認手続を申し出る必要がありません。
公証人のもとで作成しているため、形式上の不備も考えられないでしょう。必要に応じてすぐに遺産分割が可能です。
遠方に住んでいても対応しやすい点も、公正証書遺言のメリットといえます。公正証書遺言は公証役場で保管される決まりです。
そのため除籍謄本・戸籍謄本・身分証明書などの必要書類と、閲覧や遺言書の謄本請求の費用を支払えば、全国どこの公証役場からでも検索できます。他の形式のように自宅を探す手間がかかりません。
2.公正証書遺言作成の費用と必要書類

検認が不要で全国どこからでも閲覧や謄本の請求ができる公正証書遺言は、作成に費用がかかります。具体的な費用の金額と、作成時に必要な書類を確認しておくとスムーズです。
2-1.手数料は財産の価額によって異なる
公正証書遺言の作成にかかる費用は、各相続人が相続する財産の価額ごとに決められている手数料の合計で計算します。価額ごとの手数料は下記の通りです。
- 100万円まで:5,000円
- 200万円まで:7,000円
- 500万円まで:1万1,000円
- 1,000万円まで:1万7,000円
- 3,000万円まで:2万3,000円
- 5,000万円まで:2万9,000円
- 1億円まで:4万3,000円
- 1億5,000万円まで:5万6,000円
- 2億円まで:6万9,000円
- 2億5,000万円まで:8万2,000円
- 3億円まで:9万5,000円
さらに3億円を超えると5,000万円ごとに1万1,000円ずつ、10億円を超えると5,000万円ごとに8,000円ずつ加算されます。また価額が1億円までは遺言加算1万1,000円を加える決まりです。
例えば配偶者に5,000万円、子どもに3,500万円を相続する内容なら『遺言加算1万1,000円+2万9,000円+2万9,000円=6万9,000円』です。
2-2.印鑑証明書や遺産の資料などを用意する
実際に公正証書遺言を作成する日までに、必要書類の準備も欠かせません。遺言者の本人確認書類として、『印鑑証明書』や『免許証』といった公的機関発行の書類を用意しましょう。
相続人以外に遺贈をするときには、対象となる人の『住民票』も必要です。遺産の種類によって必要になる書類もあります。例えば不動産があるなら『登記事項証明書』や『固定資産の評価証明』などです。
有価証券や預貯金があるなら『種別とおおよその価額を記したメモ』も用意します。加えて2人の証人の名前・住所・生年月日・職業を書いたメモを持参しましょう。あらかじめ公証役場に必要な書類を確認しておくと確実です。
3.公正証書遺言作成の準備

必要な書類や資料をそろえただけで準備は終わりません。ほかにも公正証書遺言の作成に必要な準備があります。
3-1.証人を2人探す
公正証書遺言の作成時には『2人の証人』が必要です。事前に証人を探しましょう。ただし誰でも証人になれるわけではありません。下記に当てはまる人は証人になれないため注意しましょう。
- 未成年者
- 遺言で財産を譲り受ける人やその配偶者、もしくはその直系血族
- 公証人の配偶者や4親等内の親族
- 公証役場の職員など
- 遺言書の内容を読めない人や確認できない人
探しても証人が見つからないときには、公証役場へ紹介を依頼する方法もあります。
3-2.遺産の分け方をメモしておく
財産を誰にどれだけ相続するのか、分け方を決めメモしておくことも重要です。事前に内容を固めておくことで、目的に合う公正証書遺言を作れます。
どのように分けるかは作成者の自由です。ただし全ての財産を特定の個人や団体へ遺贈するといった内容では、法律で認められている相続人が必ず引き継げる『遺留分』を請求される可能性があります。
遺産相続時のトラブルを回避し、作成者の意図に添った相続をかなえるには、弁護士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
3-3.遺言執行者を指定する場合
『遺言執行者』は、法律関係の処理をスムーズに実行するために選任します。例えば遺言で認知するときや、相続人の廃除をするときには、必ず選ばなければいけません。
その他のケースでも、相続時のトラブル回避や、複雑な手続きの代行を依頼するために、遺言執行者を選任しておくとよいでしょう。遺言執行者は遺言者の死亡時に未成年や破産者でなければなれます。
ただし専門的な知識が必要なケースが多いため、専門家を選ぶのが一般的です。専門家へ依頼するときには、どの専門家が適切か調べ、依頼の準備もしましょう。
遺言書には、専任した遺言執行者の氏名・住所とともに『遺言執行者として選任する』という文言を記載します。
4.公正証書遺言作成の流れ
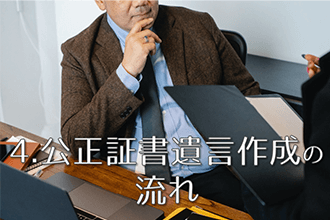
必要書類をそろえ、証人や遺言執行者を選任したら、公正証書遺言を作成します。準備をしていたからといって初回から作成できるわけでなく、まずは打ち合わせから始めるのが基本です。
4-1.公証役場で打ち合わせ
公正証書遺言を作るときには、公証役場へ出向き『打ち合わせ』をします。いきなり正式な遺言書を作るのではなく、記載する財産が正確か、確認できる書類と照らし合わせる作業が必要です。
具体的には不動産の登記簿謄本や通帳のコピーなどを持参します。本人名義の財産であることと同時に、価額を証明できる書類も必要です。
全て明らかにしなければ遺言書を作成できないため、少なくとも2週間~1カ月は打ち合わせ期間を設けます。
4-2.原案を受け取り、確認する
打ち合わせで財産の詳細を把握したら、スムーズに口述できるよう、作成者は遺言書の原案を作っておきましょう。説明しやすいようにする下書きのようなもののため、形式は決まっていません。
作成者本人にとって見やすいよう整理されていればいい書類です。原案をもとに口述した後は、公証人が公正証書遺言の素案を作成します。
公証役場からFAXやメール・郵送で届くため、正しい内容になっているか確認しましょう。
4-3.証人と公証役場へ行き、作成に入る
公正証書遺言を作成する当日は、作成者本人と証人2人で公証役場へ行きます。療養中といった理由で本人が公証役場へ行けない場合には、自宅や病院など指定の場所へ公証人と書記が訪れ、作成する仕組みです。
作成時は公証人が遺言書を読み上げます。本人と証人がその内容を聞いて確認し、問題がなければ証書へ署名・押印します。本人が寝たきりでペンを持てない場合には、公証人の代筆による署名も可能です。
最後に公証人が署名・押印します。これで公正証書遺言は完成です。完成後の公正証書遺言は公証役場で保管され、作成者の手元には謄本が残ります。
5.法的有効性が確認された遺言書に
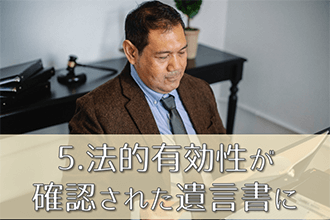
遺言書には公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。中でも公正証書遺言は、公証役場で公証人によって作成される、法的有効性が確認された遺言書です。
家庭裁判所による検認手続が不要で、全国の公証役場から検索可能という点がメリットといえます。公正証書遺言の作成には、書類の準備や証人選びが必要です。
またケースによっては遺言執行者の選任もしなければいけません。遺言書の内容を公証人へ口述するときのために、あらかじめ整理しておくことも大切です。
このとき専門家へ依頼し内容を確認してもらうと目的に合った内容で作成できます。相続税に関しても考慮するなら『税理士法人チェスター』へ相談するとよいでしょう。
『遺言書の書き方』については下記もご覧ください。
https://chester-tax.com/encyclopedia/14479.html
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
公正証書遺言の作成ならチェスターにお任せ下さい
「遺言があれば、相続発生後の多くの争いを防ぐことができます。
さらに、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができ残された方の負担が大幅に軽減されます。
チェスターグループでお客様の大切な遺言作成のサポートをお手伝いさせて下さい。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































