自己破産したら相続は無理?タイミングと注意点を税理士が解説
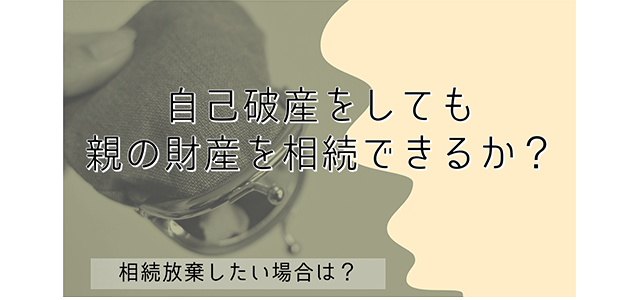
自己破産をした人でも遺産を相続できます。しかし、自己破産をするタイミングによっては、相続した遺産が処分されてしまい手元に残らないかもしれません。
また、自己破産をした人が相続人に含まれる場合は、遺産の分け方に注意が必要です。というのも、自己破産をした相続人に遺産がわたらないように分割すると、あとでトラブルになる恐れがあるためです。
そこで今回は、自己破産をしても親の財産を相続できるケースやできないケースなどを、相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.自己破産とは
自己破産とは、収入や財産が不足し借金を返済できる見込みがないことを裁判所に認めてもらい、返済義務を免除してもらえる手続きのことです。
自己破産では、所有する財産を処分して借金を返済し、それでもなお残っている借金の返済が免除されます。そのため、生活必需品と認められるものを除くすべての財産を処分して借金の返済に充てなければなりません。
手元に残るのは「99万円までの現金」や「残高が20万円以下の預貯金」など限られた財産のみです。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があります。それぞれの違いを見ていきましょう。
1-2.同時廃止事件
自己破産をする人の財産額が20万円未満であり、破産した理由がギャンブルや浪費などでない場合は「同時廃止(事件)」として処理されます。同時廃止は、同時廃止(事件)は、もっとも費用がかからず手続きも簡単であり、かつ短時間で自己破産が成立します。
1-3.管財事件
借金の原因がギャンブルや浪費などである場合や、所有財産が高額である場合などは「管財事件」として処理されます。管財事件は、同時廃止よりも手続きが複雑であるため、完了までに長い時間がかかります。
2.そもそも「相続できない」ケースはある?
被相続人が亡くなり相続が発生しても、相続欠格となっている場合や相続人排除をされている場合は遺産を相続する権利がありません。
2-1.相続欠格となっている場合
相続が発生したとき、相続欠格となっている人には、遺産を相続する権利を持ちません。 相続欠格とは、下記のような相続秩序を乱す行為をした相続人の資格を剥奪する制裁措置のことです。
- 被相続人や同順位以上の相続人をわざと死亡、または死亡させようとした
- 被相続人が殺害されたのを知っているのに告発や告訴をしなかった
- 詐欺・脅迫で被相続人の遺言の取り消しや変更を妨げた
- 詐欺・脅迫で被相続人の遺言の取り消しや変更を妨げさせた
- 被相続人の遺言書を偽造・変造・隠匿した
一度でも相続欠格となった相続人は、遺産を相続する権利を永遠に失います。相続欠格となった者に相続させると被相続人が遺言を残していたとしても、基本的には認められません。もし相続欠格となった者に子どもがいる場合は「代襲相続」が発生し、その子どもが相続人となります。
2-2.相続人廃除をされている場合
相続人廃除とは、相続権を持っている人を遺産の相続から外せる制度です。排除された相続人は「相続したい」と主張しても、相続できません。
相続人を排除できるのは、下記のようなケースで家庭裁判所に認められた場合のみです。そのため、申し立てをすれば必ず廃除できるわけではありません。
- 相続人が被相続人を虐待していた
- 相続人が被相続人に重大な侮辱を与えた
- 相続人に著しい非行があった
- 相続人が重大な犯罪を行い有罪判決を受けた
- 被相続人の財産を相続人が不当に処分した
- 賭博によって相続人が作った借金を被相続人に支払わせた
- 配偶者である相続人による不貞行為や、婚姻継続が難しい重大な理由で被相続人を苦しめていた
自己破産をする人が相続廃除の理由となる「非行行為」をしていたのであれば、相続人から廃除される可能性があります。
たとえば、自己破産をした人が被相続人の金品を勝手に持ち出して使っていたり、生活を改めるように注意すると暴力を振るったりした場合、非行行為に該当する可能性があります。
被相続人が廃除の申し立てをしており、それが認められている場合は相続廃除となるため、自己破産をするタイミングにかかわらず遺産は受け取れません。
相続人を廃除された事実は、戸籍に記載されます。相続手続きでは戸籍謄本が必須であるため、相続人廃除された人がいると必ず発覚します。
3.自己破産後に遺産を相続できるかどうかは相続発生のタイミングによる
家族が残した遺産を相続できるかどうかは「相続が発生したタイミング」と「破産手続開始のタイミング」次第です。
自己破産が裁判所に認められると「破産手続開始決定」が下ります。 決定が下されるまでの期間は通常2〜3か月ほどですが、所有する財産が多いと半年〜1年ほどかかる場合もあります。
破産手続開始決定後に相続が発生したのであれば、自己破産をしていても遺産を受け取ることが可能です。しかし、破産手続開始決定前に相続が開始された場合、たとえ遺産を相続できたとしても処分の対象となって債権者に配当されてしまうため、手元にはほとんど残らないでしょう。
厳密にいえば、相続が発生するタイミングによって相続財産の扱いが変わるだけであり、自己破産したからといって一切の遺産を相続できなくなるわけではありません。しかし、最終的には債権者への弁済や配当にあてるために遺産は処分されるため、結果的には相続できない状態になるといえます。
4.破産手続開始決定前に相続が発生した場合
自己破産の手続をしたものの、破産手続開始決定前に相続が発生すると、遺産は「破産財団」に含まれて処分され、債権者への弁済や配当に充てられます。
4-1.財産は破産管財人が管理する
破産手続開始決定前に相続が発生した場合、基本的には管財事件となり、裁判所によって選任された破産管財人が財産の管理や処分を行います。
相続については、通常と同じく遺言書や遺産分割協議の内容にもとづいて引き継ぐ財産の種類や金額などが決まります。ただし、遺産分割協議が終わっていない場合、 破産者は協議に参加できません。代わりに、裁判所が選任した破産管財人が協議に参加することになります。
破産管財人が参加したとしても、法定相続分通りに分割する場合は通常と変わりなく相続の手続きが進んでいきます。 また、法定相続分通りでなくとも「被相続人と同居していた長女が自宅を相続し、残りの現金は長男が引き継ぐ」のように常識の範囲内で分割されたのならば問題は生じません。
4-2.取得した遺産は破産財団に含まれてしまう
相続で取得した財産も含め、破産手続開始前に取得していた財産は破産財団に組み込まれ、換価処分という強制売却の対象になります。
売却されたあとは、破産管財人によって債権者に弁済・配当されるため、相続で引き継いだ財産のほとんどがなくなってしまう可能性もあります。
しかし、引き継いだ遺産を返済に充てたくないからといって存在を隠してしまうのはおすすめできません。遺産の存在を隠すような行為は「免責不許可事由」にあたり、自己破産による借金の免責さえも認められなくなる可能性があるためです。
5.破産手続開始決定後に相続が発生した場合
破産手続開始決定後に相続が発生した場合、相続財産は「新得財産」として扱われるため、破産財団には組み込まれません。
5-1.新得財産で自由財産とされる
新得財産とは、破産手続きの開始決定後に破産人が取得した財産のことです。破産手続開始決定後であれば、債権者への返済に充てられる財産はすでに破産財団に組み込まれているため、新得財産は破産者が自由に処分できます。
破産手続開始決定後に発生した相続で取得した遺産は、新得財産として扱われるため自己破産をしていたとしても相続人が自由に使用できます。
また、遺産分割協議に破産管財人が加わることもないため、破産人本人も含めた親族同士で協議をして、遺産の引き継ぎ方や処分方法を決めることが可能です。
5-2.取得した遺産は堅実に使う
新得財産は、計画的かつ堅実に使うことが大切です。自己破産をしたあとは、クレジットカードやローンでお金を工面するのが難しくなるのが主な理由です。
自己破産をした履歴は「個人信用情報機関」に掲載されます。個人信用情報機関は、クレジットカードやローンの申込状況や支払状況などの個人情報を記録する機関です。
「自己破産をした」「ローンの返済を長期にわたって滞納した」などの事故情報が個人信用情報機関に残されていると、いわゆるブラックリスト入りした状態となります。そうなると、クレジットカードやローンを申し込んでも、金融機関やカード会社の審査に基本的には通過できません。
自己破産をするとローンを含む借金が帳消しになる代わりに、所有するクレジットカードも使えなくなります。つまり、自己破産をすると手持ち資金が不足していたとしても、ローンやクレジットカードで工面するのが著しく困難になるのです。
自己破産を含む個人の信用情報は、個人信用情報に5~10年ほど登録されます。その間、手持ち資金が不足して生活が苦しくなってしまわないように、相続した遺産は大切に扱いましょう。
6.自己破産をした人がいる場合の相続
相続人のなかに自己破産をした人がいる場合は、そのまま遺産分割協議が進んでしまうと、遺産の一部が破産財団に組み込まれて処分されてしまいます。このような場合、自己破産をした人は相続放棄をするという選択があります。
6-1.遺産を失わないためには「相続放棄」を検討する
破産者である相続人が取得した遺産は、破産財団に組み込まれて債権者に配分されて手元に残らない可能性が高いといえます。そこで検討したいのが「相続放棄」です。
破産者が相続放棄の手続きをすると、始めから相続人ではなかったものとして扱われるため遺産を取得することができなくなります。
破産者からしてみれば、相続放棄をしたとしても遺産を手にできないことに変わりはありません。しかし、亡くなった家族が残した大切な財産が処分されずに済むため、他の相続人に引き継いでもらえます。
相続放棄の申述ができるのは、相続の開始を知った日から3か月以内です。破産手続開始決定前に相続が発生した場合は、相続放棄をすべきか速やかに検討しましょう。
相続放棄について詳しくは、下記の記事もご覧ください。
(参考)相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識
6-2.破産手続開始決定後に相続放棄をしてもあまり効果がない
自己破産をするのであれば、破産手続開始決定が出る前に手続きをしましょう。破産手続開始決定が出たあとは、破産者が相続放棄をしても限定承認の効果しか持たなくなるためです。
限定承認は、借金や未払金などが遺産に含まれる場合、現金や不動産などプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きのことです。
破産手続開始決定後に相続放棄で遺産を放棄することは、債権者の権利侵害にあたると考えられるため、限定承認の効果しか持たなくなると、破産法で定められています。
限定承認になると、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残りを相続することになります。そして相続した財産は、破産財団として組み込まれ債権者に配分されることになるでしょう。
7.自己破産直前に遺産分割協議をする際の注意点
遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば特定の相続人が相続する遺産をゼロにすることも可能です。しかし、自己破産をする予定の相続人が、遺産を引き継がないように分割するのはおすすめできません。
自己破産をする予定の相続人が遺産をまったく引き継がないと、債権者に配分される財産が減ることになり、債権者の権利を害する行為である「詐欺行為」に該当する可能性があるためです。
破産者が詐害行為をした場合、破産管財人による「否認権行使」の対象となる可能性があります。否認権が行使されると、遺産分割協議は法的な効力を失うことになるため、結局は破産者が相続するはずであった遺産が強制的に処分されてしまうでしょう。
また、詐害行為が悪質であると判断される場合、自己破産そのものが認められないケースもあります。財産を処分されるだけでなく、借金が残る可能性もあるため、遺産分割協議で破産者が相続する遺産を少なくすることは避けるのが賢明です。
8.自己破産の資産目録「相続財産」の書き方
自己破産を申し立てるよりも前に遺産を相続したことがある場合は、自己破産の資産目録にある相続財産欄を記入する必要があります。資産目録とは、自己破産の手続きをする際、破産者が所有する資産の内容を記載する書類のことです。
記載の対象となる相続財産には、時期的な制限が設けられていません。そのため申し立てをする前に相続をした経験があるのなら、遺産の取得時期にかかわらず、すべて相続財産欄に記載をする必要があります。
資産目録の相続財産記載欄には、被相続人や続柄、相続時期、相続した財産を記載するのが一般的です。ただし、資産目録のフォーマットや記載内容は、裁判所ごとに異なります。
8-1.遺産相続が終わっていない場合
被相続人が亡くなったあと、相続人が複数いる場合、相続財産は原則として共有となります。その状態で相続人の1人が自己破産をすると、相続財産の共有となっている財産は換価処分の対象となるため、資産目録の相続財産記載欄に記載しなければなりません。
たとえば、夫が亡くなり妻と長男が遺産を相続するとしましょう。夫が自身の名義となっている不動産が相続財産に含まれていた場合、遺産分割協議が終わるまで妻と長男が共有することになります。
遺産分割協議が終わらないまま、長男が自己破産をする場合、共有状態である不動産の2分の1は、換価処分の対象となるため、資産目録への記載が必要です。
9.両親が高齢で自己破産を検討している場合
自己破産の申立をしてから破産手続開始決定が出るまでの間に親が亡くなり相続が発生すると、遺産は破産財団に組み込まれて債権者に配分されるでしょう。
一方で、自己破産を申し立てて破産開始手続決定が出されたあとであれば、相続が発生して遺産を受け取ったとしても処分の対象になることはありません。そのため、自己破産を検討しており、かつ両親が高齢である場合は、できるだけ早く申し立てをするのも方法でしょう。
なお、破産手続開始決定が出る前に親が亡くなった場合、申し立てを取り下げることも可能です。しかし一度取り下げると再び申し立てをしても、破産を承認されない可能性があるため、自己破産するかどうかは、慎重に検討しましょう。
10.自己破産したら家を手放さなければならない?
自己破産をしたときは、家の名義人が誰であるかによって破産財団に組み込まれるかどうかが決まります。
10-1.本人名義の家
家の名義が自己破産をする本人である場合、家は破産財団に組み込まれて換価処分の対象となるため、基本的には手放す必要があります。
自己破産をしても「99万円以下の現金」のような自由財産は破産財団に組み込まれません。しかし、家は自由財産とは考えにくいため、処分の対象になると考えておきましょう。
なお、自己破産の手続きをする前に名義を家族に変更すると、財産を隠蔽して債権者を害したとされて「詐欺破産罪」に問われる可能性があります。
10-2.本人以外の名義の家
家の名義人が自己破産をする本人でない場合、破産財団には組み込まれず換価処分の対象にもなりません。そのため、家を失う心配はないでしょう。
10-3.亡くなった家族が名義人である家を共有している
家族名義の家を相続し相続人の共有状態である場合、そのままの状態で破産開始手続が決定されると破産財団に組み込まれてしまうため、その家は手放すことになる可能性があります。相続した家を破産の手続きから除外するためには、相続放棄の手続きが必要です。
ただし、破産手続開始決定後に相続放棄の申述をしても、限定承認の効力しか持たないため、相続した家は債権者への配当対象となってしまいます。相続放棄をするのであれば、破産手続開始決定が下る前に手続きをしておくことが大切です。
11.自己破産と相続の関係を理解しておこう
自己破産をしても、相続が発生すれば遺産を引き継ぐことができます。ただし、破産手続開始決定前に引き継いだ遺産は破産財団に含まれるため、強制的に売却されることになるでしょう。
一方で、破産手続開始決定後に相続が発生したのであれば、取得した遺産は新得財産として手元に残せます。引き継いだ遺産は、自己破産後の生活にける大切な資金源となるため、計画的に使いましょう。
ただし、遺産の金額によっては相続をすることで相続税の負担が発生する可能性があります。相続税が発生するときは、相続税専門の税理士に相談をして正しく納税することが大切です。
相続税専門の税理士法人であるチェスターは、お客さまだけでなく税理士業界からも高く評価いただいております。
相続税の計算や申告だけでなく遺産の分け方もご相談可能ですので、お困りの方は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































