相続税の追徴課税はいくら?計算シミュレーション・対応方法を解説
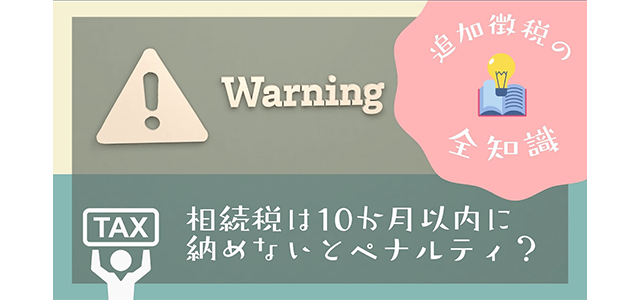
相続税の申告は、相続を知った日の翌日から10カ月以内におこなう必要があります。期限までに申告をしなかった、もしくは申告した税額が本来納めるべき税額よりも少なかった場合に「追徴課税」が課せられます。
自分では正しい税額で申告したつもりでも、税務調査によって申告漏れが指摘されることもあり、注意が必要です。
本記事では、追徴課税の概要や実態、税務調査につながりやすいケースや注意したいポイントなどを詳しく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続税の追徴課税とは?
相続税の追徴課税(ついちょうかぜい)とは、相続税の申告や納税に誤りがあった場合などに追加で支払わなければならない税金のことです。追徴課税を大きく分けると2種類あり、本来支払うべき相続税「本税」と、それに追加される加算税や延滞税といった「附帯税」(追徴金)から構成されます。
1-1.「本税」「附帯税」と追徴課税の定義
「追徴課税」という言葉は一般の用語で、相続税法において定義されている法律用語ではありません。このため、人によって異なる意味で用いられていることがある言葉です。
ただし、国税庁による「相続税の調査等の状況」などの資料では、「追徴税額=(追加の)本税+加算税」として定義されています。本記事では、納税額が不足していた場合などに「追加で支払わなければならない本税」と「附帯税」とをあわせて「追徴課税」と呼ぶこととします。
| 本税 | 相続税、所得税などの、本来納めるべき税金。 |
|---|---|
| 附帯税 | 本税の申告遅れや申告漏れがあった場合に、本税に追加して課税される下記の税を総称した呼び方。
|
1-2.相続税の税務調査と追徴課税の実態
税務調査とは、納税者の申告が適正かどうかを税務署が調べることです。相続税だけではなく、法人税や所得税についても申告内容に誤りがないかを確認するために、税務調査がおこなわれています。
相続税における税務調査や追徴課税は、実際にどの程度発生しているのでしょうか。国税庁が公表したデータを確認してみましょう。
令和5年において、相続税に関して8,556件の税務調査がおこなわれ、うち7,200件(84.2%)が追徴課税の対象とされました。データを見る限り、相続税の税務調査が実施されればほとんどのケースで追徴課税されるといえます。
なお、税務調査1件あたりの追徴税額(追加される相続税と付帯税の合計)の平均は859万円となっています。
出典:国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」
2.相続税の附帯税は4種類
追徴課税のうちの附帯税は、正しく申告納税をしていない納税者の「落ち度」に対するペナルティです(「追徴金」ということもあります)。その状況に応じて、次の4種類が設定されています。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
それぞれが追徴課税されるケースを見ていきましょう。
2-1.申告・納税した税額が少ない場合に追徴課税される「過少申告加算税」
過少申告加算税は、申告・納税した相続税が、本来の税額よりも少なかった場合に課される加算税です。ただし、過少申告加算税が適用されるのは計算ミスや勘違いなどの過失の場合で、意図的な隠蔽だと判断される場合は重加算税が適用されます。
過少申告加算税は、修正申告時期により、以下のように税率が異なります。
| 修正申告の時期 | 税率 |
|---|---|
| 税務調査の事前通知前 | なし |
| 税務調査の事前通知後から税務調査まで (更正・決定予知前)の期間 | 追加の納税額の5%相当額。 追加の納税額が当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%。 |
| 税務調査後 | 追加の納税額の10%相当額。 追加の納税額が当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。 |
2-1-1.過少申告加算税が課されない場合
税務調査の通知がなされる前に、納税者が自分で過少申告に気づいて修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません。
また、申告前に納税者が税務署で申告内容について尋ねたときに、職員が間違った指導をしていた場合など、誤った申告に正当な理由があると認められる場合も、過少申告加算税は課されません(ケースによります。)。
さらに、過少申告加算税が5,000円未満の場合は、課税免除となります。
2-2.相続税を申告しなかった場合に追徴課税される「無申告加算税」
無申告加算税は、正当な理由がなく、期限内に相続税の申告をおこなわなかった場合に追徴される税金です。
相続税の申告期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内と定められています。それまでに正当な理由がなく申告・納税をしなければ、無申告加算税が課されることとなります。
なお、ここでの正当な理由とは、「災害発生または交通や通信の途絶」と「期限後申告の特則に該当する事由」です。前者は文字そのままの意味ですが、後者は、新たな相続人が見つかった、遺産分割をめぐる裁判の確定判決が下されたなど、相続税額が変化する事情が申告期限直前に発生した場合のことです。いずれにしても、かなり例外的なケースでしょう。
無申告加算税も、過少申告加算税同様、修正申告時期により、税率が異なります。
| 期限後申告の時期 | 納付税額50万円までの部分 | 納付税額50万円を超え300万円までの部分 | 納付税額300万円を超えた部分 |
|---|---|---|---|
| 税務調査の事前通知前 | 5% | ||
| 税務調査の事前通知後から税務調査まで(更正・決定予知前)の期間 | 10%(※1) | 15%(※1) | 25%(※1、3) |
| 税務調査後 | 15%(※1、2) | 20%(※1、2) | 30%(※1、2、3) |
(※1)前年度及び前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合は、当年度分の税率が10%加算される。
(※2)期限後申告等があった日前5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、10%加算される(※1とのいずれかを適用)。
(※3)納付税額が300万円を超えることに納税者の責めに帰すべき事由がない場合は、「50万円を超え300万円まで」の税率を適用。
なお、以下の「すべて」を満たすケースでは、期限後申告でも無申告加算税は課されません。
- 申告期限から1カ月以内に自主的に期限後申告をしている。
- 申告の期限内(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日まで)に納税をおこなっている。
- 期限後申告の前日から5年以内に無申告加算税または重加算税を課されていない。
無申告加算税が5,000円未満の場合は、課税免除となります。
2-3.悪質な財産隠しなどの場合に高額の追徴課税がされる「重加算税」
重加算税は、相続財産を故意に隠して相続税を少なくするなどの悪質な仮装隠蔽があったと判断されるケースで追徴課税されるもので、加算税の中でもっとも高税率です。重加算税は、納期限までの申告の有無(過少申告か無申告か)で税率が異なります。
| 状況による区分 | 税率 |
|---|---|
| 重加算税(申告漏れや過少申告) | 35% |
| 重加算税(無申告) | 40% |
なお、次のいずれかにあてはまる場合は税率が10%加算され、申告漏れや過少申告で45%、無申告で50%になります。
- 過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合
- 前年度及び前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合
2-4.期限内に納税しない場合に追徴課税される「延滞税」
延滞税は、税金の納付遅れに対する「遅延利息」のような性質の税金です。以下の場合に発生します。
- 納期限までに相続税を納付していない場合
- 期限後申告または修正申告をした場合
- 税務調査で指摘を受けて追加で相続税を納付する場合
なお、延滞税は期限後に納める相続税(本税)に対してのみ課税され、附帯税(加算税)には課されません。
延滞税は、納期限から納付日まで2カ月以内か、2カ月超かにより、税率がわかれています。また、延滞税特例基準割合は毎年変動するため、延滞税の税率も毎年変動します。令和7年までの延滞税特例基準割合は1.4%であり、まとめると以下の通りです。
| 納付日までの日数 | 税率計算方法 | 令和7年12月31日までの税率 |
|---|---|---|
| 納期限から2カ月以内 | 年7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 | 年2.4% |
| 納期限から2カ月超 | 年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合 | 年8.7% |
なお、延滞税の計算の起算日となる「納期限」は、申告の種類やタイミングによって以下のように定められています。
| 申告の種類 | 納期限 |
|---|---|
| 申告期限内に申告書を提出した場合 | 法定納期限(申告期限=死亡日の10カ月後)と同じ日 |
| 期限後申告または修正申告の場合 | 申告書を提出した日 |
| 税務署による更正・決定を受けた場合 | 更正通知書を発した日から1カ月後の日 |
3.【計算シミュレーション】追徴課税(追徴金)はいくら?
実際に申告漏れがあったときに、どのくらいの追徴課税を支払わなければならないのでしょうか。税務調査前の通知が税務署から届いたことにより、過少申告に気付き修正申告した場合を想定して、支払うべき追徴課税のシミュレーションをします。
実際に納付すべき税額は、他の要因によって変わってくることもあります。修正申告をおこなう際は、ぜひ税理士に相談してください。
本件の状況
- 本来の相続税額:800万円
- 申告・納税した税額:600万円
- 相続税の申告期限である令和6年5月31日より前に、申告と納税をおこなった
- 令和6年10月1日に税務署から税務調査に関する通知が届いた
- 税理士に相談のうえ、令和6年10月31日に相続税の修正申告をおこなう
- 追徴課税は令和6年11月5日に支払う
上記の場合、本税と附帯税がどの程度の金額になるのかを計算していきます。
まず、すでに納付した税額と本来の相続税額との差額は200万円です。このため、本税は200万円となります。
税務署からの通知が入ったことで修正申告をおこなうと、過少申告加算税が課されます。しかし、申告漏れはあったものの相続税の申告・納税は済ませているので、無申告加算税はかかりません。意図的に脱税をしようと考えていたと判断されなければ、重加算税も対象外です。
過少申告加算税は以下の式で求められます。
納付すべき本税の金額×税率
200万円×5%=10万円
また、本税や過少申告加算税の他、延滞税も課されます。延滞税は納期限から2カ月以内なのか、2カ月を超えたのかによって税率が変わります。ここでは、修正申告をした5日後に納税をしているため、延滞税は2カ月以内の年2.4%で計算可能です。ただし、本来の相続税の申告期限である令和6年5月31日の翌日から延滞税がかかります。
延滞税の計算式は以下のとおりです。
納付すべき本税の金額×税率×日数(法定納付期限の翌日から完納の日まで)/365日
200万円×2.4%×158日/365日=2万778円
延滞税は100円未満の端数は切り捨てたうえで、納税します。
上記シミュレーションにより、本件では次の追徴課税が課されます。
200万円(本税:相続税の納税不足分)+10万円(附帯税:過少申告加算税)
+2万700円(附帯税:延滞税)=212万700円(追徴課税合計)
4.税務調査の対象となりやすい10のケースとは
相続税の申告で税務調査が入りやすいのは、国税総合管理システム(KSKシステム)などを通じて税務署が把握している財産状況と、相続税申告内容に差があるケースです。
代表的な10の状況をご紹介します。税務署にチェックされる危険度(危険度が高い順にABCで表示)も付しておきますので、参考にしてください。
4-1.生前の所得と申告財産に差がある(危険度A)
被相続人の生前の収入に比べて相続財産の申告額が少なすぎる場合、税務調査の対象になる可能性が高くなります。税務署は、亡くなった人の収入や所得の状況をほぼ把握しています。生前に高収入だった人の相続財産が収入に見合う金額でない場合、申告漏れを疑われ税務調査に入られやすくなるでしょう。
4-2.申告書に不備がある(危険度C)
相続税の申告書に計算間違いや記入漏れなどの不備があると、税務調査が入る可能性があります。ちょっとした単純ミスであれば、電話などでの「簡易な接触」により指摘され、修正申告をするだけで済むかもしれませんが、その場合であっても過少申告加算税や延滞税は原則的に追徴課税されます。
4-3.預貯金が多く資金移動の頻度が高い(危険度A)
同じ財産額でも不動産より預貯金が多い人のほうが税務調査に入られやすい傾向があるようです。不動産とは異なり、現金や預貯金は評価額を考える必要がなく、間違いを指摘しやすい財産だといえます。
相続財産のうち預貯金の割合が多く、かつ生前に入出金が多かった人は、相続人の知らない不動産取引や第三者への金銭の貸付けなどをおこなっていた可能性が疑われるようです。個人間の金銭の貸付けは親族も把握しきれない場合がありますが、発覚した場合は追徴課税の対象となります。
4-4.遺産相続額が大きい(危険度A)
遺産が多額となる富裕層は、税務調査を受ける可能性が高くなります。目安として、遺産額が2億円を超えると調査に入られやすくなるといわれています。意図的な資産隠しでなくても、財産が多いほど、抜けや漏れが発生しやすいからです。
富裕層の税務調査で追徴課税が発生すれば、当然、その税額も大きくなるため注意が必要です。
4-5.多額の借入金があるのに、それに見合う相続財産がない(危険度A)
被相続人が銀行などから多額の借入をしていた場合、借入金で不動産その他の現物資産などを購入したと推察されます。多額の借入の履歴があるにもかかわらず、それに見合った相応の財産がない場合、高い確率で税務調査が入るでしょう。
4-6.長年にわたって暦年贈与を実施していた(危険度C)
贈与税の基礎控除を活用するため長年にわたって暦年贈与を続けていた場合、多額の贈与を分割した課税回避行為とみなされる可能性があります。税務調査によって暦年贈与が否認されると、一括贈与と同様の課税とされ、追徴課税される恐れがあります。
4-7.税理士に依頼せず自分で申告していた(危険度B)
相続税の申告書を納税者が自分で作成していた場合、税務調査の対象になりやすくなります。不動産や有価証券などの評価計算、特例の適用、税額の計算など、非専門家による申告書は間違いがある可能性が高いと考えられるからです。意図的な隠蔽ではなく単なる過失でも、納税額が過少であれば追徴課税されます。
4-8.無申告の場合(危険度C)
相続税の計算の結果、相続税が非課税(相続税の基礎控除額以下)となる場合は、原則として申告の必要はありません。しかし、小規模宅地等の特例のように申告を条件として適用できる特例もあるので、そのような特例を適用して計算したにもかかわらず申告をしていなかったとなれば、当然指摘を受けることとなります。他にも、計算の過程で特例や控除の適用に誤りがあり、本来は相続税が発生することになれば、指摘を受けるでしょう。
4-9.海外に送金した資産が多い(危険度A)
課税回避のために財産を国外に移転するケースが増えたため、税務署は海外資産の把握に力を入れています。海外への送金が100万円を超える場合に「国外送金等調書」の提出が義務づけられており、そこで把握した資産額と申告内容が相違していれば、税務調査に入られる可能性はかなり高くなるでしょう。
4-10.家族の資産が収入に対して多い(危険度B)
相続人である配偶者や子の預金残高が、その人たちの収入に対して多かったり、有価証券を多く持っていたりする場合は、税務調査が入る可能性があります。収入に見合わない財産を持っていれば、その出所として多額の生前贈与などが疑われるためです。調査の結果、生前贈与などの申告漏れがあれば追徴課税されます。
5.相続税の申告漏れとして指摘されることがよくあるミスや勘違い3例
申告漏れの多くは意図的な隠蔽などではなく、単なるうっかりミスや勘違いから発生するものです。そのようなミスなどに気づいたら、早めに税理士に相談しましょう。税務署の指摘の前に修正申告をすれば、過少申告加算税などが低く抑えられます。よくある過失として挙げられるのは次の3つのケースです。
5-1.名義預金があった
相続税の申告漏れとして指摘される代表的なものの1つが「名義預金」です。
名義預金とは、口座の名義は相続人の名前であっても、実質的には被相続人が管理していたとみなされる預金のことです。名義預金だと税務署から判断されれば、相続財産に含められることになります。相続人に、名義預金だという認識がなくても、実態から名義預金が疑われれば、税務調査の対象となる可能性が高くなります。
5-2.タンス預金があった
高齢者が多額の現金を銀行に預けずに、自宅の金庫などで保管しているのが「タンス預金」です。タンス預金も、当然、相続財産として申告しなければなりません。相続人がタンス預金の存在に気づかず、あるいは気づいていたにもかかわらず、これくらいならバレないだろうと思って申告していなければ、税務調査で発覚して追徴課税される可能性があります。
5-3.持ち家を相続財産として申告することを忘れていた
不動産を相続した人は法務局で所有権移転登記をしたうえで、相続財産として申告しなければなりません。しかし、亡くなった人と同居していた相続人がそのまま同じ家に住み続ける場合、相続の手続きを忘れてしまう場合があります。
また、相続した不動産の名義を変更することを「相続登記」といいます。今までは任意で行えばよかった相続登記ですが、令和6年4月1日に義務化されました。正当な理由がないまま遺産相続から3年以内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるので注意しましょう。
出典:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
6.相続税の申告漏れを発見する税務調査とは
税務調査では、納税者が正しく申告をし、適正な納税をおこなっているのかを確認します。税務調査は相続開始の翌年から翌々年までにおこなわれることが多く、三回忌が終わってから通知が届くという声もあるほどです。
相続税の税務調査では、税務署員が実際に納税者の自宅などを訪問する「実地調査」がおこなわれます。
また、実地調査とは別に、税務署が電話などで納税者に質問したりする「簡易な接触」という方法での調査がおこなわれることもあります。
ここでは、税務調査の実態を解説します。
6-1.税務調査(実地調査)には、強制調査と任意調査の2種類がある
税務調査の実地調査には強制調査と任意調査の2種類があります。それぞれの特徴を解説します。
6-1-1.強制調査
強制調査とは、裁判所の令状を得て国税局査察部(マルサ)の査察官がおこなう税務調査です。警察の捜査と同様に、強制調査なので拒否することはできません。この対象となるのは相当に悪質なケースに限られるため、一般的な相続税申告ではあまりおこなわれないと思っていいでしょう。
6-1-2.任意調査
税務調査のほとんどは任意調査です。任意調査といっても、税務署職員は、納税義務者に税金に関する質問をしたり資料を検査したりする「質問検査権」を持ちます。納税義務者は、この質問検査権に応える義務があるのです。なお、一般的に任意調査は事前に連絡があり、日程調整などもできます。
6-2.税務調査に時効はある?何年まで遡るのか?
税務調査の時効は原則5年です。相続税申告書の提出期限の翌日から数えて5年間で時効を迎えます。ただし、不正行為によって納税を免れたり還付金を受け取ったりする脱税行為があった場合は、時効は7年に延長されます。
6-3.税務調査を受ける際の準備
税務調査の連絡を受けると、誰でも慌ててしまうことでしょう。しかし、意図的な脱税などをしていないのであれば、粛々と対応すればいいのです。準備しておくことなどを確認しておきましょう。
6-3-1.申告書の内容確認
税務調査を受けることになったら、まずは相続税申告書の内容に申告漏れや計算間違いなどがないかを見直してみましょう。多くの場合、相続税の申告は税理士に依頼しているでしょうから、調査が入った旨を担当税理士に連絡し、申告内容を確認してもらいます。
なお、相続税の申告を自分でおこなっていた場合でも、税理士に税務調査の立ち会いのみを依頼することもできます。
6-3-2.財産を再度調べる
調査を受けることになった場合、申告した相続財産に見落としがあったことも考えられます。そのため、再度財産を調べ直しましょう。見落としがちな相続財産には以下のようなものがあります。
- 名義預金
- 生命保険金(みなし相続財産)
- 死亡退職金(同)
- 知人や会社などへの貸付金
- 美術品・骨董品
- 被相続人が亡くなる前3年以内に贈与した財産で、相続財産に持ち戻していないもの
- 相続時精算課税を利用して贈与を受けた贈与財産の価額
6-4.税務調査から逃げ切るのはまず不可能
調査を受けても、財産をうまく隠せばわからないだろうと考える人もいるかもしれません。しかし、近年、相続税の調査では「KSKシステム」と呼ばれる、過去の税申告関連のデータがすべて蓄積されたネットワークシステムが活用されています。これによって、資産に大きな動きがあれば、国税庁はすべてを把握することができるようになっています。
税務署もなんの根拠もなしに実地調査は実施しません。調査をするということは、ある程度目星をつけているということです。意図的に隠蔽していた財産が発覚すれば、重加算税の対象となり、多額の追徴課税を受けることになるので、十分に注意しておきましょう。
7.気付いたら速やかに!相続税修正申告の手順
相続税の申告に誤りがあった場合や申告後に新たな財産が判明した場合などは、速やかに修正申告をすることが大切です。税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告をおこなえば、追徴課税の一種である過少申告加算税が免除されるケースもあります。ここでは、修正申告が必要となるケースや手順について解説します。
7-1.相続税の修正申告が必要なケース
相続税の申告が実態とは異なる場合、速やかに修正申告をし、追加で納税をしなければなりません。具体的に修正申告が必要なケースとして、次のような事例が考えられます。
7-1-1.申告した税額に誤りがあった
相続税の申告を自分でおこなった場合など、計算ミスや記載漏れなどが発生することがあります。とくに遺産総額が高額だった場合は計算ミスが起きやすく、申告後に見直して誤りが見つかることがあります。
7-1-2.新たな財産が見つかった
相続税の申告後に新しく故人の財産が見つかることもあります。たとえば、遺品整理をしているときにタンス預金や隠し財産(へそくり)、デジタル遺品を発見するケースが挙げられます。とくにデジタル遺品のひとつであるオンライン口座は、紙の通帳がないので遺族が存在を知らなければ見つけることができません。相続税の申告後に偶然発見されることもあります。
7-1-3.仮の申告で済ませていた
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月と決まっています。しかし、場合によっては遺産分割協議がまとまらず、とりあえず法定相続分で計算して仮の相続税申告をするケースもあるでしょう。その場合は、遺産分割協議が完了した時点で正しい金額で申告し直す必要があります。
仮の申告時よりも取得した遺産が少ない場合には、納めすぎた税金を取り戻すことができます。
7-1-4.特例制度を誤って適用させていた
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減できる特例はありますが、それぞれ適用要件は異なります。要件を満たしていないにもかかわらず、特例を使って税額を算出した場合には修正が必要です。
相続税の特例制度は要件が細かく規定されているため、確実に利用できるようにあらかじめ専門家に相談することをおすすめします。
相続税で活用できる税額控除については、次の記事で詳しく解説しています。税額を大きく軽減できる特例もあるので、ぜひご確認ください。
参考:【相続税の控除】活用できる税額控除6選&その他の控除3選を紹介|税理士法人チェスター
7-2.修正申告の手順
相続税の修正申告をする際は、次の手順でおこないます。
- 必要な書類を集める(「相続税の申告書」・納付書・本人確認書類)
- 相続税の修正申告書に記入する
- 申告書を提出する前に、不足している税額と延滞税を納める
- 税務署に修正申告書と必要書類を提出する
修正申告の詳しい手順や提出する書類については、次の記事で詳しく解説しています。
参考:相続税の修正申告をする方法│事例・期限・ペナルティも解説│税理士法人チェスター
8.追徴課税を受けた場合の対応方法と注意点
相続税の申告漏れなどで追徴課税を受けることになった場合の、納税の方法など対応上の注意点について解説します。
8-1.納税の方法は現金払いのみ
通常の相続税申告の場合、現金での納税が困難な人は、現金の代わりに「物納」という方法を採ることが可能です。しかし、追徴課税の支払いは現金払いのみとなっており、物納はできません。また、下記の猶予措置が適用される場合を除いて一括払いが原則で、分割納税もできません。
8-2.追徴課税に納得がいかない場合は不服申立てできる
税務調査の結果、課税処分に納得できない場合は不服申立てをすることが可能です。税務署長又は国税局長が行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に「再調査の請求」を行うことができます。再調査の請求を受け取った税務署長などは、正当な判断がなされたのかどうかを再調査し、納税者にその結果を「再調査決定書謄本」として送付します。
この通知が受け入れられないものであった場合、今度は国税不服審判所長に不服申立てをすることが可能です。その際は、再調査決定書謄本が送付された日の翌日から1カ月以内に「審査請求書」を国税不服審判所長宛に提出しましょう。国税不服審判所長は再度判断が正しいかどうかを調査、審理して、その結果を採決書謄本として通知します。
なお、再調査の請求を経ずに、国税不服審判所長に対して直接審査請求を行うことを選択することができます。
8-3.支払いをしないと最終的には財産が差し押さえられる
追徴課税を支払わないと、まず督促状が、次に差し押さえ予告書が届きます。それでも払わないでいると、最終的には財産が差し押さえられてしまいます。差し押さえの対象となるのは、給料(会社員・公務員)、売掛金(事業者)、金融資産(預金口座、証券口座)、不動産、動産(自動車など)、保険契約の解約返戻金などです。
8-4.自己破産しても免責されない
普通の債務(借金)であれば、自己破産をして免責の決定がなされることで返済する必要がなくなります。しかし、税金は「非免責債権」といい、自己破産をしても免責されず、支払わなければならない債権です。たとえ自己破産をしても、追徴課税からは、逃げられないということです。
8-5.支払えないときの対処法として納税猶予制度が利用できる場合がある
追徴課税が多額で、一括納付が難しい場合、猶予制度を活用すれば差し押さえを回避できます。あくまで猶予であって免除ではありません。ただし、どちらの猶予制度でも、適用されれば延滞税については一部または全部が免除されます。
8-5-1.換価の猶予
換価とは、差し押さえを受けた財産が換金されてしまうことです。換価の猶予とは、差し押さえられた財産の売却と、新たな差し押さえが猶予される制度です。換価の猶予が認められるのは、下記の条件を満たしている場合です。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
- 納付すべき国税の納期限から6カ月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること(なくても認められる場合もあります)
8-5-2.納税の猶予
納税の猶予とは、追徴課税の納税が猶予される制度です。納税の猶予が認められるのは、下記の(1)から(4)の「すべて」に該当する場合であり、換価の猶予よりもさらにハードルが高いでしょう。
納税猶予の要件(概略)
- 自然災害や盗難で財産に被害を受けた、または、病気やけがをした、事業を廃止した、などの事情がある。または、本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定している。
- 上の事情によって、税金を一括納付することができないと認められること
- 申請書が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること
納税の猶予の適用を受けるには、修正申告書と納税の猶予申請書を同時に提出します。納税の猶予によって、追徴課税を1年以内に分割して納付(正当な事由があれば最大2年間)できるようになります。
8-6.追徴課税は誰が支払う?相続人全員に「連帯納付義務」がある
追徴課税された税金は、基本的には対象となった遺産を相続した人が支払います。しかし、相続税には「連帯納付義務」というルールがあります。各相続人は、「相続によって受けた利益額」を限度として、連帯して相続税を納付する義務があるのです。
追徴課税にも連帯納付義務は適用されるため、本来支払うべき相続人からの納付がなければ他の相続人が、支払いを求められることがあります。そういう事態になれば、相続人間の関係は非常に悪化するため、十分に注意したいところです。
9.相続税の申告が間に合わない場合は期限後申告で
相続税の申告と納付は、ともに相続が開始してから10カ月以内におこなわなければなりません。しかし、事情によっては申告期限に間に合わないケースもあるでしょう。
申告に間に合わなかった場合でも、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。早く期限後申告をすれば、延滞税や無申告加算税などは、その申告時までの分で済みます。しかし、申告をしないまま放置すれば、延滞税などがどんどんふくらんでいく恐れがあるのです。
相続発生から6~8カ月後に税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届く場合があります。これは、一定以上の遺産があると見込まれる方に対して、相続税の申告を促す目的で送られる書類です。相続税のお尋ねが届いた段階で対応していれば、追徴課税を未然に防げる可能性があります。また、特例制度などを利用して、相続税を軽減できるかもしれません。
相続税についてのお尋ねが届いたら、ぜひ相続を専門としている税理士にご相談することをおすすめします。
10.まとめ:追徴課税を防ぐためにも、相続税申告は専門税理士に相談しよう
追徴課税は、相続税の申告の手続きミスや勘違いにより税額が過少だったと発覚することで、納める必要が出てくる税金です。故人が保有するすべての財産を洗い出し、評価するのには労力がかかります。脱税の意図がなくても、申告漏れや計算ミスが発生するのはめずらしいことではありません。
申告後に財産が新たに見つかったときは早めに修正申告をおこなうことで、追徴課税をおさえることができます。反対に「見つからないだろう」と放置していると、あとから多額の追徴課税を課されることがあります。
特例制度を活用して相続税を軽減させたいと考えている方は、要件が細かくなっているためとくに確認が必要です。他にも、相続財産が多い人は追徴課税も高額になるので、相続税の申告に注意しなければなりません。
誤りのない相続税申告のためには、相続税申告に慣れた専門税理士に申告書作成を依頼することが何よりも大切です。追徴課税を防止するためにも、豊富な実績を持つ相続税専門の税理士法人チェスターに、ぜひご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は84名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編






































