土地の生前贈与と相続どちらが得?【プロが解説】生前贈与の注意点
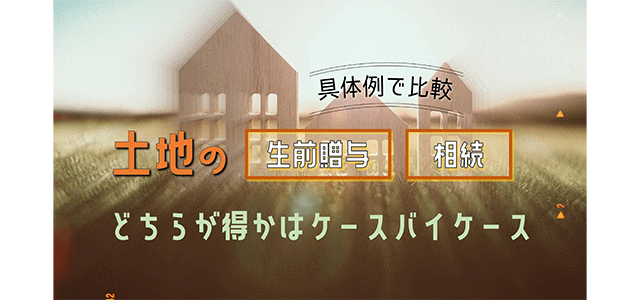
土地を生前贈与することによって相続財産が減少するため、相続税の節税につながります。
ただし贈与税の支払いもあるので、トータルで生前贈与と相続のどちらが得かはケースバイケースです。
登録免許税や不動産取得税も含めて考える必要もあります。
本記事では生前贈与と相続の税金を比較し、向き・不向きの具体的なケースもチェックしていきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.土地の生前贈与と相続はどちらがお得?税金の負担をチェック
土地を生前贈与した場合と、相続した場合、どちらが得かはケースバイケースとなります。なぜならそれぞれの資産の状況、取得する人との関係によって異なるためです。
生前贈与、相続それぞれの税金の非課税制度や特例を確認してみましょう。
土地の生前贈与と相続はどちらがお得?
1-1.ケース1:生前贈与では相続時精算課税制度の利用で2500万円まで贈与税がかからない
生前贈与をした場合、相続時精算課税制度を利用することで贈与税がかからない可能性があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親または祖父母から18歳以上の子や孫に対し贈与した場合に、令和6年1月1日以降は、毎年110万円までの基礎控除を適用した後に、累計2500万円まで贈与税の課税対象から控除できる制度のことをいいます。
仮に贈与者が死亡して相続が発生した場合には、贈与した財産の価額を贈与者(被相続人)の相続財産に加算し、相続税を計算します。

▲相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税と相続税
詳細については、以下の生前贈与のメリットに関する記事で詳しく解説しています。
資産の種類や受贈者との関係から、どの制度や特例が自分に適しているか慎重に検討することが大切ですので、ぜひ参考にしてみてください。
参考:不動産を生前贈与するメリットは?相続税節税対策・非課税にする方法と意外なデメリットを解説
1-2.ケース2:相続では控除や特例の利用で相続税額を抑えられる
相続では基礎控除や特例などの利用で相続税の納税額が軽減され、相続税の納税が不要となる場合があります。
相続税の課税対象となる課税価格が基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えていない場合は、相続税の申告と納税の手続が不要なためです。また、基礎控除以外にも、相続人の属性によっては以下のような相続税控除を適用することで、さらに相続税の納税額を軽減できます。
相続税控除の例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 贈与税額控除
参考:【相続税の控除】活用できる税額控除6選&その他の控除3選を紹介|税理士法人チェスター
また、土地(宅地)については、居住用・事業用・賃貸用などの利用状況等によって、相続税評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」を使える場合があります。
相続での基礎控除や特例などの利用で相続税の納税が不要になりそうな場合は、節税の観点からは生前贈与を検討する必要はありません。ただし、相続税控除などを適用し納税額が0円になった場合でも、税務署に対して税額控除や特例を適用した旨の申告が必要になることがあります。
1-3.ケース3:生前贈与か相続かで登録免許税の税率が異なる
生前贈与、相続どちらの場合も、不動産の名義変更時に登録免許税がかかります。不動産を取得した場合、法務局で不動産登記簿の所有者名義を変更する手続を行いますが、そのときに登録免許税を納付する必要があります。
生前贈与と相続の場合の登録免許税の税率は以下のとおりです。
| 登録免許税 | |
|---|---|
| 生前贈与 | 固定資産税評価額の2% |
| 相続 | 固定資産税評価額の0.4% |
生前贈与と相続の場合の登録免許税を比較してみましょう。
たとえば、所有している土地の固定資産税評価額が5000万円の場合、生前贈与と相続で比較すると、以下のとおり相続のほうが登録免許税を抑えられます。
| 登録免許税 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 生前贈与 | 100万円 | 5000万円×2% |
| 相続 | 20万円 | 5000万円×0.4% |
登録免許税を抑えたい場合は、相続で不動産を承継する方法を検討しましょう。
生前贈与、相続どちらの場合でも登録免許税を納税する必要があるため、事前に固定資産税の納税通知書(課税明細書)などで評価額を確認し、納税額がいくらくらいになるのか把握しておくことが大切です。
1-4.ケース4:生前贈与では不動産取得税を納付する
生前贈与の場合は、不動産取得税を納付する必要があります。不動産取得税とは、売買や贈与などで不動産を取得した人に対し課される税金のことで、不動産が所在する都道府県に納付します。相続・包括遺贈で不動産を取得した場合は納付する必要がありません。
不動産取得税の税率は以下のとおりです。不動産を生前贈与した場合には、不動産取得税を納付する必要があることに注意しましょう。
| 土地・家屋(住宅) | 家屋(非住宅) | |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額の3% (宅地は固定資産税評価額に1/2をかけた金額の3%) (令和9年3月31日まで) | 固定資産税評価額の4% |
1-5.【結論】生前贈与と相続のどちらが得かはケースバイケース
生前贈与と相続のどちらが得かはそれぞれの資産の状況、取得する人との関係によって異なります。また、登録免許税や不動産取得税などの金額は、生前贈与に比べ相続の方が抑えられますが、不動産の評価額によって変わります。
生前贈与をうまく利用して相続税も節税できるよう、特例や制度を理解したうえで生前贈与か相続のどちらが適しているのか検討することが大切です。
2.土地の生前贈与と相続で支払う税金を具体例で比較
土地の生前贈与と相続で支払う税金を、以下の具体例で比較してみましょう。父が子へ生前贈与した場合と、相続した場合で計算します。
2-1.ケース1:固定資産税評価額が5000万円の土地を生前贈与する場合
父が子(18歳以上)へ固定資産税評価額が5000万円の土地(宅地)を生前贈与した場合、以下の税金がかかります。
父が子(18歳以上)へ固定資産税評価額が5000万円の土地(宅地)を生前贈与した場合にかかる税金
- 贈与税
- 登録免許税
- 不動産取得税
金額と計算式は以下のとおりです。
| 税金 | 金額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 贈与税 | 2049万5000円 | (5000万円−110万円)×55%(速算表の税率)−640万円(控除額) |
| 登録免許税 | 100万円 | 5000万円×2% |
| 不動産取得税 | 75万円 | 5000万円×1/2×3% |
(贈与税算定に用いる相続税評価額は固定資産税評価額と同額の5000万円とし、相続税との比較を単純にするため、各特例や控除の適用はないものとして計算。)
贈与税は贈与として受け取った贈与財産の価額が、年間(1月1日~12月31日)で110万円を超える場合、原則として受贈者が申告し納付します。贈与をした人と贈与を受けた人の関係性により、財産を「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区別し、贈与税が課税されます。
| 税率 | 関係性 | 具体例 |
|---|---|---|
| 一般贈与財産 |
|
|
| 特例贈与財産 | 直系尊属から成年者への贈与 (贈与される年の1月1日に受贈者が18歳以上であること) |
|
父が子(18歳以上)へ相続税評価額が5000万円の土地を生前贈与した場合にかかる贈与税額は、贈与税の速算表を用いると以下計算式のとおり2049万5000円となります。
(贈与税は相続税評価額をもとに計算します。ここでは固定資産税評価額と同額の5000万円とします。)
| 贈与税額 | 計算式 |
|---|---|
| 2049万5000円 | (5000万円−110万円)×55%(速算表の税率)−640万円(控除額) |
参考:贈与税の速算表を使って試算しよう。一般税率と特例税率の違いは?|税理士法人チェスター
生前贈与を行った場合、贈与税の他に登録免許税と不動産取得税の納付が必要となります。税率は以下のとおりです。
| 税率 | |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額の3% (宅地は固定資産税評価額に1/2をかけた金額の3%) (令和9年3月31日まで) |
父から子(18歳以上)へ固定資産税評価額が5000万円の土地(宅地)を贈与した場合、以下の計算式のとおり、登録免許税は100万円、不動産取得税は75万円となります。
| 金額 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 100万円 | 5000万円×2% |
| 不動産取得税 | 75万円 | 5000万円×1/2×3% |
2-2.ケース2:固定資産税評価額が5000万円の土地を相続する場合
父が死亡し、子(相続人は1人)が固定資産税評価額5000万円の土地を相続した場合、以下の税金がかかります。
父が死亡し、子(相続人は1人)が固定資産税評価額5000万円の土地を相続した場合にかかる税金
- 相続税
- 登録免許税
金額と計算式は以下のとおりです。
| 税金 | 金額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 相続税 | 160万円 | (5000万円−(3000万円+600万円×1人))×15%(速算表の税率)−50万円(控除額) |
| 登録免許税 | 20万円 | 5000万円×0.4% |
(相続税算定に用いる相続税評価額は固定資産税評価額と同額の5000万円とし、贈与税との比較を単純にするため、各特例や控除の適用はないものとして計算。)
相続税の課税対象となる課税価格が、基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続人が申告し相続税を納付します。
相続税の課税対象となる課税価格が5000万円、相続人が1人の場合、1400万円(5000万円-3600万円)の部分について相続税が課税されることになるのです。
父が死亡し子(相続人は1人)が相続税評価額5000万円の土地を相続した場合、相続税の速算表を用いると相続税額は以下の計算式のとおり160万円となります。
| 相続税額 | 計算式 |
|---|---|
| 160万円 | (5000万円−(3000万円+600万円×1人))×15%(速算表の税率)−50万円(控除額) |
参考:【早見表】相続税の速算表を活用して税額を簡単に計算しよう!|税理士法人チェスター
土地を相続した場合、相続税の他に登録免許税がかかります。税率は以下のとおりです。
| 税率 | |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
父が死亡し、子(相続人は1人)が固定資産税評価額5000万円の土地を相続した場合、以下の計算式のとおり、登録免許税は20万円となります。
| 金額 | 計算式 | |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 20万円 | 5000万円×0.4% |
3.土地を生前贈与したほうがよいケース
土地の生前贈与を検討したほうがよいのは、以下のようなケースに該当する場合です。
土地を生前贈与したほうがよいケース
3-1.ケース1:相続人による遺産トラブルの発生が想定されるとき
将来遺産をめぐって相続人間でトラブルが発生しそうな場合は、土地の生前贈与を検討しましょう。贈与する相手と財産を自由に決められるため、相続が発生した場合の相続人間のトラブルを予防することができます。また、急病や事故などで思いがけず相続が発生し、譲りたい人に財産を承継することができなくなってしまったといった事態を避けることも可能です。
相続人間のトラブルを回避し、自分が財産を譲りたい人に財産を確実に承継できるよう、生前贈与を検討してみましょう。
3-2.ケース2:認知症などによる判断能力の低下が見込まれるとき
今後、認知症といった加齢による判断能力の低下が見込まれる場合は、生前贈与を検討しましょう。将来、判断能力が低下している状態で土地を売却する必要が発生しても、売却が困難になる可能性があるためです。
たとえば、親に介護が必要となり、親の所有している不動産を売却し、老人ホームへの入居を検討したとします。親の判断能力がほとんどない状態であった場合、不動産を売却することが困難になってしまうのです。建物が建っていた場合は空き家の問題も生じてしまう可能性があります。
将来土地の売却手続が心配な場合は、生前贈与を検討してみましょう。
3-3.ケース3:将来的に土地の評価額が上がると見込まれるとき
土地の資産価値が将来上昇し、評価額の上昇が見込まれる場合は生前贈与で節税につながる可能性があります。贈与税は贈与時、相続税は死亡時の評価額を基準に課税されるためです。
たとえば、現在の評価額が5000万円の土地を所有していたとします。現時点で生前贈与をおこなえば受贈者は5000万円に対し贈与税を支払うことになります。しかし、この土地を生前贈与せず相続時に土地の相続税評価額が2億円になっていた場合は、相続人は2億円に対し相続税を支払うことになります。
将来的に土地の評価額が上がると見込まれる場合は、生前贈与の方が税額を抑えられる可能性があるのです。この場合、通常の贈与税(暦年贈与)の負担は高額になりますので、あわせて「相続時精算課税制度」による贈与を検討することとなります。
3-4.ケース4:特定の人に土地を分与したいとき
生前贈与であれば、財産を所有する本人の意思で財産を受け取る人(受贈者)や渡すタイミングを選ぶことができます。特定の人に土地を渡したいのであれば、生前贈与をするとよいでしょう。
たとえば、所有する土地を弟に引き継ぎたいと考えているとしましょう。自身には配偶者がおり、また両親も健在であるため、相続では弟に土地を引き継ぐことができません(遺言書により指定している場合を除きます)。
そこで、生前贈与をすると、相続では取得が困難な弟に土地を引き継ぐことができます。
また、生前贈与は財産を渡す人に制限がないため、双方の合意があれば配偶者や親族ではない人に土地を譲ることも可能です。血縁関係はないものの、お世話になった人に土地を渡したいと考えているのであれば、生前贈与を検討してはいかがでしょうか。ただし、遺言により相続人でない人に財産を承継する方法(遺贈)もありますので、あわせて検討しましょう。
4.土地を相続したほうがよいケース
土地を相続で承継することを検討したほうがよいのは、以下のようなケースに該当する場合です。
土地を相続したほうがよいケース
4-1.ケース1:相続財産の評価額が基礎控除に満たないとき
相続税の課税対象となる課税価格が、基礎控除額(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えていない場合は相続での承継をおすすめします。相続税が発生しないため、節税のために生前贈与を検討する必要がない可能性があります。
生前贈与で特例や制度を利用しない場合、贈与として受け取った贈与額が年間(1月1日~12月31日)で110万円を超えると贈与税がかかることになります。
事前に相続税の課税対象となりそうな遺産額を把握し、相続と生前贈与のどちらを利用するべきか確認することが大切です。
4-2.ケース2:小規模宅地等の特例による節税効果を得たいとき
小規模宅地等の特例による節税効果を得たいときは、相続での承継をおすすめします。生前贈与を行うと、相続税の計算において小規模宅地等の特例が利用できなくなるためです。
被相続人が住んでいた自宅の土地や事業をしていた土地などを相続した場合に、小規模宅地等の特例の要件を満たすと、相続した土地の評価額を最大80%減額することができます。小規模宅地等の特例を利用し、相続税評価額を減らすことで、相続税を節税することが可能です。しかし、生前贈与することで、小規模宅地等の特例が利用できなくなります。宅地の利用状況や取得者によって適用要件が異なります。
自宅(居住用)であれば、小規模宅地等の特例は、取得者が以下の3つのうち1つにあてはまることが要件となります。
小規模宅地等の特例(居住用)が利用できる取得者
- 被相続人の配偶者が土地を相続
- 被相続人と同居していた親族が土地を相続
- 被相続人に配偶者も同居の親族もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得
小規模宅地等の特例によって相続税を節税したい場合は、適用対象から外れないように適用要件を確認しておくことが大切です。
4-3.ケース3:土地を渡す相手を指定したいとき
「元気なうちは自分自身で管理をしたい」などの理由で生前贈与を希望しない人が、特定の人に土地を渡したいときは、遺言書を作成する方法があります。
相続では亡くなった人の意思が尊重されるため、基本的に遺言書に記載された内容に沿って遺産が引き継がれます。土地を相続させたい人が決まっているのであれば、遺言書で指定しておくとよいでしょう。
遺言には、自筆で作成する「自筆証書遺言」や公証人が関与して作成する「公正証書遺言」などの種類があります。遺言には法律で定められた形式があり、不備があると効力を発揮しません。自署で作成する自筆証書遺言では、不備が発生して無効となるリスクが高まります。
その点、公正証書遺言は作成時に費用がかかりますが、公証人に確認してもらうため無効となるリスクが低く、紛失や偽造などの心配もありません。遺言書が無効となるリスクを抑えたいのであれば、公正証書遺言の作成を検討するとよいでしょう。
公正証書遺言書について詳しくは、以下の記事をご一読ください。
(参考)公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説
5.マンションは生前贈与と相続どちらが得?
相続する不動産がマンションである場合、生前贈与と相続のどちらで承継すると良いのでしょうか。マンションの承継における、生前贈与と相続それぞれのメリットをみていきましょう。
5-1.マンションを生前贈与するメリット
マンションを生前贈与する主なメリットは、以下の2点です。
- 承継する人を選べる
- トラブルのリスクを回避できる
1つずつみていきましょう。
5-1-1.承継する人を選べる
生前贈与であれば、マンションを贈与する人がもらう人を自由に選べます。
たとえば、マンションを所有している父親に長女と次女がいたとしましょう。父親は介護が必要な状態であったため、同居する次女が献身的に世話をしてくれました。
一方で、長女は離れて暮らしており、父親と連絡を取ることもあまりありません。
そのため、父親は献身的に介護をしてくれている次女にマンションを渡したいと考えています。しかし、何も対策することなく父親が亡くなって相続が発生すると、長女はマンションを相続したいと言い出すかもしれません。
父親は次女にマンションを生前贈与することで、相続財産に含まれなくなるため、長女に取られにくくなるでしょう。
5-1-2.トラブルのリスクを回避できる
マンションが相続財産に含まれていると、相続人同士でトラブルに発展することも考えられます。マンションをはじめとした不動産は、現金や有価証券などの財産と比較して分割しにくいためです。
マンションを売却して現金化したうえで分割する方法もありますが、都合良く買い手が見つかるとも限りません。また、売り急いでしまい、購入希望者に足元を見られて相場よりも安値で売却してしまうかもしれません。
マンションを共有状態にして相続するという方法もあります。しかし、物件の管理や売却などの方針で共有者の意見が合わずに、相続人間でのトラブルに発展してしまうかもしれません。
マンションを生前贈与して相続財産に含まれないようにすると、不動産の相続時に発生するトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
5-2.マンションを相続するメリット
マンションを相続する主なメリットは、以下の3点です。
- 基礎控除額内であれば相続税がかからない
- 小規模宅地等の特例を適用できる
- 相続したときの評価額で課税される
1つずつ解説します。
5-2-1.基礎控除額内であれば相続税がかからない
マンションの評価額を含む遺産総額が、相続税の基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人)」の範囲内であれば、相続税はかかりません。
一方で、生前贈与の場合、マンションの評価額が110万円を超えると贈与税が発生します。マンションの多くは評価額が110万円を超えるため、相続時精算課税制度を利用しない限り、生前贈与をすると高い確率で贈与税が発生してしまうでしょう。
そのため、マンションを含む遺産総額が相続税の基礎控除額の範囲内であり、生前贈与をする特別な理由がない人は、相続でマンションを渡したほうが税負担は少なくて済むでしょう。
5-2-2.小規模宅地等の特例を適用できる
被相続人が住んでいたマンションや、貸付事業を営んでいたマンションを相続する場合は、所定の要件を満たすと小規模宅地等の特例を適用できます。
小規模宅地等の特例が適用されると、マンションの土地(敷地権)部分の相続税評価額が減るため相続税の負担を軽減することが可能です。
具体的には、被相続人が住んでいたマンションを相続した場合は、土地部分の相続税評価額が330㎡まで80%減額されます。また、被相続人が貸付事業を営んでいたマンションを相続した場合は、200㎡まで50%減額されます。
小規模宅地等の特例の要件を満たせるのであれば、相続でマンションを引き継いだほうが税負担を抑えることが可能でしょう。
5-2-3.相続したときの評価額で課税される
相続税と贈与税は、どちらも相続税評価額をもとに計算します。マンションをはじめとした不動産は、基本的には時間が経つにつれて価値が低下していくため、それにともなって相続税評価額も下っていくのが一般的です。
そのため「生前贈与をしたものの、相続の発生時にはマンションの価値が下がっており、相続したほうが税負担は少なく済んだ」という事態も起こりえます。急いでマンションを贈与すべき理由がないのであれば、相続でマンションを引き継いだほうがよいでしょう。
6.生前贈与をするときの注意点
不動産を生前贈与するときの主な注意点は、以下のとおりです。
1つずつみていきましょう。
6-1.相続開始前の一定期間に贈与された財産は相続財産に含めなければいけない
相続税を計算する際、相続が開始される前の3年以内(※)に、相続人が生前贈与で取得した財産は相続財産に加算されます。これを「生前贈与加算」といいます。
そのため、配偶者や子などに生前贈与をしたとしても、相続が発生する3年以内(※)に贈与された財産の価額については、相続税を計算する際に含めて計算しなければなりません。
(※)令和6年(2024年)1月1日以降の贈与については、生前贈与加算の対象となる期間が段階的に延長されていき、最終的に相続開始前の7年間となります。
ただし、生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前の一定期間に相続人に対して行われた贈与です。孫や甥、姪など相続人にならない人に行われた生前贈与は、加算の対象になりません。
相続対策のために生前贈与をするときは、相続税専門の税理士にも相談のうえ、生前贈与加算の仕組みを理解することが大切です。
生前贈与加算の制度内容や令和6年以降の取り扱いなどは、以下の記事をご覧ください。
(参考)相続開始前3年(7年)以内の贈与は相続税の対象になる!? 相続時加算される贈与とは?
(参考)生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説
6-2.贈与契約書などの書面が必要
贈与契約は口頭でも成立しますが、できる限り贈与契約書を取り交わすことをおすすめします。贈与契約書があると、実際に贈与が行われたことの証拠になるためです。
不動産の贈与を受けて、法務局で不動産登記簿の所有者名義を変更する手続をする場合は、贈与契約書を添付します。贈与契約書がない場合は、契約の内容を記載した書面を別途作成する必要があります。
贈与契約書に記載すべき項目は、以下の通りです。
- いつ贈与するのか(贈与契約締結日や贈与履行日)
- 誰が贈与するのか(贈与者の住所と氏名)
- 誰が贈与されるのか(受贈者の住所と氏名)
- 何を贈与するのか(贈与財産に関する情報)
贈与契約書は2通作成し、贈与した側と贈与された側で保管をしておきましょう。また、贈与契約書に押印をする印鑑は、実印をおすすめします。実印のほうが、認め印よりも契約書に信憑性を持たせられるためです。
贈与契約書を作成する際は、以下の記事で書き方をご確認ください。
(参考)【雛形つき】贈与契約書とは?書き方・生前贈与の注意点を解説!
6-3.定期贈与とみなされることがある
贈与税の基礎控除額である110万円以内で暦年贈与をしたとしても、税務署から定期贈与(連年贈与)とみなされると課税の対象になる可能性があります。定期贈与とは「毎年100万円を10年間にわたって贈与する」のように、一定期間にわたって一定の財産を贈与する契約のことです。現金を贈与するときに使われる方法ですが、不動産の持分を少しずつ贈与する場合もあります。
年間100万円を10年間にわたって贈与する場合、年間の贈与額は基礎控除額の範囲内であるため、贈与税はかかりません。しかし、定期贈与とみなされると「100万円×10年間=1,000万円」を贈与する契約であったと解釈され「1,000万円−110万円=890万円」に対して贈与税がかかります。
定期贈与とみなされないようにするためには、財産を贈与するたびに贈与契約書を取り交わすことが大切です。また、同じ時期に同じ金額を贈与していると定期贈与とみなされやすくなるため、贈与する時期や金額を変えるのも一つの方法です。
生前贈与をする際は、税理士にも相談のうえ、定期贈与とみなされないようにするとよいでしょう。
定期贈与については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。
(参考)定期贈与(連年贈与)とみなされない3つの回避方法とは?
7.土地を生前贈与するか相続するかどちらが得か不安が残るなら専門家へ相談を
不動産の生前贈与は相続財産の減少による相続税の節税になるだけでなく、非課税枠や特例を適用することで贈与税を抑えられる場合があります。しかし、状況によっては相続で財産を承継したほうが税金を抑えられる場合もあるのです。相続税の課税対象となる財産を事前に把握し、生前贈与と相続どちらが適しているか想定したうえで財産の承継を検討することが大切です。
相続税と贈与税の負担を抑える確実な相続対策を行うためには、相続を専門とする税理士に相談することをおすすめします。
相続税や贈与税の負担が心配な場合や、特例が適用できるかといった判断が難しい場合は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。贈与に詳しい専門税理士に任せることで、不安を解決できるでしょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































