土地を名義変更すると親子間でも贈与税が発生する-相続税との比較も
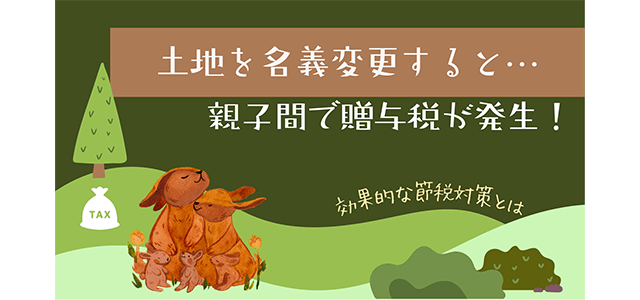
親子間でも、土地を名義変更すると贈与税がかかります。土地の名義を子に変えたときは、そのときの土地の価格に贈与税が課され、納税しなければなりません。
通常、土地は高価であるため贈与税の基礎控除や相続時精算課税制度などを適用しても、贈与税を支払う場合が少なくありません。贈与税率は相続税率に比べて高いため、土地を生前に贈与するかどうか、相続と比較検討することも大切です。
この記事の目次 [表示]
1.親子でも土地の名義変更をすると贈与税がかかる
贈与税にいう「贈与」とは、個人が財産を渡すことです。したがって、他人のみならず親子間で財産の授受があった場合も、贈与税が発生します。親子間で土地の名義を変更することも贈与にあたり、贈与税課税の対象になるため注意しましょう。
1-1.年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる
贈与税の申告方式は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つで、原則的には暦年課税が用いられます。暦年課税の場合、年間110万円までの贈与であれば非課税であり、110万円を超えた分に対し贈与税がかかります。年間の贈与額が110万円以下の場合は税務署への申告も不要です。
110万円を超えた場合は、税務署へ申告し贈与税を納めなければなりません。
仮に、親から子に1000万円を贈与するとします。一度に1000万円を贈与すると年間の贈与額が110万円を超えてしまうため、贈与税がかかってしまいます。
これに対し、1年に100万円ずつ贈与すれば年間110万円以下になるため贈与税はかかりません。土地の場合は、持分を毎年少しずつ贈与していく方法があります。
参考:生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!注意点や節税対策を解説
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
2.土地の贈与税の節税対策
親子間での土地の名義変更にも贈与税がかかりますが、なるべく課税額を少なくする方法もあります。土地の贈与税の節税対策法は以下のとおりです。
土地の贈与税の節税対策法2つ
- 暦年課税制度を選択
- 相続時精算課税制度を選択
これら2つの制度では、贈与額に対する控除額があります。贈与額の合計や制度の利用条件を加味したうえで、どちらの制度を利用するか検討するとよいでしょう。
2-1.暦年課税制度-基礎控除の範囲内で数年にわたり贈与する
暦年課税制度とは、一人が1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額のうち110万円を超える部分につき贈与税を課税する制度です。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
土地の場合、持分を分けて贈与することで年間の贈与額を110万円以下に抑えられます。例えば、2000万円の土地を贈与したい場合、持分を毎年20分の1ずつ20年かけて贈与すれば贈与税はかかりません。
注意点としては以下の点が挙げられます。
暦年課税方式で土地を贈与する際の注意点
- すべての持分を贈与するまで時間がかかる
- 贈与契約書や持分の変更登記などの手間がかかる
- 暦年課税制度自体が改正される可能性がある
契約書や登記は、税務署に贈与の成立を認めてもらうために必要です。贈与として認められないと、親が亡くなった場合に相続税の対象となってしまうため注意しましょう。
参考:暦年贈与とは?廃止は見送りに。活用方法と注意点、7つの対策を解説
2-2.相続時精算課税制度-親子だからできる贈与税の節税手段
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(2022年3月31日以前の贈与については20歳)以上の子または孫などに財産を贈与した場合に選択できる制度です。
相続時精算課税制度であれば、贈与財産の合計額のうち2500万円までは贈与税がかかりません。(2024年以降は、年間110万円の基礎控除が適用されます。)
例えば、親から子へ4000万円の財産を贈与した場合の税額は以下のとおりです。
【2024年以降に贈与した場合】(年間110万円の基礎控除(注)を適用)
4000万円-110万円(基礎控除額(注))-2500万円(特別控除額)=1390万円
1390万円×20%=278万円(贈与税額)
(注) 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で按分します。
【2023年以前に贈与した場合】(基礎控除なし)
4000万円-2500万円(特別控除額)=1500万円
1500万円×20%=300万円(贈与税額)
相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税制度は選択できません。また、税務署への申告が必須であることに注意しましょう。(2024年以降は、年間110万円以下であれば申告不要です。)
参考:相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!
3.生前贈与の名義変更で贈与税以外にかかる費用
不動産の名義変更をした際にかかる費用は、贈与税だけではありません。他にも以下の費用が発生します。
土地の名義変更で贈与税以外にかかる費用
- 不動産取得税
- 登録免許税
- 司法書士への報酬
親子間で土地の名義変更をおこなう際は、これらの費用がかかることを前提のうえ、贈与税の軽減対策について考えることをおすすめします。
3-1.不動産取得税-不動産を取得するとかかる税金
不動産取得税とは、不動産を取得した人、つまり名義を変更したあとの所有者に課税される道府県税です。不動産の所有者が不動産のある都道府県に納税します。
税率は以下のとおりです。
| 税率 | 標準は4%、土地と住宅は3% (2027年3月31日までの取得に限る) |
|---|---|
| 住宅用地の特例 | 住宅用地、商業地等の取得は課税標準としての価格を評価額の1/2で計算 (2027年3月31日までの取得に限る) |
参照:不動産取得税|総務省
税額の計算の元となる不動産の額には、固定資産税評価額が用いられます。固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に載っている額のことで、販売価格ではありません。不動産取得税は「固定資産税評価額×税率」で算出できます。
基本的な計算方法は以下のとおりです。
(2)土地(住宅用地):固定資産税評価額×1/2×3%
(1)+(2)=不動産取得税
不動産取得税は、都道府県ごとに細かくルールが定められています。税率や軽減措置、手続に関する決まりなど役所の公式サイトもしくは窓口で確認しましょう。
参考:相続した不動産に不動産取得税はかかる?他の税金や注意点について解説
3-2.登録免許税-名義変更登記の際にかかる税金
土地の名義変更をした際は、登録免許税を納める必要があります。登録免許税とは、新たに取得した不動産の所有権を法務局に登録するために必要な税金です。
登録免許税の税額は「(土地の)固定資産税評価額×税率」で計算が可能です。税率は不動産の種類や不動産の取得理由によって異なります。
| 不動産の取得理由 | 税率 |
|---|---|
| 相続 | 0.4% |
| 贈与 | 2% |
| 財産分与 | 2% |
| 売買 | 1.5% (2026年3月31日までの間に登記を受ける場合。本則は2%) |
なお、建物の名義変更についても、税率は同様です。ただし、個人が2027年3月31日までの間に土地と一緒に住宅用家屋を購入し、自分の居住用にする場合は、税率が2%から0.3%に軽減されます。
参考:相続登記にかかる登録免許税とは?免税措置/計算方法/納付まで徹底解説
3-3.名義変更を司法書士に依頼する場合の費用
土地の名義変更を登記のプロである司法書士に依頼する場合、報酬を支払う必要があります。報酬の相場は、典型的な名義変更であれば6~10万円程度です。
注意すべきは、司法書士報酬は完全に自由化されているため、司法書士事務所によって報酬額に差が生じる点です。また、土地の数が複数だったり権利関係が複雑だったりした場合、報酬も高くなる可能性があります。
司法書士に依頼する際は、一度見積もりを作成してもらうようにしましょう。
参考:相続登記にかかる司法書士の報酬はいくら?その他の費用の相場も徹底紹介
4.生前贈与と相続はどちらが得か-相続による名義変更は贈与より税金面で優遇される
土地の取得について贈与と相続のどちらが得かについては、双方の前提が異なるため一概に決められません。
贈与と相続では、次のとおり性格の違いがあります。
| 贈与 | 財産を少しずつ分けて渡していくことが前提 |
|---|---|
| 相続 | 全財産を一度に渡すことが前提 |
相続税のほうが税率が低くなっているため、財産を一度に渡すことを考えると相続のほうが課税額を低く抑えられます。一方、親が生前のうちに贈与税がかからない程度の額で土地の持分を少しずつ渡していけば、贈与税および相続税を節税することが可能です。
したがって、贈与と相続のどちらが得かは、ケースによりけりです。親子間の関係や財産状況を考慮し検討しましょう。
4-1.相続税には3600万円の基礎控除がある
相続税には、課税対象となる相続財産の総額のうち、一定の額であれば課税対象にならない基礎控除が認められています。
そのため、相続財産の総額が基礎控除額を下回れば相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。
言い換えれば、法定相続人が1人の場合でも3600万円の基礎控除があり、法定相続人の数で最終的な基礎控除額が変わります。
例えば、相続財産5000万円を法定相続人2人が相続した場合、相続税がかかる額は以下のとおりです。
5000万円-4200万円=800万円(相続税がかかる額)
この例の場合、相続財産が4200万円以下であれば相続税はかかりません。
参考:相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法
4-2.相続税の税率は贈与税より低い
相続税と贈与税の税率を比較した場合、相続税の税率のほうが低く設定されています。
しかし、税率が低いからといって必ずしも相続のほうが得とは限りません。生前贈与の場合、財産を一度にすべて贈与するのではなく、少しずつ贈与すれば1回の贈与額を抑えて税金をかけずに済むこともあります。
相続税と贈与税の税率はそれぞれ以下のとおりです。
相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | ― |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
贈与税の税率(親から成人した子への贈与(特例贈与財産)の場合)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
参照:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
例えば、親(配偶者はすでに死亡)の財産5000万円を子2人が相続したケースを、相続した場合と贈与した場合の税額で比較すると、以下のとおりです。
| 相続した場合 |
|---|
| 3000万円+(600万円×2人)=4200万円(基礎控除額) 5000万円-4200万円=800万円 800万円×1/2=400万円(子1人の法定相続分) 400万円×10%-0円(控除額なし)=40万円(子1人あたりの相続税額) 40万円×2人=80万円 |
| 全体で80万円の相続税が課税 |
| 贈与した場合 |
|---|
| ※子2人が1年に2500万円ずつ贈与を受けた場合 2500万円-110万円=2390万円(暦年課税制度) 2390万円×45%-265万円=810.5万円(子1人あたりの贈与税額) 810.5万円×2人=1621万円 |
| 全体で1621万円の贈与税が課税 |
相続した場合と贈与した場合を比べると1541万円の差がつき、相続のほうが得しているように思えるかもしれません。
しかし、1年間の贈与額を暦年課税制度の基礎控除額である110万円以下に抑えて少しずつ贈与すれば、贈与税額をゼロにできます。
ただし、相続開始前の一定期間の贈与については、相続財産に加算されるため注意しましょう。生前贈与で節税をしたいなら、早めに取り組むことが重要です。
参考:贈与税の基礎控除はいくら?計算方法・節税対策・併用できる特例・注意点を解説
4-3.条件によっては小規模宅地等の特例が適用され相続税を下げられる
親から子へ土地の相続があったとき、「小規模宅地等の特例」が適用され相続税額を減らせる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、故人が居住していた土地や事業をおこなっていた土地について一定の条件を満たす場合は、土地の相続税評価額を80%または50%まで減額する制度です
参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
故人の自宅がある土地の相続税評価額が5000万円の場合、小規模宅地等の特例が適用されたら、評価額1000万円で相続税を計算できます。
故人の居住用地や事業用地は、相続人にとっても生活基盤となる重要な財産です。そこへ相続税を最大限に課してしまうと相続人の生活を脅かす可能性があるため、相続税の大幅な軽減措置が用意されています。
参考:小規模宅地等の特例の計算方法と具体例。土地別にみる減額計算
4-4.相続の場合は不動産取得税と登録免許税も少なくて済む
不動産取得税の課税対象である「取得」に「相続」は含まれていないため、原則として相続によって不動産を受け継いだ場合に不動産取得税はかかりません。ただし、相続の方法によっては不動産取得税が発生します。例外的に不動産取得税が発生するケースは以下のとおりです。
相続において不動産取得税が発生するケース
- 法定相続人以外が特定遺贈を受けた場合
- 死因贈与を受けた場合
特定遺贈とは、遺言で特定の財産を指定して譲り渡すことをいいます。
参考: 民法964条|e-GOV法令検索
親が亡くなった場合、子は第一順位の法定相続人であるため、法定相続人以外への特定遺贈による不動産取得税の課税には当てはまりません。
死因贈与とは「私が死んだらこの土地をあなたに差し上げます」というように、死亡を原因とする贈与契約のことです。あくまで契約であり相続ではないため、不動産取得税の課税対象になります。
また、登録免許税については、相続による土地の所有権移転登記の場合、税率は0.4%です。
売買や贈与などは税率2%であることと比較すると、相続の場合は登録免許税が少なく済むといえます。
5.親子間で土地を名義変更する際の贈与税の計算から納付までの流れ
親子間で土地の名義変更をしたら、贈与税を算出して決められた期間内に納付する必要があります。贈与税の計算から納付までの流れは次のとおりです。
贈与税の計算から納付までの流れ
- 土地の贈与財産としての価格を調べる
- 贈与税額の計算式に当てはめて計算する
- 贈与税の申告
- 贈与税を税務署に納付する
贈与税の計算は、贈与などによって得た不動産の価額を評価することから開始します。このときの価額は売買時の価額ではないことに注意しましょう。
5-1.土地の贈与財産としての価格を調べる
土地を贈与した場合の贈与税を計算するにあたっては、まず、土地の贈与財産価額を調べます。一般的な調査方法に「路線価方式」と「倍率方式」があり、違いは以下のとおりです。
| 路線価方式 | 路線価が定められている地域での評価方法。道路に面する宅地1平方メートルあたりの価格(路線価)に面積をかけて計算 |
|---|---|
| 倍率方式 | 路線価が定められていない地域の評価方法。土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算 |
路線価は土地の公示価格の80%が目安になっており、毎年1月1日が基準です。7月初旬に国税庁により発表されます。
また、贈与財産価額は土地の販売価格ではない点に注意しましょう。
参考:路線価方式と倍率方式
5-2.贈与税額の計算式に当てはめて計算する
土地の贈与財産価額がわかったら、計算式に当てはめて贈与税額を計算します。使用する計算式は以下のとおりです。
土地の贈与税額を計算するにあたっては、路線価方式で算出した財産価額と倍率方式で算出した財産価額とで計算方法に違いはありません。
5-2-1.土地の贈与税の計算シミュレーション
贈与税の税率は、贈与額が大きいほど高くなります。土地の贈与財産価額が1億円の場合、贈与税額は以下の計算になります。
(親から成人した子への贈与(特例贈与財産)に対する税率を適用)
贈与税の税率や控除額は、「4-2.相続税の税率は贈与税より低い」に掲載しています。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
参考:不動産の贈与税の計算シミュレーション-土地・贈与税を安く抑える方法
5-3.贈与税の申告
贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税を申告しなければなりません。
申告の方法には以下のものがあります。
贈与税の申告方法
- 郵便もしくは信書便による送付
- 税務署の時間外収受箱への投函
- e-Tax(インターネット)
自分が申告すべき税務署がわからない場合は、国税庁のサイトで確認できます。申告の期限を過ぎると延滞税や加算税が課されてしまい、節税対策の意味がなくなります。贈与税の申告は必ず期限内におこないましょう。
5-4.贈与税を税務署に納付する
贈与税の申告とは別に税金の納付手続が必要です。納付方法には以下のものがあります。
贈与税の納付方法
- 納付書(税務署・金融機関で納付)
- ダイレクト納付(e-Tax)
- インターネットバンキング
- クレジットカード
- スマホアプリ
- コンビニエンスストア
贈与税は、原則として期限までに一括納付しなければなりません。ただし、期限までに納付することが困難な場合は、一定の条件を満たすことで最長5年間の分割納付(延納)が可能です。
贈与税の分割納付(延納)が認められるための条件
- 納付税額が10万円超であること
- 金銭で一度に納付することが困難な理由があること
- 担保を提供すること
参照:延納・物納申請等|国税庁
なお、延納する場合は贈与税の他に利子税がかかります。
贈与税は所得税のように毎年申告するものではないため、手続に戸惑う人も多いでしょう。手続のやり方がよくわからない場合は、税理士法人チェスターへご相談ください。贈与税を正確に申告するためのお手伝いをします。また、延納についてのご相談も承ります。
6.土地の名義変更の必要書類
親の財産である不動産の名義を子に変更するためには、法務局に対し登記申請する必要があります。名義変更は、第三者に対して不動産の所有者の権利を主張するために必要です。親子の贈与の意思表示だけでは、子が新たな所有者になったことを他の人たちへアピールできません。すると、子がもらい受けた土地を売りに出したり担保にしたりできなくなってしまいます。
したがって、第三者に権利を主張するために名義変更が必要です。贈与した不動産の名義変更手続に必要な書類は、以下のとおりです。
| 贈与する人 | 不動産の登記識別情報通知(登記済権利証) 印鑑証明書(3ヵ月以内のもの) |
|---|---|
| 贈与される人 | 住民票 |
| その他 | 固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) 贈与契約書、贈与証書など(贈与があった事実を証明できるもの) |
登記申請は、不動産を管轄している地域の法務局に申請します。遠方からでもインターネットで手続が可能です。
なお、2024年4月1日から不動産の名義変更(相続登記)が義務づけられ、3年以内に名義変更をする必要があります。同日以降に相続する不動産のほか、過去に相続した不動産も対象です。
7.親子間での土地相続の名義変更で起こるトラブル
法定相続人たちの理解を得られない生前贈与は、親の死後に相続でもめる可能性もあります。主に考えられるトラブルは以下の2点です。
土地の生前贈与で起こりうるトラブル
- 土地の名義変更をされた子の相続時の取り分が減る
- 他の相続人から金銭を請求される
民法では、特定の相続人だけに利益が生じた場合に、他の相続人との公平を図る制度を定めています。子が親から土地の贈与を受けた場合、相続時の取り分が減ったり、他の相続人から金銭を請求される可能性があることに留意しましょう。
7-1.土地の名義変更をされた子の相続時の取り分が減る
民法には特別受益の制度が定められています。
特別受益とは、特定の相続人が故人から多額の生前贈与を受けた場合の利益を指します。この場合、相続人間の公平のために、特別受益分を相続財産に含めて最終的な相続分を決定するのが特別受益の制度です。
例えば、被相続人に子A、Bの2人の相続人がおり、相続財産が5000万円のケースで、親が生前子Aに対して2000万円の土地を贈与していたとします。子Aに対する贈与を特別受益として計算した最終的な相続分は、以下のとおりです。
子Aの相続分:(5000万円+2000万円)×1/2-2000万円=1500万円
子Bの相続分:(5000万円+2000万円)×1/2=3500万円
このように、特別受益を受けたと認められる相続人は、他の相続人よりも相続分が少なくなります。
特別受益に該当する贈与は「遺贈」「婚姻もしくは養子縁組もしくは生計の資本」です。不動産の場合、子の居住のためなど生計の資本といえるものであれば特別受益にあたります。
7-2.他の相続人から金銭を請求される
子が親から土地の生前贈与を受けていた場合、親の死後に他の相続人から「遺留分侵害があった」として金銭を請求される可能性があります。
「遺留分」とは、一定の相続人に対して遺言によっても奪うことのできない遺産の留保分です。
特定の相続人に全財産を相続させるといった遺言により、他の相続人の遺留分が侵害された場合に、自身の遺留分を請求できることを「遺留分侵害額請求」といいます。相続により生じた侵害だけでなく、生前贈与に対しても可能です。
相続人が婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与を受けていたと認められる場合は、相続開始前10年間におこなわれた贈与に限って遺留分侵害額請求ができます。
親から子への土地の贈与であれば、生計の資本であると認められる可能性が高いでしょう。
なお、贈与者である親と贈与を受けた子が、あらかじめ遺留分を侵害することを知っていたうえで贈与をおこなった場合は、相続開始前10年よりもさらにさかのぼった贈与についても遺留分侵害額請求の対象です。
参考:遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?備える方法・計算方法・時効・手続きの流れを紹介
8.できるだけ税金を抑えて親子間で土地の名義変更をするには専門家に相談を
親から子へ土地を贈与する場合、まずは贈与税がいくらになるのか計算する必要があります。また贈与税以外にも税金がかかるため、親子間での土地の名義変更については贈与税や相続税に詳しい専門家に手続を依頼しましょう。
税理士法人チェスターであれば、節税対策に詳しい税理士が複雑な手続をスムーズかつ最適な方法でおこなえるようサポートします。
また、土地の名義変更の手続に不安がある場合は、司法書士にご相談ください。司法書士法人チェスターであれば、名義変更の手続の代行はもちろん、将来のトラブル防止を見すえた土地の譲渡方法を提案いたします。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編






































