遺産の不動産は名義変更が必須!方法・費用・期限を解説

遺産として不動産を相続したら名義変更を行いましょう。現時点で名義変更は任意のため期限は設けられていません。しかし2024年から義務化され、過去にさかのぼって罰則の対象となります。手続きの方法を確認し、確実に不動産の名義変更を行いましょう。
この記事の目次 [表示]
1.故人の土地や建物を相続するには

故人が土地や建物といった不動産を保有していた場合、相続人は遺言書に従い引き継ぐか、遺産分割協議で分割割合を決定します。代表的な4種類の分割方法について確認しておくと、不動産の分割時に役立つはずです。
1-1.遺言書がある場合
故人が遺言書を残していたなら、その内容に従い不動産を分割します。相続時には故人の意思が尊重されます。遺言書が正しい方法と書式で作成されたものであれば、その内容に従い手続きするのが原則です。
遺産の中に不動産があるなら、遺言書には誰にどのような割合で不動産を相続させるか記載されています。
遺言書に従い不動産の相続を実施するなら、名義変更のために実施する相続登記は、不動産を取得する相続人のみが行えば問題ありません。
遺産分割協議の実施時には、遺産分割協議書へ相続人全員の実印による押印が必要です。不動産を相続しない相続人にも協力してもらわなければいけません。
一方、遺言書がある場合には、不動産の相続をしない相続人は押印も不要です。
1-2.遺産分割協議で相続の範囲を決める場合
相続人全員が集まり遺産の分け方を話し合う『遺産分割協議』を実施する際には、不動産の分割割合を決めなければいけません。不動産の分割には以下の4種類の方法があります。
- 代償分割:相続人のうち1人が不動産を引き継ぎ、他の相続人には不動産を等分した場合に相当する現金を支払う
- 換価分割:不動産を売却して得た現金を相続人で等分する
- 現物分割:不動産を分割し相続する
- 共有分割:相続人全員の共有財産とする
4種類の方法はどれを採用してもメリット・デメリットがあるものです。例えば代償分割を選べば、不動産を手放さずに済みますが、引き継ぐ相続人の金銭的な負担が大きくなってしまいます。
1-2-1.共有は避けたい理由
中でも不動産の『共有分割』は避けた方がよいでしょう。共有すると、相続人全員が自身の持ち分に応じて不動産の所有者となります。
そのため権利関係が複雑になり、賃貸に出して活用することも、売却して現金にすることも難しくなってしまいます。例えば賃貸物件として貸し出そうとした場合、所有者である相続人全員の同意が必要です。
その後の管理にも、持ち分価格が過半数になる人数の同意を得なければいけません。手続きの手間が増えるため、不動産の活用を諦めざるを得ないケースもあるでしょう。
2.土地や建物の名義変更は必要?

相続で土地や建物を取得したときには、『名義変更』の手続きにあたる『相続登記』を実施しましょう。手続きを実施する法務局をチェックしておくとスムーズです。また手続きに慣れていない人や、複雑な相続登記なら司法書士に任せるとよいでしょう。
2-1.令和6年より相続登記が義務化
相続登記は現時点では義務ではなく、期限も定められていません。しかし2024年4月1日からは、相続による不動産の取得を知ってから『3年以内』の相続登記が義務化されます。
過去の相続も対象となるため、2024年4月1日より前に故人より引き継いだものの相続登記していない不動産も対象です。義務化は、登記をせず放置された所有者不明の不動産が増加している現状と関係しています。
故人から引き継いだ不動産の相続人となったにもかかわらず相続登記をせずにいるのは、今後罰則の対象となる行為です。
2-2.相続登記は管轄の法務局で行う
故人から不動産を引き継いだ際に行う相続登記は、全国どこの法務局でもできるわけではありません。手続きができるのは、相続した不動産を管轄する法務局のみです。
相続したのが遠く離れた実家の場合、最寄りの法務局では手続きを受け付けません。遠方であったとしても、管轄の法務局を探して申請する必要があります。
管轄の法務局がどこなのかは、法務局のホームページで確認が可能です。例えば相続した不動産が京都府にあるなら、京都地方法務局が申請先です。
2-3.自分で行うか専門家に依頼する
管轄の法務局で行う手続きは、自力でもできます。ただし手続きに慣れていない場合や、平日の日中は仕事で忙しくて時間が取れない場合には、相続登記の全ての手続きを自分で行うのは難しいかもしれません。
特に故人が相続時に相続登記していなかったケースや、子どもや孫・おいやめいへの代襲相続が発生している場合は、そろえる書類が複雑になり分かりにくいでしょう。
自力では難しそうと感じるならば『司法書士』へ手続きを依頼しましょう。必要な書類の収集や作成も任せられます。
司法書士に任せると、手続きに必要な実費や登録免許税に加え、司法書士への報酬も必要です。報酬の金額はさまざまですが6~7万円程度が相場といえます。
3.必要書類を作成しよう
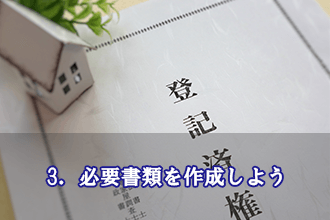
2024年4月1日から義務化する相続登記を実施するには、必要書類を作成しなければいけません。何より必要な『登記申請書』に加え、場合によっては『委任状』も必要です。加えて郵送での申請方法も紹介します。
3-1.登記簿謄本を見ながら登記申請書を記入する
相続登記の手続きに必要な書類は『登記申請書』です。この書類には、必ず正確な地番や家屋番号などを書かなければいけません。そのため登記簿謄本や登記事項証明書を見ながら、間違いのないように記入しましょう。
登記簿謄本・登記事項証明書は、あくまでも確認のために用意した書類です。提出が必要なのは登記申請書のみという点に注意しましょう。
『登記申請書』の作成には下記もご覧ください。
相続登記の申請書作成を徹底解説!様式/書き方/綴じ方/作成時の必要書類|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
3-2.本人以外が手続きする場合は委任状も作成
家族や司法書士など、相続した本人以外が相続登記を実施する場合には、原則として『委任状』も用意します。委任状を作るのは相続人本人でも、手続きを任された委任者でも構いません。
司法書士へ依頼する場合には、司法書士が委任状を用意しているケースが多いでしょう。委任状を本人以外が用意した場合でも、署名と押印は本人が行います。
3-3.郵送で相続登記の申請をする場合
引き継いだ土地が遠方にあり、直接訪れて申請できないケースもあるでしょう。そのようなときに便利なのが『郵送』での申請です。
作成した申請書や必要書類を封筒に入れ、封筒の表面に『不動産登記申請書在中』と書きます。郵送は普通郵便ではなく、配達状況が記録される『書留郵便』で送りましょう。
必要書類を登記完了後に返してもらうときや、登記完了証の受け取りにも郵送を希望するなら、宛名を書いた『返信用封筒』と料金分の『切手』を同封します。
4.その他の必要書類を用意しよう
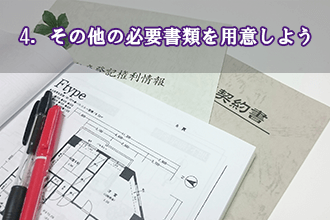
登記申請書と一緒に提出する必要書類の用意も欠かせません。必要書類として何を用意すべきかは、相続の状況によって異なります。相続人が大勢いる場合や、故人が相続の手続きをしていない場合は、より多くの資料が必要です。
4-1.登記原因証明情報に関する書類
まず必要なのは、下記の『登記原因証明情報』に関する書類です。
- 遺産分割協議書
- 故人の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書
- 故人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
また『法定相続情報証明制度』を利用している場合には、『法定相続情報一覧図』を提出すれば、故人の戸籍全部事項証明書・故人の除籍全部事項証明書・相続人の戸籍全部事項証明書は必要ありません。
加えて住所証明情報として『不動産取得者の住民票』も添付しましょう。
4-2.評価額が分かる「固定資産評価証明書」
相続登記をする際には『登録免許税』の申告を行います。登録免許税の金額が正確であると分かるよう、課税標準を確認できる『固定資産評価証明書』を用意しましょう。
都税事務所や県税事務所など、不動産のある自治体の事務所で発行してもらいます。また地域によっては『固定資産課税明細書』の添付により、相続登記の実施が可能です。
5.相続登記にかかる税金
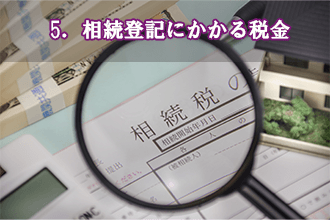
不動産を取得すると『登録免許税』と『不動産取得税』を納めなければいけません。相続で取得した土地や建物の場合には、どのような税金がかかるのでしょうか?
5-1.登録免許税
登録免許税は、不動産の登記をするときにかかる税金です。相続を理由に引き継いだ土地や建物も、『不動産の価額×4/1000』の計算式で求めた登録免許税を支払います。
納付は原則として現金です。ほかには銀行振り込みで指定の口座へ入金し、領収証書を申請書に貼り付ける方法も可能です。税額が3万円以下であれば、登録免許税額相当の収入印紙を貼って提出してもよいでしょう。
オンライン申請であれば、電子納付もできます。
5-2.不動産取得税はかかる?
不動産を取得すると『不動産取得税』がかかります。不動産のある都道府県へ、取得時に一度だけ納付する税金です。ただし相続をきっかけに土地や建物を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
また故人が相続人以外に遺産を遺贈した場合、遺産の全てや一定割合を遺贈する『包括遺贈』なら非課税です。ただし同じ遺贈でも、特定の遺産を引き継ぐ『特定遺贈』は課税される点に注意しましょう。
6.現在は義務がなくても相続登記をしよう

相続登記の手続きは、義務ではなく手続きの期限も定められていません。ただし2024年4月1日から、3年以内の相続登記が義務化されます。
加えて2024年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記しなければ罰則の対象です。そのため、不動産を相続したなら早めに手続きしましょう。
相続登記の義務化と罰則については「相続登記の義務化はいつから?違反者への罰則/新制度に備える方法も解説」でも詳しく紹介しています。
相続登記には登記申請書や委任状のほか、故人の戸籍全部事項証明書や相続人の戸籍全部事項証明書などを用意しなければいけません。さらに税金の支払いも必要です。
遺産の金額によっては、相続税が発生するかもしれません。相続税についての相談は『税理士法人チェスター』がおすすめです。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































