相続登記の抹消とは?遺産分割協議やり直しや贈与・相続放棄した場合も紹介
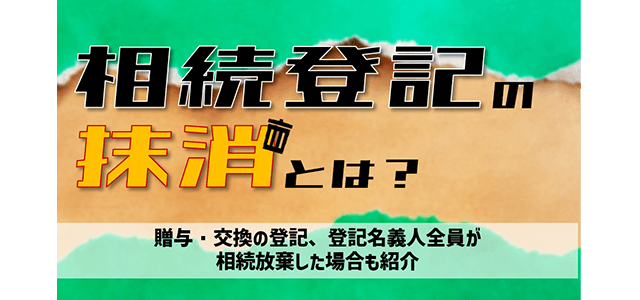
いったん相続登記をしたにもかかわらず、何らかの理由により相続登記をやり直すことになった場合、最初になされた相続登記をどうするのか、また再度行う相続登記をどのように申請するのかなどの問題が生じてきます。
今回は、そのような相続登記の抹消にまつわるお話をしていきたいと思います。
相続登記の抹消(所有権抹消登記)とは
相続登記の抹消とは、相続を原因とする所有権移転登記を何らかの事情で抹消する登記のことをいいます。
相続登記を抹消する例として、遺産分割協議が無効又は取り消された場合、遺産分割協議をやり直した場合、相続登記を行った後に相続放棄をした場合などが挙げられます。
相続登記を抹消すると、登記記録上、所有権の移転がなかったことになりますので、元の登記名義人、すなわち亡くなられた人の名義に戻ることになります。
相続登記を抹消できるケース
以下では、いったんなされた相続登記が抹消されるケースについて、ケース毎に見ていきたいと思います。
①遺産分割協議が無効となるケース
一つ目は、相続人全員で遺産分割協議をし、その結果を法務局に申請して相続登記が完了したものの、その元となる遺産分割協議が無効であったようなケースです。このような場合、相続を原因とする所有権移転登記を抹消する登記をすることができます。
では、無効となる具体的事情とはどのようなものでしょうか。
まず、遺産分割協議は相続人全員でしなければならないにも関わらず、勝手に遺産分割協議書を作成された、というような場合には、全員で遺産分割協議をしていないことになり、無効となります。
また、法律には「錯誤」というものがあり、簡単に言えば「そんな重要なこと知っていたら、決断しなかったのに」という場合に取り消すことができます。たとえば、遺産分割協議がなされた後に遺言書が存在することが判明し、その遺言書に定められた遺産分割方法からすると「それだったら遺産分割協議に合意しなかったのに」と判断されるような場合などが考えられます。
遺産分割協議を取り消すと、その遺産分割協議は無効となります。
このように、遺産分割協議が無効となり、相続登記の抹消(所有権移転登記の抹消登記)をする場合の登記手続きの当事者は誰になるのでしょうか。
不動産登記では、権利を失う人を「義務者」といい、権利を得る人を「権利者」といいます。相続登記の抹消登記の場合、義務者は最初に相続登記で名義を取得した人、権利者は亡くなられた人を指します。ただ、亡くなられた人は当然もう手続きができないので、義務者となる相続人以外の相続人全員が権利者となります。
②遺産分割協議をやり直したケース
二つ目のケースは、遺産分割協議をやり直したケースです。
相続人全員が合意すれば、既になされた遺産分割協議をやり直すことができます。遺産分割協議に基づいて相続登記を行った後であっても同様です。
ただし、第三者の権利を害することはできませんので、相続した不動産を既に第三者に売却していた場合は注意が必要です。
やり直した遺産分割協議を登記に反映させるには、まず遺産分割協議に基づく相続登記を抹消し、その上でやり直した遺産分割協議書を添付して相続登記の申請をすることになります。
また、相続登記の抹消の登記権利者は登記名義人以外の相続人全員、登記義務者は登記名義人となります。
なお、遺産分割協議をやり直すことはできますが、相続税とは別に想定外の課税がなされてしまう可能性があります。この点については、記事の最後で解説します。
③登記名義人が相続放棄したケース
三つ目のケースは、相続登記を完了させたにもかかわらず、その後亡くなられた人が多額の借金をしていたことが判明した場合において、相続人全員が「相続放棄」をするようなケースです。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをして「相続人にはなりません」ということを認めてもらう手続きです。つまり、プラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて引き継がないことになるため、この多額の借金は背負わなくてもよくなります。
ただ、原則としていったん相続財産に手を付ける行為(遺産分割協議)をした後で「相続放棄」をすることはできません。このケースは極めて特殊なケースではありますが、「錯誤」が認められて遺産分割協議が取り消された場合には、相続放棄が認められる可能性があります。
では、相続放棄が認められた場合に行う相続登記の抹消登記は誰が手続きの当事者になるのでしょうか。
義務者は相続登記で名義を取得した人、権利者は亡くなられた人(被相続人)ですが、亡くなられた人は手続きができないので、義務者となる相続人以外の相続人全員が権利者となります。しかし、相続人は全員が相続放棄をしているため、もはや相続人ではないので、この登記申請に当事者として参加することができません。
このように相続人が不存在の場合には、裁判所に「相続財産清算人」の選任申し立てを行います。相続財産清算人には、通常は弁護士が選任されることが多いです。その相続財産清算人が権利者として所有権抹消登記を申請し、被相続人に戻った権利を管理していくという流れになります。
相続登記を抹消するメリット
相続登記を抹消するメリットは、事実とは異なる登記記録上の権利関係を正す点にあります。もし抹消すべき相続登記を放置すると、登記上は所有権者となっている方が借金をしていた場合、その不動産が差し押さえられてしまうこともあり得ます。
また、相続登記を抹消せずに直接他の相続人に対して所有権移転登記をすることも可能ですが(後述)、相続登記を抹消した方が、登録免許税が安く済むこともメリットの一つといえます。
相続登記を抹消するデメリット
上記のとおり、抹消すべき相続登記を放置することは危険を伴いますが、やり直す遺産分割協議が整わないうちに相続登記の抹消登記だけを先にすることにも注意が必要です。
通常、相続登記を抹消した後は、あらためて相続人全員で遺産分割協議を行って、協議が整い次第、協議の結果に即した相続登記の申請をすることになります。
ところが、もし相続登記を抹消してからしばらく時間が経過して、相続人のうちの一人が認知症になってしまったような場合には、もはや相続人全員での遺産分割協議はできなくなります。こうなってしまうと、認知症となった相続人について、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをしたうえで、選任された成年後見人も交えて遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、成年後見人は、その立場上、認知症となった相続人の財産を維持しなければなりません。つまり、遺産分割協議も、当該相続人が有する相続分以上の権利を確保する内容でなければなりません。したがって、他の相続人は、当該相続人の相続分に見合う不動産の共有持分を取得させたり、金銭を支払う必要が生じるため、思い通りに遺産分割協議をやり直すことができない可能性が高くなるといえます。
また、相続登記を抹消してから新たに相続登記を行うまでの間に相続人の誰かが亡くなられた場合には、さらに相続が発生することになるため、相続関係が複雑となってしまいます。
このようなデメリットがありますので、相続登記を抹消する前に、新たな相続登記を速やかに行うことができるか、よく検討してから抹消登記をするべきです。
相続登記の抹消以外に有効な手段
上述したとおり、相続登記を抹消するためには、相続人全員が改めて登記手続きに関与しなければなりません。そうすると、相続登記を行ってから時間が経過している場合には、相続人の一人が認知症になってしまっていたり、亡くなられてしまっていたりするなどして、相続人全員の協力が得られないといったケースも考えられます。
では、相続登記の抹消以外に他の相続人に名義を移す方法はないものでしょうか。この点について説明していきます。
①贈与の登記
たとえば、相続人がA、B、Cの3人で、遺産分割協議によりCが不動産を取得することになり、相続登記を完了した後で、当該遺産分割協議が錯誤により取り消されたとします。この場合、いったんC名義の相続登記を抹消した後、被相続人名義に戻った状態で再度遺産分割協議をし直し、あらためて遺産分割協議書を添付してAの名義に変更する旨の相続登記を申請するのが上記で説明したやり方です。
ところが、相続登記を抹消する段階で、Bが相続登記の抹消手続きにも再度の遺産分割協議にも協力できないとなった場合、このような方法をとることができません。この場合に、CからAに直接所有権を移転する方法があれば、Bの協力がなくても、Aの名義に変える目的は達成することができます。
その手続きとしては、贈与を原因として所有権を直接CからAに移転させるという方法が考えられます。
贈与の登記を行うメリット・デメリット
贈与を原因とする所有権移転登記を行う場合、その登記権利者は贈与によって不動産を取得する人(A)、登記義務者は登記名義人(C)となりますので、たとえ他の相続人(B)の協力を得られなくても所有権移転登記を行うことができます。
しかし、このような方法にはデメリットもあります。
まず、贈与の登記を選択する場合には、登記の登録免許税(印紙代)が不動産評価額の1,000分の20かかります。1,000万円の評価額の不動産であれば登録免許税(印紙代)が20万円かかります。
ちなみに相続登記を抹消して、再申請した場合の登録免許税(印紙代)は、抹消が不動産の個数×1,000円、相続登記が不動産評価額の1,000分の4です。1,000万円の不動産(1個)の場合には、登録免許税(印紙代)は4万1,000円となります。このように、相続登記の抹消と贈与の登記とではかなりの差が生じます。
また、相続税と贈与税では、控除できる金額も税率も贈与の方が厳しくなりますから、お金の面でいえばかなり負担がかかることになるでしょう。
②交換の登記
贈与以外の方法としては、「交換」という手続きがあります。これも贈与と同様に他の相続人の協力なしに直接所有権を移転することができます。その内容は、文字通りお互いが所有している不動産と不動産を「交換する」登記です。
たとえば、被相続人が甲土地と乙土地を持っていた場合に、遺産分割で甲土地はA、乙土地はBがそれぞれ相続した場合に、相続登記後になんらかの錯誤があり、Aが乙土地を取得するはずだったとします。
その場合に、Bは承諾しているものの他の相続人の協力が得られないような場合には、甲土地と乙土地を「交換」を原因として、所有者をいわば入れ替えてしまう、という手続きができます。
これも贈与と同様にAとBの2人の手続きで登記が完了します。
交換の登記を行うメリット・デメリット
「交換」は実務上頻繁に登場する手続きではなく、かなりレアなケースにはなりますが、メリットとしては贈与と同様に相続登記を抹消してやり直すのに支障があり、登記名義を移す目的を重視するのであれば使える方法ではあります。
デメリットとしては、登記申請時の登録免許税(印紙代)が不動産評価額の1,000分の20となり、上記の贈与の場合と同じになります。また、交換という手続きではありますが、譲渡による所得税や不動産取得税が課税されますので、やはり費用面での負担が大きくなってきます。
相続登記の抹消に関する手続き
実際に相続登記がされた後で、抹消登記を申請する場合には具体的にどのようにしたらよいのでしょうか。これまでは、流れを見てきましたが、実際の手続きに則して説明していきます。
①相続登記の抹消を行う
権利を失う相続人が義務者、権利が戻る被相続人の相続人全員(ただし義務者となる相続人以外)が申請人となって登記申請をします。例えば、被相続人をA、相続人がBCDであり、最初の相続登記で名義人になったのがBの場合で説明します。
義務者であるBの必要書類は、相続登記の際に通知された「登記識別情報通知(登記済権利証)」と「印鑑証明書」であり、司法書士に依頼する場合には実印を押印した委任状が必要となります。
権利者である他の相続人CDは、自分たちが相続人であることが証明できる戸籍謄本等一式と司法書士への委任状が必要となります。そのほかには、「登記原因証明情報」といって、その登記申請の原因となった事柄を記載し、義務者が押印したものを添付します。様式は難しいので司法書士に作成を依頼するとよいです。
そして、登録免許税(印紙代)が不動産の個数×1,000円ですから、たとえば土地と建物1つずつであれば2,000円になります。
②新たに相続登記の申請を行う
上記の抹消登記が完了したら、正しい内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印して印鑑証明書を用意します。戸籍などの相続人を特定するのに必要な書類や最後の住所と登記簿上の住所のつながりを証明する住民票の除票等は、さらに亡くなられた方がおられない限り最初の相続登記の際と同様ですので、再度利用してかまいません。
あとは不動産の名義人になる人が司法書士への委任状に署名押印し、住民票を用意すれば申請の準備ができます。登録免許税(印紙代)は、不動産評価額の1,000分の4となります。
相続登記の抹消で遺産分割をやり直した場合の税金
1度目の相続登記を抹消し、正しい相続登記を申請し直すと、登記簿上は1度目の相続登記が消され、正しい登記がされます。注意が必要なのは、税務上はこのようにきれいにはいかないということです。
税務上は、相続のやり直しは贈与と同視されます。相続税の課税対象は、相続財産の課税価格の合計-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)となります。たとえば、相続財産の課税価格の合計が4,000万円で、法定相続人が3名の場合には、4,000万円-(3,000万円+600万円×3)=マイナス800万円となり控除される額のほうが多いわけですから、相続税はかからないことになります。
贈与税の場合には、贈与された額から110万円しか控除されず、その額に税率をかけて算出されます。
税率につきましては、財産が多くなるほど高い税率が課せられます。具体的には不動産評価額により異なってきますので、国税庁のホームページを参考にされるとよいでしょう。高い税率が課せられます。具体的には不動産評価額により異なってきますので、国税庁のホームページを参考にされるとよいでしょう。
また下記ページでも相続税と贈与税の税率について解説していますので、こちらもご覧ください。
相続税の税率は何%か。控除額とは?計算手順や早見表も解説
贈与税の速算表を使って試算しよう。一般税率と特例税率の違いは?
まとめ
相続登記をするためには、不備のないように遺産分割をしなければなりません。遺言書はないか、被相続人の財産や借金をすべて確認したか、相続人全員で合意したかといったことを、登記の前に再確認することが大切です。
今回説明したようなやり直しはごくまれなケースであり、税金面などの負担が増えることなどからも、やり直しができるという前提で考えることはよくありません。
あとから問題が起きないように弁護士や司法書士に十分相談したうえで手続きをしていくことをお勧めします。
失敗しないための相続登記についてのご相談は司法書士法人チェスターまでお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































