実家の遺品整理の手順は?相続財産や重要書類の見極め方法とポイント
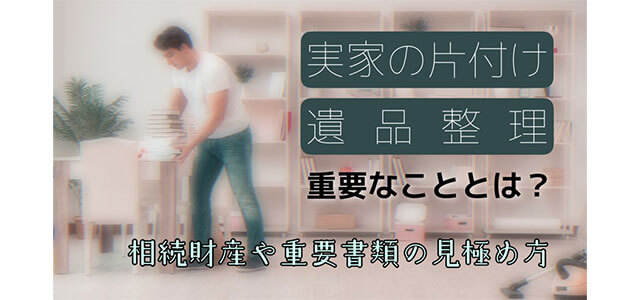
故人の実家の片付けや遺品整理は、相続財産を確認したり重要書類を見つけたりするために必要です。
実家の片付けにうんざりすることもあるでしょうが、面倒だからと遺品整理をおこなわないと、後々大変なトラブルに見舞われる可能性があります。例えば管理不行き届きで特定空き屋に認定されると、固定資産税が本来支払うべき金額の6倍まで膨れ上がることもあるのです。自分で遺品整理を実施する際は事前の計画も大切であるため、流れをしっかりチェックしておきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.実家の片付け・遺品整理をするのは相続人
故人の遺品は相続人の相続財産になるため、遺品整理も相続人がおこなうのが適切です。法律上、故人が遺したものは家財道具から小物に至るまで相続人が受け継ぐため、相続人の財産である遺品を他人は勝手に処分できません。
一方で、相続人としては「故人の家から遠方に住んでいる」「忙しくて遺品整理の時間が取れない」などの事情から、近所に住んでいる知人に遺品整理を依頼したくなることもあるでしょう。
しかし、遺品は相続人の所有物であるため、いくら近所に住む親しい間柄の人間とはいえ処分する権利はありません。また、他人が処分することによって思わぬトラブルが生じる可能性もあります。
以上のことから、家の片付けや遺品整理は相続人がおこなうようにしましょう。
1-1.【注意】遺品整理に関わることで相続放棄できなくなる可能性がある
遺品整理に手を付けると民法上の『単純承認』にあたり、相続放棄できなくなる可能性があるため注意しましょう。相続人は、故人の遺産を相続するかしないかを選択できます。相続しないことを『相続放棄』といい、相続放棄を選択すれば故人のプラスの財産(不動産、金融資産など)もマイナスの財産(借金など)もすべて受け継がないことになります。
もし、相続放棄の選択肢も考えている場合、決断する前に遺品整理に手を付けるのは避けましょう。遺品整理を開始することで、民法921条に定められている『単純承認』に該当する可能性があるからです。
なお、民法920条と921条では以下のように定められています。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
引用:民法|e-Gov法令検索
つまり、相続財産の一部であっても処分してしまうと単純承認とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があるのです。
したがって、遺品整理に着手する際は相続放棄ができなくなる可能性があることを押さえておきましょう。
2.相続した実家の片付け・遺品整理をすべき理由
相続した財産の遺品整理は、単に片付けてきれいにする以上に重要な意味があります。遺品整理をするのは、次のような理由があるからです。
遺品整理すべき理由
- 相続財産を把握するため
- 重要書類を見つけるため
遺品整理をせず相続財産の内容があいまいなまま放置すると、正しい相続税額が算出できなかったり適切な遺産分割ができなかったりします。また、故人が生前におこなった契約に関して後々トラブルが生じた場合にスムーズに解決できない可能性もあります。
したがって、相続した家の片付けや遺品整理は早めにおこないましょう。
2-1.相続財産を把握するため
早めに相続財産の全容と総額を確定させるためにも遺品整理は必要です。相続税の計算をしたり相続人間で遺産分割をしたりするには、すべての相続財産を把握しなければなりません。相続財産として扱われるものは不動産や金融資産に限らず多くの種類があります。相続財産の主な種類は以下のとおりです。
| プラスの財産 |
|---|
|
| マイナスの財産 |
|
相続するかしないかの申告(相続放棄)は相続開始があったことを知ったときから3ヵ月以内、相続税の申告は10ヵ月以内が期限です。相続財産をすべて整理すると時間がかかるため、遺産整理にはできるだけ早めに取りかかりましょう。
参考:相続財産とは。絶対に知っておきたい相続財産の定義と具体例|税理士法人チェスター
2-2.重要書類を見つけるため
相続した不動産を売却する場合、権利証や不動産売買契約書などの重要書類で購入時の費用を確認する必要があります。購入時に生じた費用がわからないと、支払う所得税の額が本来よりも多くなってしまうことがあるためです。したがって、不動産購入時の証拠資料として、権利証や不動産売買契約書などの重要書類を遺品整理の段階で見つけておく必要があります。
3.相続した実家の片付けを放置したときに起こりうるトラブル
相続した家の片付けを放置したままでいると、無視できないレベルのデメリットが生じます。主な内容は下記のとおりです。
相続した家の片付けを放置した際のデメリット
- 住んでいない家でも固定資産税の支払が続く
- 家の価値が下がり続け希望の金額で売却しにくくなる
- 特定空き家に指定され増税となるリスクがある
「距離が遠い」「面倒くさい」などの理由で片付けを放置すると、余計な税金がかかったり希望の金額で売却できなかったりするなど損をする可能性が生じます。したがって相続した家は、面倒でも遺品整理を実施しましょう。
3-1.住んでいない家でも固定資産税の支払が続く
人が住んでいるかどうかにかかわらず、日本国内に存在するすべての不動産は固定資産税の課税対象です。固定資産税を支払う義務があるのは所有者のため、所有者が亡くなった場合は相続人に支払義務があります。
具体的には『1月1日時点の土地の登記上の所有者』に対して課せられます。したがって、1月1日時点で所有者が亡くなっている場合、相続人が納税義務者です。遺品整理や売却手続が面倒だからといって放置したままでいると、ずっと固定資産税を払い続けなければならないことを押さえておきましょう。
3-2.家の価値が下がり続け希望の金額で売却しにくくなる
相続した不動産の売却を考えているなら、値下がりによる損失を見込んだうえで早めに売却手続をおこないましょう。不動産の価格は一定ではなく、株価のように変動を続けるものです。相続した家の遺品整理や売却手続を手付かずで放置していると、値下がりにより希望の価格で売却できない可能性が生じます。
家の価値が下がる原因
- 少子高齢化による人口減少
- デフレ
- 株価のピークアウト
少子高齢化で空き家が急増し住宅供給数が過多になれば、不動産の価値が下落する可能性があります。また、日本全体でデフレが進めば不動産の価値も下がるでしょう。さらに、株価がピークアウトすると半年から1年後に地価が下がる可能性があります。
このように、相続した家をそのまま放置した場合、価値が下がる要因は複数あります。希望の価格で売却したいなら、早めに売却手続に取りかかるのがよいでしょう。
3-3.特定空き家に指定され増税となるリスクがある
空き家のうちでも特に状態が悪く、周辺地域に悪影響を及ぼす可能性がある家は『特定空き家』に認定され、固定資産税が6倍にのぼる可能性があります。特定空き家に認定される可能性のある空き家は下記のとおりです。
特定空き家の特徴
- 公衆衛生上有害である
- 景観を著しく損ねている
- 近隣の生活環境を損ねている
参考:空家等対策の推進に関する特別措置法2条2項|e-Gov
特定空き家に認定されると、翌年から固定資産税の課税額が最大6倍になります(課税基準日は1月1日)。住宅用地の特例による課税の軽減も受けられなくなるため注意しましょう。
参考:空き家対策特別措置法の内容とその対策【空き家オーナー必見!】|税理士法人チェスター
4.実家の片付け・遺品整理で不安を抱きやすい点の解決策
故人が住んでいた家を片付け、遺品を整理する作業は普通の片付けと異なり不安を抱きやすいでしょう。遺品整理に対する不安を漠然としたままにせず、原因を洗い出し解決策を探す必要があります。遺品整理で不安を抱きやすい主な点は以下のとおりです。
遺品整理で不安を抱きやすい点
- 人手が足りないため時間がかかってしまう
- 昔の思い出が浮かんできて辛くなる
- 業者に依頼するにも費用を支払えるか不安に感じる
遺品整理は非常にデリケートな作業です。辛さや不安を少しでも解消してスムーズに作業を進めるためにも、各不安点に対する解決策を押さえておきましょう。
4-1.人手が足りないため時間がかかってしまう-業者に依頼を検討
人手が足りない、忙しいなどの理由で遺品整理に着手しにくい場合は、遺品整理専門業者への依頼を検討しましょう。遺品整理を先延ばしにしていると、固定資産税や空き家問題などのデメリットが生じます。
事情により相続人や家族による遺品整理が難しい場合は、遺品整理専門の業者に依頼するのも有用です。業者に依頼すれば、遺品整理を熟知したプロがスムーズに整理してくれます。その分料金はかかりますが、自分でおこなうよりも時間や労力を大幅に削減できます。
よって、人手や時間の不足から遺品整理を躊躇している場合は、業者への依頼を検討するとよいでしょう。
参考:遺品整理は専門業者に依頼すべき?遺品整理のタイミングと方法
4-2.昔の思い出が浮かんできて辛い-区切りのよい時期から開始
故人との思い出がよみがえってきて辛い場合は、葬儀や四十九日などの節目が過ぎてから遺品整理を始めましょう。遺品整理では、故人が日常的に使っていた衣類や小物類、写真などを手に取ることになります。相続人としては、生前の故人との懐かしい思い出がよみがえり、今はもう故人がいないことへの喪失感や「もっと大切にしてあげたかった」との後悔の念にさいなまれるかもしれません。
もし悲しく辛い思いが生じたならば、いったん気持ちを整理することが大切です。遺品整理は気持ちの区切りがついてから再開しましょう。具体的には、葬儀や四十九日、一周忌法要などの法事を済ませることを気持ちの区切りとします。法事には親族も集まるため、遺品整理について相談し協力を得られる可能性もあります。
遺品整理は辛い作業ですが、放置するわけにはいきません。法要を節目とし、気持ちを少しでも落ち着かせてから取りかかるとよいでしょう。
4-3.業者に依頼するにも費用を支払えるか不安-心身の負担を考慮
専門業者への依頼は費用の面で不安がある場合でも、上手な業者の選び方をすれば金額を安く抑えられます。遺品整理の料金は遺品の『量』と『質』で決まります。遺品の量が多いほど料金は高くなり、遺品の状態が悪ければ清掃や処分にかかる費用が高くなることがほとんどです。相続した財産が少額の場合や、マイナスの財産の金額が大きいと高い費用を払えるか不安が強くなるでしょう。
不安を解消するためには、まず信頼できる遺品整理業者を選ぶことが大切です。遺品整理業者を選ぶ際は、『古物商許可』または『一般廃棄物収集運搬許可』を得ている業者かどうかを確認しましょう。許可の有無は業者のサイトや自治体のサイトから確認できます。業者に直接連絡して確認することも可能です。
また、数社の業者で相見積もりをとることで、費用を安く抑えられます。各業者に同じ条件で見積もり金額を出してもらい、サービス内容と料金を比較しましょう。比較の際は金額だけでなく、スタッフの接客態度やどこまで相談に乗ってくれるかといったことも見ておくと、安心感につながります。
4-4.価値が高い遺品の相続で揉めないか不安-遺言書確認や早期整理
遺品のなかに不動産や株式などの金銭的価値が高い財産が含まれていると、相続人同士で揉める可能性があります。相続人間のやり取りに不安がある場合は、まず遺言書の内容を確認し、早めに遺品整理をして相続財産の総額を算出しましょう。
故人が遺言書を作成していれば、相続規定に反しているような特別な事情がない限り、書かれた内容どおりの相続がおこなわれます。遺言書がない場合は、相続人同士の協議によって遺産分割の合意をとることが必要です。遺産分割協議の時点で遺産の内容が不明確だと、例えば不動産を「売却するのか」「相続人間で共有するのか」など結論が出ず揉める原因になります。
不動産以外にも、株式やゴルフの会員権など価値の高い遺品が次々と出てくることがあります。遺産分割協議のあとになって価値の高い遺品の存在が明らかとなり相続人同士で揉めることのないよう、早めに遺品整理に着手することが大切です。
5.自分で実家の片付け・遺品整理をする手順
遺品整理は相続財産のすべてを確定する作業も含まれるため、かなりの時間と労力がかかります。したがって、いきなり手を付けるのではなく手順を確認したうえで作業を進めることが重要です。遺品整理の大まかな手順は以下のとおりです。
遺品整理の手順
- 詳細なスケジュールを決める
- 作業に必要なものを準備する
- 片付けをはじめる前に遺言書や相続財産の有無を確認する
- リサイクルが必要なものに注意して不用品を処分する
- 必要な場合は遺品整理業者に依頼する
具体的な日程や必要な道具などは紙に書き出して視覚化すると、把握しやすくなります。
5-1.詳細なスケジュールを決める
遺品整理をすると決めたら、まずは「どこから手をつけるか」「いつまでに終わらせるか」「誰と一緒にやるか」など詳細なスケジュールを決めましょう。漫然と着手するよりも、細かくスケジュールを決めてから取りかかったほうがスムーズに作業を進められます。
遺品整理をおこなうタイミングはなるべく早いほうがよいですが、期日が決まっているわけではないため自由に始めてかまいません。着手開始のタイミングとしては主に以下の時期が挙げられます。
遺品整理着手の主なタイミング
- 四十九日を迎えたあと
- 死亡届、電気水道ガス、年金など諸手続の完了後
- 葬儀のすぐあと
- 相続税が発生する前
上記はあくまで目安であり、基本的には自分の気持ちが落ち着いたタイミングで取りかかりましょう。遺産分割協議や相続税の申告などを念頭に置きつつ、心の整理がついた段階でスケジュールを組んでみてください。
5-2.作業に必要なものを準備する
遺品整理では大小合わせて大量の物を整理しなければならないため、作業に必要な道具を準備しておきましょう。
遺品整理作業で必要なもの
- 汚れてもいい服
- マスク
- 手袋
- ゴミ袋
- 段ボール
- 収納ケース
- ガムテープ
- ビニールひも
- はさみ・ドライバー・ペンチ
遺品整理では長年使わないままでいた場所や物に手をつけることもあるため、ホコリやゴミを被る可能性があります。また多くの荷物を運ぶこともあるため、動きやすく汚れてもいい服で作業しましょう。なお、マスクや手袋はホコリやカビから身を守るだけではなく怪我防止にもなります。
大型の荷物を大量に運ぶ必要がある場合は、台車もあると便利です。
5-3.片付けをはじめる前に遺言書や相続財産の有無を確認する
遺品整理で誤って重要書類を処分してしまうと、あとでトラブルの原因になったりゼロから手続をする必要が生じたりするため大変です。遺品整理の着手前に、まずは重要書類の有無を確認し仕分けしておきましょう。
遺品整理で残すべき重要書類の代表例は以下のとおりです。
遺品整理で残すべきもの
- 身分証明書
- 印鑑
- 通帳
- クレジットカード
- 年金手帳
- 遺言書
- 不動産の権利証や売買契約書
個人情報に該当するものや契約関係書類、遺言書は誤って捨てないように注意しましょう。免許証や保険証などの身分証明書は生前から保管場所を共有しておくと、入院や通院などとっさの事態にも対処しやすいため便利です。
5-4.リサイクルが必要なものに注意して不用品を処分する
整理した物のなかで、衣類や家具など状態のよい物はできる範囲でリサイクルに出しましょう。また、家電リサイクル法の対象となる家電はリサイクルが義務付けられています。対象品目は以下のとおりです。
リサイクルの対象となる家電4品目
- エアコン
- テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
家電4品目のリサイクル方法には「電気店に引き取りを依頼する」「指定の引き取り場所に持ち込む」などの方法があります。家電を購入した店舗に問い合わせて引き取ってもらえるか確認しましょう。
リサイクル方法がわからない場合は、市区町村のホームページを確認するか直接問い合わせてみてください。
5-5.必要な場合は遺品整理業者に依頼する
「自分たちだけで遺品整理をするのは難しい」と感じたら、遺品整理業者への依頼も検討しましょう。料金はかかりますが、メリットもあります。
遺品整理を業者に依頼するメリット
- 遺品整理が短期間で終わる
- 大型家具でも簡単に運び出せる
- 相続や空き家のトラブルにも相談に乗ってもらえる
遺品整理を依頼する場合の料金は、間取りや遺品の量と質などから総合的に算出されるため、一律ではありません。大体の相場は以下のとおりです。
| 間取り | 料金相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 30,000円~80,000円 |
| 1DK | 50,000円~120,000円 |
| 1LDK | 70,000円~200,000円 |
| 2DK | 90,000円~250,000円 |
| 2LDK | 120,000円~300,000円 |
| 3DK | 150,000円~400,000円 |
| 3LDK | 170,000円~500,000円 |
| 4LDK以上 | 220,000円~600,000円 |
同じ条件でも業者によって料金が変わることもあります。はじめから1社だけに依頼するのではなく、数社の相見積もりをとり比較検討するとよいでしょう。
6.自分で実家の片付けをおこなう際の注意点
自分で家の片付けをする場合は、できるだけスムーズに作業を進めるために押さえておくべきコツがあります。「費用をかけたくない」「故人の大切な物に他人の手を触れさせたくない」などの理由から自分で遺品整理をする場合は、以下の注意点を押さえておきましょう。
自分で遺品整理をおこなう際の注意点
- 相続人全員と事前に予定を合わせる
- 捨てるべきか判断がつかないものはいったん保留にする
- 近隣に悪影響を与えないよう配慮する
複数人で作業に取りかかる場合は、これらのポイントを事前に共有しておくと作業しやすくなります。
6-1.相続人全員が集まれる日には限りがあるため事前に予定を合わせる
相続人が全員集まって遺品整理をする場合は、事前に余裕を持ったスケジュールを立てておきましょう。遺産分割協議をスムーズに進めたいならば、遺品整理の段階で相続人が全員集まり、協力して片付ける必要があります。ただし、相続人全員が集まれる日となると限られるケースが多いでしょう。
また、遺品整理は大型の家具の運び出しに想像以上の時間を要したり、故人との思い出に浸ってしまったりしてスケジュールどおりに進まないケースもあります。
したがって、事前に全員でスケジュールを調整し、万が一に備えて予備日も設けておきましょう。
6-2.捨てるべきか判断がつかないものはいったん保留にする
遺品整理をしていると、処分していいかどうか判断がつかないものも出てくるため、一時保管用のスペースを作っておきましょう。段ボールやコンテナを用意し、捨てるべきか迷うものがあったら入れていくと片付けがスムーズに進みます。また、一時保管用のスペースを用意することで本来価値があるものを誤って処分してしまうことを防げます。
一時保管用のスペースに保留したものは、一定の期間をおいて、あらためて吟味しましょう。遺品整理を開始した頃よりは気持ちも落ち着き、冷静かつ客観的な判断ができるようになっているはずです。3ヵ月経っても迷う場合はそのまま保管しておき、さらに数ヵ月後に判断してもかまいません。少しずつものを減らしていくだけでも遺品整理は進みます。
6-3.近隣に悪影響を与えないよう配慮する
遺品整理をする際は、騒音や悪臭など近隣へ迷惑がかからないよう配慮しましょう。建物を解体する場合はもちろん、遺品整理では大きな家具を運び出すことや、大量のゴミが出ることがあります。あまりに騒音や悪臭がひどい場合は行政に通報されたり、近隣に被害が生じれば訴えられたりする可能性もあります。
したがって、気をつけていても騒音や悪臭が生じそうな場合は、できれば作業前に近所の人たちに挨拶をし、断りを入れておきましょう。
7.遺品整理にともなう相続手続に不安があるなら専門家を頼ろう
遺品整理は大きな荷物の運び出しや細かい物の仕分けなど、自分でやるとかなりの時間と労力を要します。また、相続が絡むため相続財産の把握や相続税の計算、遺産分割協議など必要手続をすべておこなうだけでも大変です。
遺品整理をはじめ、相続手続に少しでも不安があるなら専門家への依頼をおすすめします。
司法書士法人チェスターは、経験豊富な専門家が遺品整理から相続手続まで依頼人にあわせて適切なアドバイスが可能です。また、手続の代行も承っています。
相続や遺品整理でお困りの際は、ぜひお気軽に司法書士法人チェスターにご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































